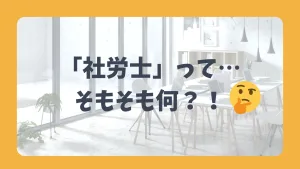【給与計算担当者必見!】社会保険料の納付は翌月?当月?徴収の仕組みと変更点を徹底解説
給与計算担当者の皆様、社会保険料のことで頭を悩ませていませんか? 社会保険料は頻繁に制度改正が行われるため、常に最新情報を把握しておく必要があります。
この記事では、社会保険料の変更タイミングや、保険料率について、事業主の皆様、そして給与計算担当者の皆様が知っておくべきポイントをまとめました。 「毎年3月」というキーワードにも注目しながら、社会保険料の仕組みを改めて確認していきましょう。
1. 社会保険料の基本的な仕組みをおさらい
まず、社会保険料の基本的な仕組みを簡単に確認しておきましょう。 社会保険とは、以下の5つの保険制度の総称です。
- 健康保険:病気やケガをした際の医療費を補助する制度
- 介護保険:高齢者の介護費用を補助する制度
- 厚生年金保険:老後の生活を保障する年金制度
- 雇用保険:失業した際の生活を保障する制度
- 労災保険:業務上のケガや病気を補償する制度
このうち、健康保険、介護保険、厚生年金保険の保険料を「社会保険料」と呼ぶことが一般的です。 これらの保険料は、事業主と従業員が一定割合で負担し、納付する義務があります。
2. 社会保険料の「保険料率」とは?
社会保険料を計算する上で重要なのが、「保険料率」です。 保険料率とは、給与や賞与に対して、保険料がどのくらいの割合でかかるかを示すものです。 この保険料率は、一定のサイクルで見直されます。
社会保険料の保険料率は、以下のタイミングで見直されます。
- 健康保険と介護保険:毎年3月に見直されます。健康保険料率は都道府県ごとに異なり、医療費の水準などに応じて、介護保険料率は全国一律で、高齢化の進展に伴う介護費用の増加などを考慮して見直されます。協会けんぽのホームページには、従業員が健康になって医療費が減れば、保険料も抑えられる可能性があるという情報も掲載されています。
- 厚生年金保険: 原則として固定されていますが、将来的な制度見直しで変更される可能性があります。現在は、平成29年9月以降、私立学校の職員(第4号厚生年金被保険者)以外のほとんどの方が18.3%です。
- 雇用保険: 基本的には4月ですが、社会情勢や経済状況に応じて年度ごとに見直されます。令和4年は4月と10月にも改定がありました。これは、新型コロナウイルスの影響による雇用情勢の悪化に対応するためのもので、失業等給付の財源を確保する目的でした。
- 労災保険: 事業の種類ごとに設定されており、労働災害の発生状況などを考慮して、数年に一度見直されます。
3. あなたの会社は翌月徴収?保険料納付の仕組みと注意点
「従業員の給与から控除している社会保険料、いつ、どうやって納付しているんだっけ?」
社会保険料の納付の仕組みは、実はちょっと複雑です。特に、健康保険と介護保険の保険料は、原則として翌月に徴収されるという点に注意が必要です。
例えば、4月分の保険料は、5月に支払われる給与から控除され、事業主は5月末までに納付します。このように、翌月に徴収することで、従業員の給与から社会保険料を控除するタイミングと、事業主が納付するタイミングをできるだけ近づけているのです。
しかし、当月徴収の会社もあります。
3月から健康保険料が変わっていたら、『当月徴収』。4月からだと『翌月徴収』ということです。
就業規則を確認して見てもいいですし、過去の社会保険料の変動を見てみてもいいですし。確認手段は色々あります。
4. 健康保険料率はどうやって計算する? 具体的な料率と全国平均
健康保険料率は、都道府県ごとに異なります。これは、各都道府県の医療費水準や加入者の所得状況などが異なるためです。
具体的な保険料率は、ご加入の健康保険組合や協会けんぽのウェブサイトで確認できます。
例えば、協会けんぽの場合、ウェブサイトで都道府県別の保険料率が一覧で掲載されています。ご自身の事業所が所在する都道府県の保険料率を確認するようにしましょう。
なお、令和7年度の健康保険料率の全国平均は10.00%、介護保険料率は全国一律で1.59%です。
5. 最後に、社会保険料のポイントをおさらい!
この記事では、社会保険料の変更タイミング、特に健康保険と介護保険の保険料率が毎年3月に改定される点と、その納付の仕組みについて解説しました。
社会保険料は、従業員の生活を支える上で非常に重要な制度であり、事業主の皆様、そして給与計算担当者の皆様には、その仕組みを正しく理解し、適切に対応することが求められます。
社会保険料に関する最新情報は、日本年金機構や厚生労働省のウェブサイトなどで確認できますので、定期的にチェックするようにしましょう。