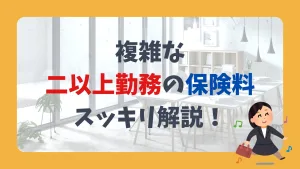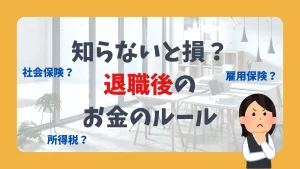「24協定」とは?給与からの天引きルールを社労士がやさしく解説
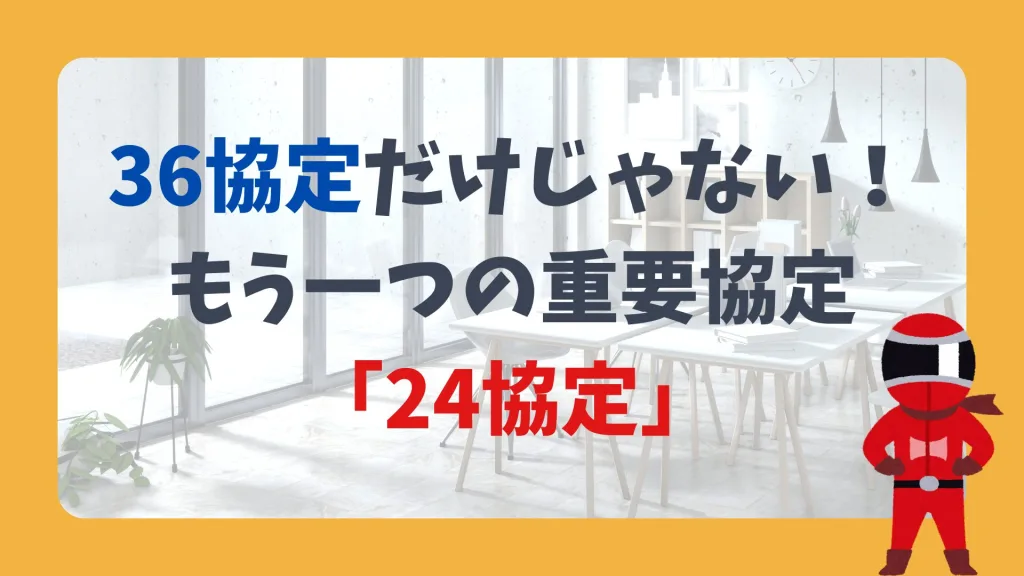
「社宅の家賃や親睦会費を給与から天引きしたいけど、法的に問題ないの?」
「そもそも、給与から天引きして良いものと悪いものの違いって何?」
経営者や人事担当者の皆様から、このようなご相談をよくお受けします。この「給与からの天引き(控除)」を適法に行うために不可欠なのが、「24協定(ニイヨンきょうてい)」です。
「36(サブロク)協定」に比べて知名度は低いかもしれませんが、適切な労務管理を行う上で非常に重要な協定です。
この記事では、「24協定」とは何か、なぜ必要なのか、そして具体的な手続きについて、社会保険労務士が分かりやすく解説します。
「24協定」の根拠は「賃金支払いの5原則」
「24協定」を理解するためには、まず労働基準法第24条で定められている「賃金支払いの5原則」を知る必要があります。
これは、労働者の生活を守るための基本的なルールです。
- 通貨払いの原則:賃金は通貨(日本円)で支払う
- 直接払いの原則:賃金は労働者本人に直接支払う
- 全額払いの原則:賃金はその全額を支払う
- 毎月1回以上払いの原則:賃金は毎月1回以上支払う
- 一定期日払いの原則:賃金は毎月決まった日に支払う
この中で、24協定に最も深く関わるのが3番目の「全額払いの原則」です。
原則として、会社は給与から所得税や住民税、社会保険料といった法律で定められたもの以外を、一方的に差し引く(控除する)ことはできません。
なぜ「24協定」が必要なのか?
では、法律で定められていない社宅の家賃や組合費、親睦会費、財形貯蓄の積立金などを給与から天引きしたい場合はどうすればよいのでしょうか。
そこで必要になるのが、「賃金控除に関する労使協定」です。
これが、労働基準法第24条を根拠とすることから、通称「24協定」と呼ばれているのです。
この協定を、会社の労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)と書面で結ぶことにより、「全額払いの原則」の例外として、合意した項目を賃金から控除することが適法に認められます。
もし、この協定を結ばずに給与天引きを行ってしまうと、労働基準法違反(30万円以下の罰金)となる可能性がありますので、注意が必要です。
36協定との違い
同じ労使協定でも、36協定と24協定には大きな違いがあります。
| 24協定(賃金控除) | 36協定(時間外労働) | |
|---|---|---|
| 届出義務 | 労働基準監督署への届出は不要 | 労働基準監督署への届出が必須 |
| 有効期間 | 定める必要なし(一度結べば永年有効) | 定める必要あり(通常は1年) |
24協定は一度締結すれば、労使双方から破棄の申し出がない限り有効です。
届出も不要なため、締結した協定書は社内で大切に保管してください。
まとめ
「24協定」は、給与から法定控除以外の項目(家賃や親睦会費など)を天引きするために不可欠な労使協定です。
この協定がないまま安易に給与天引きを行うと、法律違反となるだけでなく、従業員との信頼関係を損なう原因にもなりかねません。
従業員が安心して働ける職場環境を整えるためにも、自社の給与控除が適切に行われているか、この機会に一度確認してみてはいかがでしょうか。
「自社の場合はどうなんだろう?」「協定書の作り方が分からない」
そのようなお悩みがございましたら、ぜひ一度、私たち労務管理の専門家である社労士事務所ぽけっとにご相談ください。
【免責事項】
本記事は、2025年7月時点の法令に基づき作成しております。今後の法改正等により、内容が変更となる可能性があります。個別の事案については、必ず社会保険労務士等の専門家にご相談ください。