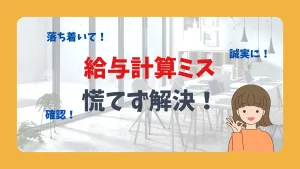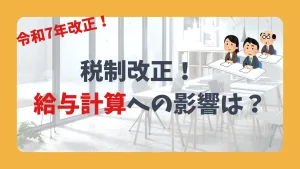36協定とは?知らないとマズい!残業・休日出勤のルールと手続き

従業員の皆様に気持ちよく働いてもらうため、そして会社の成長のため、労務管理は非常に重要ですよね。中でも、「時間外労働」や「休日労働」、いわゆる残業や休日出勤をお願いする際に避けて通れないのが「36協定(さぶろくきょうてい)」です。
「名前は聞いたことあるけど、詳しくは知らない…」
「手続きが面倒くさそう…」
「ウチは大丈夫かな?」
そんな風に思っていませんか? 今回は、経営者の皆様が知っておくべき36協定の基本から、具体的な手続き、そして注意点まで解説します!
そもそも「36協定」って何?なぜ必要なの?
まず基本からおさえましょう。 日本の法律(労働基準法)では、従業員の労働時間は原則として「1日8時間・週40時間」までと決められています。これを法定労働時間といいます。また、休日は毎週少なくとも1回(または4週間を通じて4日以上)与えなければなりません。これを法定休日といいます。
しかし、実際の業務では、繁忙期や突発的な対応などで、どうしてもこの法定労働時間を超えて働いてもらったり、法定休日に出勤してもらったりする必要が出てくることがありますよね。
そこで登場する「36協定」です!
労働基準法第36条に基づく労使協定(労働者と会社側の約束)であることから、「36協定」と呼ばれています。この協定を労働者の代表(労働組合または労働者の過半数を代表する者)と締結し、労働基準監督署に届け出ることで、初めて法定労働時間を超える時間外労働(残業)や法定休日労働(休日出勤)が適法となるのです。
つまり、36協定を結ばずに残業や休日出勤をさせることは、法律違反になってしまう可能性があるということです。知らなかったでは済まされない、非常に重要なルールなのです。
36協定で定めるべきこと【ここがポイント!】
では、36協定では具体的にどのようなことを定める必要があるのでしょうか?主な項目を見ていきましょう。
- 時間外労働・休日労働をさせる必要のある具体的な理由: なぜ残業や休日出勤が必要なのか、具体的に記載します。(例:「繁忙期における受注増加への対応」「臨時のシステムトラブル対応」など)
- 対象となる業務の種類: どのような業務で残業・休日出勤が発生する可能性があるのかを明確にします。(例:「製造業務」「営業業務」「事務処理」など)
- 対象となる労働者の数: その業務に従事する労働者の数を記載します。
- 時間外労働の上限時間: これが一番重要です!
- 原則: 1ヶ月45時間、1年360時間が上限となります。
- 臨時的な特別な事情がある場合(特別条項付き36協定): 原則の上限を超えて働いてもらう必要がある場合に、「特別条項」を設けることができます。ただし、これにも厳しいルールがあります。
- 時間外労働は年720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計について、「2ヶ月平均」「3ヶ月平均」「4ヶ月平均」「5ヶ月平均」「6ヶ月平均」が全て1月あたり80時間以内
- 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6ヶ月が限度
- 特別条項を発動する場合の具体的な理由、労働者への健康・福祉確保措置なども定める必要があります。
- 有効期間: 36協定の有効期間を定めます(通常は1年間)。毎年更新が必要です。
特に「時間外労働の上限時間」は、働き方改革関連法によって上限規制が厳格化されました。違反すると罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科される可能性もあるため、正確な理解と運用が不可欠です。
36協定の手続き【どうすればいいの?】
36協定の効力を発生させるためには、適切な手続きを踏む必要があります。
- 労働者代表の選出
- 労働組合がある場合:その労働組合
- 労働組合がない場合:労働者の過半数を代表する者(投票や挙手などで民主的な方法により選出された者)
- ※会社側が一方的に指名したり、管理監督者が代表になったりすることはできません。
- 労使での協議・合意: 選出された労働者代表と、36協定の内容について十分に協議し、合意します。
- 協定書の作成: 合意した内容を「時間外労働・休日労働に関する協定届」(様式第9号など)にまとめ、労使双方で記名・押印(または署名)します。
- 労働基準監督署への届出: 作成した協定届を、管轄の労働基準監督署に提出します。
- ※電子申請(e-Gov)も可能です。
- 届出の際には、協定の効力が発生する「起算日」がいつになっているか、意図した期間と合っているかを必ず確認しましょう。起算日を間違えると、意図しない期間に時間外労働が違法となってしまう可能性があります。
- 従業員への周知: 締結した36協定の内容を、事業場の見やすい場所に掲示したり、書面を交付したりするほか、社内の共有ドライブなど、従業員がいつでもアクセスできる場所にデータを格納しておくといった方法で、従業員に周知します。
この一連の手続きを経て、初めて36協定は有効となり、時間外労働や休日労働をさせることが可能になります。毎年、有効期間が切れる前に更新手続き(再度の協議・作成・届出・周知)が必要な点も忘れないでください。
36協定の運用で注意すべきこと
- 上限時間の遵守: 協定で定めた上限時間を超えないよう、日々の労働時間管理が重要です。
- 健康への配慮: 特に特別条項を適用する場合は、長時間労働になりがちです。従業員の健康状態に十分配慮し、必要に応じて医師による面接指導などの措置を講じる義務があります。
- 記録の保存: 労働時間の記録(タイムカード、勤怠管理システムのログなど)は適切に保存しましょう。
- 労働者代表の選出手続き: 適正な手続きで選出されているか、毎年確認しましょう。
面倒な36協定の手続き、専門家にお任せしませんか?
ここまで読んで、「やっぱり36協定って複雑で大変そう…」と感じた経営者の方もいらっしゃるかもしれません。
- 自社の状況に合った協定内容になっているか不安
- 労働者代表の選出方法が分からない
- 特別条項の運用ルールが難しい
- 毎年、労働基準監督署へ届け出るのが手間だ
- そもそも、他の労務管理も手が回っていない
そんなお悩みは、私たち社労士事務所ぽけっとにお任せください!
私たち社会保険労務士は、労働法規の専門家です。貴社の状況を丁寧にヒアリングし、法改正にも対応した適切な36協定の作成から、労働基準監督署への届出代行まで、責任をもってサポートいたします。
当事務所にご依頼いただくメリット
- 法令遵守: 最新の法律に基づいた、適切な36協定を作成・届出できます。
- リスク回避: 届出漏れや内容の不備による法違反のリスクを防ぎます。
- 時間と手間の削減: 複雑な手続きは専門家にお任せいただき、経営者様は本業に専念できます。
- 労務相談: 36協定だけでなく、日々の労務管理に関するご相談にも対応します。
36協定は、従業員に安心して働いてもらい、会社を守るための重要なルールです。少しでも不安や疑問があれば、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。初回のご相談は無料です。
まとめ
今回は、経営者が知っておくべき「36協定」について、その内容と手続き、注意点を解説しました。
- 法定労働時間を超える残業や休日出勤には「36協定」の締結・届出が必須!
- 時間外労働には厳しい上限規制がある!
- 特別条項付き協定にはさらに細かいルールがある!
- 毎年、適切な手続き(協議・作成・届出・周知)が必要!
コンプライアンス(法令遵守)がますます重視される現代において、36協定の適切な運用は企業経営の基本です。
「ウチは大丈夫かな?」と思ったら、すぐに専門家である社労士にご相談ください。私たち社労士事務所ぽけっとが、貴社の健全な発展を全力でサポートいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください!