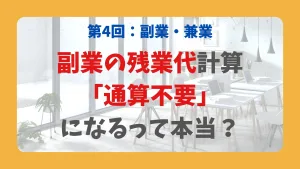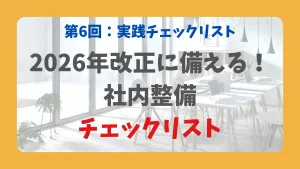【特例見直し案】週44時間ルールは廃止へ?40時間統一への議論(全6回連載・第5回)
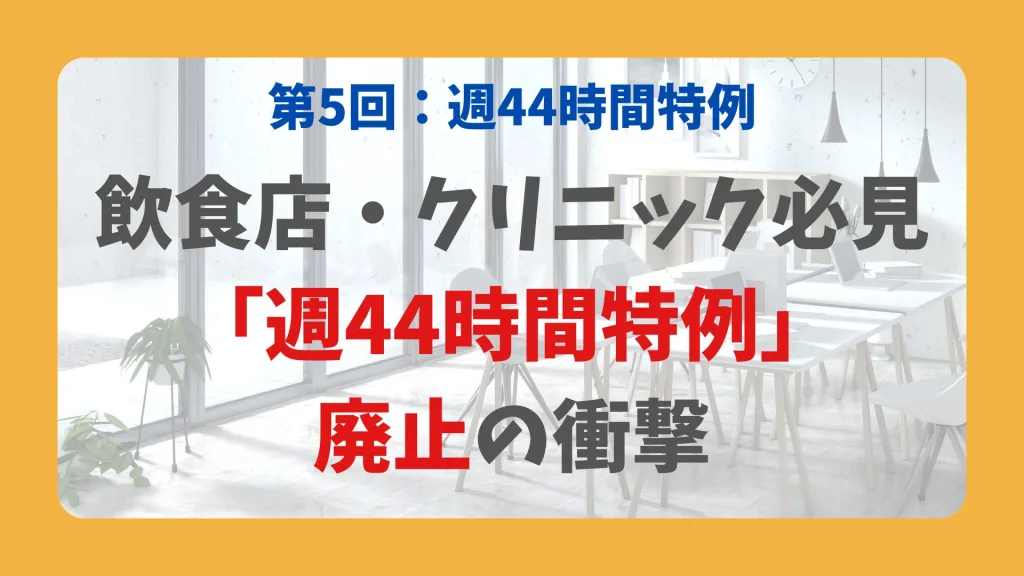
※本記事に関する重要なお知らせ※
本記事は、2025年11月に厚生労働省「労働基準関係法制研究会」より公表された報告書の内容に基づき執筆しています。
解説内容は現時点での「提言」や「検討の方向性」であり、決定事項ではありません。今後の法改正議論の参考としてお読みください。
小規模な飲食店、美容室、クリニックなどの経営者様へ。
「うちは10人未満だから、週44時間まで働いてもらっても残業代はかからない」
この常識が、近いうちに覆される可能性があります。
2026年改正の議論の中で、「週44時間特例措置」の廃止・見直しが重要な論点として挙がっています。
今回は、この特例が廃止された場合のインパクトと対策について解説します。
1. 週44時間特例措置とは?(現状)
労働基準法では、原則として法定労働時間を「1日8時間・週40時間」と定めています。
これを超えると残業代(割増賃金)が必要です。
しかし、例外として、「商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業」の4業種で、かつ「常時使用する労働者が10人未満」の事業場については、法定労働時間を「週44時間」とする特例が認められています。
これにより、例えば「月〜金曜:8時間勤務、土曜:半日(4時間)勤務」で合計44時間働かせても、現状は残業代が発生しません。
多くの小規模店舗やクリニックが、このルールに基づいてシフトを組んでいます。
2. 報告書の内容:「週40時間への統一」を提言
研究会の報告書では、この特例措置について厳しい見直し案が示されました。
理由は以下の通りです。
- 労働者の健康確保の観点からは、事業規模に関わらず労働時間は短い方が望ましい。
- 10人以上の事業場や、他業種との公平性が保たれていない。
これらの理由から、報告書は「本特例を廃止し、原則通り週40時間とすることが適当である」と提言しています。
急激な変化を避けるために一定の猶予期間が設けられる可能性はありますが、「将来的には廃止」という方向性は明確です。
3. 実現した場合の経営への具体的インパクト
もし特例が廃止され、「週40時間」に統一された場合、経営にどのような影響があるでしょうか。
- 残業代コストの増加
今まで週44時間働かせていた場合、差分の「4時間」がすべて時間外労働(残業)になります。
月間に換算すると、従業員1人あたり約16時間〜17時間分の割増賃金が新たに発生します。 - 営業時間の見直し
コスト増を避けるためには、労働時間を減らす必要があります。
その結果、営業時間を短縮したり、診療時間を短くしたりといった対応を迫られる可能性があります。
4. 今からできる対策:変形労働時間制の活用
特例廃止が決まってから慌てるのではなく、今からできる対策として「1ヶ月単位の変形労働時間制」の導入・活用をお勧めします。
変形労働時間制とは、月単位で平均して週40時間以内になれば良いという制度です。
これを使えば、「忙しい週は44時間働くけれど、暇な週は36時間にする」といったメリハリのあるシフトを組むことで、トータルの残業代を抑えることが可能です。
(※導入には就業規則の整備や労使協定が必要です)。
【まとめ】特例依存からの脱却を
週44時間特例は、あくまで「例外」でした。
時代の流れは、事業規模にかかわらず「労働時間の短縮」に向かっています。
この議論をきっかけに、今の業務フローを見直し、「短い時間で同じ成果を出す(生産性を上げる)」経営へシフトする準備を始めましょう。
最終回となる次回は、これまでの議論を総括し、2026年の改正に向けて今すぐ取り組める「社内整備チェックリスト」を公開します。
【免責事項】
本記事は、2025年12月7日時点で公表されている厚生労働省「労働基準関係法制研究会報告書」等の情報に基づき作成しています。記事内で紹介している法改正の方向性や内容は現時点での提言であり、今後の国会審議等を経て変更される可能性があります。本記事の情報を用いて行う一切の行為について、当事務所は何ら責任を負うものではありません。具体的な実務対応にあたっては、最新の公式情報を確認するか、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。