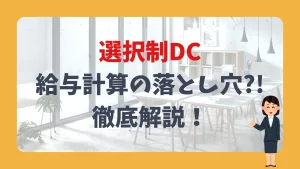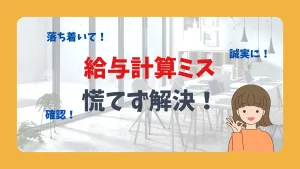従業員持株会の給与計算、キホンと注意点を分かりやすく解説!

「従業員のやる気を引き出したい」「長く会社に貢献してほしい」…そうお考えの事業主様にとって、従業員持株会は魅力的な制度ですよね。従業員が自社の株を持つことで、経営への参画意識を高め、株価上昇への貢献意欲を引き出す効果が期待できます。
しかし、いざ導入するとなると、「給与計算ってどうやるの?」「税金や社会保険料の扱いは?」といった疑問も出てくるのではないでしょうか。
この記事では、事業主様に向けて、従業員持株会を導入した際の給与計算の基本的な考え方と、間違いやすいポイント、注意点を分かりやすく解説します。従業員持株会をスムーズに運営し、そのメリットを最大限に活かすために、ぜひ参考にしてください。
そもそも従業員持株会とは?
従業員持株会とは、従業員が毎月の給与や賞与から一定額を拠出し、自社株を共同で購入・保有する制度です。多くの企業では、従業員の拠出額に対して会社が「奨励金」を上乗せし、従業員の資産形成を支援しています。
従業員にとってのメリット
- 少額から自社株に投資できる
- 奨励金による有利な資産形成
- 株価上昇や配当による利益享受の可能性
- 経営への参画意識向上
会社にとってのメリット
- 従業員のモチベーション向上、エンゲージメント強化
- 長期的な人材確保、リテンション効果
- 安定株主の確保
このように、従業員と会社双方にメリットのある制度ですが、給与計算においては、拠出金の控除や奨励金の扱いなど、いくつか押さえておくべきポイントがあります。
従業員持株会の給与計算:基本の流れ
従業員持株会の掛け金(拠出金)は、通常、毎月の給与から天引き(控除)されます。給与計算の基本的な流れは以下のようになります。
- 総支給額の計算: 基本給、各種手当などを合計して総支給額を算出します。
- 社会保険料の計算・控除: 総支給額(標準報酬月額)を基に健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料(該当者のみ)を計算し、控除します。
- 雇用保険料の計算・控除: 総支給額に雇用保険料率を掛けて計算し、控除します。
- 所得税(源泉徴収税)の計算・控除: 社会保険料控除後の金額を基に、所得税を計算し、控除します。
- 住民税の控除: 前年の所得に基づいて決定された住民税額を控除します。(特別徴収の場合)
- その他の控除: 従業員持株会拠出金、財形貯蓄、労働組合費などを控除します。
- 差引支給額(手取り額)の計算: 総支給額から全ての控除額を差し引いて、最終的な手取り額を計算します。
ポイントは、従業員持株会の拠出金が控除されるタイミングです。多くの場合、所得税や住民税、社会保険料などが計算された後に、その他の控除項目として扱われます。
給与計算における重要ポイントと注意点
従業員持株会の給与計算で特に注意すべき点を詳しく見ていきましょう。
1. 拠出金の控除:所得税・社会保険料への影響は?
従業員が給与から拠出する持株会の掛け金は、原則として所得税や社会保険料の計算対象から除外されません。
- 所得税: 拠出金は、所得税計算前の「課税対象額」から控除されるものではありません。つまり、拠出する金額分、手取りは減りますが、所得税額が直接減るわけではない点に注意が必要です。(給与から天引きされる前に、すでに所得税の計算基礎に含まれています)
- 社会保険料: 健康保険料や厚生年金保険料の計算基礎となる「標準報酬月額」は、持株会拠出金を控除する前の給与額で決定されます。したがって、拠出金が社会保険料の計算に影響を与えることは基本的にありません。
- 雇用保険料: 雇用保険料も同様に、拠出金を控除する前の総支給額を基に計算されます。
よくある誤解: 「給与から天引きされるのだから、税金や社会保険料が安くなるのでは?」と思われがちですが、従業員の拠出金に関しては、原則としてそのような効果はありません。
2. 会社からの「奨励金」の扱い
従業員の拠出に対して会社が上乗せする「奨励金」は、給与計算上どのように扱われるのでしょうか?
この奨励金は、多くの場合、従業員に対する「給与所得」として扱われます。つまり、
- 所得税の課税対象となる
- 社会保険料の算定基礎に含まれる可能性がある
ということです。
奨励金を支給する場合、その金額を従業員の総支給額に加算した上で、社会保険料や所得税を計算する必要があります。奨励金の分だけ、従業員の税金や社会保険料の負担が増える可能性があることを、事前に従業員へ説明しておくと丁寧でしょう。
注意点: 奨励金の支給形態や持株会の規約によっては、扱いが異なるケースも考えられます。不明な点は、税理士や社会保険労務士などの専門家にご確認ください。
3. 拠出額の変更・休止・退会時の処理
従業員から拠出額の変更や、拠出の休止、持株会からの退会などの申し出があった場合は、給与計算システムへの反映を速やかに行う必要があります。
- 変更・休止: 変更・休止が適用される給与計算期間を確認し、間違いなく控除額を修正します。
- 退会: 退会に伴う拠出金の最終控除や、保有株式の精算手続き(証券会社との連携など)が必要になります。退会手続きのフローを明確にしておきましょう。
これらの手続きが遅れたり、誤ったりすると、給与の支払いミスにつながり、従業員との信頼関係を損なう原因にもなりかねません。
ミスを防ぐためにできること
従業員持株会の給与計算を正確に行うためには、以下の点が重要です。
- 給与計算ソフトの活用: 従業員持株会の控除や奨励金の計算に対応した給与計算ソフトを利用することで、計算ミスや処理漏れのリスクを大幅に減らすことができます。
- 担当者間の情報共有: 経理・人事・総務など、関連部署間での情報共有体制を確立し、拠出額の変更や異動・退職などの情報を確実に連携できるようにします。
- 規約・ルールの明確化: 持株会の規約や、拠出・変更・退会に関する社内ルールを明確にし、従業員にも周知徹底します。
- 専門家への相談: 不明な点や複雑なケースについては、税理士や社会保険労務士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが賢明です。特に、奨励金の扱いや制度設計については、専門家の意見を参考にすることをおすすめします。
【まとめ】正確な給与計算で、従業員持株会を成功させよう!
従業員持株会は、従業員の資産形成を支援し、エンゲージメントを高める有効な手段です。しかし、その効果を最大限に引き出すためには、正確な給与計算が大前提となります。
特に、従業員拠出金は所得税・社会保険料の計算基礎から控除されないこと、会社からの奨励金は給与所得として扱われる可能性があること、この2点は重要なポイントです。
給与計算ソフトの活用や専門家への相談も視野に入れながら、ミスのない、スムーズな運用体制を構築しましょう。正確な給与計算を通じて、従業員との信頼関係を深め、従業員持株会制度をより良いものにしていきましょう。
毎月の給与計算、専門家に任せてみませんか?
従業員持株会のような制度を導入すると、給与計算はさらに複雑になります。毎月の社会保険料や税金の計算、法改正への対応など、担当者様の負担は少なくありません。
「計算ミスがないか不安」「もっとコア業務に集中したい」…そんなお悩みは、私たち社労士事務所ぽけっとにお任せください!
給与計算のプロフェッショナルとして、正確かつ迅速な処理はもちろん、従業員持株会に関するご相談にも丁寧に対応いたします。アウトソーシングで、貴社の負担軽減とコンプライアンス遵守をサポートします。
まずはお気軽にご相談ください。