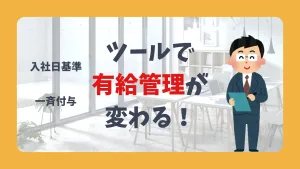現物給与とは?給与計算・労務管理上の重要ポイントを解説!

「現物給与って何?」
「給与計算や労務管理でどう扱えばいいの?」
そんな疑問をお持ちの事業主様も多いのではないでしょうか。従業員のモチベーションアップや福利厚生の充実にもつながる現物給与ですが、その取り扱いには注意が必要です。特に給与計算においては、社会保険料に関わる重要なポイントがいくつか存在します。
この記事では、押さえておくべき現物給与の基本から、給与計算・労務管理上の具体的な注意点、さらにはメリット・デメリットまで、社会保険労務士の視点から分かりやすく解説します。この記事を読めば、現物給与に関する疑問がスッキリ解消し、適切な事務処理が行えるようになるはずです。
現物給与とは? 具体例を交えて解説
現物給与とは、従業員に対して金銭以外の「モノ」や「サービス」で支給される給与のことです。労働基準法第24条では、賃金は原則として通貨で支払うこととされています(賃金の通貨払いの原則)。しかし、法令に別段の定めがある場合や、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)がある場合には、通貨以外のもの(現物)で支払うことが認められています。
現物給与は、従業員の生活をサポートしたり、企業文化を形成したりする上で有効な手段となり得ます。
現物給与の主な例
具体的にどのようなものが現物給与にあたるのでしょうか。代表的な例を見てみましょう。
- 食事の支給・補助: 社員食堂での食事提供や、仕出し弁当の補助など。
- 社宅・寮の貸与: 従業員に対して、相場よりも安い家賃で住居を提供する。
- 通勤手当(定期券など): 通勤用の定期券を現物で支給する。
- 自社製品・サービスの割引: 自社の製品やサービスを従業員割引で提供する。
- 記念品・永年勤続表彰品: 創業記念品や、長年勤務した従業員への表彰品など。
- レクリエーション施設の利用: 保養所やスポーツジムなどを無料で利用させる。
これらの他にも、会社が従業員に提供する経済的利益は、原則として現物給与に該当する可能性があります。
事業主にも従業員にも影響!現物給与のメリット・デメリット
現物給与は、事業主側・従業員側双方にメリットとデメリットがあります。導入を検討する際には、これらを総合的に比較することが大切です。
事業主側のメリット
- 福利厚生の充実による従業員満足度の向上: 魅力的な現物給与は、従業員の満足度を高め、人材の確保や定着につながります。
- 企業文化の醸成: 会社独自の現物給与は、企業文化を育む一助となります。
事業主側のデメリット
- 給与計算・事務処理の複雑化: 現物給与の評価や社会保険料算定への影響など、事務処理が煩雑になる可能性があります。
- コスト管理の難しさ: 現物給与の種類によっては、コスト管理が難しくなることがあります。
- 公平性の確保: 全ての従業員が平等に利益を享受できるよう、制度設計に配慮が必要です。
従業員側のメリット
- 実質的な生活サポート: 食事や住居の補助など、実質的な生活サポートを受けられる場合があります。
- 割安または無料でサービスを受けられる: 市場価格よりも安く、あるいは無料でモノやサービスを利用できます。
従業員側のデメリット
- 換金性・選択の自由度が低い: 現金給与と比べて、必要な時に換金したり、自由に使い道を選んだりすることが難しい場合があります。
- 所得税・住民税の課税対象となる場合がある: 現物給与の種類や価額によっては、税法上の給与として扱われ、所得税や住民税が増えることがあります。この点については、税理士などの専門家にご確認ください。
【最重要】現物給与の給与計算・労務管理 押さえるべきポイント
現物給与を導入する上で最も注意すべきは、給与計算と労務管理の取り扱いです。ここでは、社会保険労務士の観点から押さえておきたいポイントを解説します。
ポイント①:現物給与の「価額」を適切に評価する
現物給与は、金銭ではないため、その「価額」を金銭に見積もる必要があります。この評価額が、社会保険料の計算基礎となります。
価額の評価方法は、原則として「その物や権利を他から購入したり、利用したりする場合にかかる費用(時価)」となります。ただし、厚生労働大臣が定める「現物給与の価額」(都道府県ごとに定められています)がある場合は、それに基づいて評価します。例えば、食事や住宅の利益については、この定めが適用される場合があります。
食事の現物給与価額の考え方(社会保険): 食事を現物給与として支給する場合、社会保険料の算定基礎に含めるべき価額は、原則として厚生労働大臣が定める基準によります。この基準は、都道府県ごとに定められており、食事の種類(例:昼食のみ、朝昼夕の3食など)や提供形態によって、1人1日あたりまたは1ヶ月あたりの標準価額が示されています。
- 従業員から食事代を徴収している場合
- 原則(従業員負担が著しく低い場合を含む): 従業員が負担している金額が、厚生労働大臣が定める価額の3分の2未満である場合は、厚生労働大臣が定める価額から従業員が負担している金額を差し引いた額が、現物給与としての報酬額となります。この「3分の2基準」の解釈と具体的な計算については、必ず管轄の年金事務所や社会保険労務士にご確認ください。
- 例外(従業員負担が一定以上の場合): 従業員が厚生労働大臣の定める価額の3分の2以上を負担している場合は、現物給与としての報酬額は0円となります(つまり、会社からの経済的利益はないものとして扱われます)。
- 従業員から食事代を徴収していない場合(無償支給): 厚生労働大臣が定める価額そのものが、現物給与としての報酬額となります。
重要なのは、所得税法上の食事の非課税基準(従業員負担が半分以上で、かつ会社負担が月額3,500円以下など)とは別に、社会保険上の評価基準が存在するということです。所得税法上非課税であっても、社会保険上は報酬として扱われるケースがありますので、混同しないように注意が必要です。
具体的な価額や詳細な取り扱いについては、日本年金機構のウェブサイトや管轄の年金事務所、または社会保険労務士にご確認いただくのが確実です。
ポイント②:社会保険料の算定基礎に含める
現物給与は、原則として社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料)の算定基礎となる「報酬」に含まれます。これを「報酬月額」に含めて標準報酬月額を決定し、保険料を計算します。
これを怠ると、社会保険料の徴収漏れとなり、後日、遡って徴収される可能性があります。事業主負担分だけでなく、従業員負担分も発生するため、正確な処理が必要です。
注意点:所得税法上の評価額と社会保険上の評価額 現物給与の評価について、所得税法上の評価額と社会保険上の評価額は必ずしも一致するわけではありません。社会保険料の算定においては、厚生労働大臣が定める価額を優先して適用する必要がある点に注意が必要です。
補足:現物給与価額の改正と固定的賃金の変動 厚生労働大臣が定める現物給与の価額が改正された場合、これは社会保険における「固定的賃金の変動」に該当します。その結果、他の固定的賃金の変動(昇給・降給など)と同様に、一定の条件(標準報酬月額に2等級以上の差が生じるなど)を満たせば、随時改定(月額変更届の提出)の対象となる可能性があります。現物給与の価額の改正があった場合には、随時改定の要件に該当しないか確認することが重要です。
ポイント③:就業規則や賃金規程への明記と従業員への説明
現物給与を支給する場合は、その種類、評価方法、支給基準などを就業規則や賃金規程に明記しておくことが強く推奨されます。これにより、労使間の認識の齟齬を防ぎ、トラブルを未然に防止することができます。
また、従業員に対して、現物給与が給与の一部であること、社会保険料の算定に含まれること、場合によっては税法上の課税対象となる可能性があることなどを丁寧に説明し、理解を得ることが重要です。特に、税法上の取り扱いについては、従業員自身が税理士に相談するか、会社として税理士に確認するなどして、誤解が生じないようにすることが望ましいでしょう。
ポイント④:労働協約または労使協定の締結
前述の通り、賃金の現物支給は、労働協約に定めるか、労使協定を締結した場合に限り認められます。現物給与の導入・変更にあたっては、これらの手続きを適切に行うことが法令遵守の観点から不可欠です。
間違いやすいケースと対策(労務管理の観点から)
- ケース1:社宅の貸与における社会保険上の評価 従業員から徴収する家賃が、社会保険上の評価額(厚生労働大臣が定める現物給与の価額など)と著しく乖離している場合、差額が報酬として扱われ、社会保険料の算定に影響を与える可能性があります。適切な評価と処理が必要です。
- ケース2:食事補助の取り扱い 食事の提供や補助についても、社会保険上の評価額に基づいて報酬に含めるか否かを判断する必要があります。所得税法上の非課税措置とは別に、社会保険上の取り扱いを確認しましょう。特に、従業員負担額が厚生労働大臣の定める価額の3分の2未満でないか注意が必要です。
- ケース3:労働条件の不利益変更 既存の金銭給与の一部を現物給与に置き換えるような場合、労働条件の不利益変更にあたる可能性があります。その場合は、従業員の個別の同意を得るなど、慎重な手続きが求められます。
これらのケースに注意し、不明な点は社会保険労務士にご相談ください。
現物給与に関するご相談・お問い合わせ
現物給与の取り扱いは、社会保険や労務管理において専門的な知識が求められ、複雑な判断が必要となる場面が少なくありません。特に、現物給与の価額評価や社会保険料への影響、就業規則への適切な記載方法など、個別のケースに応じた対応が重要となります。
「自社の場合は具体的にどう対応すれば良いのか」「この現物給与の扱いで間違いないか確認したい」「従業員への説明をどのように行えば良いか」など、現物給与に関する疑問やお困り事がございましたら、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。
経験豊富な社会保険労務士が、貴社の状況を丁寧にヒアリングし、法令に基づいた適切なアドバイスとサポートをご提供いたします。円滑な現物給与制度の運用と、より良い職場環境づくりのお手伝いをさせていただきます。