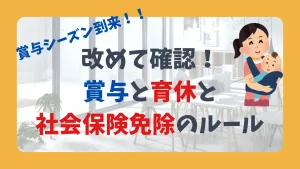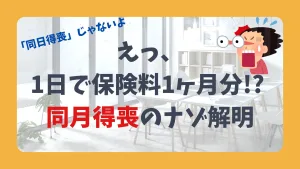人事制度変更で手当増減!社会保険の月額変更、どう判断する?注意点まとめ
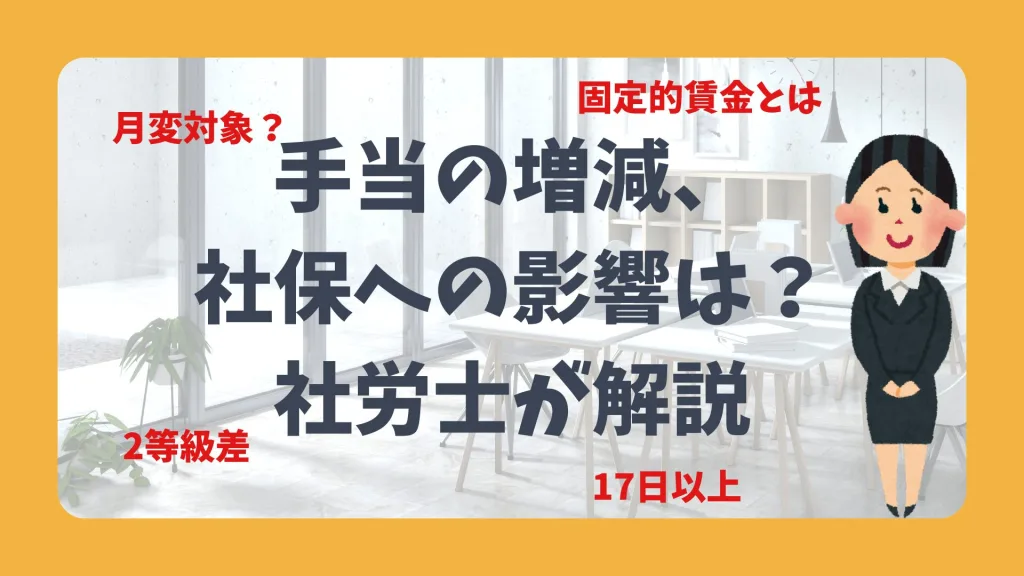
こんにちは!社労士事務所ぽけっとです。 日々の企業経営、人事労務管理、本当にお疲れ様です。
さて、企業の成長や働き方の変化に合わせて、人事制度を見直すことは珍しくありません。その際、「特定の役職手当を増額し、代わりに調整手当を減額する」といったように、手当の種類や金額が変更になるケースがありますよね。
このような人事制度の変更に伴う手当の増減があった場合、従業員の社会保険料に影響はあるのでしょうか?特に「月額変更」という手続きが必要になるのかどうか、判断に迷う人事担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、そんな人事制度変更に伴う手当の増減があった場合の、社会保険の月額変更(随時改定)の判断基準と注意点について、分かりやすく解説していきます。
そもそも社会保険の月額変更(随時改定)とは?
「なんだか難しそう…」と感じるかもしれませんが、まずは基本から押さえましょう。
標準報酬月額とは?
従業員さんが受け取る給与などを一定の範囲(等級)で区分したもので、毎月の健康保険料や厚生年金保険料、そして将来受け取る年金額などを計算する際の基礎となる金額です。
月額変更(随時改定)とは?
この標準報酬月額は、毎年1回、7月1日現在の給与を基に見直されます(これを「定時決定」といいます)。しかし、定時決定を待たずに、給与額に大きな変動があった場合に、実態に合わせて標準報酬月額を見直す手続きがあります。これが「月額変更(随時改定)」です。
なぜ月額変更が必要なの?
月額変更を行わないと、実際の給与額と標準報酬月額が大きくかけ離れてしまい、従業員さんが本来支払うべき保険料よりも多く(または少なく)支払ってしまう、あるいは将来受け取る年金額が実態と合わない、といった不公平が生じる可能性があります。そのため、適正な保険料負担と給付のために月額変更は重要な手続きなのです。
人事制度変更による手当の増減と月額変更の判断基準
では、本題の人事制度変更により、ある手当が増加し、別のある手当が減少した場合、月額変更は必要になるのでしょうか?
月額変更(随時改定)の対象となるのは、以下の3つの条件すべてに該当した場合です。
- 昇給・降給などにより「固定的賃金」に変動があったこと。
- 固定的賃金が変動した月から継続した3ヶ月間に支払われた給与(報酬)の平均月額に該当する標準報酬月額と、これまでの標準報酬月額との間に「2等級以上の差」が生じたこと。
- 固定的賃金が変動した月から継続した3ヶ月間の「支払基礎日数」がすべて17日以上(短時間労働者の場合は11日以上)であること。
これらの条件を一つずつ見ていきましょう。
1. 「固定的賃金」の変動とは?
今回のケースで最も重要なのが、この「固定的賃金」の変動に当たるかどうかです。
固定的賃金とは?
勤務時間や業績に関わらず、毎月決まって支給される賃金のことです。 具体例としては、
- 基本給(月給、週給、日給など)
- 役職手当
- 家族手当
- 住宅手当
- 通勤手当(月額固定の場合)
- 勤務地手当
- 資格手当 など
が挙げられます。
人事制度変更で手当が増減した場合の考え方
ご質問の「ある手当が増加し、ある手当が減少した場合」ですが、これは固定的賃金の変動に該当する可能性が高いです。
重要なのは、個々の手当の増減ではなく、固定的賃金の「総額」に変動があったかどうかで判断します。
- 例1:営業手当(固定的)が20,000円増額、調整手当(固定的)が10,000円減額された場合 この場合、固定的賃金の総額としては「+10,000円」の変動があったとみなします。
- 例2:職務手当(固定的)が10,000円増額、技能手当(固定的)が20,000円減額された場合 この場合、固定的賃金の総額としては「-10,000円」の変動があったとみなします。
- 例3:A手当(固定的)が10,000円増額、B手当(固定的)が10,000円減額された場合 この場合、固定的賃金の総額としては「変動なし」となります。この場合は、月額変更の最初の要件である「固定的賃金の変動」には該当しません。
このように、人事制度変更によって複数の手当が増減した場合は、それらを合算して固定的賃金全体の変動額を把握する必要があります。
2. 「2等級以上の差」の判定
固定的賃金に変動があった場合、次に、変動後の給与(残業代などの非固定的賃金も含む)の3ヶ月平均額と、これまでの標準報酬月額を比較します。
具体的には、
- 固定的賃金が変動した月から3ヶ月間に支払われた給与(税引前の総支給額)の平均額を計算します。
- その平均額を「標準報酬月額等級表」に当てはめて、改定後の新しい標準報酬月額を決定します。
- これまでの標準報酬月額と、新しい標準報酬月額の等級を比較し、そこに2等級以上の差があるかを確認します。
注意点:固定的賃金と非固定的賃金の兼ね合い
ここで注意したいのは、固定的賃金が上がったとしても、同時に残業時間が大幅に減るなどして非固定的賃金(残業手当、インセンティブなど)が大きく減少した場合、結果として3ヶ月の平均給与額が下がり、2等級以上の差が生じない、あるいは逆に等級が下がってしまうケースです。
原則として、固定的賃金が上がった(下がった)ことにより、その結果として報酬全体の平均も上がり(下がり)、2等級以上の差が生じた場合に月額変更の対象となります。
- 固定的賃金は増額したが、非固定的賃金が大幅に減少し、結果として報酬全体の平均が下がり、2等級以上の差が生じた場合 →この場合は、月額変更の対象とはなりません。
- 固定的賃金は減額したが、非固定的賃金が大幅に増加し、結果として報酬全体の平均が上がり、2等級以上の差が生じた場合 →この場合も、月額変更の対象とはなりません。
判断に迷う場合は、必ず年金事務所や社労士にご相談ください。
3. 「支払基礎日数」の確認
3つ目の要件は、固定的賃金が変動した月から継続した3ヶ月間の「支払基礎日数」がすべて17日以上であることです。短時間労働者の場合は11日以上となります。
支払基礎日数とは、給与計算の対象となる日数のことで、月給者の場合は暦日数、日給者や時給者の場合は出勤日数となります。
この3ヶ月間のうち、1ヶ月でも支払基礎日数が17日(または11日)未満の月があれば、他の2つの要件を満たしていても月額変更の対象とはなりません。
月額変更の手続きと注意点
上記の3つの要件をすべて満たした場合、月額変更の手続きが必要になります。
手続きの流れ
- 固定的賃金の変動発生: 人事制度の変更が適用され、給与に反映される。
- 変動後3ヶ月間の給与支払い: 変動が反映された月から3ヶ月間、給与を支払います。
- 報酬平均額の算出と等級確認: 3ヶ月の平均給与額を算出し、標準報酬月額等級表で2等級以上の差があるかを確認します。
- 「被保険者報酬月額変更届」の作成・提出: 該当する従業員について「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届」を作成し、速やかに管轄の年金事務所または健康保険組合に提出します。
- 新しい標準報酬月額の適用: 原則として、固定的賃金が変動した月から4ヶ月目の社会保険料から、新しい標準報酬月額が適用されます。
特に注意すべきポイント
- 起算月: 固定的賃金の変動が「実際に給与に反映された月」が起算月となります。例えば、4月から人事制度が変更になっても、給与への反映が5月支払い分からであれば、5月が起算月です。
- 遡及昇給・降給があった場合: 遡及して差額が支払われた場合、その差額は月額変更の算定には含めず、変動後の(本来の)給与額で判断します。ただし、遡及して固定的賃金自体が変更された場合は、その変更後の金額で判断する必要があり、判断が複雑になることがあります。
- 同月内に複数の固定的賃金変動があった場合: 例えば、月の途中で昇給し、さらに別の手当が新設されたような場合、それぞれの変動を個別にみるのではなく、その月の固定的賃金の総額の変動で判断します。
- 1等級差でも届出が必要な例外ケース: 標準報酬月額の等級には上限と下限があります。現在の標準報酬月額が上限に近い等級や下限に近い等級の場合、1等級の変動でも月額変更の対象となる例外的なケースがあります。
Q&A:こんな時どうなる?
Q1: 人事制度変更はなく、残業代だけで給与が3ヶ月間大幅に増えました。月額変更の対象になりますか?
A1: いいえ、残業代は「非固定的賃金」ですので、残業代だけの変動では月額変更の対象にはなりません。月額変更は、あくまで「固定的賃金」の変動がきっかけとなります。ただし、固定的賃金の変動があり、その結果として非固定的賃金も含めた報酬総額が大きく変わった場合には対象となる可能性があります。
Q2: 人事制度変更で、手当の「名称」が変わっただけで、支給される手当の「総額」は変わりませんでした。月額変更は必要ですか?
A2: 手当の名称変更のみで、固定的賃金の総額に変動がなければ、月額変更の最初の要件である「固定的賃金の変動」には該当しないため、月額変更の対象にはなりません。
Q3: うっかり月額変更の手続きを忘れてしまいました。どうなりますか?
A3: 気づいた時点で速やかに手続きを行う必要があります。手続きが遅れると、遡って社会保険料の追徴(不足分を支払う)や還付(払い過ぎ分が戻る)が発生する可能性があります。また、年金事務所から指摘を受けることもあります。従業員さんの不利益に繋がる可能性もあるため、正確な手続きが重要です。
Q4: 固定的賃金の変動が月途中からでした。例えば、4月16日付で基本給が昇給し、4月分の給与は新しい基本給を基に日割りで計算・支給され、5月分の給与から満額で支給される場合、月額変更の起算月はいつになりますか?
A4: 昇給後の新しい基本給(単価)で計算された給与が、まる1ヶ月分の実績として確保され支払われた月を、3ヶ月の最初の月(起算点)として判断します。例:4月16日に昇給(月末締め翌月末払い)の場合、4月の昇給分が含まれる5月末払いの給与では1ヶ月分の実績が確保できておらず、5月分の給与(新単価でまる1ヶ月分計算)が支払われる6月末を3ヶ月の起算点(最初の月)とします。
複雑な判断は専門家(社労士)にご相談を
ここまで、人事制度変更に伴う手当の増減と月額変更について解説してきましたが、実際の運用では「このケースは固定的賃金の変動に当たるの?」「うちの会社の人事制度だとどう判断すればいい?」など、判断に迷う場面も少なくないと思います。
特に、複数の手当が複雑に絡み合って変動する場合や、給与体系が特殊な場合などは、慎重な判断が求められます。
そのような時は、ぜひ私たち社労士にご相談ください。
社労士に相談するメリット
- 正確な判断: 個別の状況を詳しくお伺いし、法令に基づいて月額変更の要否を正確に判断します。
- 手続きの代行: 面倒で時間のかかる月額変更届の作成・提出を代行し、人事担当者様の負担を軽減します。
- 法令改正への対応: 目まぐるしく変わる法令にも迅速に対応し、常に適正な労務管理をサポートします。
- コンプライアンス強化: 正しい社会保険手続きは、企業のコンプライアンス遵守に不可欠です。従業員が安心して働ける職場環境づくりにも繋がります。
- 潜在的なリスクの低減: 月額変更だけでなく、労務管理全般に関する潜在的なリスクを早期に発見し、対策をご提案することも可能です。
まとめ
人事制度の変更は、企業にとって大きな変化点です。それに伴う手当の増減があった場合、社会保険の月額変更が必要になるケースがあることをご理解いただけたでしょうか。
月額変更の3つの要件(固定的賃金の変動、2等級以上の差、支払基礎日数)を正しく理解し、適切なタイミングで手続きを行うことが非常に重要です。
「うちの会社の場合はどうなんだろう?」 「手続きが合っているか不安…」
少しでも疑問や不安を感じたら、どうぞお気軽に社労士事務所ぽけっとにご相談ください。専門家の視点から、貴社の人事労務管理をしっかりとサポートさせていただきます。
【免責事項】
本記事は、掲載時点の法令や情報に基づき、一般的な情報提供を目的として作成しております。特定の事実関係によっては、本記事の記載と異なる取り扱いとなる場合もございます。個別具体的な事案に対する法的アドバイスを提供するものではありませんので、実際の判断や手続きに際しては、必ず管轄の年金事務所や社会保険労務士等の専門家にご相談ください。