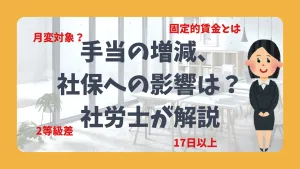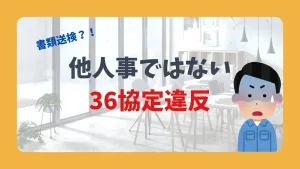社会保険の「同月得喪」とは?保険料の扱いや手続き、注意点をわかりやすく説明!
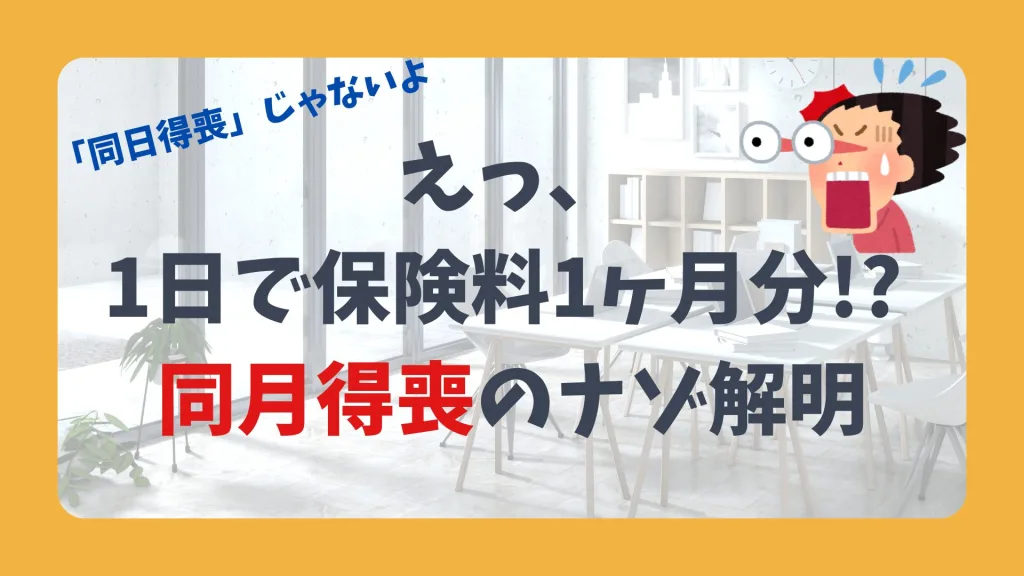
「従業員が月末に入社したけど、すぐに辞めてしまった…社会保険はどうなるの?」
「同月得喪(どうげつとくそう)って言葉は聞いたけど、具体的にどういうことなのかよくわからない…」
中小企業の経営者様や人事ご担当者様の中には、このようなお悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。従業員の入退社に伴う社会保険手続きは複雑で、特に短期間での退職があった場合には対応に迷うことも少なくありません。
こんにちは!社労士事務所ぽけっとです。私たちは、中小企業の皆様の身近なパートナーとして、給与計算や社会保険手続きをはじめとする労務管理全般をサポートしています。
社会保険の手続きには、時折「ん?これはどういうことだろう?」と迷ってしまうようなケースがありますよね。以前、当ブログで60歳以上の従業員が退職後すぐに再雇用される際などに使われる「同日得喪(どうじつとくそう)」について解説しましたが、今回はそれとは異なる「同月得喪(どうげつとくそう)」というケースについて詳しく見ていきましょう。言葉は似ていますが、対象となる状況や手続きのポイントが異なりますので、その違いも意識しながら読み進めてみてください。
この記事では、この「同月得喪」について、その基本的なルールから具体的な手続き、企業様が注意すべき点まで分かりやすく解説します。この記事を読めば、いざという時も慌てず適切に対応できるようになるはずです。
「同月得喪」とは?まずは基本を理解しよう
「同月得喪(どうげつとくそう)」とは、健康保険や厚生年金保険といった社会保険の資格を取得した月(入社月など)と、同じ月にその資格を喪失する(退職月など)ことを指します。
ここで、「あれ?前に聞いた『同日得喪』と何が違うの?」と思われた方もいらっしゃるかもしれませんね。
簡単に触れておくと、「同日得喪」は、主に60歳以上の方が定年退職後、嘱託社員などとして引き続き同じ会社に再雇用される際に、厚生年金保険の被保険者資格を一度喪失し、同日に再取得するような特殊な手続きを指します。これは、在職老齢年金の支給調整や雇用条件の変更などに関連して行われることが多い手続きです。文字通り、資格の「取得日」と「喪失日」が同じ日になるのが特徴です。
一方、今回ご説明する「同月得喪」は、例えば、従業員が入社したものの、何らかの理由で入社した月と同じ月のうちに退職してしまった、というようなケースを指します。資格取得日と資格喪失日が同じ月内にはありますが、必ずしも同じ日であるとは限りません(例:4月1日入社、4月15日退職など)。このように、対象となる状況が異なる点をまず押さえておきましょう。
原則的な保険料の扱い
では、この「同月得喪」の場合、社会保険料はどうなるのでしょうか?
原則として、健康保険料・厚生年金保険料ともに、1ヶ月分の保険料がまるまる発生します。 社会保険料は日割り計算されませんので、たとえ数日間の在籍であっても、1ヶ月分の保険料が被保険者(従業員)負担分、会社負担分ともに必要となるのです。
従業員負担分は、その従業員に支払う給与から控除することになります。
どんなケースで「同月得喪」が発生するの?具体例で見てみよう
同月得喪は、以下のようなケースで発生することが考えられます。
- 月の初めや中旬に入社し、同月内に退職した場合
- 例:4月1日に入社(資格取得)し、4月15日に退職(資格喪失日は4月16日)。この場合、4月が取得月かつ喪失月となります。
- 例:5月10日に入社(資格取得)し、5月25日に退職(資格喪失日は5月26日)。この場合も5月が取得月かつ喪失月です。
- 入社後、試用期間中や研修期間中に短期間で退職した場合
- 例:5月1日に入社(資格取得)したが、業務内容や社風が合わず、5月10日に退職(資格喪失日5月11日)。
- 試用期間であっても、社会保険の加入要件(所定労働時間・日数が常時雇用者の4分の3以上など)を満たせば、入社日から加入義務が発生します。
これらのケースでは、企業側も従業員側も「こんなに短期間で保険料がかかるの?」と疑問に思うかもしれませんが、ルール上は支払いが必要となることを覚えておきましょう。
(※なお、月の末日に退職した場合、資格喪失日は翌月の1日となるため、厳密には同月得喪には該当しません。例えば4月30日退職の場合、資格喪失日は5月1日となり、4月分の保険料が徴収されますが、喪失月は5月となります。)
【重要ポイント】厚生年金保険料には「還付」の可能性がある!
原則として1ヶ月分の保険料が発生すると説明しましたが、厚生年金保険料については、一定の条件下で還付される仕組みがあります。 これは非常に重要なポイントです。
厚生年金保険料が還付されるケースとは?
同月得喪となった従業員が、その資格を喪失した月と同じ月内に、別の会社で再び厚生年金保険の被保険者資格を取得した場合、または国民年金の第1号被保険者になった場合などには、前に支払った(徴収された)厚生年金保険料が還付されます。
例えば、
- A社を4月15日に退職(資格喪失日4月16日)し、同月得喪となった。
- その後、4月20日からB社で働き始め、B社で厚生年金保険に加入した。
この場合、A社で徴収された4月分の厚生年金保険料(従業員負担分・会社負担分ともに)は還付の対象となります。
なぜ還付されるの?
厚生年金保険料は、月末時点での加入状況に基づいて納付義務者が決まるという考え方があります。そのため、月末時点で新たな年金制度に加入していれば、それ以前の会社で同月得喪により徴収された保険料は、重複して徴収しないように調整されるのです。
還付の手続き
還付の手続きは、通常、日本年金機構が各事業所の資格取得・喪失の記録から判断し、対象となる事業所へ還付に関する通知(「厚生年金保険料等還付請求書」など)を送付します。事業所はその通知に基づき手続きを行い、従業員へ還付分を返金します。
健康保険料には還付の仕組みがないので注意!
ここで注意が必要なのは、健康保険料については、このような還付の仕組みはないという点です。 同月得喪の場合、健康保険料は1ヶ月分が徴収され、還付はありません。ただし、後述するように、保険給付を受ける権利はあります。
健康保険の扱いはどうなる?保険給付は受けられる?
厚生年金保険料には還付の可能性がある一方、健康保険料は1ヶ月分が徴収され、還付はありません。
「では、健康保険料を支払ったメリットは何もないの?」と思われるかもしれませんが、そんなことはありません。
同月得喪の場合であっても、被保険者であった期間内に病気やケガをして医療機関を受診した場合、健康保険を使って治療を受けることができます。 たとえ数日間の加入であっても、保険証が交付されていれば(または交付前でも資格取得手続きが完了していれば)、保険給付を受ける権利は保障されています。
ただし、保険証が手元に届く前に退職し、医療機関にかかった場合などは、一旦医療費を全額自己負担し、後日、加入していた健康保険組合や協会けんぽに「療養費」として請求手続きが必要になることがあります。
「同月得喪」の手続き、企業側はどうすればいい?
同月得喪が発生した場合、企業の人事担当者様が行うべき手続きは以下の通りです。
- 「被保険者資格取得届」の提出:まず、従業員が入社した際に通常通り、資格取得の手続きを行います。
- 「被保険者資格喪失届」の提出:次に、従業員が退職した際に資格喪失の手続きを行います。
同月得喪の場合は、この「資格取得届」と「資格喪失届」を、事実発生から速やかに、管轄の年金事務所または健康保険組合へ提出することが望ましいです。
特に、厚生年金保険料の還付が発生する可能性があるため、正確な資格取得日と資格喪失日を届け出ることが重要になります。
添付書類として、退職日が確認できる書類(退職届のコピーなど)を求められる場合もありますので、事前に確認しておくとスムーズです。
企業側(事業主・人事担当者)が注意すべきポイント
同月得喪は、企業側にとってもいくつか注意すべき点があります。
- 手続き漏れ・遅延の防止
短期間での退職の場合、つい手続きが後回しになったり、失念してしまったりする可能性があります。しかし、手続きが遅れると、保険料の計算や還付処理に影響が出ることがあります。速やかな届出を徹底しましょう。 - 給与計算の正確性
同月得喪の場合、給与から社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)を1ヶ月分控除する必要があります。また、厚生年金保険料の還付があった場合は、速やかに従業員へ返金処理を行わなければなりません。給与計算システムの設定や手計算の場合の徴収額・還付額の確認を慎重に行いましょう。 - 従業員への丁寧な説明
従業員からすると、「数日しか働いていないのに、なぜ1ヶ月分の保険料が引かれるのか?」と疑問や不満を感じる可能性があります。- 社会保険料は月単位で計算されるため、日割りにはならないこと。
- 厚生年金保険料については、同月内に次の就職先で厚生年金に加入するなどの条件を満たせば、還付される可能性があること。
- 健康保険は、短期間であっても加入期間中に医療機関にかかれば給付を受けられること。 などを丁寧に説明し、従業員の不安や誤解を解消することが大切です。信頼関係の構築にも繋がります。
- 国民年金・国民健康保険への切り替え案内
同月得喪により社会保険の資格を喪失し、すぐに次の就職先が決まらない場合や自営業になる場合などは、従業員本人が国民年金や国民健康保険への切り替え手続きを行う必要があります。退職時にその旨を伝え、手続きを促すことも親切な対応と言えるでしょう。 - 【重要】給与計算ソフトの限界と専門家の必要性
最近では多くの企業様で給与計算ソフトが導入され、日々の業務効率化に貢献しています。しかし、大変便利な給与計算ソフトでも、「同月得喪」のようなイレギュラーで複雑な処理については、必ずしも全てのソフトが完全自動で対応しているわけではない、という点はご留意いただく必要があります。 例えば、ソフトによっては、たとえ正しく入社日と退職日をシステムに登録したとしても、同月得喪特有の保険料計算(特に厚生年金保険料の還付が絡む場合など)が自動で行われず、手動での設定や個別の調整が必要になるケースが見受けられます。 もし、この「同月得喪」のルールやご使用のソフトの仕様を十分に理解しないまま、ソフトの自動計算結果だけを信頼してしまうと、意図せず誤った保険料を徴収してしまったり、本来従業員に返金すべき還付金を見逃してしまったりするリスクが潜んでいます。 このような誤りは、後々従業員との間の信頼関係を損ねる原因になったり、場合によっては行政からの指導に繋がったりする可能性も否定できません。 「うちの会社のソフトは、この同月得喪のケースに正しく対応できているのだろうか?」「この従業員の保険料計算、本当にこれで大丈夫?」など、少しでも疑問や不安を感じられた場合は、決してそのままにせず、ぜひ私たち社労士事務所ぽけっとにご相談ください。専門家の視点から、貴社の状況やご利用のソフトの特性も踏まえつつ、正確な処理方法について具体的なアドバイスをさせていただきます。
Q&Aコーナー:同月得喪に関するよくあるご質問
ここで、同月得喪に関してよく寄せられるご質問とその回答をいくつかご紹介します。
Q1. 月末に入社し、その月の最終日に退職しました。これは同月得喪ですか?保険料はどうなりますか?
A1. この場合、資格喪失日は退職日の翌日である翌月1日となります。そのため、退職月(入社月と同じ月)の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が1ヶ月分かかりますが、資格取得月と資格喪失月が異なるため、厳密な定義での「同月得喪」には該当しません。ただし、保険料徴収の考え方としては、入社月に1ヶ月分の保険料が発生するという点で似たような状況と言えます。
Q2. パートタイマーやアルバイトの従業員でも、同月得喪は発生しますか?
A2. はい、パートタイマーやアルバイトの方であっても、週の所定労働時間および月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上であるなど、社会保険の加入要件を満たして被保険者となっている場合は、正社員と同様に同月得喪が発生する可能性があります。
Q3. 健康保険証が発行される前に退職してしまいました。この場合、健康保険料は払わなくても良いですか?
A3. いいえ、健康保険証の交付状況にかかわらず、社会保険の資格を取得した事実があれば、保険料の支払い義務は発生します。保険証が未交付の状態で医療機関にかかった場合は、一旦全額自己負担し、後日、加入していた健康保険組合や協会けんぽに療養費の支給申請を行うことで、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
Q4. 従業員から「数日しか在籍していないのに、1ヶ月分の社会保険料が給与から引かれるのは納得いかない」と言われました。どう説明すれば良いでしょうか?
A4. まず、社会保険料は日割り計算ではなく月単位で計算されるため、月の途中で資格を取得(入社)したり喪失(退職)したりした場合でも、1ヶ月分の保険料が発生する旨を丁寧に説明しましょう。その上で、厚生年金保険料については、同月内に新たな勤務先で厚生年金に加入するなどの条件を満たせば、後日還付される可能性があることを伝えると、従業員の理解を得やすくなるでしょう。健康保険については、支払った保険料が無駄になるわけではなく、加入期間中は保険給付を受けられる権利があることも併せて説明すると良いでしょう。
Q5. 「同月得喪」と「同日得喪」の具体的な違いをもう一度教えてください。
A5. 「同月得喪」は、従業員が入社した月と同じ月の間に退職してしまった場合など、資格取得日と資格喪失日が同じ月内にあるケースを指します(例:4月10日入社、4月25日退職)。一方、「同日得喪」は、主に60歳以上の方が定年退職し、同日付で再雇用される場合など、資格喪失日と資格取得日が同じ日になる特殊なケースを指します。適用される状況や目的が異なります。
【まとめ】同月得喪を正しく理解し、企業も従業員も安心できる労務管理を
今回は、社会保険の「同月得喪」について、類似する「同日得喪」との違いにも触れながら解説しました。ポイントをまとめると以下の通りです。
- 同月得喪とは:社会保険の資格を取得した月と同じ月にその資格を喪失すること。
- 保険料:健康保険料・厚生年金保険料ともに原則1ヶ月分が発生。
- 厚生年金保険料の還付:同月内に再就職先で厚生年金に加入した場合など、条件を満たせば還付される。
- 健康保険料:還付なし。ただし、加入期間中の保険給付は受けられる。
- 手続き:「資格取得届」と「資格喪失届」を速やかに提出。
- 企業側の注意点:手続きの迅速化、給与計算の正確性、従業員への丁寧な説明が重要。
- 同日得喪との違い:「同日得喪」は資格取得日と喪失日が同日である特殊ケース。
同月得喪は、頻繁に起こることではないかもしれませんが、いつ発生してもおかしくないケースです。いざという時に慌てないためにも、企業の人事労務ご担当者様は、この制度について正しく理解しておくことが大切です。
従業員との無用なトラブルを避け、信頼関係を保つためにも、正確な情報提供と丁寧なコミュニケーションを心がけましょう。
社労士事務所ぽけっとでは、このような複雑な社会保険手続きや給与計算に関するご相談も承っております。「うちの会社の場合はどうなんだろう?」「手続きが煩雑でよくわからない…」など、少しでもご不安な点がございましたら、どうぞお気軽に私たち専門家にご相談ください。貴社の状況に合わせた最適なアドバイスをさせていただきます。
【免責事項】 本記事は、掲載時点の法令や情報に基づいて作成しておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。また、法令改正等により内容が変更される可能性があります。具体的な個別の事案につきましては、必ず社会保険労務士等の専門家にご相談いただくか、管轄の行政機関にご確認くださいますようお願い申し上げます。本記事の情報を用いて行う一切の行為について、当事務所は何ら責任を負うものではありません。