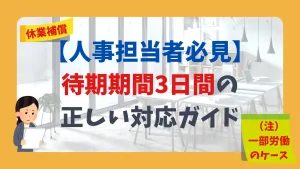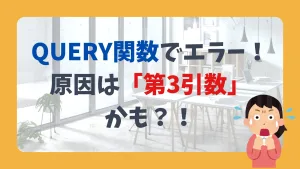平均賃金の計算方法|休職・有給・労災…あらゆる疑問を解決!
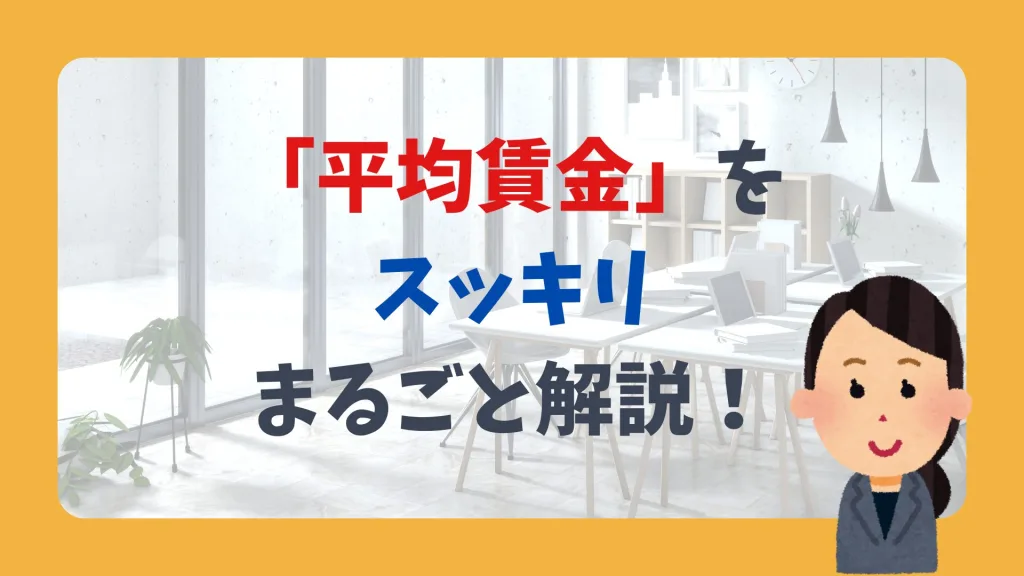
「解雇予告手当を計算するように言われたけど、平均賃金ってどうやって計算するの?」
「休業手当の計算で、休職していた期間はどう扱えばいいんだろう?」
「パートさんの有給休暇分の賃金、計算方法が合っているか不安…」
中小企業の経営者様や人事労務のご担当者様にとって、平均賃金の計算は、避けては通れないながらも、少し複雑で分かりにくい業務ではないでしょうか。
特に、従業員の方のお休みや特殊な手当が絡むと、どの期間や金銭を計算に含めて、どの期間を除外すれば良いのか、迷ってしまうことも多いはずです。
計算を間違えてしまうと、従業員の方へ支払う手当や補償の金額が変わってしまい、後々のトラブルに発展しかねません。
そこで今回は、人事労務の基礎とも言える「平均賃金」について、基本的な計算方法から、休職や有給休暇、労災など、あらゆるケース別の疑問に分かりやすくお答えしていきます!
この記事を最後までお読みいただければ、平均賃金の計算に自信が持てるようになります。ぜひ、貴社の労務管理にお役立てください。
そもそも「平均賃金」は何のために計算するの?
平均賃金は、労働基準法で定められており、従業員の生活を保障するために、様々な手当や補償金の額を算定する際の基礎となります。
具体的には、以下のような場面で必要になります。
- 解雇予告手当(労働基準法第20条)
- 休業手当(労働基準法第26条)
- 年次有給休暇中の賃金(労働基準法第39条)
- 労災保険の休業(補償)給付など(労働基準法第76条)
- 減給の制裁の制限額(労働基準法第91条)
このように、平均賃金は従業員の権利や金銭に直結する、非常に重要な指標なのです。
まずは、基本となる計算方法をしっかり押さえましょう。
原則の計算式
平均賃金は、原則として以下の式で計算します。
平均賃金 = 算定事由が発生した日以前3ヶ月間に支払われた賃金の総額 ÷ その期間の総日数(暦日数)
ポイント
- 「算定事由が発生した日」とは、解雇を通知した日、休業した初日などを指します。この日は含めずに、その前日から遡って3ヶ月間を計算期間とします。
- 賃金締切日がある場合(例:毎月末締め、翌25日払い)は、直前の賃金締切日から遡って3ヶ月間で計算します。
- 例:8月10日に算定事由が発生した場合 → 7月31日から遡り、5月、6月、7月の3ヶ月間が計算対象期間となります。
- 「賃金の総額」には、基本給のほか、通勤手当、時間外手当、家族手当など、税金や社会保険料を控除する前のすべての賃金が含まれます。ただし、結婚手当などの臨時手当や、3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賞与(ボーナス)は含みません。(※通勤手当の扱いはQ&Aも参照)
- 「総日数」とは、実際に働いた日数ではなく、カレンダー上の日数(暦日数)であることに注意が必要です。
パート・アルバイト等の最低保障額
日給制、時間給制、出来高払制の従業員の場合、出勤日数が少ないと原則の計算式では平均賃金が著しく低くなってしまうことがあります。
そのため、労働者を保護する目的で「最低保障額」が定められています。
最低保障額 = ( 算定事由が発生した日以前3ヶ月間に支払われた賃金の総額 ÷ その期間の労働日数 ) × 100分の60
原則の計算式で算出した金額と、この最低保障額を比較し、高い方の金額を平均賃金とします。
【計算例】最低保障額の計算が必要なケース
実際にモデルケースで計算してみましょう。
【モデルケース】
- 対象者:パートタイマー(時給1,100円)
- 賃金締切日:毎月末日
- 算定事由発生日:2025年7月10日
- 直近3ヶ月間の勤務状況
- 4月分給与(計算期間4/1~4/30)
- 労働日数:10日
- 賃金額:55,000円
- 暦日数:30日
- 5月分給与(計算期間5/1~5/31)
- 労働日数:8日
- 賃金額:44,000円
- 暦日数:31日
- 6月分給与(計算期間6/1~6/30)
- 労働日数:12日
- 賃金額:66,000円
- 暦日数:30日
- 3ヶ月間の合計
- 賃金総額:55,000円 + 44,000円 + 66,000円 = 165,000円
- 総日数(暦日数):30日 + 31日 + 30日 = 91日
- 総労働日数:10日 + 8日 + 12日 = 30日
- 4月分給与(計算期間4/1~4/30)
Step 1:原則の方法で計算
165,000円(賃金総額) ÷ 91日(総日数) ≒ 1,813.18円
Step 2:最低保障額を計算
( 165,000円(賃金総額) ÷ 30日(総労働日数) ) × 0.6 = 5,500円 × 0.6 = 3,300円
Step 3:2つの金額を比較
- 原則の金額:1,813.18円
- 最低保障額:3,300円
【結論】この場合、最低保障額の方が高いため、このパートタイマーの方の平均賃金は 3,300円 となります。
このように、出勤日数が少ない月があるパート・アルバイトの方の場合は、必ず両方を計算し、労働者にとって有利な方(高い方)を採用するようにしましょう。
【本題】ケース別!平均賃金の計算 Q&A
ここからは、皆さまが特に悩みがちな、特殊なケースでの平均賃金の計算方法について、Q&A形式で詳しく解説していきます。
Q1. 業務外の病気やケガで「休職」した期間は計算に含まれる?
A1. 休職期間の長さに応じて計算方法が異なりますが、いずれの場合も労働者に不利益がないように配慮されます。
業務外の私的な病気やケガ(私傷病)による休職は、平均賃金計算における最も複雑な点の一つです。
ポイントは、休職期間の長さです。
- ケース①:休職期間が短く、計算期間(3ヶ月)内に収まる場合 →その休職期間の日数と賃金を控除して計算します。
例えば、直近3ヶ月のうち1ヶ月間だけ休職した、というようなケースです。この場合、その1ヶ月の日数とその間に支払われた賃金(もしあれば)を、賃金総額と総日数の両方から差し引きます。これは、たとえ1日の休職であっても同様です。 - ケース②:休職期間が長く、計算期間(3ヶ月)の全部または大半を占める場合 →休職が始まった日を「起算日」として計算し直します。
例えば、6ヶ月前からずっと休職が続いているようなケースです。この場合、直近3ヶ月は丸ごと休職期間となり、通常の計算ができません。そこで、その休職が始まった日を新しいスタート地点(起算日)とし、その日から遡って3ヶ月間の賃金と日数で平均賃金を計算するという特例ルールが適用されます。
したがって、「3ヶ月未満の休職だから控除できない」ということはなく、期間の長短にかかわらず、必ず労働者の不利益にならないような方法で計算する、と覚えておきましょう。
Q2. 「年次有給休暇」を取得した日はどう扱えばいい?
A2. 通常通り出勤したものとして、計算に含めます。
年次有給休暇を取得した日については、その日に支払われた賃金を賃金総額に含め、日数も総日数に含めて計算します。
つまり、控除せずに通常通り計算する、ということです。
年次有給休暇は労働者の権利であり、取得したことで不利益が生じないように配慮されています。
Q3. 業務上のケガ(労災)で休業した期間は?
A3. 計算から除外します(Q1と同様の考え方です)。
業務上の負傷や疾病により療養のために休業した期間も、私傷病の場合(Q1)と同様の考え方をします。
休業が3ヶ月未満ならその期間を控除し、3ヶ月以上にわたる場合は休業開始日を起算日として計算します。
Q4. 「育児休業」や「介護休業」の期間はどうなる?
A4. これらも計算から除外します(Q1と同様の考え方です)。
育児・介護休業法に基づくこれらの休業も、同様に扱います。
休業期間が3ヶ月未満ならその期間を控除、3ヶ月以上なら休業開始日を起算日として計算します。
Q5. 「試用期間」中の場合は?
A5. 試用期間も計算から除外します。
試用期間は、上記の休業とは少し異なり、期間の長短にかかわらず、その日数と賃金を単純に計算期間から控除します。(労働基準法第12条第3項)
Q6. 「6ヶ月定期」の通勤手当はどう計算する?
A6. 月割りの額を各月の賃金に加算して計算するのが一般的です。
通勤手当は給与の一部であるため、これを含めずに計算すると、従業員の実態の賃金よりも平均賃金が不当に低くなってしまう可能性があります。
そのため、多くの会社では労働者の不利益とならないよう、就業規則や労働協約で通勤手当を平均賃金の計算に含めると定めています。その場合の具体的な計算手順は以下の通りです。
通勤手当を算入する場合の計算手順
【前提】
【前提】6ヶ月定期代:60,000円
Step 1:1ヶ月あたりの通勤手当額を算出する
まず、支給された定期代を有効期間の月数で割り、1ヶ月分の金額を算出します。
60,000円 ÷ 6ヶ月 = 10,000円(1ヶ月あたりの通勤手当額)
Step 2:計算対象となる各月の賃金に月割額を加算する
平均賃金の計算対象となる3ヶ月間、それぞれの月の給与総額に、Step1で算出した月割額を加算します。
(例)
- 4月の給与: 300,000円 + 10,000円 = 310,000円
- 5月の給与: 305,000円 + 10,000円 = 315,000円
- 6月の給与: 300,000円 + 10,000円 = 310,000円
Step 3:平均賃金計算の基礎となる「賃金総額」を算出する
Step2で計算した3ヶ月分の賃金を合計します。これが平均賃金を計算するための「賃金総額」となります。
310,000円 + 315,000円 + 310,000円 = 935,000円
Step 4:平均賃金を計算する
Step3で算出した賃金総額を基に、通常通り「原則の計算」と「最低保障額の計算」を行い、高い方の金額を平均賃金とします。
控除対象となる期間のまとめ
以下に該当する期間がある場合は、その日数と期間中の賃金を、平均賃金の計算から除外(控除)する必要があります。
- 業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間
- 産前産後休業期間
- 使用者の都合による休業期間
- 育児・介護休業期間
- 試用期間
- 争議行為(ストライキなど)により労務を提供しなかった期間
- 公民権の行使(裁判員としての出頭など)を許可された休業期間
これらの期間を計算に含めてしまうと、平均賃金が不当に低く算出され、トラブルの原因となりますので十分にご注意ください。
具体的な計算例で確認してみよう!
【モデルケース】
- 賃金締切日:毎月末日
- 算定事由発生日:8月10日(解雇予告)
- 直近3ヶ月間の給与状況
- 5月分(4/1~4/30):総支給額 31万円、暦日数 30日
- 6月分(5/1~5/31):総支給額 30万円、暦日数 31日
- うち、私傷病で10日間休職(無給)
- 7月分(6/1~6/30):総支給額 32万円、暦日数 30日
【計算方法】
- 計算期間の特定
8月10日の直前の賃金締切日は7月31日。よって、計算期間は5月、6月、7月の3ヶ月間。 - 休職期間の控除
6月分給与の計算期間である5月中に10日間の休職があるため、この期間の日数と賃金を控除します。- 賃金総額から控除:
6月分の総支給額は30万円ですが、これは休職期間を除いた労働に対する賃金です。
もし休職期間中に何らかの賃金が支払われていればそれを控除しますが、今回は無給なので控除額は0円です。 - 総日数から控除:
5月の暦日数31日から、休職日数10日を引きます。
- 賃金総額から控除:
- 平均賃金の計算
- 賃金総額:31万円 + 30万円 + 32万円 = 93万円
- 総日数:30日(4月) + (31日 - 10日)(5月) + 30日(6月) = 81日
- 平均賃金:930,000円 ÷ 81日 = 11,481.48円(銭未満は切り捨て)
もし休職期間を考慮せずに計算すると、930,000円 ÷ 91日 ≒ 10,219.78円となり、本来の金額より低くなってしまうことが分かります。
【まとめ】正確な計算で、信頼される職場づくりを
平均賃金の計算は、一見すると単純な割り算ですが、実際には従業員一人ひとりの勤務状況や手当の支給形態に応じて、含めるもの・控除するものを正確に判断する必要があります。
「うちのケースは少し複雑で、計算が合っているか心配…」
「給与計算や社会保険の手続き、もっと効率化したい」
そうお考えの経営者様、人事担当者様は、ぜひ一度、社労士事務所ぽけっとにご相談ください。
給与計算や社会保険手続きのアウトソーシングはもちろん、日々の労務管理に関するちょっとした疑問にも、親身になってお応えします。
専門家と連携することで、ミスのない正確な労務管理を実現し、従業員が安心して働ける職場環境を一緒に作っていきましょう。
【免責事項】
本記事は、掲載日時点の法令等に基づき、一般的な情報を提供するものです。個別の事案については、必ず社会保険労務士等の専門家にご相談いただくか、管轄の労働基準監督署にご確認ください。この記事の情報に基づいて生じたいかなる損害についても、当事務所は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。