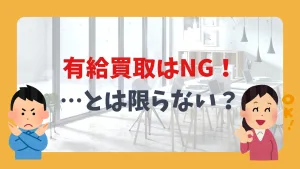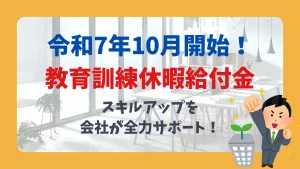給与明細の控除がマイナス?「経費精算 -5,000円」の謎を社労士が徹底解明!

「出張旅費を立て替えた分が、給与と一緒に振り込まれた。
でも給与明細を見たら、控除の欄に『経費精算 -5,000円』と書かれている…。」
経理や人事のご担当者様の中には、このような給与明細を作成したり、目にしたりした経験がある方も多いのではないでしょうか。
プラスで支給されるはずの経費が、なぜ「控除」の欄に?
しかも、なぜ金額の前に「マイナス(-)」がついているの?
一見すると不思議で、「もしかして間違っているのでは?」と不安になってしまうこの処理方法。
実は、今でも多くの企業で使われている、計算を正しく合わせるための実務上のテクニックなのです。
こんにちは!社労士事務所ぽけっとです。
今回は、この少し分かりにくい「控除でマイナス計上する経費精算」の謎について、その仕組みから背景まで、分かりやすく解説していきます。
【メイン解説】なぜ「控除でマイナス」するのか?その仕組みを解明
結論からお伝えすると、この方法は「所得税や社会保険料の計算対象に影響を与えずに、従業員に立替経費を正しく支払うため」の工夫です。
言葉だけでは分かりにくいので、具体的な数字で見ていきましょう。
【設例】
- 基本給:300,000円
- 社会保険料:50,000円
- 所得税:10,000円
- 立替経費:5,000円
この場合の給与明細が、以下のようになっているケースです。
▼「控除でマイナス」処理の給与明細例
【支給】
基本給 300,000円
---------------------------------
総支給額 300,000円
【控除】
社会保険料 50,000円
所得税 10,000円
経費精算 -5,000円
---------------------------------
控除合計額 55,000円
差引支給額(手取り)= 300,000円 - 55,000円 = 245,000円
一見すると複雑ですが、計算の内訳を見てみると納得できます。
- 本来の給与の手取り額を計算する
(基本給 300,000円) - (社会保険料 50,000円) - (所得税 10,000円) = 240,000円 - 最終的な振込額を確認する
給与明細上の手取り額は 245,000円 となっています。
これは、本来の手取り額 240,000円に、立替経費の5,000円が正しく上乗せされた金額と一致します。
つまり、「控除項目にマイナスの数値を入れる」ことで、差し引く金額の合計(控除合計額)がその分だけ少なくなり、結果として手取り額が増える、という仕組みなのです。
この方法なら、総支給額は300,000円のままなので、所得税や社会保険料の計算基礎となる金額に影響を与えずに、手取り額だけを調整できるという訳です。
なぜ、この方法が今でも使われているのか?
この処理が行われる最大の理由は、給与計算ソフトの仕様や、昔ながらの経理の慣習にあります。
特に、古い給与計算ソフトや簡易的なシステムの中には、「支給」として設定した項目は、すべて自動的に所得税などの課税対象として計算してしまうものがあります。
そうしたソフトで立替経費を非課税で支払うための、いわば「裏技」や「テクニック」として、この「控除でマイナス」という方法が長年使われてきたのです。
【原則・理想的な方法】専門家が推奨する「非課税支給」とは
ここまで「控除でマイナス」の方法を解説してきましたが、この方法は従業員にとって分かりにくい、というデメリットもあります。
そこで、私たちが専門家として最も推奨している、よりシンプルで理想的な方法もご紹介します。
それが「非課税の支給項目」として計上する方法です。
そして、専門的な給与計算ソフトでは、この項目設定はさらに細かく分かれています。
新しい手当などを作る際には、主に以下のような設定を一つひとつ正しく行う必要があるのです。
- 課税か、非課税か (所得税の計算対象になるか)
- 社会保険の算定基礎に含めるか (健康保険・厚生年金保険料の計算対象になるか)
- 雇用保険の賃金に含めるか (雇用保険料の計算対象になるか)
- 固定的賃金に該当するか (月給が大きく変動した際の社会保険料見直し(月額変更届)の対象になるか)
少し専門的で難しく感じますよね。
ちなみに、今回テーマとなっている「立替経費」の場合は、これら4つすべてを『非課税』『含めない』『該当しない』に設定するのが正解です。
なぜなら、立替経費はそもそも労働の対価である「賃金」や「報酬」ではないからです。
このように、それぞれの支給項目が持つ性質を正しく理解し、ソフト上で設定することが、正確な給与計算の要となります。
この設定を正しく行った場合の給与明細は、以下のようになります。
▼「非課税支給」処理の給与明細例
【支給】
基本給(課税) 300,000円
立替経費(非課税) 5,000円
---------------------------------
総支給額 305,000円
【控除】
社会保険料 50,000円
所得税 10,000円
---------------------------------
控除合計額 60,000円
差引支給額(手取り)= 305,000円 - 60,000円 = 245,000円
いかがでしょうか。
最終的な手取り額は同じ 245,000円 ですが、こちらの方が「何が、いくら支払われたのか」が一目で分かりやすいと思いませんか?
このように、支給の内訳が明確であることは、従業員との信頼関係においても非常に大切です。
【まとめ】自社の運用に合った、分かりやすい方法を選びましょう
「控除でマイナス」という方法は、計算上は正しく、今でも実務で使われている有効なテクニックです。
この方法を使っているからといって、直ちに問題があるわけではありません。
しかし、その仕組みや背景を知っておくことは、担当者としてとても重要です。
そして、もしお使いのソフトが対応しているなら、従業員にとってより分かりやすい「非課税支給」の方法へ移行を検討してみるのも良いかもしれません。
「うちの給与計算、もっと分かりやすくできないかな?」
「今の運用方法で合っているのか、専門家の意見を聞きたい」
そんな時は、ぜひ私たち社労士事務所ぽけっとにご相談ください。
それぞれの会社の実情に合わせた、最適な給与計算の運用方法をご提案します。
【免責事項】
本記事は、掲載日時点の法令や情報に基づき作成しております。法改正などにより、最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。また、個別の事案については、必ず専門家にご相談いただきますようお願い申し上げます。