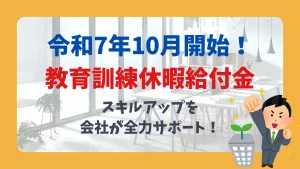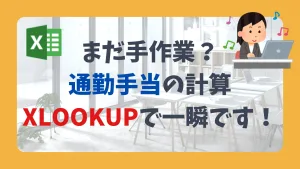高給与の社員が育休取得!育児休業給付金の上限と会社の給与補填、注意点を徹底整理
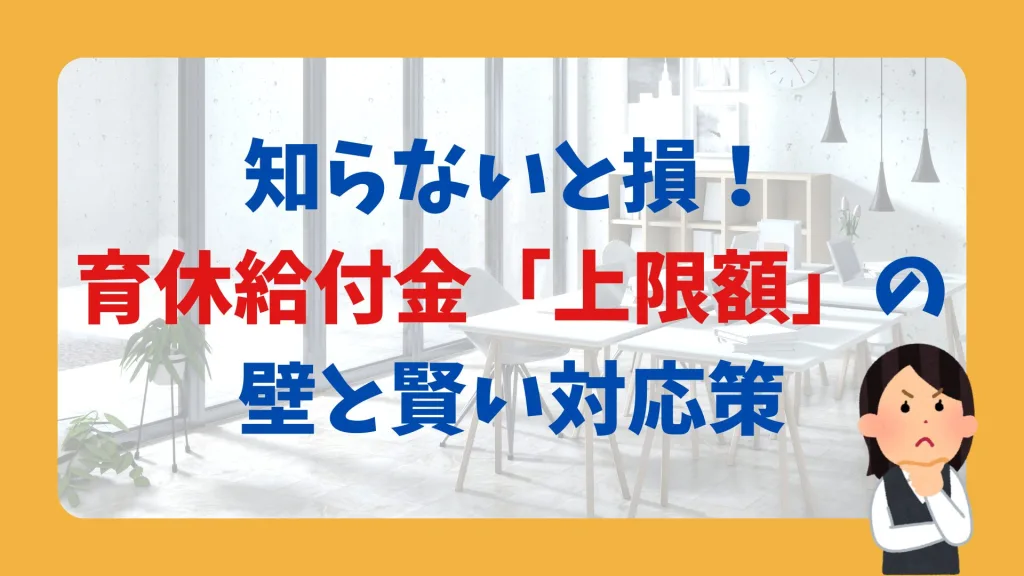
近年、男性の育児休業取得も増え、給与水準の高い従業員が育休を取得するケースも珍しくなくなりました。
従業員の生活をサポートしたいと考える経営者や人事担当者の方から、「育児休業給付金だけでは収入減が大きいと聞く。会社として何か補填できないか?」というご相談をいただく機会が増えています。
しかし、この「給与の補填」、実は注意が必要です。
良かれと思って支給した給与が、かえって従業員が受け取る育児休業給付金を減らしてしまう可能性があるのです。
そこで今回は、社労士事務所ぽけっとが、給与額が高い従業員の育児休業給付金に焦点を当て、「支給の上限額」と「会社が給与を補填する際の注意点」について、分かりやすく解説します。
まずは基本から。育児休業給付金とは?
育児休業給付金は、雇用保険に加入している従業員が、原則として1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、国から支給される給付金です。
従業員が育休中も安心して子育てに専念できるよう、収入の一部を補償することを目的としています。
支給額は、以下の計算式で算出されます。
- 育休開始から180日間:休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
- 育休開始から181日目以降:休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%
「休業開始時賃金日額」とは、育休開始前の6ヶ月間の賃金(賞与は除く)を180で割った額のことです。
ざっくりと「育休前の給料の約3分の2(半年後からは約半分)がもらえる」とイメージしてください。
この給付金は非課税で、社会保険料の負担も免除されるため、従業員にとっては非常に重要な制度です。
知っておきたい「育児休業給付金の上限額」
従業員の生活を支える大切な育児休業給付金ですが、実は支給額に上限があることをご存知でしょうか。
給与水準が高い従業員の場合、この上限額に達してしまう可能性があります。
2024年8月1日以降の制度では、育児休業給付金の計算の基となる「休業開始時賃金月額」の上限が470,700円と定められています。
これを基に計算すると、1ヶ月あたりの支給上限額は以下のようになります。
- 給付率67%の場合(育休開始から180日間) 470,700円×67%=315,369円
- 給付率50%の場合(育休開始181日目以降) 470,700円×50%=235,350円
つまり、育休開始前の月収が約47万円を超えている従業員の場合、実際の給与額にかかわらず、受け取れる育児休業給付金は月額約31.5万円が上限となります。
例えば、月収60万円の従業員であっても、月収47万円の従業員であっても、支給される育児休業給付金は同額の315,369円(上限額)となるのです。
【最重要】会社が給与を補填するときの落とし穴
「上限額があるなら、会社が差額を補ってあげたい」と考えるのは自然なことです。
しかし、ここに大きな注意点があります。
育児休業期間中に会社から賃金が支払われると、その金額に応じて育児休業給付金が減額または不支給になる場合があるのです。
ルールは以下のようになっています。
- 会社からの給与が「休業開始前賃金の13%」以下の場合 → 育児休業給付金は減額されずに全額支給されます。
- 会社からの給与が「休業開始前賃金の80%」以上の場合 → 育児休業給付金は支給されません。
- 会社からの給与が「13%超~80%未満」の場合 → 「休業開始前賃金の80%」から会社支給の給与を差し引いた額が、育児休業給付金として支給されます。
(※育休開始181日目以降の給付率50%の期間は、「13%」を「30%」と読み替えます。)
具体的なシミュレーションで見てみましょう
月収60万円(休業開始時賃金月額も同額と仮定)の従業員のケースで考えてみましょう。この従業員の給付金は上限額(315,369円)が適用されます。
ケース1:会社が善意で月10万円を給与として補填した場合
- 休業開始前賃金の80%は、600,000円×80%=480,000円です。
- 会社から10万円の給与が支払われると、支給調整後の育児休業給付金は、480,000円−100,000円=380,000円 となります。
- しかし、もともとの給付金上限額は315,369円です。
- この場合、調整後の支給額(38万円)が上限額を上回っていますが、実際に支給されるのは上限額である315,369円です。
- 結果:従業員の手取りの合計は、会社の給与10万円+給付金315,369円=415,369円。
- ただし、会社が支払った10万円は課税対象となり、雇用保険料もかかります。
ケース2:会社が月20万円を給与として補填した場合
- 同様に、休業開始前賃金の80%は480,000円です。
- 会社から20万円の給与が支払われると、支給調整後の育児休業給付金は、480,000円−200,000円=280,000円 となります。
- この金額は、本来の給付金上限額(315,369円)よりも低くなっています。
- 結果:従業員が受け取る育児休業給付金は280,000円に減額されます。
- 従業員の手取り合計は、会社の給与20万円+減額された給付金28万円=48万円。
- この場合も、会社が支払った20万円は課税対象となり、雇用保険料も発生します。
このように、会社が給与を補填することで、非課税であるはずの給付金が減額され、代わりに課税対象の給与が増えるという、従業員にとって必ずしも有利とは言えない状況が生まれてしまうのです。
Q&Aでさらにスッキリ!
Q1. 会社からの補填分を「給与」ではなく「見舞金」として支給すれば問題ない?
A1. 「育児休業中の生活補填」といった実質的な意味合いを持つ場合、名称が「見舞金」であってもハローワークから「賃金」と見なされ、給付金の減額対象となる可能性が高いです。安易な判断は避け、慎重に検討する必要があります。
Q2. 育休中でも、少しだけ業務を手伝ってもらうことは可能?その分の給与は?
A2. 臨時・一時的な業務であれば、育児休業中と認められる場合があります。ただし、1支給単位期間(通常1ヶ月)の就業日数が10日(または80時間)を超えると育児休業とは認められず、給付金は支給されません。10日以下であっても、支払われた賃金額に応じて上記で解説した減額調整が行われます。
まとめ:従業員への丁寧な説明と専門家への相談が鍵
給与の高い従業員が育休を取得する際、会社として生活を支援したいという想いは非常に尊いものです。
しかし、良かれと思って行った給与補填が、育児休業給付金の減額につながり、かえって従業員を混乱させてしまう可能性があります。
重要なのは、育児休業給付金の仕組み(特に上限額と減額調整)を会社側が正しく理解し、対象となる従業員に事前に丁寧に説明することです。
その上で、本当に補填が必要かどうか、どのような方法が最適かを一緒に考える姿勢が、従業員との信頼関係を深めるでしょう。
給与計算や社会保険手続きは、法改正も多く非常に複雑です。
判断に迷われた際は、ぜひ私たち社労士のような専門家にご相談ください。それぞれの会社の実情に合わせた最適なアドバイスをさせていただきます。
【免責事項】
本記事は、2025年7月時点の法令情報に基づき作成しています。掲載内容の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。個別の事案については、必ず管轄のハローワークや社会保険労務士等の専門家にご相談ください。