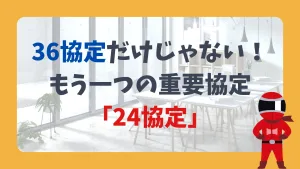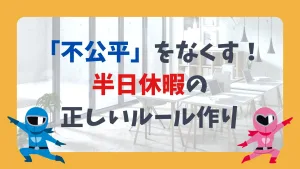退職後の遡及払いに雇用保険・社会保険・所得税は引かれるの?
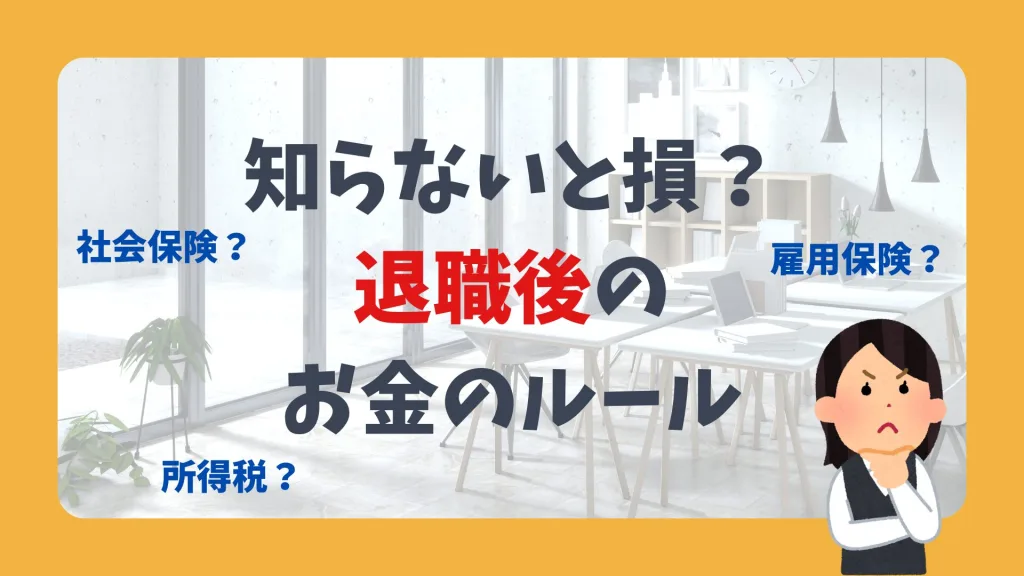
「会社を退職したはずなのに、後から給与が振り込まれた…?」
「未払いだった残業代が支払われたけど、これって手取り額がそのままもらえるの?」
退職後に、会社から思いがけず追加の支払い(遡及払い)を受けることがあります。
これは、給与計算の誤りや、未払いだった残業代が後から支払われるケースなどで発生します。
突然の入金は嬉しいものですが、同時に「このお金から、税金や社会保険料は引かれるんだろうか?」という疑問が浮かびますよね。
こんにちは、社労士事務所ぽけっとです。
今回は、そんな退職後の「遡及払い」にまつわるお金の疑問について、分かりやすく解説していきます。
ご自身のケースと照らし合わせながら、ぜひ最後までご覧ください。
【結論】遡及払いから引かれるもの・引かれないもの
早速ですが、結論からお伝えします。
退職後の遡及払いから各種保険料や税金が引かれるかどうかは、種類によって扱いが異なります。
- 雇用保険料 → 引かれる
- 社会保険料(健康保険・厚生年金保険) → 原則、引かれない
- 所得税 → 引かれる
「どうしてこんなにバラバラなの?」と思いますよね。
一つずつ、その理由を詳しく見ていきましょう。
1.雇用保険料は「引かれる」
雇用保険料は、原則として遡及払いから控除されます。
これは、雇用保険料が「労働の対価として支払われるすべての金銭(=賃金)」を対象に計算されるためです。
退職後に支払われたものであっても、それが在職中の労働に対する対価(未払いだった給与や残業代など)であれば、「賃金」とみなされます。
したがって、会社は支払う給与の総額に対して、定められた保険料率をかけて雇用保険料を計算し、給与から天引きする必要があるのです。
2.社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は「原則、引かれない」
社会保険料は、原則として遡及払いからは控除されません。
社会保険料は、「被保険者資格のある月」に対して発生します。通常、退職日の翌日に被保険者資格を喪失するため、資格を失った後に支払われる給与からは、社会保険料を天引きする必要がないのです。
例えば、10月20日に退職した場合、資格喪失日は10月21日です。
社会保険料は9月分までが徴収対象となり、10月分の保険料はかかりません。(すでに国民健康保険やご家族の扶養に入っているため)
【注意点:月末退職の場合】
ただし、月末(例:10月31日)に退職した場合だけは例外です。この場合、資格喪失日は翌月の11月1日となります。
すると、「10月分」の社会保険料も発生するため、最後の給与や遡及払いから10月分の社会保険料が控除されることになります。
3.所得税は「引かれる」
所得税も、遡及払いから源泉徴収(天引き)されます。
遡及払いは、税法上「給与所得」に分類されます。
そのため、会社は支払い時に所得税を源泉徴収する義務があります。
ここで少し複雑なのが、退職後の給与支払いでは、所得税の計算方法が通常(在職中)と異なる場合がある点です。
多くの場合、税額表の「乙欄」という高い税率で計算されるため、「思ったより手取りが少ない」と感じるかもしれません。
最終的な正しい税額は、年末調整や確定申告によって精算されます。
【退職者向け】ここが重要!注意点Q&A
理屈は分かっても、実際に退職者ご本人が「何をすべきか」が一番気になるところですよね。
よくある疑問をQ&A形式でまとめました。
Q1. 確定申告は必要になりますか?
A1. 必要になる可能性が高いです。
退職後、会社はあなたの年末調整を行いません。遡及払いによって年間の所得額が確定したら、会社から新しい源泉徴収票(遡及払い分が反映されたもの)を取り寄せ、原則としてご自身で確定申告を行い、所得税の過不足を精算する必要があります。
Q2. 失業保険(基本手当)をもらっています。何か影響はありますか?
A2. 影響があります!すぐにハローワークへ申告してください!
これは非常に重要なポイントです。遡及払いは、失業保険の受給額に影響を与える可能性が非常に高いです。影響には「増額」と「減額」の2つの側面があります。
【増額の可能性】
失業保険の1日あたりの支給額(基本手当日額)は、離職前6ヶ月間の賃金総額をもとに計算されます。もし、遡及払いがこの離職前6ヶ月間の賃金に該当する場合、計算の基礎となる賃金総額が増えることになります。その結果、基本手当が増額される可能性があるのです。増額を受けるためには、会社に「離職票」の金額を訂正してもらい、ハローワークへ再提出する必要があります。
【減額・不支給の可能性】
一方で、遡及払いが「収入」とみなされた場合、失業認定日に基本手当が減額されたり、不支給になったりする可能性があります。
いずれにせよ、正直に申告しないと不正受給とみなされるリスクがあります。
支払いの事実が分かり次第、ご自身の権利を正しく主張するためにも、また、ペナルティを避けるためにも、必ず管轄のハローワークに相談しましょう。
Q3. 会社から渡された源泉徴収票の金額が、遡及払い前のままです。
A3. 会社に再発行を依頼しましょう。
遡及払いが行われた場合、会社は支払額を反映した正しい源泉徴収票を発行する義務があります。確定申告で必要になりますので、経理担当者の方に連絡し、再発行を依頼してください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
退職後の遡及払いについて、ポイントをもう一度おさらいします。
- 雇用保険と所得税は引かれるが、社会保険料は原則引かれない。
- 正しい所得税額を精算するために、原則として確定申告が必要。
- 失業保険を受給中の場合は、必ずハローワークへの申告を忘れないこと。
退職後の手続きは、ただでさえ複雑で不安に感じることが多いものです。
特に、予期せぬ遡及払いがあった場合は、ご自身で全てを判断するのが難しいかもしれません。
「計算が本当に合っているか不安…」
「会社とのやり取りがスムーズにいかない」
「自分の場合はどうなるのか、具体的に知りたい」
そんな時は、私たち社会保険労務士のような専門家にご相談ください。
あなたの状況を丁寧にお伺いし、最適な解決策を一緒に見つけていきます。
一人で抱え込まず、お気軽に社労士事務所ぽけっとまでお問い合わせくださいね。
【免責事項】
この記事は、公開日時点の法令や情報に基づき、一般的な情報提供を目的として作成しております。個別の事案については、必ず管轄の行政機関や専門家にご相談ください。本記事の情報を利用した結果生じた損害等について、当事務所は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。