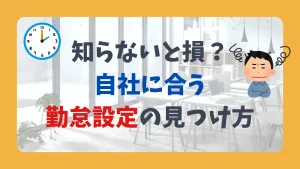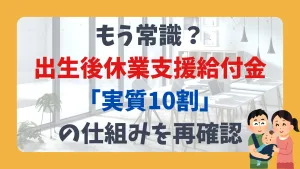【裁判事例】妊娠した社員の降格はマタハラ?「広島中央保険生協事件」から学ぶ企業の正しい対応
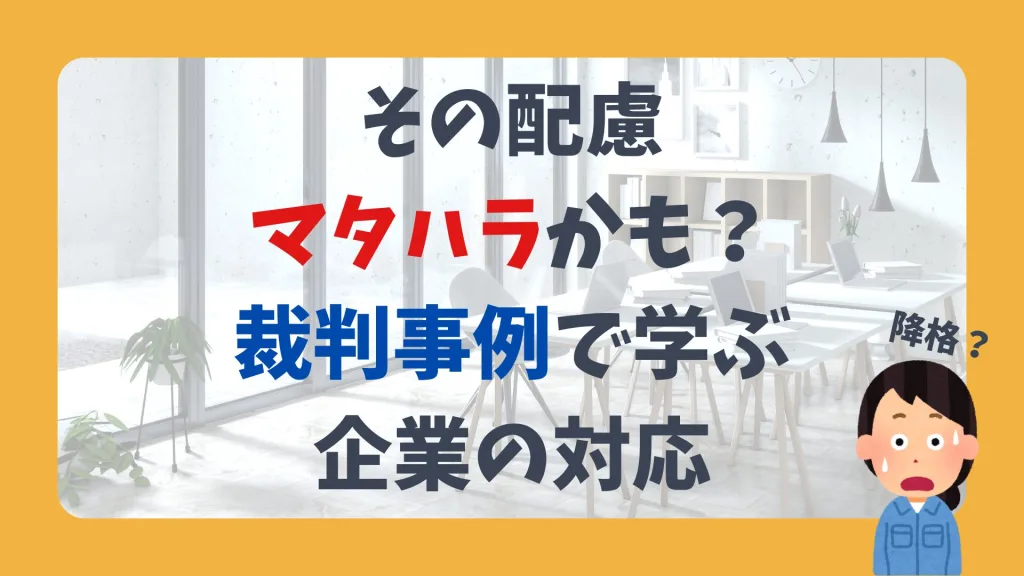
「社員が妊娠した。母体に配慮して、負担の少ない業務についてもらおう」
これは、多くの経営者や人事担当者が考える、ごく自然な配慮だと思います。
しかし、その配慮の仕方を一歩間違えると、「マタニティハラスメント(マタハラ)」と判断され、法的なトラブルに発展する可能性があります。
こんにちは!あなたの会社の「困った」に寄り添う、社労士事務所ぽけっとです。
今回は、妊娠した従業員への対応をめぐる有名な最高裁判例「広島中央保険生協事件」を取り上げます。
この事例から、良かれと思って行った「降格」がなぜ問題になるのか、そして企業としてどのような対応が求められるのかを、分かりやすく解説していきます。
何が起きた?「広島中央保険生協事件」の概要
まずは、どのような事件だったのか、ポイントを絞って見ていきましょう。
【事件の概要】
- 病院で「副主任」として働いていた女性職員が妊娠しました。
- 彼女は、男女雇用機会均等法に基づき、体に負担の少ない「軽易な業務」への転換を病院に請求しました。
- 病院は軽易業務への転換を認めましたが、それと同時に「副主任」の役職を解き、一般職員へと降格させました。
- この降格処分を不服とした女性職員が、「妊娠を理由とする不利益な取り扱いで違法だ」として、病院を訴えました。
病院側としては、「副主任としての責任ある業務は負担が大きいだろう」という配慮だったのかもしれません。
しかし、最高裁判所は「原則として、この降格は違法・無効である」という判断を下しました。一体、どこに問題があったのでしょうか?
裁判所が「違法」と判断した核心部分
この裁判の最大の争点は、「妊娠に伴う軽易業務への転換」をきっかけ(契機)として従業員を降格させることが、男女雇用機会均等法第9条3項で禁止されている「不利益な取扱い」にあたるかどうか、という点でした。
最高裁は、以下の2つの重要なルールを示しました。
ルール1:妊娠を「契機」とした降格は、原則違法!
裁判所は、妊娠や出産、あるいは軽易業務への転換といった出来事から、時間的に接着して(=きっかけとなって)降格などの不利益な取り扱いが行われた場合、それは「妊娠等を理由としてなされた」ものと推定され、原則として均等法に違反し無効である、と判断しました。
つまり、「妊娠して軽易業務に変わったから、役職も変更ね」という安易な降格は、たとえ会社に悪意がなくても許されない、ということです。
ルール2:「例外」として降格が許される「特段の事情」とは?
ただし、裁判所は降格が許される「例外」も示しました。
それは、以下のいずれかの場合です。
- 労働者本人が、自由な意思に基づいて降格を承諾した場合。
- 事業主側に、その降格措置を取らなければ円滑な業務運営や人員配置に重大な支障が生じるなどの「特段の事情」が存在する場合。
この事件で、病院側はこの「特段の事情」を具体的に証明することができませんでした。
そのため、「原則」通り、降格は違法・無効と判断されたのです。
【深掘り解説】降格が許される「特段の事情」とは?
では、この「特段の事情」とは、具体的にどのような状況を指すのでしょうか。
これは、会社が「これ以上どうしようもない」というくらい、極めて限定的な状況に限られます。「降格させなければ事業の運営が不可能になる」レベルの重大な支障を、会社側が具体的に証明する必要があります。
例えば、以下のようなケースが考えられます。
- ケース1:代替不可能な「必置資格者」である場合
事業の運営に法律で義務付けられている資格(例:工場の安全管理者、建設業の専任技術者など)を持つ人が、その従業員しかいない状況。そして、その資格者業務の中に妊娠中には行えない危険な作業が含まれており、あらゆる手を尽くしても代わりの資格者が見つからず、このままでは事業が違法状態になってしまう、といった場合です。 - ケース2:客観的に見て、その人でなければ事業が成り立たない場合
会社の命運をかけたプロジェクトの総責任者で、その人でなければ引き継ぎが不可能であり、役職から外れるとプロジェクトが頓挫して会社が倒産しかねない、といった客観的な状況がある場合です。
一方で、「他の社員の負担が増える」「一時的に業績が落ちる」「引き継ぎが大変」といった理由は、「特段の事情」とは認められません。これらは会社が経営努力で乗り越えるべき課題と見なされるためです。
したがって、ほとんどのケースでは「特段の事情」は認められないと考えるのが妥当です。
この事例から学ぶ、企業が取るべき3つの正しい対応
では、この重要な判例から、私たちは何を学び、日々の労務管理に活かすべきでしょうか。中小企業が押さえるべき3つのポイントを解説します。
1.「降格=配慮」という誤解を捨てる
この事例から学ぶべき最も重要な教訓は、「役職はそのままに、業務内容を調整する」のが大原則だということです。
安易な降格は絶対に避けなければなりません。
では、なぜ病院側は貴重な人材を降格させるという、一見不合理な手段をとってしまったのでしょうか。
その背景には、多くの企業が陥りがちな「誤解」があったと推測されます。
例えば、「責任の重い仕事から外してあげることが、本人への配慮であり善意なのだ」という、会社側の一方的な思い込みがあったのかもしれません。
また、「副主任なら全ての激務をこなせて当たり前。一つでもできなくなれば、もう副主任ではない」という、役職と業務を切り離せない固定観念も影響していたと考えられます。
しかし、裁判所はこの考え方を明確に否定しました。
法律が企業に求めているのは、こうした一方的な「配慮」ではなく、本人のキャリアを尊重し、役職を維持したまま働き続けられるように、業務のやり方を工夫したり、周囲がサポートしたりする体制を整える「義務」なのです。
2.「本人の同意」の取り方には細心の注意を
「本人が納得すればいいんでしょ?」と考えるのは早計です。
裁判所が言う「自由な意思に基づく承諾」とは、会社からのプレッシャーがなく、降格によるメリット・デメリットを本人が正しく理解した上での、真に自由な同意を指します。
「同意しないと不利益があるかも」と従業員が感じるような状況で得た同意書は、後から無効と判断されるリスクが非常に高いです。
面談の記録を残すなど、慎重な手続きが求められます。
3.妊娠報告から復帰までの「支援体制」を整える
トラブルを防ぐ最善策は、妊娠した従業員が安心して働き続けられる体制を普段から作っておくことです。
- 相談窓口の明確化:妊娠の報告を誰に、どのように行えばよいかルールを明確にしておきましょう。
- 代替業務の準備:軽易業務への転換に備え、どのような業務を任せるか、あらかじめいくつかパターンを想定しておくとスムーズです。
- 情報共有と理解促進:管理職向けにマタハラ研修を行うなど、社内全体で「妊娠した従業員を支える」という意識を醸成することが、何よりの予防策になります。
【まとめ】正しい知識で、働く女性を応援できる企業へ
今回は、「広島中央保険生協事件」という重要な判例をもとに、妊娠した従業員への対応について解説しました。
従業員の妊娠は、本来、会社にとっても喜ばしい出来事のはずです。
その大切な時期に、法的な知識不足から従業員を傷つけ、会社自身もリスクを負ってしまうのは、あまりに悲しいことです。
正しい知識を持つこと、そして働く人を大切にする姿勢を示すこと。
それが、従業員から選ばれ、持続的に成長できる企業になるための第一歩です。
「自社の就業規則は大丈夫?」「マタハラ防止のために何をすればいい?」など、具体的なご相談がありましたら、いつでも私たち社労士事務所ぽけっとにお声がけください。
あなたの会社に寄り添い、最適なサポートを提供します。
【免責事項】
本記事は、掲載時点の法令や情報に基づき、一般的な情報提供を目的として作成しております。特定の事実関係によっては、結論が異なる場合がありますので、具体的な事案については、必ず専門家にご相談ください。本記事の情報を利用した結果生じた損害について、当事務所は一切の責任を負いかねます。