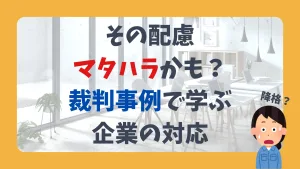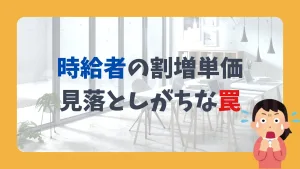【2025年最新版】育休で手取り10割実現へ!「出生後休業支援給付金」を社労士が徹底解説

企業の経営者様、人事担当者の皆様、こんにちは!社労士事務所ぽけっとです。
2025年度は、育児・介護休業法に関して多くの重要な法改正がありました。
その中でも、特に注目されているのが「出生後休業支援給付金(しゅっしょうごきゅうぎょうしえんきゅうふきん)」です。
この新しい制度の登場により、ついに「手取り収入が変わらない育児休業」が現実のものとなりました。
「本当にそんなことが可能なの?」「どんな条件があるの?」と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。
この制度は、産後の大変な時期に従業員が安心して子育てできるよう支援するものであり、企業にとっては人材の定着や採用力の強化にも繋がる大きなチャンスです。
しかし、その内容が複雑で、正確な情報を掴みきれていないというお声も耳にします。
そこで今回は、労務管理の専門家である社労士が、この「出生後休業支援給付金」について、どこよりも分かりやすく、詳しく解説していきます。
この記事を読めば、新制度のすべてが分かり、自信を持って従業員の皆様に説明できるようになります。
【結論】「出生後休業支援給付金」とは?3つのポイント
まず、この新しい制度の核心部分を3つのポイントにまとめました。
出生後休業支援給付金のポイント
- ポイント1:子の出生後、父親は8週間以内、母親は16週間以内に、それぞれ14日以上の育休を取得することが給付の基本です。
- ポイント2:従来の育児休業給付金(67%)に13%が上乗せされ、給付率が合計80%にアップ!
- ポイント3:社会保険料免除と非課税の仕組みにより、実質的な手取り額が休業前の10割相当に!
この制度の最大の目的は、産後の最も大変な時期に夫婦で協力して育児を行うことを経済的に支援し、特に男性の育児休業取得を強力に後押しすることです。
これにより、従業員の家庭と仕事の両立をサポートし、エンゲージメント向上を図ります。
男性育休のリアル:最新データから見る現状と未来
このような強力な制度がなぜ今、導入されたのでしょうか。
その背景には、男性の育児休業取得の大きな変化があります。
厚生労働省の最新調査(令和5年度雇用均等基本調査)によると、男性の育児休業取得率は30.1%となり、前年度の17.13%から約13ポイントも上昇し過去最高を記録しました。
これは、育休取得が男性にとっても当たり前の選択肢になりつつあることの表れです。
しかし、女性の取得率(84.1%)と比較するとまだ差があり、取得期間も「1か月~3か月未満」が最多と、短期の取得に留まるケースが多いのが現状です。
今回ご紹介する「出生後休業支援給付金」は、こうした「取得率の上昇」と「取得期間の短期化」という現状を踏まえ、経済的な不安を解消することで、より長く、ためらわずに育休を取得できる環境を整えることを目的とした、まさに時宜にかなった制度と言えるでしょう。
なぜ「実質手取り10割」が実現するのか?専門家がカラクリを徹底解説!
「給付率は80%なのに、どうして手取りが10割になるの?」
これが、この制度で最も多くの方が疑問に思う点です。
社会保険料の免除(約15%)を足しても、80% + 15% = 95%にしかならず、計算が合わないように感じますよね。
「実質手取り10割」のカラクリを理解するカギは、「税金(特に所得税)」の存在にあります。
普段のお給料から天引きされているものを思い浮かべながら、以下のステップで見ていきましょう。
Step1:普段のお給料から引かれているものを確認
従業員の毎月の「手取り額」は、会社の「総支給額(額面)」から、以下のものが天引きされて計算されています。
- ① 社会保険料(健康保険・厚生年金):約14~15%
- ② 雇用保険料:約0.6%
- ③ 所得税:数%(収入や扶養状況による)
- ④ 住民税(前年の所得に対して課税)
つまり、休業前の手取り額は、総支給額から社会保険料だけでなく、所得税なども引かれた後の金額である、という点が重要です。
Step2:育休中の収入の内訳
次に、出生後休業支援給付金を利用して育休を取得した場合の収入の内訳です。
- 支給されるもの
・育児休業給付金(休業前賃金の67%)
・出生後休業支援給付金(休業前賃金の13%)
※これらを合計して、休業前賃金の80%が支給されます。 - 免除されるもの:①社会保険料、②雇用保険料
- かからないもの:③所得税(給付金は非課税のため)
- 支払うもの:④住民税(前年所得にかかるため支払いは継続)
Step3:手取り10割の答え合わせ
ここで、パズルのピースがすべて揃いました。
休業前の手取り額は、総支給額から「社会保険料(約15%)」と「所得税(数%)」の両方が引かれています。
一方で、育休中は「社会保険料」が免除になり、さらに「給付金が非課税」のため「所得税」もかかりません。
結論として、【給付率80%】と【休業前総支給額100%】の差である20%のうち、約15%分を「社会保険料の免除」が、残りの約5%分を「所得税の非課税」が埋めてくれるのです。
【簡単シミュレーション:月収30万円の例】
<休業前>
総支給額:300,000円
- 社会保険料等:約45,000円
- 所得税・住民税等:約20,000円
→ 手取り額:約235,000円<育休中(新制度利用)>
給付金(80%):240,000円(非課税)
- 住民税:約13,000円
→ 実質収入:約227,000円
いかがでしょうか。
個人の状況により多少の誤差はありますが、休業前の手取り額とほぼ同等の収入が確保できることがお分かりいただけると思います。
これが「実質手取り10割」の正体です。
給付金を受け取るための詳しい条件
この魅力的な給付金ですが、受け取るためにはいくつかの条件があります。
人事担当者として正確に把握しておきましょう。
1. 対象となる期間
給付の対象となる育児休業の期間は、父親と母親で異なります。
・父親の場合:子の出生後8週間以内に取得した育児休業
・母親の場合:産後休業(8週間)が終了した翌日から、子の出生後16週間までの間に取得した育児休業
2. 本人(申請者)の休業日数
上記の各対象期間内に、通算して14日以上の育児休業を取得していること。(※所定労働日が10日以上含まれている必要があります)
3. 配偶者の休業日数
原則として、配偶者もそれぞれの対象期間内に、通算して14日以上の育児休業を取得している必要があります。
【重要】配偶者の育休取得が「不要」となるケース
この制度の大きなポイントですが、以下のような場合は本人のみの育休取得で対象となります。
- 配偶者がいない(ひとり親家庭)
- 配偶者が専業主婦(夫)や自営業者など、雇用保険の被保険者ではない
- 父親が申請する場合で、母親が産後休業期間中である
- 事実婚の配偶者が、育児休業を取得できない場合 など
特に、父親が「産後パパ育休」と合わせてこの制度を利用する場合、母親は産後休業中であることが一般的なため、母親が別途育休を取得していなくても、父親は給付の対象となるケースが多いです。
これは実務上、非常に重要なポイントなので覚えておきましょう。
企業として今すぐ準備・対応すべきこと
この新制度をスムーズに活用し、企業の成長に繋げるために、経営者・人事担当者の皆様には以下の3つの対応をおすすめします。
- 就業規則の確認と見直し
育児・介護休業規程が最新の法改正に対応しているか確認しましょう。
新しい給付金制度について追記し、従業員が利用しやすい環境を整えることが大切です。 - 従業員への積極的な周知
「育休を取ると収入が減る」という不安は、いまだに根強く残っています。
「手取りが変わらない育休制度ができた」というポジティブな情報を、社内説明会や社内報などで積極的に発信し、男女問わず育休を取得しやすい風土を醸成しましょう。 - 申請手続きのサポート体制構築
従業員からの問い合わせにスムーズに対応できるよう、申請の流れや必要書類を事前に確認しておきましょう。
手続きを会社がサポートする姿勢を見せることで、従業員の安心感に繋がります。
よくある質問(Q&A)
Q1. 母親だけが育休を取得する場合、この給付金はもらえますか?
A1. 原則として、配偶者(この場合は父親)も14日以上の育休を取得する必要があります。ただし、配偶者が自営業であるなど育休を取得できない事情がある場合は、母親のみの取得でも対象となる可能性があります。
Q2. 父親が「産後パパ育休」を2回に分けて、合計14日間取得しました。対象になりますか?
A2. はい、対象になります。休業は連続している必要はなく、対象期間内に「通算して」14日以上であれば問題ありません。
Q3. 申請はいつ、どこに行えばよいですか?
A3. 申請は、原則として事業主(会社)を経由して、会社の所在地を管轄するハローワークに行います。申請期間がありますので、育休を取得する従業員には早めに申し出てもらうよう周知しておきましょう。
【まとめ】新制度は企業と従業員の未来を支えるカギ
今回は、2025年4月からスタートした「出生後休業支援給付金」について詳しく解説しました。
この制度は、単なる給付金の上乗せではありません。
産後の従業員の経済的な不安を解消し、男女がともに育児に参加する文化を育むための、国からの強力なメッセージです。
企業がこの制度の活用を後押しすることは、従業員の満足度と定着率を高め、ひいては企業の持続的な成長を支える重要な一手となります。
「うちの会社の規程はどうだろう?」「従業員への説明会を開きたいけれど、どう説明すれば…」など、具体的なお悩みやご相談がございましたら、いつでも私たち社労士事務所ぽけっとにご連絡ください。
貴社の状況に合わせた最適なサポートをご提案させていただきます。
【免責事項】
本記事は2025年7月時点の法令情報に基づき作成しております。法改正等により内容が変更となる可能性がありますので、最新の情報は厚生労働省のホームページ等でご確認いただくか、専門家にご相談ください。本記事の情報を利用した結果生じたいかなる損害についても、当事務所は一切の責任を負いかねます。