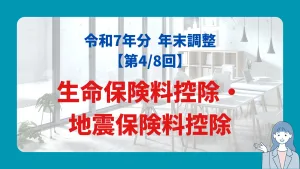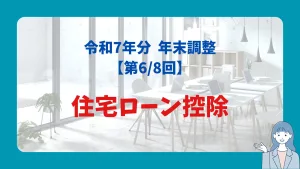【第5/8回】社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除-iDeCoや国民年金も全額控除!忘れると損する節税術
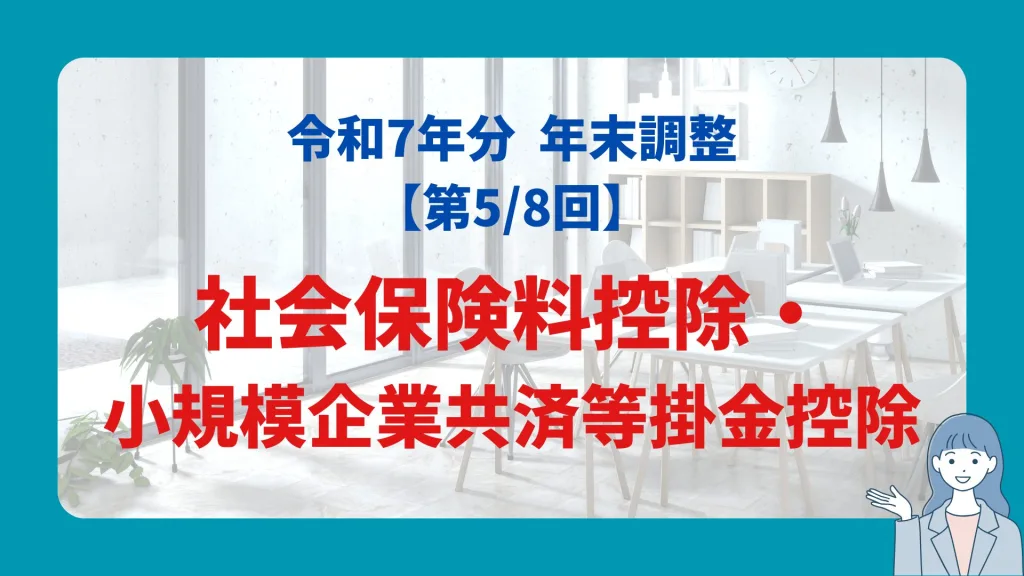
こんにちは!社労士事務所ぽけっとです。
令和7年分年末調整の解説、第5回は、知っていると知らないとでは大違いの「社会保険料控除」と「小規模企業共済等掛金控除」についてです。
この2つの控除の最大の魅力は、なんといっても支払った保険料や掛金の全額が所得から控除されるという点です。これまでの控除とは節税効果のインパクトが違います!
「社会保険料控除」とは?家族の分も対象になる?
社会保険料控除とは、その年に支払った社会保険料の全額を所得から差し引ける制度です。
給与から天引きされている健康保険料や厚生年金保険料は、会社が計算してくれるので申告の必要はありません。
しかし、以下の保険料をご自身で支払った場合は、年末調整での自己申告が必須です。
- 国民年金保険料:20歳以上の学生のお子様の分を親が支払った場合など。
- 国民健康保険料(税):年の途中で退職し、次の就職までに国民健康保険に加入していた期間がある場合など。
- その他、介護保険料や後期高齢者医療保険料など。
特に重要なのが、生計を同一にする配偶者や親族の社会保険料を支払った場合も、支払った本人の控除対象になるという点です。
「大学生の子どもの国民年金保険料を代わりに払ってあげた」というケースは、この控除の申告漏れが非常に多いので、ぜひ覚えておいてください。
「小規模企業共済等掛金控除」とは?iDeCoが対象!
こちらも、支払った掛金の全額が所得控除の対象となる、非常にパワフルな制度です。会社員の方にとって最も身近なのは、iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)の掛金でしょう。
- iDeCo(個人型確定拠出年金):ご自身で加入し、毎月積み立てている掛金が全額この控除の対象です。
- 小規模企業共済:主に個人事業主や会社の役員が加入する退職金制度ですが、こちらの掛金も全額控除の対象です。
iDeCoは、運用益が非課税になるだけでなく、この掛金の全額所得控除によって、毎年の所得税・住民税も安くなるという二重の節税メリットがあります。
加入している方は、絶対に申告を忘れてはいけません。
手続き方法は?証明書の保管がカギ!
これらの控除を受けるためには、第4回で解説した生命保険料控除と同様に、支払いを証明する書類が必要です。
- 証明書の受け取りと保管
- 国民年金保険料:秋頃に日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」がハガキで届きます。
- iDeCo:加入している金融機関(国民年金基金連合会)から「小規模企業共済等掛金払込証明書」が届きます。
- 国民健康保険料:自治体によって異なりますが、専用の証明書は発行されず、納付した際の領収書や通帳の記録で確認するケースが一般的です。
- 保険料控除申告書への記入
「給与所得者の保険料控除申告書」の「社会保険料控除」または「小規模企業共済等掛金控除」の欄に、支払った保険料・掛金の合計額を記入します。 - 証明書の添付・提出
国民年金保険料やiDeCoの控除証明書を申告書に添付して提出します。提出方法は会社のルールに従ってください。
まとめ
今回は、節税効果が絶大な「社会保険料控除」と「小規模企業共済等掛金控除」について解説しました。
- 支払った保険料・掛金の「全額」が所得から控除される、最強クラスの節税術!
- 自分で支払った国民年金や国民健康保険料が対象。
- 生計を同一にする家族の分の国民年金保険料を支払った場合も対象になる!
- iDeCoの掛金も全額控除の対象。加入者は申告必須!
上限額がある他の控除と違い、支払った分だけ税金が安くなる非常に有利な制度です。
申告漏れがないよう、ご自身の支払状況を今一度ご確認ください。
次回は、マイホームをお持ちの方に関係が深い「住宅ローン控除」について解説します。
どうぞお楽しみに。
次は
【令和7年分 年末調整ブログ 全8回シリーズ】
▶ 第1回:【基礎控除・給与所得控除】すべての給与所得者必見!令和7年税制改正の基本
▶ 第2回:【配偶者控除・配偶者特別控除】「103万円の壁」はもう古い!令和7年からの新しい働き方
▶ 第3回:【扶養控除】大学生に新制度!令和7年改正の重要ポイント
▶ 第4回:【生命保険料控除・地震保険料控除】改正はなくても節税効果大!申告書の書き方ガイド
▶ 第5回:【社会保険料控除と小規模企業共済等掛金控除】iDeCoや国民年金も全額控除! ★現在この記事を読んでいます
▶ 第6回:【住宅ローン控除】2年目以降の手続きと令和7年改正後の注意点
【免責事項】
本記事は、2025年8月時点の法令等に基づき作成されております。今後の法改正等により、内容が変更となる可能性があります。また、個別の税務相談等には応じかねますので、ご了承ください。正確な情報提供を心がけておりますが、本記事の内容に基づくいかなる行為についても、当事務所は一切の責任を負いかねます。