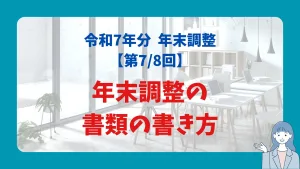【第8/8回】総まとめ編-令和7年改正対応!企業担当者がやるべきことチェックリスト
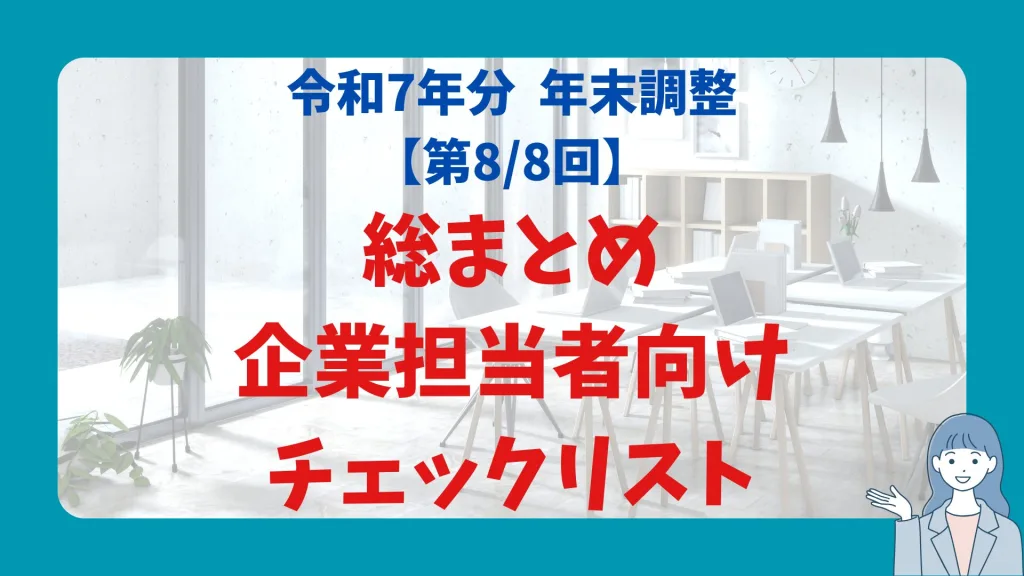
こんにちは!社労士事務所ぽけっとです。
全8回にわたってお届けしてきた「令和7年分 年末調整」ブログも、いよいよ最終回を迎えました。
今回は、これまでの内容を総括し、企業の人事・労務ご担当者様が、いつ、何をすべきかを時系列で確認できる、実用的なチェックリスト形式でご紹介します。
今年の年末調整は改正点が多く複雑ですが、このリストに沿って準備を進めれば、きっとスムーズに乗り切れるはずです!
【準備段階:9月~10月】段取りが成功のカギ!
年末調整は、この時期の準備が9割と言っても過言ではありません。
- 改正内容の再確認と理解
まずは担当者自身が、今回の大きな改正点をしっかり理解しましょう。
特に重要なのは、「基礎控除の複雑化」「配偶者控除の壁の変更」「扶養控除(特定親族特別控除)の新設」の3点です。 - 従業員への事前アナウンス準備
11月に申告書を配布する前に、社内報や掲示板などで「今年の年末調整は大きく変わります」という予告をしておくと、従業員の意識が高まります。
特にパートタイマーの方には、「税金の壁と社会保険の壁は別です」という注意喚起が重要です。 - 年末調整ツールの確認・導入検討
年末調整ツール(システム)を利用している場合は、令和7年の改正に完全対応しているか、ベンダーに確認しましょう。
まだ導入していない場合は、業務効率化のために導入を検討する絶好の機会です。 - 申告書類の準備
税務署から送られてくる、あるいは国税庁のサイトからダウンロードする申告書の様式が、令和7年分の新しいものであることを確認します。
特に、あの長い名前の申告書(基礎控除申告書…)が新しくなっているか要チェックです。
【実施段階:11月~12月】丁寧な対応がミスを防ぐ
いよいよ従業員への書類配布と回収が始まります。
丁寧なコミュニケーションを心がけましょう。
- 申告書類の配布と説明
申告書を配布する際は、変更点をまとめた簡単な説明資料を添付すると親切です。
特に、新設された「特定親族特別控除」の欄は、対象となる従業員(19歳~22歳の子がいる方)に個別に声をかけると、申告漏れを防げます。 - 控除証明書等の回収
生命保険料や地震保険料、iDeCoなどの控除証明書の提出を呼びかけます。
電子申告の場合は、原本を後日回収する旨を明確に伝えましょう。 - 問い合わせ対応と書類チェック
従業員からの質問が増える時期です。特に多いと予想される質問への回答例を準備しておくとスムーズです。
(下記Q&A参照) 回収した書類は、記入漏れや計算ミス、証明書の添付漏れがないか、丁寧に確認します。
【完了段階:12月~1月】最後の仕上げを確実に
年税額を確定させ、最終的な精算を行います。
- 年税額の計算と過不足額の確定
回収した申告書に基づき、一人ひとりの年税額を計算し、毎月徴収してきた源泉所得税額との差額(還付または追徴)を確定させます。 - 給与への反映
確定した過不足額を、12月または1月の給与で精算します。
給与明細には「年末調整還付」「年末調整追徴」などの項目で分かりやすく記載しましょう。 - 法定調書の作成・提出
源泉徴収票や支払調書などの法定調書を作成し、翌年1月末までに税務署や市区町村へ提出します。
従業員からよくある質問(Q&A)
Q1. パートの壁が160万円になったと聞きました。扶養に入ったまま、160万円まで働けますか?
A1. いいえ、注意が必要です。
ご自身の所得税がかからなくなるのが「160万円の壁」です。
ご主人が税金の扶養に入れる壁は、満額の「配偶者控除」が受けられる「123万円の壁」となります。
ただし、年収が123万円を超えても、すぐに控除がゼロになるわけではなく、収入に応じて段階的に控除が受けられる「配偶者特別控除」という制度があります。
また、健康保険などの「社会保険の壁(106万円など)」はこれらとは全く別の制度ですので、ご注意ください。
Q2. 大学生の子どもがいます。何か変わりますか?
A2. はい、大きく変わります。
お子様のアルバイト収入が年収123万円を超えた場合でも、新しくできた「特定親族特別控除」を受けられる可能性があります。
申告書の新しい欄に、お子様の所得などを記入してください。
全8回にわたり、令和7年分の年末調整について解説してまいりました。
今年の改正は複雑ですが、一つひとつを正しく理解し、計画的に準備を進めることが、担当者様ご自身の負担を軽くし、従業員の皆様の安心にも繋がります。
この連載が、皆様の年末調整業務の一助となれば幸いです。最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
【令和7年分 年末調整ブログ 全8回シリーズ】
▶ 第1回:【基礎控除・給与所得控除】すべての給与所得者必見!令和7年税制改正の基本
▶ 第2回:【配偶者控除・配偶者特別控除】「103万円の壁」はもう古い!令和7年からの新しい働き方
▶ 第3回:【扶養控除】大学生に新制度!令和7年改正の重要ポイント
▶ 第4回:【生命保険料控除・地震保険料控除】改正はなくても節税効果大!申告書の書き方ガイド
▶ 第5回:【社会保険料控除と小規模企業共済等掛金控除】iDeCoや国民年金も全額控除!
▶ 第6回:【住宅ローン控除】2年目以降の手続きと令和7年改正後の注意点
▶ 第7回:【書類の書き方編】令和7年改正対応!新しい年末調整申告書の記入例
▶ 第8回:【総まとめ編】令和7年改正対応!企業担当者がやるべきことチェックリスト ★現在この記事を読んでいます
【免責事項】
本記事は、2025年8月時点の法令等に基づき作成されております。今後の法改正等により、内容が変更となる可能性があります。また、個別の税務相談等には応じかねますので、ご了承ください。正確な情報提供を心がけておりますが、本記事の内容に基づくいかなる行為についても、当事務所は一切の責任を負いかねます。