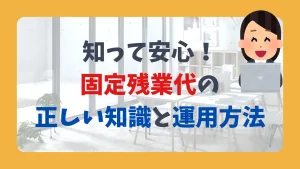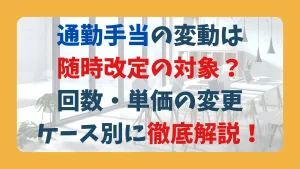休日出勤の割増賃金、払う必要ある?「法定休日」と「所定休日」の違いがカギ!
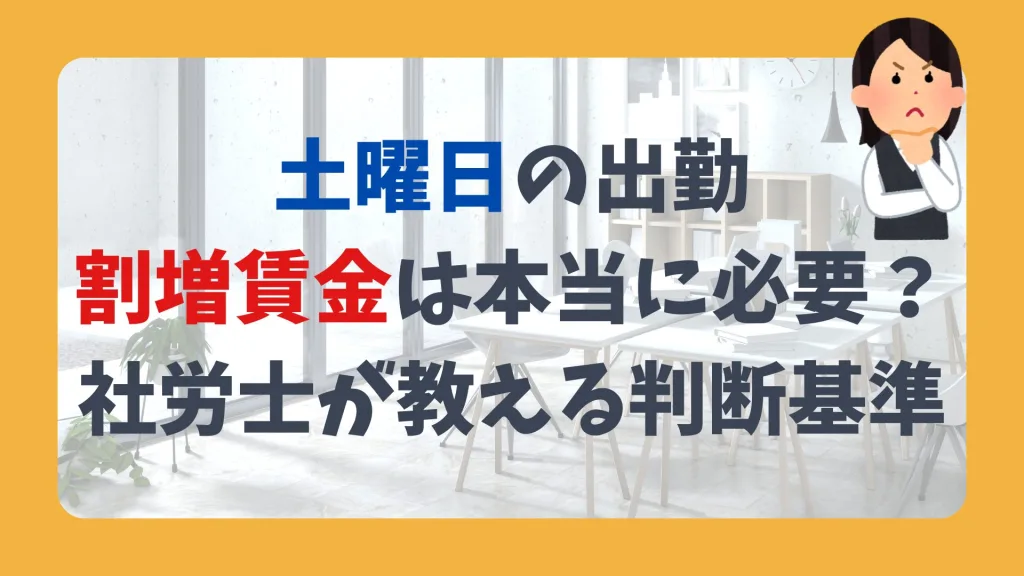
こんにちは!社労士事務所ぽけっとです。
中小企業の経営者様や人事担当者様から、給与計算に関するご相談をよくいただきます。
中でも特に間違いやすく、質問が多いのが「休日出勤の際の賃金」についてです。
「急な仕事で、土曜日に従業員に出勤してもらった。割増賃金は必要?」
「振替休日を取得させたから、割増は払わなくていいんだよね?」
「カレンダー上は休みだけど、週の労働時間は40時間を超えていない。この場合はどうなる?」
こんな風に悩んだ経験はありませんか?
もし、休日出勤の賃金計算を正しく行わないと、従業員とのトラブルや、労働基準監督署からの是正勧告、最悪の場合は未払い賃金の請求といった大きなリスクに繋がる可能性があります。
そこで今回は、休日出勤における割増賃金の考え方について、その基本となる「法定休日」と「所定休日」の違いから、具体例を交えて分かりやすく解説していきます。
まず結論!その休日出勤、割増賃金が不要なケースもあります
所定休日の労働であり、かつ、その週の合計労働時間が40時間を超えていない場合、原則として割増賃金の支払い義務はありません。
「え、そうなの!?」と思われた方も多いかもしれませんね。
この結論を正しく理解するためには、休日には2つの種類があることを知る必要があります。
それが「法定休日」と「所定休日」です。この違いが、割増賃金の有無を分ける最も重要なポイントなのです。
最重要ポイント!「法定休日」と「所定休日」の違いとは?
休日と一括りに考えがちですが、法律上の扱いは全く異なります。
まずはこの2つの違いをしっかり押さえましょう。
法定休日とは?
法律(労働基準法第35条)で定められた、会社が従業員に必ず与えなければならない最低限の休日のことです。
- 原則:毎週少なくとも1回
- 例外:4週間を通じて4日以上(変形休日制)
この法定休日に労働させることを「休日労働」と呼び、これには35%以上の割増賃金(休日労働手当)の支払いが必要です。
これは、その週の労働時間が40時間に満たない場合でも、必ず発生します。
所定休日とは?
会社が独自に就業規則などで定めている、法定休日以外の休日のことです。
例えば、完全週休2日制(土日休み)の会社で、日曜日を「法定休日」と定めている場合、土曜日が「所定休日」にあたります。
この所定休日の労働は、法律上「休日労働」にはなりません。
そのため、休日労働の割増率(35%以上)は適用されません。
ではどう扱われるかというと、「時間外労働(残業)」と同じ扱いになります。
つまり、所定休日の労働によって、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた部分に対して、25%以上の割増賃金(時間外手当)が発生するのです。
ポイントのまとめ
- 法定休日の労働 → 休日労働
→ 労働時間に関わらず賃金割増率35%以上 - 所定休日の労働 → 時間外労働としてカウント
→ 週の労働時間が40時間を超えた部分に賃金割増率25%以上
【具体例で確認】3つのケースで給与計算をシミュレーション
言葉だけでは分かりにくい部分を、具体的なケースで見ていきましょう。
時給1,500円、月~金が労働日、土曜が所定休日、日曜が法定休日、1日の所定労働時間8時間の会社とします。
ケース1:所定休日に短時間労働し、週40時間を超えない場合
月~木:8時間勤務(計32時間)
金曜日:休み
土曜日(所定休日):5時間勤務
日曜日(法定休日):休み
週の合計労働時間:32時間 + 5時間 = 37時間
この場合、週の合計労働時間が40時間を超えていません。
したがって、土曜日に働いた5時間分に割増賃金は不要です。
【土曜日の給与】
1,500円 × 5時間 = 7,500円
ケース2:所定休日に労働し、週40時間を超えた場合
月~金:8時間勤務(計40時間)
土曜日(所定休日):3時間勤務
日曜日(法定休日):休み
週の合計労働時間:40時間 + 3時間 = 43時間
この場合、月~金ですでに週の法定労働時間40時間に達しています。
そのため、土曜日に働いた3時間はすべて時間外労働となり、25%以上の割増賃金が必要です。
【土曜日の給与】
(1,500円 × 1.25) × 3時間 = 5,625円
ケース3:法定休日に労働した場合
月~金:8時間勤務(計40時間)
土曜日(所定休日):休み
日曜日(法定休日):6時間勤務
週の合計労働時間:40時間 + 6時間 = 46時間
この場合、労働したのは法定休日です。したがって、日曜日に働いた6時間はすべて休日労働となり、35%以上の割増賃金が必要です。
【日曜日の給与】
(1,500円 × 1.35) × 6時間 = 12,150円
給与計算前に要チェック!休日労働の注意点
基本的な考え方は上記のとおりですが、いくつか注意すべき点があります。
1. 就業規則の規定が法律を上回る場合がある
会社によっては、「所定休日の労働にも一律で割増賃金を支払う」といった、法律を上回る有利な条件を就業規則で定めている場合があります。
その場合は、会社のルールが優先されます。
まずは自社の就業規則を必ず確認しましょう。
2. 法定休日は特定が必要
「土日休みのうち、どちらが法定休日?」という問題があります。
労働基準法では曜日の指定はないため、会社が就業規則で「法定休日は日曜日とする」のように特定しておくことが望ましいです。
特定がない場合、暦週(日~土)において後順の休日(土曜日)が法定休日と解釈されるなど、判断が複雑になる可能性があります。
3. 「振替休日」と「代休」は全くの別物
休日労働とセットでよく出てくるのが「振替休日」と「代休」です。
この2つも混同されがちですが、割増賃金の計算に大きく影響します。
- 振替休日
事前に休日と労働日を入れ替えること。
もともとの休日は労働日になるため、「休日労働」とはならず、割増賃金は発生しない(ただし、週40時間を超えた分は時間外割増が必要)。 - 代休
事後的に、休日労働の代償として他の労働日に休みを与えること。
休日労働の事実は消えないため、休日労働に対する割増賃金(35%以上)の支払いは必要。
【まとめ】正しい知識で、適切な労務管理を
今回は、休日出勤における割増賃金の考え方について解説しました。
最後に、重要なポイントを3つにまとめます。
- まずは「法定休日」と「所定休日」を区別する。自社の就業規則でどちらが法定休日かを確認しましょう。
- 所定休日の労働は「時間外労働」として考える。週の合計労働時間が40時間を超えるかどうかで割増の有無を判断します。
- 法定休日の労働は「休日労働」となる。労働時間に関わらず35%以上の割増賃金が必要です。
給与計算は、従業員の生活に直結する非常に重要な業務です。
そして、会社の信頼を守る上でも欠かせません。
もし、「自社の運用が正しいか不安…」「就業規則を見直したい」「給与計算を専門家に任せたい」といったお悩みがありましたら、ぜひ一度、私たち社労士事務所ぽけっとにご相談ください。
貴社の状況に合わせた最適なサポートをご提案させていただきます。
【免責事項】
本記事は、掲載時点の法令・情報に基づき作成しております。法改正や情報更新により、一部内容が現状と異なる場合があります。また、個別の事案については、具体的な状況によって結論が異なる可能性があります。本記事の情報を利用した結果生じた損害等について、当事務所は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。最終的な判断は、顧問社労士等の専門家にご相談ください。