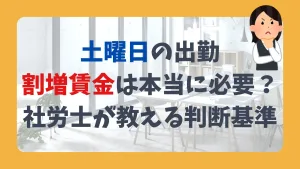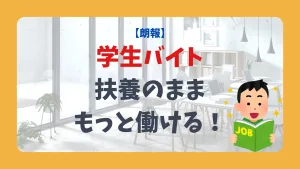通勤手当の変動は随時改定の対象?回数・単価の変更ケース別に徹底解説!
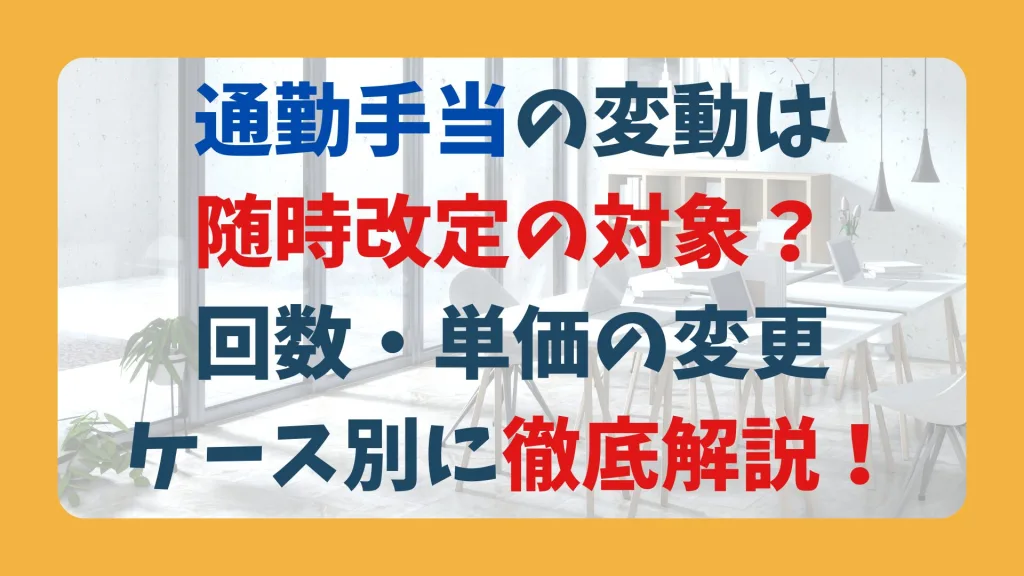
こんにちは。社労士事務所ぽけっとです。
社会保険料の計算の基礎となる「標準報酬月額」。
その見直しのために行われるのが「随時改定(月額変更届)」です。
何度も随時改定については解説してきましたが、実務では「このケースは対象になるのだろうか?」と判断に迷う場面が少なくありません。
特にご相談が多いのが、「通勤手当」の変動です。
従業員の働き方の変化や交通費の改定など、通勤手当は意外と変動する機会が多いもの。
しかし、その変動が随時改定の対象になるかどうかは、ケースバイケースで判断が分かれます。
そこで今回は、一歩踏み込んで、通勤手当の変動と随時改定の関係について、具体的なケースを交えながら詳しく解説していきます。
通勤手当の変動と随時改定の基本的な考え方
まず大前提として、通勤手当は社会保険の「報酬」に含まれます。
そのため、通勤手当の金額が変更されれば、随時改定の対象になる可能性があります。
随時改定は、以下の3つの条件をすべて満たした場合に行います。
- 昇給・降給などにより「固定的賃金」に変動があった
- 変動月以後継続した3か月間に支払われた報酬の平均月額と、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた
- 3か月とも支払基礎日数が17日以上である
ここでの最大のポイントは、通勤手当の変動が「1. 固定的賃金の変動」に該当するかどうかです。
固定的賃金とは、支給額や支給率が固定されているものを指します。
基本給や役職手当などが代表例です。
一方で、残業手当のように、毎月の勤務状況によって変動するものは「非固定的賃金」と呼ばれ、これだけが増減しても随時改定の対象にはなりません。
では、通勤手当の変動はどちらに当てはまるのでしょうか。
ケース別に見ていきましょう。
ケース1:通勤「回数」の変動は対象になる?
在宅勤務の導入などにより、出社日数に応じて通勤手当を実費支給するケースが増えています。
このような「回数」の変動は、随時改定の対象になるのでしょうか。
原則:固定的賃金の変動ではないため「対象外」
例えば、「1日往復500円」のように日額で通勤手当を支給しているとします。
ある従業員が、在宅勤務が増えたことで1か月の出社日数が20日から15日に減り、通勤手当が10,000円から7,500円に減ったとします。
この場合、通勤手当の単価(1日500円)自体は変わっていません。
変動したのは「出社日数」という、月によって変動する要素です。
これは残業時間と同じように考え、「非固定的賃金」の変動とみなされます。
したがって、単に出社日数が変わっただけで通勤手当の支給額が変動した場合は、固定的賃金の変動には該当せず、随時改定の対象にはなりません。
注意点:支給「方法」の変更は「対象」になる可能性
ただし、注意が必要です。
もし会社が支給方法そのものを変更した場合は、話が変わってきます。
例えば、これまで「出社日数に応じた実費支給」だったものを、「在宅勤務の有無にかかわらず、全員に1か月分の定期代相当額を支給する」というルールに変更したとします。
また、支給する定期券の種類を6か月のものから3か月のものへ変更した場合も、社会保険料の計算のもととなる1か月あたりの報酬額が変わるため、「固定的賃金」の変動とみなされます。
これらは、賃金の計算方法(単価や支給形態)そのものが変更されたことになるため、「固定的賃金」の変動に該当します。
この変更によって、他の条件(2等級以上の差など)も満たせば、随時改定の対象となります。
ケース2:通勤「単価」の変動は対象になる?
次に、通勤に使う交通機関の運賃改定や、マイカー通勤の支給額の計算根拠が変わった場合など、「単価」が変動したケースを見ていきましょう。
公共交通機関の定期代が改定された場合 → 「対象」
これは判断がしやすいケースです。
従業員が利用している鉄道会社の運賃が改定され、会社が支給する定期代が月額12,000円から12,500円に上がったとします。
これは、通勤手当の算定の基礎となる単価そのものが変わったため、「固定的賃金」の変動に該当します。
したがって、随時改定の対象となります。
マイカー通勤手当の計算方法が変更された場合 → 「対象」
マイカー通勤の場合も同様に考えます。例えば、以下のようなケースは「固定的賃金」の変動です。
- 距離に応じて支給する単価を変更した(例:1kmあたり15円 → 20円に変更)
- 支給額の計算式そのものを変更した(例:距離だけでなく、燃費も考慮した新しい計算式を導入した)
これらのように、会社の規程変更などによって通勤手当の計算の基礎が変わった場合は、随時改定の対象となります。
【要注意】ガソリン単価の変動を支給額に反映させる場合
少し複雑なのが、ガソリンの市場価格の変動を通勤手当に反映させるケースです。
もし、「毎月のガソリンの平均価格を算出し、それに基づいて翌月の支給単価を決定する」というように、毎月のように単価が見直されるルールになっている場合、その変動は「非固定的賃金」の扱いとなり、随時改定の対象にはなりません。
一方で、「半期に一度、ガソリン単価を見直して次の半年間の支給単価を固定する」といったルールであれば、その単価が改定されたタイミングは「固定的賃金」の変動とみなされ、随時改定の対象になります。
ポイントは、その単価が一時的なものか、一定期間固定されるものか、という点です。
まとめ
今回は、通勤手当の変動に伴う随時改定の判断について、具体的なケースを挙げて解説しました。
ポイントをまとめると以下のようになります。
- 通勤手当の変動が「固定的賃金」の変動かどうかが重要。
- 出社日数など、月によって変わる要素で支給額が変動するのは「非固定的」→ 対象外。
- 定期代の改定や支給単価の変更など、算定基礎が変わるのは「固定的」→ 対象。
- 支給方法そのものを変更した場合も「固定的」→ 対象。
通勤手当は、従業員一人ひとりの状況によって異なり、管理が煩雑になりがちです。
随時改定の要否の判断は、社会保険料の正しい計算に不可欠であり、誤ると将来の年金額にも影響を与えかねません。
「うちの会社のこのケースは、どう判断すればいいんだろう?」
もし判断に迷われた際は、ぜひ一度、私たち社労士事務所ぽけっとにご相談ください。
専門家の視点から、貴社の状況に合わせた適切なアドバイスをさせていただきます。
※免責事項
本記事は、作成日時点の法令および情報に基づき作成しております。法改正や情報更新により、掲載内容が最新の状況と異なる場合がございます。また、個別の事情によっては本記事の内容が当てはまらない場合もございます。最終的なご判断は、必ず専門家にご相談いただくか、管轄の行政機関にご確認くださいますようお願い申し上げます。