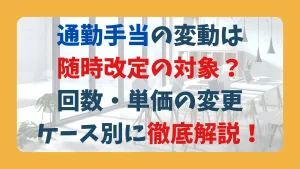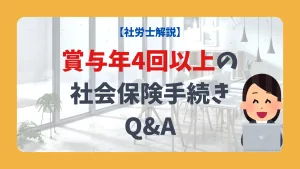【令和7年10月改正】19歳~22歳の扶養は「150万円の壁」に!変更点を社労士が解説
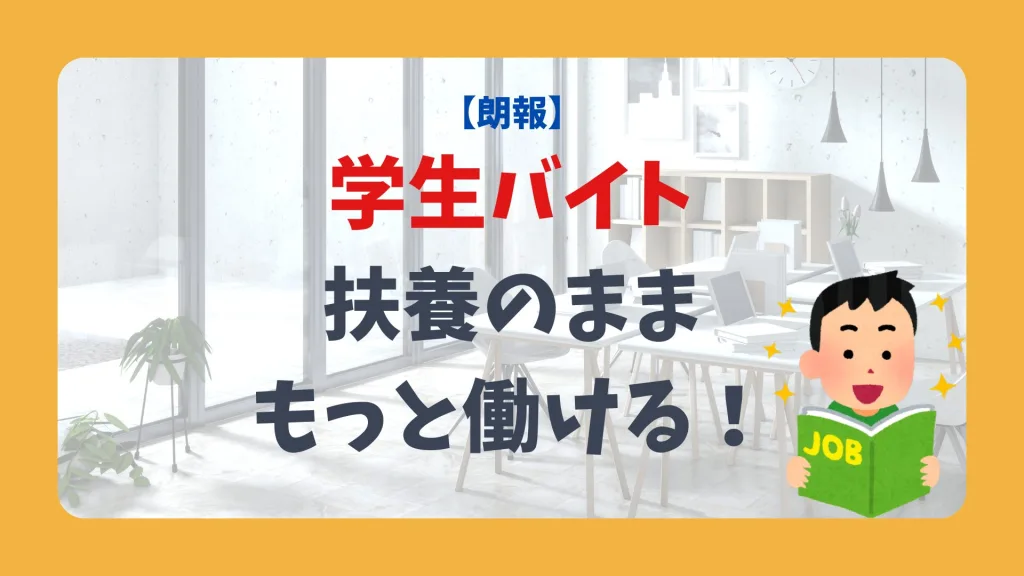
こんにちは!社労士事務所ぽけっとです。
日々の労務管理、お疲れ様です。
さて、今回は企業の社会保険手続きご担当者様、そして大学生などのお子様を扶養されている保護者の方にとって、非常に大きな影響のある制度改正について、改めて解説します。
すでにご存じの方も多いかと思いますが、令和7年10月から19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が、現行の130万円未満から150万円未満に引き上げられます。
いわゆる「130万円の壁」が、この年齢層に限って緩和されることになります。
今回はこの新しいルールについて、変更点や注意すべき「年齢判定のタイミング」などを解説していきます!
【最大の変更点】年間収入要件が「150万円未満」に緩和されます
今回の制度改正で最も重要なポイントは、収入要件そのものが変更される点です。
【変更点のポイント】
令和7年10月1日以降の扶養認定から、19歳以上23歳未満の方については、健康保険の被扶養者となるための年間収入要件が、現行の「130万円未満」から「150万円未満」に緩和されます。
これは、主に学生アルバイトなどで働くことが多いこの年齢層の方々が、収入を気にすることなく就業経験を積めるように支援する目的があると考えられます。
ただし、この150万円未満という基準が適用されるのは、あくまで19歳以上23歳未満の方のみであり、それ以外の年齢の方(配偶者など)は、引き続き原則130万円未満の基準となりますので注意が必要です。
【要注意】年齢判定は「いつの時点」で行う?
収入要件が緩和される一方で、誰がその対象になるのか、という「年齢判定のタイミング」は非常に重要です。
この点については、日本年金機構から明確な基準が示されています。
【年齢判定の基準】
扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
「扶養認定日」とは、被扶養者として認定されるべき事実が発生した日(例:退職日の翌日、開業日など)のことです。この日が含まれる年の、年末12月31日時点での年齢で判断する、ということです。
ケーススタディで理解を深めよう!
ケース1:年の途中で19歳になるAさんの場合
- Aさんの状況:2025年11月1日に19歳の誕生日を迎える。2025年10月15日から扶養に入りたい。
- 扶養認定日:2025年10月15日
- 年齢判定の基準日:扶養認定日(10月15日)が属する年の年末 → 2025年12月31日
- 判定:2025年12月31日時点でAさんは19歳です。したがって、Aさんは年間収入150万円未満の新基準が適用されます。
→ 扶養に入りたい時点ではまだ18歳ですが、その年の年末には19歳になっているため、新基準の対象となります。
ケース2:年の途中で23歳になるBさんの場合
- Bさんの状況:2026年5月1日に23歳の誕生日を迎える。2026年4月1日から扶養に入りたい。
- 扶養認定日:2026年4月1日
- 年齢判定の基準日:扶養認定日(4月1日)が属する年の年末 → 2026年12月31日
- 判定:2026年12月31日時点でBさんは23歳です。今回の緩和措置は「19歳以上23歳未満」が対象です。23歳は「23歳未満」には含まれません。
→したがって、Bさんは新基準の対象外となり、従来の「130万円未満」の基準で判断されます。
【重要】「150万円の壁」と「勤務先の社会保険加入」は別の話!
今回の改正で扶養に入れる収入上限が150万円未満に緩和されましたが、ここで一つ大きな注意点があります。
それは、ご自身のアルバイト先での社会保険の加入義務です。
たとえ年収が150万円未満でも、ご自身の働き方によってはアルバイト先で社会保険に加入することになり、その結果、親の扶養から外れることになります。
特に、いわゆる「106万円の壁」と言われる短時間労働者の社会保険加入要件には注意が必要です。
▼短時間労働者の社会保険加入要件(106万円の壁)
お勤め先の従業員数(※)が51人以上の場合、以下の要件をすべて満たすと、原則として社会保険の加入対象となります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上
- 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではないこと
※従業員数は、令和6年10月からは51人以上ですが、将来的にはさらに拡大される予定です。
【重要:学生の特例について】
上記の通り、昼間学生の方は、この短時間労働者の社会保険加入の対象外です。
そのため、従業員数51人以上の企業で週20時間以上働いたとしても、学生である限りは勤務先で社会保険に加入せず、親の扶養に入り続けられるケースが多くなります。
ただし、休学中の方や、大学の夜間学部・定時制課程の方は加入対象となる場合がありますので、個別の確認が必要です。
では、どのような働き方であれば、この150万円の緩和措置を最大限活用できるのでしょうか。
ポイントは、ご自身が勤務先の社会保険に加入しない働き方を選択することです。
- ケース① 複数のアルバイトを掛け持ちする
社会保険の加入義務は、1社ごとの労働条件で判断されます。例えば、A社で週15時間(年収80万円)、B社で週10時間(年収65万円)といった働き方であれば、どちらの会社でも加入義務は発生せず、合計年収145万円でも扶養に入り続けられます。 - ケース② 時給が高く、労働時間が短い
時給1,500円で週18時間勤務といった場合、週20時間未満なので加入義務は発生せず、年収約140万円でも扶養に入ることが可能です。
この点を従業員の方、特にお子様本人にしっかり伝えておくことが、後のトラブルを防ぐために重要です。
人事担当者が注意すべき実務上のポイント
- 従業員への積極的な周知
今回の変更は、対象となるお子様がいる従業員にとっては朗報です。社内ポータルや給与明細への同封などで、「お子様の扶養の収入上限が150万円に緩和されますが、働き方には注意が必要です」といった形で、セットで周知しましょう。 - 年齢確認の徹底
130万円と150万円の基準が混在することになるため、「扶養認定日が属する年の12月31日」時点での年齢確認が、これまで以上に重要になります。手続きの際には生年月日を正確に確認しましょう。 - 年間収入の見込み額での判断
収入の判定は、あくまで「今後1年間の収入見込額」で行います。直近の給与明細や雇用契約書などから、年間収入が150万円未満に収まるかを確認する必要があります。
よくある質問(Q&A)
Q1. なぜ19歳以上23歳未満だけが対象なのですか?
A1. 背景には令和7年度税制改正があります。
深刻な人手不足への対策として、税制上の特定扶養控除の要件が見直されたことと歩調を合わせた対応とされています。
Q2. 税金の扶養(103万円の壁)も変わりますか?
A2. はい、税金の扶養の考え方も大きく変わります。
今回の社会保険の変更と歩調を合わせ、令和7年分の所得税から19歳以上23歳未満の扶養親族についても、事実上「150万円の壁」が設定されることになりました。
具体的には、従来の「特定扶養控除」が見直され、年収103万円を超えても150万円までであれば、収入に応じて段階的に控除が受けられる新しい仕組み(特定親族に対する扶養控除の特例)に変わります。
ただし、社会保険の扶養と税金の扶養は別の制度である点に変わりはありませんので、詳細は個別の確認が必要ですが、この年齢層については収入上限の考え方が近しくなるとご理解ください。
Q3. 令和7年9月30日以前の扶養認定はどうなりますか?
A3. 令和7年9月30日以前の扶養認定については、現行の「130万円未満」の基準で審査されます。
新基準は、あくまで令和7年10月1日以降の認定から適用されます。
まとめ
今回は、令和7年10月から変更される、19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定の新しいルールについて解説しました。
重要なポイントは、「対象年齢であれば、年間収入の壁が150万円未満に緩和される」という点と、「対象年齢かどうかは、年末12月31日時点で判断する」という2点です。
このルールを正しく理解し、社内で周知することが大切です。
特に、企業の担当者様は、以下の2つの視点で従業員の方へ案内すると、より分かりやすくなります。
▼ 19歳~22歳のお子様等を扶養している従業員の皆様へ
今回の上限緩和により、お子様がこれまで以上にアルバイト等で働きやすくなります。
ただし、お子様自身の勤務先で社会保険の加入義務(週20時間以上勤務など)が発生すると、年収150万円未満でも扶養から外れてしまいます。
この点を、ぜひご家族で共有してください。
▼ 自社で働く19歳~22歳の従業員(学生アルバイト等)を雇用している担当者様へ
自社で働く学生アルバイトの方が親の扶養に入っている場合、今回の改正で年収上限を気にする方が増えるかもしれません。
その従業員が扶養内で働くことを希望している場合は、年収だけでなく「週20時間未満」といった社会保険に加入しない働き方のルールも合わせて説明してあげることが、後のトラブル防止に繋がります。
社会保険の手続きは法改正も多く、複雑で分かりにくい点も多いかと思います。
もしご不明な点や、給与計算・社会保険手続きのアウトソーシングにご興味がございましたら、いつでもお気軽に社労士事務所ぽけっとまでご相談ください。
【免責事項】
本記事は、公開日時点の法令や情報に基づいて作成しております。法改正等により、今後の取り扱いが変更される可能性があることをご了承ください。記事の内容の正確性については万全を期しておりますが、本記事を利用して生じたいかなる損害についても、当事務所は一切の責任を負いかねます。具体的な個別の事案については、必ず専門家にご相談ください。