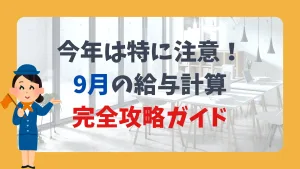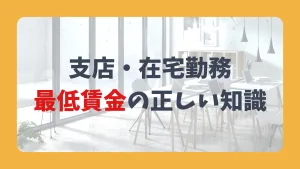夜勤の給与計算はココに注意!深夜手当や日付またぎの割増賃金の計算方法
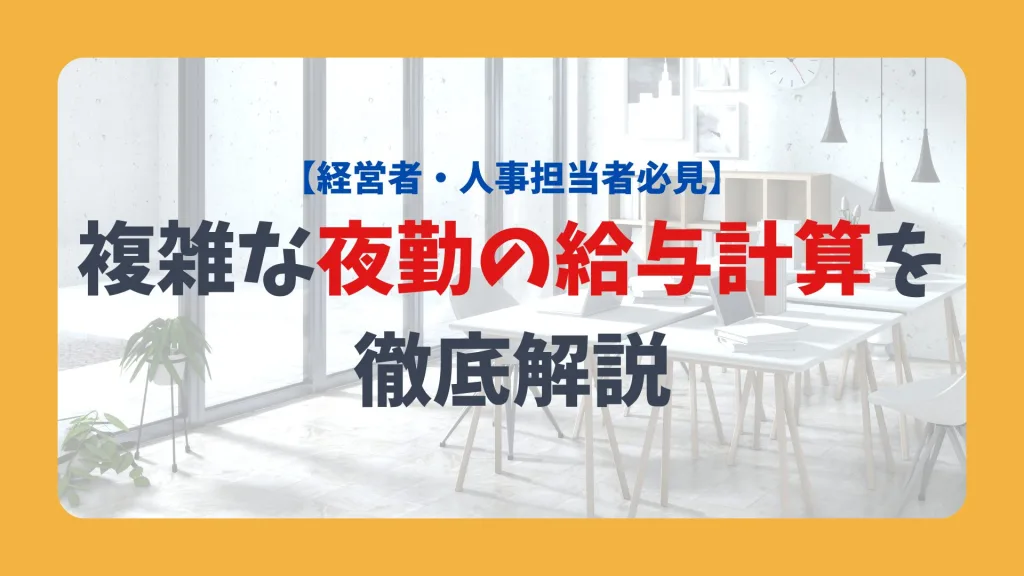
24時間稼働する工場や、夜間の見守りが必要な介護施設、年中無休のコンビニエンスストアなど、私たちの社会は夜間に働く人々によって支えられています。
従業員の方々が安心して働ける環境を提供するためには、正確な給与計算が不可欠です。
しかし、夜勤の給与計算は、日勤のみの場合と比べて少し複雑になります。
「深夜手当の計算は?」「勤務が日付をまたぐ場合はどうなるの?」といった疑問をお持ちの経営者や人事担当者の方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、社会保険労務士が夜勤の給与計算における重要な注意点を分かりやすく解説します。
正しい知識を身につけ、適切な労務管理にお役立てください。
まずは基本から!労働時間と割増賃金のルール
夜勤の計算を理解する前に、まずは労働基準法で定められている労働時間と割増賃金の基本ルールをおさらいしましょう。
- 法定労働時間:原則として、1日8時間・1週40時間以内
- 時間外労働(残業):法定労働時間を超えて労働させた場合、25%以上の割増賃金が必要
- 休日労働:法定休日(週1日または4週4日)に労働させた場合、35%以上の割増賃金が必要
- 深夜労働:午後10時(22時)から午前5時までの間に労働させた場合、25%以上の割増賃金が必要
夜勤の給与計算で特に重要になるのが、この「深夜労働」に対する割増賃金(深夜手当)です。
【注意点1】深夜労働と時間外・休日労働が重なった場合の割増率
夜勤で最も間違いやすいのが、割増賃金が重複するケースです。
例えば、「法定時間外労働」が「深夜」に行われた場合、それぞれの割増率を足し合わせる必要があります。
具体的なパターンと割増率を見ていきましょう。
パターン1:時間外労働 + 深夜労働
法定労働時間(1日8時間)を超えた残業が、深夜時間帯(22時~翌5時)に行われた場合です。
割増率:時間外25% + 深夜25% = 50%以上
(例)所定労働時間が13時~22時(休憩1時間)の従業員が、24時まで残業した場合
- 22時まで:通常の賃金
- 22時~24時:時間外労働かつ深夜労働にあたるため、50%以上の割増賃金が必要
パターン2:休日労働 + 深夜労働
法定休日に出勤し、その労働が深夜時間帯(22時~翌5時)に及んだ場合です。
割増率:休日35% + 深夜25% = 60%以上
【ポイント】
法定休日労働には、時間外労働という概念がありません。
したがって、休日に8時間を超えて働いても、時間外の割増率(25%)は加算されず、休日労働の割増率(35%)のみが適用されます。
ただし、深夜に働いた分の深夜割増(25%)は別途必要です。
【注意点2】勤務が暦日をまたぐ場合の労働時間の考え方
夜勤は、勤務開始日と終了日で日付が変わることがほとんどです。
この場合、労働時間はどのようにカウントすればよいのでしょうか。
原則として、労働時間は「始業時刻が属する日」の労働として、まとめて計算します。
これを「継続勤務の原則」と呼びます。
(例)8月1日の22時から、8月2日の朝7時まで勤務した場合(休憩1時間)
- 勤務日:8月1日
- 労働時間:実働8時間(22:00~翌7:00のうち休憩1時間を除く)
- 労働時間のカウント:この8時間は、すべて「8月1日」の労働時間として扱います。
この考え方は、時間外労働が発生するかどうかを判断する際に非常に重要です。
例えば、上記の勤務のあと、8月2日の日中に再度勤務した場合、それは前日からの継続勤務とはならず、新たな「8月2日」の勤務として労働時間を計算します。
【注意点3】仮眠時間の取り扱い
夜勤には仮眠時間が設けられていることがあります。
この仮眠時間を「労働時間」に含めるべきか、「休憩時間」として扱ってよいかは、労務管理上の重要なポイントです。
判断基準は、「労働からの解放が保障されているか」どうかです。
- 労働時間とみなされるケース(手待ち時間)
仮眠中であっても、警報が鳴ったり、電話がかかってきたりした際に、すぐに対応する義務がある場合は、実質的に会社の指揮命令下にあると判断され「労働時間」となります。この場合、もちろん賃金の支払いが必要です。 - 休憩時間とみなされるケース
仮眠室などで完全に業務から離れ、自由な利用が保障されている場合は「休憩時間」として扱えます。この場合、賃金の支払いは不要です。
トラブルを防ぐためにも、仮眠時間のルールを就業規則などで明確に定めておくことが大切です。
【応用編】夜勤専従者の有給休暇、深夜手当は支払うべき?
もう一つ、実務で判断に迷うのが「夜勤専従の従業員が有給休暇を取得した際の賃金」の扱いです。
原則として、深夜割増賃金は「実際に深夜に労働したこと」に対して支払われるため、有給休暇を取得した日については、割増部分(25%以上)を支払わなくても法律違反にはなりません。
しかし、夜勤専従者にとっては、深夜労働が常態であり、深夜割増賃金も生活を支える恒常的な賃金(生活給)の一部と捉えられます。
そのため、有給休暇を取得したことで収入が大きく減ってしまうのは、従業員にとって大きな不利益となり、休暇の取得をためらわせる原因にもなりかねません。
この点について、行政通達や判例で明確な基準が示されているわけではなく、いわば「グレーゾーン」となっています。
しかし、労使トラブルを防止し、従業員が安心して働ける環境を整備する観点からは、より丁寧な対応が望まれます。
【推奨される対応】
トラブルを避けるためには、有給休暇の賃金計算方法を「平均賃金」で支払うルールにすることが最も公平です。
平均賃金には、過去3ヶ月の深夜割増賃金も含まれて計算されるため、労働の実態が反映されやすくなります。
もし「通常の賃金」で支払う場合でも、就業規則に「夜勤専従者の有給休暇については、深夜割増相当額を含めて支払う」といった有利な取り扱いを明記しておくことが、無用な紛争を防ぐ上で非常に有効です。
【まとめ】複雑な夜勤の給与計算は専門家への相談も有効です
今回は、夜勤の給与計算における重要な注意点について解説しました。
- 割増賃金の重複計算を正しく行う(特に「時間外+深夜」「休日+深夜」)
- 日付をまたぐ勤務は「始業日の労働」として1日でカウントする
- 仮眠時間が「労働時間」にあたるか「休憩時間」にあたるかを明確にする
- 【特に注意】夜勤専従者の有給休暇の賃金は、トラブル防止のため実態に即した配慮あるルール作りを
給与計算は、従業員の生活を支えるだけでなく、会社との信頼関係の基盤となる非常に重要な業務です。
特に夜勤を含む勤務体系の場合は、計算が複雑になりがちです。
少しでも不安や疑問がある場合は、労働法の専門家である社会保険労務士にご相談ください。
当事務所では、各企業様の実情に合わせた給与計算のアドバイスや、給与計算代行業務も承っております。お気軽にお問い合わせください。
【免責事項】
本記事は、掲載時点の法令や情報に基づき作成しておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。また、具体的な個別の事案については、必ず専門家にご相談の上、ご対応ください。本記事の情報を用いて行う一切の行為について、当事務所は何ら責任を負うものではありません。