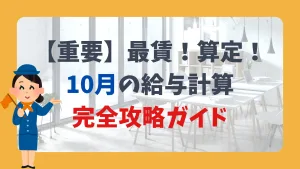退職時の有給休暇の買い取りは「退職所得」?「給与所得」?!
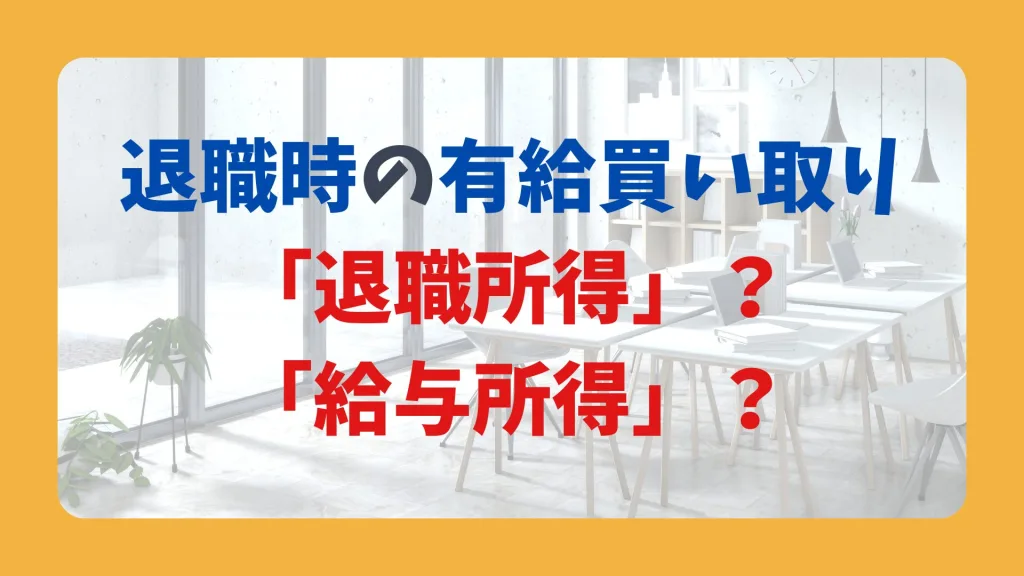
従業員が退職する際、未消化の年次有給休暇(有給)を買い取るケースは実務上珍しくありません。
その際に経理担当者や経営者が直面するのが、「この買い取り金は、税務や社会保険の手続き上、どう処理すればいいのか?」という問題です。
給与と同じように源泉徴収するのか、それとも退職金として扱うのか。
この判断を誤ると、従業員の手取り額や会社の納税額にも影響が出てしまいます。
退職時の有給買い取りの基本的な考え方についてはこちらの記事でも解説していますが、今回は特に多くの担当者が悩む「税務上の正しい取り扱い」に焦点を当て、さらに詳しく掘り下げていきます。
結論:退職時の有給買い取りは「退職所得」として処理する
まず、この記事の核心となる結論からお伝えします。
退職時に、未消化の有給休暇を会社が買い取って支払う金銭は、税務上「退職所得」として扱います。
これは、その支払いが「退職したことに基因して支払われる一時金」とみなされるためです。
そのため、退職金などと合算して「退職所得控除」という、税制上非常に優遇された控除を適用することができます。
勤続年数が長いほど控除額が大きくなるため、従業員にとっては税負担が軽くなる大きなメリットがあります。
また、退職所得は原則として社会保険料の算定対象外となるため、この点でも給与所得とは大きく異なります。
一方で、在職中に時効で消滅する有給などを会社が恩恵的に買い取る場合は「給与所得(賞与)」となり、通常の給与と同じように扱われます。
この所得区分の違いを明確に理解しておくことが、正しい経理処理の第一歩です。
【前提知識】有給買い取りの基本ルール
税務の話に入る前に、法律上の大原則を簡単におさらいしておきましょう。
本来、有給の買い取りは違法
有給休暇は、労働者の心身のリフレッシュを目的とした制度です。
そのため、お金を払う代わりに休暇を与えない、という考え方は制度の趣旨に反します。
したがって、事前に有給を買い上げる「予約買い取り」などは明確に違法です。
例外的に買い取りが認められるケース
ただし、退職によって権利が消滅してしまう有給など、休暇として取得することが事実上不可能なものについては、労使の合意に基づき、会社が任意で買い取ることは法律上問題ないとされています。
重要なのは、これが会社の「義務」ではないという点です。
【実務】買い取りから税務処理までの具体的な流れ
では、実際に買い取りを行う際の手順と注意点を、ステップごとに見ていきましょう。
ステップ1:買い取りの合意形成と金額の算出
前述の通り、買い取りは会社の義務ではありません。
まずは、会社として買い取りに応じるか否かを決定します。
応じる場合は、買い取り額を算出します。
計算方法に法的な決まりはありませんが、一般的には以下のいずれかの方法で、就業規則の定めに従って算出します。
- 通常の勤務をした場合に支払われる賃金
- 平均賃金
- 健康保険の標準報酬月額の日割額(※要労使協定)
この際、後のトラブルを防ぐため、買い取り日数、単価、合計金額を明記した「合意書」を必ず書面で取り交わしましょう。
ステップ2:「退職所得の受給に関する申告書」の受理
買い取り金を退職所得として処理するためには、従業員から「退職所得の受給に関する申告書」を提出してもらう必要があります。
この申告書の提出があってはじめて、正規の税額で源泉徴収することができます。
もし提出がない場合は、退職金の支払額に対し、一律20.42%の税率で源泉徴収しなければならず、従業員自身が確定申告で精算する必要が出てきてしまいます。
ステップ3:退職所得として源泉徴収税額を計算・納付
有給の買い取り額は、他の退職金と合算した上で「退職所得」として所得税の計算を行います。大まかな計算の流れは以下の通りです。
【参考】退職所得の所得税 計算の流れ
- 課税退職所得金額を計算する
(収入金額 - 退職所得控除額)× 1/2 = 課税退職所得金額- 所得税額を計算する
課税退職所得金額 × 所得税率 - 控除額 = 所得税額※上記で算出した所得税額に、別途、復興特別所得税(所得税額の2.1%)が加わります。
▶国税庁:退職金を受け取ったとき(退職所得)
【重要】個別の具体的な税額計算や税務相談、税務申告の代理は、法律により税理士の独占業務と定められています。
私たち社会保険労務士は、労働法・社会保険の専門家として、有給休暇のルールや就業規則の整備といった労務管理上のアドバイスは行いますが、最終的な所得税の計算や決定を行うことはできません。
上記の計算式はあくまで概要を掴むための参考情報です。
実際の計算は非常に複雑ですので、必ず顧問税理士にご確認いただくか、専門の税理士にご相談ください。
【まとめ】所得区分の正しい理解が、円満な退職手続きの鍵
今回は、退職時の年次有給休暇の買い取りについて、特に「退職所得」としての取り扱いに絞って解説しました。
- 退職時の有給買い取り金は、税務上「退職所得」として扱う。
- 「退職所得控除」が適用されるため、従業員の税負担は「給与所得」よりも軽くなる。
- 社会保険料の算定対象からも外れるため、会社・従業員双方の負担が軽減される。
- 正しい税務処理には「退職所得の受給に関する申告書」が不可欠。
- 基本的なルールと合わせて、就業規則で買い取りに関する規定を整備しておくことが最も重要。
有給の買い取りは、法律論だけでなく、税務の知識も必要となる複雑なテーマです。
特に退職金の計算や社会保険の手続きとも密接に関わってきます。
「うちの就業規則、このままで大丈夫だろうか」「退職者の税金計算に不安がある」など、具体的なお悩みやご相談がございましたら、ぜひ一度、私たち社労士事務所ぽけっとにご相談ください。
貴社の実情に合わせた、最適なご提案をさせていただきます。
【免責事項】
本記事は、掲載日時点の法令および情報に基づいて作成しております。法改正や情報更新により、一部の内容が現状と異なる場合がございますのでご了承ください。また、本記事の情報を利用して生じたいかなる損害についても、当事務所は一切の責任を負いかねます。具体的な事案については、必ず専門家にご相談ください。