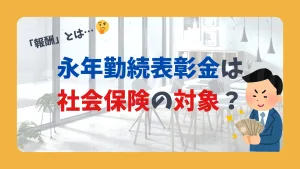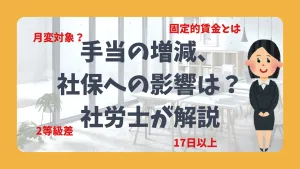賞与の社会保険料、どうなる?育休中の免除条件もスッキリ解説!
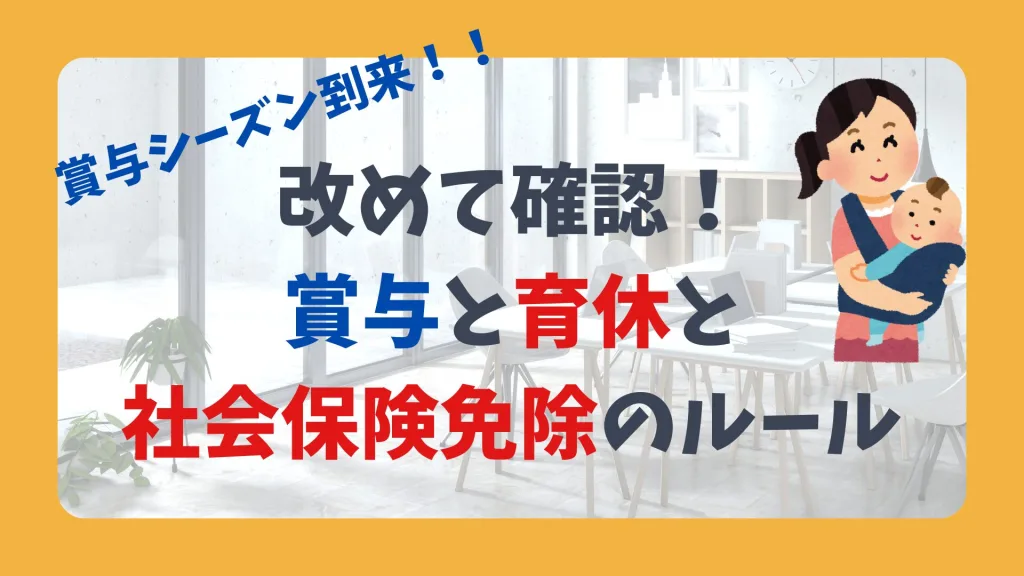
「まもなく賞与の支給日だ!」と楽しみにされている従業員の方も多いのではないでしょうか。経営者や人事ご担当者の皆様にとっては、賞与計算や社会保険の手続きなど、準備に追われる時期かもしれませんね。
特に社会保険料の取り扱いは、毎月の給与とは異なる点もあり、少し複雑に感じることもあるでしょう。また、育児休業を取得されている従業員がいる場合の賞与にかかる社会保険料については、「育休期間が1ヶ月以上ないと免除されないの?」といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、社労士事務所ぽけっとが、賞与にかかる社会保険料の基本的なルールから、多くの方が気になる育児休業中の免除条件まで、分かりやすく解説します!
賞与にかかる社会保険料とは?
まず、賞与から控除される社会保険料には、以下のものがあります。
- 健康保険料
- 厚生年金保険料
- 介護保険料(40歳以上65歳未満の方)
- 雇用保険料
これらのうち、健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料は、賞与の額面金額(税引前)から1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」を基に計算されます。雇用保険料は、賞与の額面金額にそのまま保険料率を乗じて計算します。
標準賞与額には上限があります
- 健康保険・介護保険料:年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)の累計額で573万円まで
- 厚生年金保険料:1ヶ月あたり150万円まで(同月内に複数回支給された場合は合算)
つまり、非常に高額な賞与が支給された場合でも、上記の金額を上限として保険料が計算されることになります。
【重要ポイント】育児休業中の賞与、社会保険料はどうなる?
育児・介護休業法に基づき育児休業を取得している期間中は、一定の要件を満たすことで健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料が被保険者負担分・事業主負担分ともに免除されます。これは、賞与にかかる社会保険料についても同様です。
では、どのような場合に賞与の社会保険料が免除されるのでしょうか?ポイントは以下の2点です(2022年10月施行の改正内容に基づきます)。
- 賞与が支払われた月の末日に育児休業を取得していること
- その賞与が支払われた月の末日を含めて、1ヶ月を超える育児休業を取得していること (例:賞与支払月の末日が5月31日の場合、育休期間が5月31日~7月1日以降であれば対象。5月31日~6月30日までの場合は対象外)
「育休期間が1ヶ月以上ないと社会保険が適用される(免除されない)」と耳にすることがあるかもしれませんが、正確には上記のように「1ヶ月を超える」育児休業期間が必要となります。暦の上で1ヶ月間ぴったりでは要件を満たさない点に注意が必要です。
例えば、6月30日に賞与が支給され、従業員Aさんが6月15日から7月14日まで育児休業を取得した場合、賞与支払月の末日(6月30日)に育児休業を取得していますが、育休期間はちょうど1ヶ月のため、この賞与にかかる社会保険料は免除されません。もし、Aさんの育休期間が6月15日から7月15日までであれば、「1ヶ月を超える」ため免除の対象となります。
月々の社会保険料免除との違いは?
ちなみに、毎月の給与にかかる社会保険料の免除要件は、賞与の場合と少し異なります。 月々の保険料は、
- その月の末日に育児休業を取得している場合
- または、同じ月内で14日以上の育児休業を取得した場合(その月に賞与が支給された場合の賞与保険料は、このケースでは免除されません) に免除となります。
賞与の場合は、上記に加えて「育休期間が1ヶ月を超える」という要件が加わる点をしっかり押さえておきましょう。
Q&A:育休中の賞与と社会保険料、こんな時はどうなる?
Q1:賞与支払月の途中で育休が始まる(または終わる)場合は?
A1:上記2つの要件(賞与支払月の末日に育休中であること、かつ、その育休期間が1ヶ月超であること)を満たせば免除対象となります。月の途中からであっても、末日に育休を取得しており、トータルの育休期間が1ヶ月を超えていれば問題ありません。
Q2:賞与支払月に、育休とは別に14日以上の産後パパ育休(出生時育児休業)を取得しました。この場合の賞与の社会保険料は免除されますか?
A2:産後パパ育休も育児休業の一種です。したがって、賞与支払月の末日に産後パパ育休を取得しており、かつ、その産後パパ育休の期間(または連続する他の育児休業期間と合わせて)が1ヶ月を超える場合は、賞与にかかる社会保険料は免除されます。
Q3:賞与支給月に育休が始まり、当初は1ヶ月を超える予定だったので社会保険料を免除として処理しました。しかし、予定より早く復帰し、実際の育休期間が1ヶ月以内になってしまった場合はどうなりますか? また、免除の場合でも賞与支払届の「標準賞与額」は報告が必要なのでしょうか?
A3:育休が予定より短縮し、賞与の社会保険料免除の対象外となった場合、保険料は遡って納付が必要です。
産前産後休業中の賞与と社会保険料
産前産後休業期間中も、育児休業と同様に社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料)が免除されます。こちらは、休業期間中に支払われた賞与であれば、期間の長短にかかわらず免除の対象となります。
賞与から引かれるのは社会保険料だけじゃない!所得税も忘れずに
賞与からは、社会保険料の他に「所得税」も源泉徴収されます。賞与の所得税は、前月の給与額や扶養親族の数などによって税率が変動します。社会保険料控除後の金額に所定の税率を乗じて計算されます。
その他、賞与と社会保険料に関する注意点
- 同月に複数回賞与が支給された場合:厚生年金保険料の標準賞与額の上限(150万円)は、同月内に支給された賞与を合算して判断します。健康保険料・介護保険料の年度累計上限(573万円)も同様に合算して管理します。
- 退職月に賞与が支給された場合:資格喪失日の前日までに支給された賞与は、社会保険料の対象となります。ただし、月末退職でなければ、その月の厚生年金保険料も健康保険料もかかりませんが、賞与支払届の提出が必要です。資格喪失日以降に支給される賞与は、原則として社会保険料の対象外で、賞与支払届の提出は必要ありません。
【まとめ】社労士に相談するメリット
今回は、賞与にかかる社会保険料、特に育児休業中の取り扱いについて解説しました。制度が複雑で、個別のケースによって判断が難しい場合もあるかと存じます。
「うちの会社のこのケースはどうなるの?」 「最新の法改正に対応できているか不安…」
そのような場合は、ぜひ私たち社労士事務所ぽけっとにご相談ください。専門家である社会保険労務士が、貴社の状況を丁寧にヒアリングし、最適なアドバイスをさせていただきます。給与計算や社会保険手続きのアウトソーシングも承っておりますので、人事労務に関するお悩みは、どうぞお気軽にお問い合わせください。
この記事が、中小企業の経営者様、人事ご担当者様の疑問解消の一助となれば幸いです。
免責事項
当ブログ記事は、掲載時点の法令や情報に基づいて作成しておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。また、個別具体的なケースへの適用を保証するものでもありません。実際に意思決定をされる際には、必ず専門家にご相談いただくか、最新の法令等をご確認いただきますようお願い申し上げます。当ブログ記事を利用したことにより何らかの損害が発生した場合でも、当事務所は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。