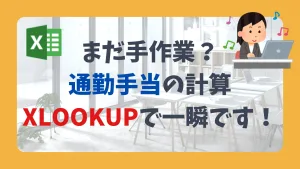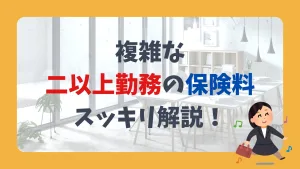裁量労働制と固定残業代の落とし穴!その休日出勤、固定残業代に含めて大丈夫?

「うちは裁量労働制だから、残業代は固定で払っている」
「みなし労働時間制なので、休日に少し働いても給与は変わらない」
中小企業の経営者や人事担当者の方から、このようなお話を聞くことがあります。
裁量労働制や固定残業代制度は、柔軟な働き方を促進し、給与計算の簡略化にも繋がる便利な制度です。
しかし、その運用、特に休日の取り扱いを誤解していると、後から「未払い残業代」を請求されるという大きなリスクを抱えることになります。
今回は、特に誤解の多い「裁量労働制における休日出勤と固定残業代」の関係について、分かりやすく解説します。
そもそも「裁量労働制」とは?基本をおさらい
裁量労働制とは、実際の労働時間ではなく、あらかじめ労使で定めた時間(みなし労働時間)働いたものとみなして給与を計算する制度です。
例えば「みなし労働時間を9時間」と定めた場合、実際の労働時間が7時間でも10時間でも、9時間働いたものとして扱われます。
この制度は、業務の進め方を労働者の裁量に大きく委ねる専門的な職種(専門業務型裁量労働制)や、事業の運営に関する企画・立案・調査・分析の業務(企画業務型裁量労働制)に導入できます。
【重要ポイント】
裁量労働制は、あくまで「労働時間」の計算を「みなし」にする制度です。以下の2つは、裁量労働制であっても適用除外にはなりません。
- 休日: 法律で定められた休日のルールは、通常通り適用されます。
- 深夜労働: 午後10時から午前5時までの間に労働した場合は、別途「深夜労働手当(25%以上)」の支払いが必要です。
裁量労働制を導入する上での大前提
裁量労働制は、労働者に大幅な裁量を与える代わりに、時間管理を厳格に行わないという制度です。
しかし、これは「いくら働かせても良い」ということでは決してありません。
厚生労働省の通達でも、「各事業場における所定労働時間をみなし労働時間として設定するような場合において、所定労働時間相当働いたとしても明らかに処理できない分量の業務を与えながら相応の処遇を確保しないといったことは、制度の趣旨を没却するものであり、不適当です」と明確に示されています。
つまり、到底終わらないような業務量を押し付け、それに見合った給与を支払わないといった運用は、裁量労働制の趣旨に反するものであり、認められません。
制度を導入する際は、労働者の健康確保や、業務量と処遇のバランスに十分配慮することが大前提となります。
「固定残業代」が有効になるための大切なルール
次に、固定残業代(みなし残業代)制度です。
これは、毎月一定時間分の残業代を、実際の残業時間にかかわらず固定で支払う制度ですが、正しく運用しないと法的に「無効」と判断されてしまうことがあります。
この制度が法的に有効と認められるためには、特に重要な以下の2つの条件をクリアしている必要があります。
ルール1:給料と残業代がハッキリ分かれていること(明確区分性)
給与明細を見たときに、「どこまでが基本のお給料で、どこからが固定残業代なのか」が、誰の目にも明らかである必要があります。
【ダメな例 🙅】
- 給与:30万円(固定残業代含む)
- これでは、基本給がいくらで、残業代がいくらなのか全く分かりません。
【良い例 🙆】
- 基本給:25万円
- 固定残業手当:5万円(月30時間分として)
- このように、金額が明確に分かれていることが大前提です。
ルール2:何の残業代なのかハッキリしていること(対価性)
ルール1で分けた「固定残業手当」が、「何時間分の、どの種類の労働」に対する手当なのかを、雇用契約書や就業規則で具体的に定めておく必要があります。
例えば「月30時間分の時間外労働に対する手当」として固定残業代を設けている場合、それはあくまで「時間外労働(いわゆる普通の残業)」の対価です。
この場合、後で解説する「休日労働」の対価は含まれていないことになり、これが今回のテーマの重要なポイントになります。
この2つのルールが守られていないと、固定残業代制度そのものが無効と判断され、計算しなおした残業代の全額を請求されるリスクがあります。
【本題】裁量労働制で「休日」に働いた場合の給与計算
それでは、本題です。
裁量労働制で固定残業代(月30時間分)を導入している会社で、従業員が土曜日に出勤した場合を考えてみましょう。
この土曜出勤の時間は、固定残業代の30時間の中に含めて良いのでしょうか?
答えは、「その土曜日が『法定休日』か『法定外休日』か」によって全く異なります。
ケース1:出勤した日が「法定休日」の場合
法定休日とは、労働基準法で定められた、週に1回(または4週に4回)必ず与えなければならない休日のことです。
この法定休日に労働させた場合、それは「休日労働」となり、割増率は35%以上となります。
一方で、固定残業代が通常対象とする「時間外労働(残業)」の割増率は25%以上です。法律上、「休日労働」と「時間外労働」は明確に区別される全くの別物です。
したがって、「時間外労働」を対象とする固定残業代に、「休日労働」の時間を含めることはできません。
この場合、会社は固定残業代とは別に、「(その日の労働時間)×(基礎時給)× 1.35」で計算した休日労働手当を支払う義務があります。
ケース2:出勤した日が「法定外休日(所定休日)」の場合
法定外休日とは、会社が就業規則などで独自に定めている「法定休日以外の休日」のことです。
例えば、完全週休2日制(土日休み)で、日曜日を法定休日と定めている場合、土曜日は法定外休日となります。
この法定外休日の労働は、法律上「休日労働」にはあたりません。その週の労働時間が週40時間を超えた部分について、「時間外労働」として扱われます。
そのため、法定外休日の労働時間は、「時間外労働」として月30時間の固定残業代に含めることが可能です。
最重要!トラブル防止のポイント
ただし、これには非常に重要な条件があります。それは、就業規則や雇用契約書において、
「固定残業代には、時間外労働手当だけでなく、法定外休日労働に対する割増賃金も含む」
という趣旨が、誰が読んでも明確にわかるように記載されていることです。
この記載がない場合、「固定残業代はあくまで平日の残業分であり、休日に働いた分は別途支払われるべきだ」と労働者から主張され、トラブルに発展する可能性があります。
就業規則の規定例
第〇条(固定残業手当) 1.固定残業手当は、月30時間分の時間外労働に対する割増賃金、および法定外休日における労働に対する割増賃金として支給する。 2.時間外労働および法定外休日労働の合計が月30時間を超えた場合は、その超えた時間について、別途割増賃金を支給する。
【まとめ】複雑な制度こそ専門家のチェックを
裁量労働制と固定残業代は、正しく運用すれば労使双方にメリットのある制度です。
しかし、見てきたように、休日の扱い一つをとっても非常に複雑で、誤解が大きなトラブルに繋がりかねません。
- 自社の就業規則で、法定休日はいつに定められているか?
- 固定残業代の規定は、法定外休日の労働を含むことが明記されているか?
- そもそも、従業員の業務量や処遇は、裁量労働制の趣旨に合っているか?
もし、少しでも自社の制度に不安を感じたら、ぜひ一度、私たち社労士事務所ぽけっとにご相談ください。
専門家の視点で貴社の就業規則をチェックし、労務リスクを未然に防ぐお手伝いをさせていただきます。
【免責事項】
本記事は、執筆時点の法令に基づき、一般的な情報提供を目的として作成しております。特定の事実関係によっては、結論が異なる場合がありますので、具体的な事案については必ず専門家にご相談ください。本記事の情報を利用した結果生じた損害について、当事務所は一切の責任を負いかねます。