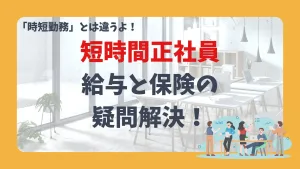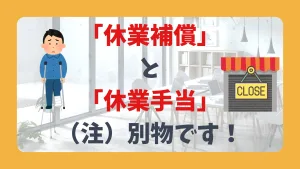定年退職者の「同日得喪」手続き、忘れていませんか?スムーズな手続きで従業員も会社も安心!
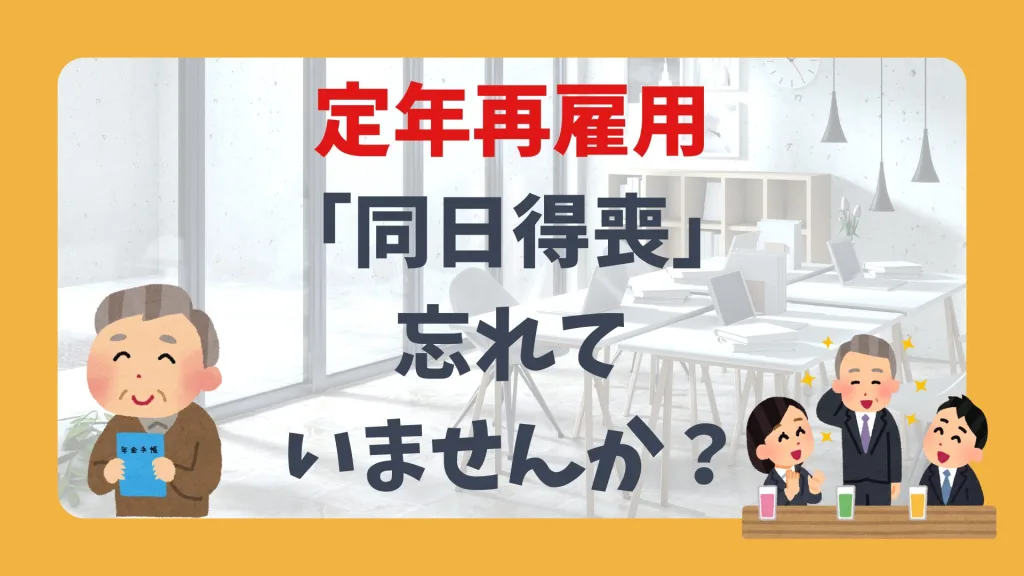
長年、会社のために尽力してくれた従業員の定年退職。事業主様にとっても、従業員ご本人にとっても、大きな節目ですよね。「本当にお疲れ様でした!」と、感謝の気持ちで送り出す…とても大切なことです。
さて、感動的なセレモニーの後には、現実的な「手続き」が待っています。特に、定年退職された方を嘱託社員や契約社員として再雇用する場合、「同日得喪(どうじつとくそう)」という社会保険の手続きが、従業員・会社双方にとってメリットをもたらす場合があることをご存知でしょうか?
「同日得喪? なんだか専門用語で難しそう…」「うちは定年後も給料変わらないから関係ないかな?」
ちょっとお待ちください! この「同日得喪」、実は従業員の年金受給額に関わってきたり、会社の社会保険料負担に影響したりと、従業員・会社双方にとって見逃せないポイントがあるんです。手続きを正しく理解し、適切に行うことが、後のトラブル防止にも繋がります。
今回は、そもそも「同日得喪」とはどのような制度で、なぜ必要なのか、そして従業員(特に年金面)や会社にとって具体的にどのようなメリットがあるのかを解説します。さらに、実際の手続きの流れや、手続きを行う上での注意点についてもお伝えしていきます。ぜひ最後までお読みいただき、今後の手続きにお役立てください!
そもそも「同日得喪」って何? なぜ必要なの?
まずは、「同日得喪」という言葉の意味からご説明しますね。
- 同日(どうじつ): 同じ日
- 得喪(とくそう): 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の資格を「取得」したり「喪失」したりすること
つまり、「同日得喪」とは、社会保険の資格を「喪失」した日と「同じ日」に、再び資格を「取得」する手続きのことです。これは主に、定年退職日の翌日に、1日の空白もなく継続して再雇用される場合に行われる手続きです。
なぜこのような手続きがあるのでしょうか?
それは、定年により雇用契約の形態が変わっても(例:正社員から嘱託社員へ)、実質的な雇用関係は続いているとみなされるケースがあるためです。そして、この手続きの重要な点は、再雇用後の給与額に応じて社会保険料の基準額(標準報酬月額)を、再雇用された月から速やかに見直すことができる点にあります。これが、後述するメリットに大きく関わってきます。
同日得喪のメリットは? 従業員にも会社にも恩恵が!
では、同日得喪の手続きを行うことで、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか?
従業員にとっての大きなメリット:年金受給額が増える可能性!
これが最大のポイントかもしれません。60歳以降、厚生年金を受け取りながら働く場合、「在職老齢年金」という制度が適用されます。これは、給与(正確には標準報酬月額)と年金の合計額に応じて、年金の一部または全額が支給停止される仕組みです。
定年退職後、再雇用で給与が下がることが多いですよね。同日得喪の手続きを行うと、下がった給与に基づいて、再雇用された月からすぐに標準報酬月額が再計算(改定)されます。
標準報酬月額が下がると…?
→ 在職老齢年金による年金の支給停止額が減る、あるいは支給停止がなくなる可能性があります!
つまり、働きながら受け取れる年金の額が増えることが期待できるのです。これは、再雇用で働く従業員にとって、非常に大きなメリットと言えるでしょう。
その他のメリット
- 社会保険の継続: 健康保険の資格が途切れることなく継続されます。マイナンバーカードを健康保険証として利用している場合も、手続きにより資格情報が更新され、継続して利用できます。従業員が一時的に国民健康保険などに加入する手間もありません。
- 従業員の手続き負担軽減: 社会保険の資格が途切れないため、従業員が一時的に国民年金や国民健康保険へ切り替える手間が省けます。
会社にとってのメリット
- 社会保険料負担の軽減: 従業員の標準報酬月額が下がれば、会社が負担する社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)も軽減されます。
- コンプライアンス遵守: 適切な手続きを行うことで、法令遵守の観点からも安心です。
- 従業員満足度の向上: 年金受給額が増えるなど、従業員にメリットのある手続きをきちんと行うことで、従業員の会社に対する信頼感や満足度を高める効果も期待できます。
同日得喪の手続き、具体的にどうすればいいの?
手続きは、思ったよりも難しくありません。以下の2つの書類を、同時に年金事務所(または健康保険組合)に提出します。
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格 喪失 届
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格 取得 届
【添付書類】
原則として、以下のいずれかの添付が必要です。
- 就業規則や退職辞令の写し等、退職したことがわかる書類
- 継続して再雇用されたことが客観的に判断できる書類(雇用契約書、労働条件通知書等)
- 上記書類が提出できない場合は、「事業主の証明」(特に様式は指定されていませんが、退職日と再雇用日が明記されている必要があります)
※提出先によって取り扱いが異なる場合があるため、事前に確認することをおすすめします。
【記入のポイント】
- 資格喪失届
- 喪失年月日:定年退職年月日
- 喪失原因:「70歳到達(健康保険のみ)」「退職」等の中から該当するものを選びますが、備考欄に「定年再雇用」など、同日得喪の対象者であることがわかるように記載しておくと、より丁寧です。(提出先によっては必須の場合もあります)
- 資格取得届
- 取得年月日:再雇用年月日(=定年退職日の翌日)
- 報酬月額:再雇用後の新しい給与(見込み額)を記入します。
- 備考欄: 「同日得喪」と必ず記入してください。これが非常に重要です!
【提出先】
- 管轄の年金事務所
- 加入している健康保険組合(協会けんぽの場合は年金事務所へ)
【提出期限】
- 原則として、事実発生(再雇用日)から5日以内です。
ポイントは、「喪失届」と「取得届」を必ずセットで、同時に提出すること、そして必要な添付書類を忘れないことです。
手続きの際の注意点! ここは押さえておきましょう
スムーズな手続きのために、以下の点にご注意ください。
- 手続きの対象となる方
- 主に、会社の定めた定年年齢で退職し、退職日の翌日から継続して再雇用される方が対象です。
- 自己都合退職などの場合は、通常の資格喪失・取得手続きとなります。
- 同日得喪を行わないとどうなる?
- この手続きをしない場合や、退職日と再雇用日の間に空白期間がある場合は、通常の資格喪失・取得手続きを行います。
- その場合、新しい給与に基づく標準報酬月額への改定は、原則として毎年9月の「定時決定」を待つか、給与が大幅に変わった場合の「随時改定」まで適用されません。
- 同日得喪なら、再雇用された月からすぐに新しい標準報酬月額が適用されるため、社会保険料や年金計算への反映が早くなるメリットがあります。
- 再雇用後の働き方
- 再雇用後も、社会保険の加入要件(週の所定労働時間や月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上など)を満たす働き方である必要があります。
- 給与が変わらない場合
- 再雇用後に給与が下がらない(維持または上がる)場合、同日得喪の主なメリットである標準報酬月額の即時改定による影響はありません。
- ただし、雇用契約の種類が変わる(例:正社員から嘱託社員へ)ことを理由に、手続きを求める行政機関もあります。実務上の取り扱いについては、念のため管轄の年金事務所等にご確認ください。
- 従業員への説明は丁寧に
- なぜこの手続きをするのか、特に年金受給額にどのような影響があるのかなどを、従業員ご本人に分かりやすく説明しましょう。
- 困ったときは専門家へ
- 手続きに不安がある場合や、個別のケースで判断に迷う場合は、社会保険労務士(社労士)や年金事務所に相談することをおすすめします。
【まとめ】適切な「同日得喪」手続きで、円満な再雇用スタートを!
今回は、定年退職時の「同日得喪」について解説しました。この手続きは、定年退職日の翌日に継続して再雇用する場合にメリットが大きいものです。一見、少し複雑に感じるかもしれませんが、ポイントを押さえれば難しい手続きではありません。
長年貢献してくれた従業員が、定年後も安心して働き続けられるように、そして会社としても適切な労務管理ができるように、この「同日得喪」の手続きをしっかりと行いましょう。それが、従業員との良好な関係を継続し、会社のさらなる発展にも繋がるはずです。
この記事が、事業主様の疑問解消の一助となれば幸いです。
煩雑になりがちな社会保険の手続きも、当事務所にお任せいただければ、専門家が迅速かつ正確に対応いたします。
手続きに関するご相談や代行のご依頼は、ぜひお気軽に当事務所までお問い合わせください。