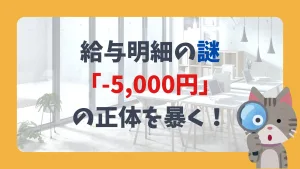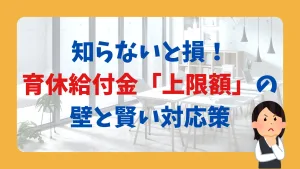【令和7年10月新設】「教育訓練休暇給付金」とは?社員の学びを応援する新制度を解説!
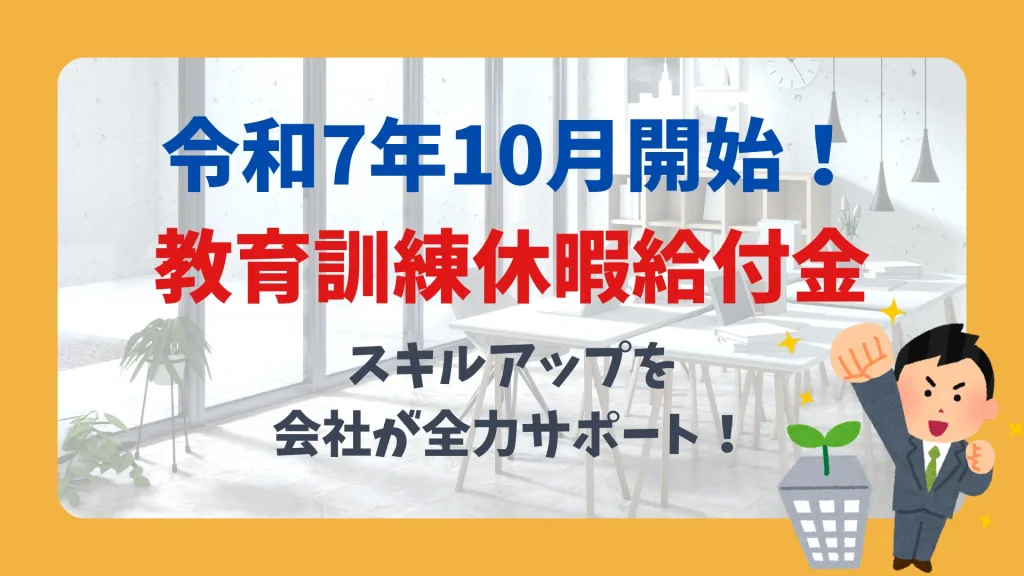
こんにちは!
社労士事務所ぽけっとです。
働きながら新しいスキルを身につけたい、キャリアアップのために学びたい。
そう考える従業員の方も、また、従業員のスキルアップを後押ししたいと考える経営者・人事担当者の方も多いのではないでしょうか。
今回は、そんな従業員の主体的な学びを支援する新しい制度、令和7年10月1日からスタートする「教育訓練休暇給付金」について解説します。
教育訓練休暇給付金とは?
「教育訓練休暇給付金」とは、労働者が自発的に教育訓練を受けるために休暇を取得した場合に、その休暇中の生活を支えるために雇用保険から支給される新しい給付金です。
これまでも、教育訓練の受講費用を補助する「教育訓練給付金」という制度はありましたが、今回の「教育訓練休暇給付金」は、休暇を取得して教育訓練を受ける間の生活費をサポートするという点が大きな特徴です。
これにより、労働者の方は経済的な心配を軽減しながら、キャリアアップや再就職に必要なスキル習得に専念しやすくなります。
どんな人が対象になるの?(支給要件)
この給付金を受け取るためには、
以下の①と②の両方の要件を満たす必要があります。
- 休暇開始日前の2年間に、被保険者期間が12か月以上あること (原則として、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月として計算します )
- 休暇開始日前に、雇用保険の被保険者であった期間が通算で5年以上あること (過去に基本手当(失業給付)などを受給した場合、その期間は通算されないことがあるので注意が必要です )
この2つの条件をクリアしている方が対象となります。
どんな休暇が対象?
給付金の対象となるのは、以下の要件をすべて満たす休暇です。
- 就業規則や労働協約に定められた制度に基づく休暇であること
- 労働者が自発的に取得を希望し、事業主の承認を得た30日以上の無給の休暇であること
- 大学での学習や教育訓練給付金の指定講座など、定められた教育訓練を受けるための休暇であること
業務命令によるものではなく、あくまで従業員本人の意思で取得する休暇が対象です。
いくらもらえるの?(支給額・日数)
気になる支給額ですが、原則として
休暇開始前の6か月の賃金から算出した「賃金日額」に応じた額が支給されます。
これは、雇用保険の基本手当(失業手当)の算定方法と同じです。
また、給付を受けられる日数は、雇用保険に加入していた期間に応じて、90日、120日、150日のいずれかになります。
| 加入期間 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
| 所定給付日数 | 90日 | 120日 | 150日 |
会社として何をすればいい?(手続きの流れ)
この制度を活用するためには、会社側の準備と協力が不可欠です。
- 就業規則への規定 従業員が教育訓練休暇を取得できる制度を、就業規則や労働協約に規定する必要があります。
- 休暇の合意・承認 従業員から休暇の申し出があった際に、事業主がその内容を確認し、合意・承認します。
- ハローワークへの書類提出 従業員の休暇開始後、10日以内に「賃金月額証明書」などを事業所の所在地を管轄するハローワークへ提出します。
- 労働者への書類交付 ハローワークから交付された申請書等を、速やかに労働者本人へ渡します。
従業員の学びたいという意欲を後押しし、会社の成長につなげるためにも、早めに社内制度を整えておくことをお勧めします。
導入するメリットは?
この制度を導入することは、会社にとっても大きなメリットがあります。
- 従業員のスキルアップと定着
従業員が新たなスキルを身につけることで、生産性の向上が期待できます。
また、学びの機会を提供する企業として、従業員の満足度やエンゲージメントが高まり、人材の定着にも繋がります。 - 企業の魅力向上と採用力強化
人材育成に積極的な企業であることは、企業の大きなアピールポイントになります。
採用活動においても、魅力的な労働条件として求職者にPRできます。 - 変化に対応できる組織づくり
急速に変化する社会において、従業員一人ひとりが学び続けることは、企業全体の対応力や競争力を高める上で不可欠です。
まとめ
「教育訓練休暇給付金」は、従業員の「学びたい」という意欲を金銭面で支え、キャリアの可能性を広げる画期的な制度です。
そして、従業員の成長は、必ず会社の成長へと繋がります。
令和7年10月の施行に向けて、今から社内での準備を進めてみてはいかがでしょうか。
「自社ではどのように制度を整えれば良いのだろう?」「就業規則の変更はどうすれば?」など、ご不明な点がございましたら、ぜひお気軽に社労士事務所ぽけっとまでご相談ください。専門家の視点から、貴社に最適な導入プランをご提案いたします。
【免責事項】
本記事は、令和7年7月時点の公開情報に基づき作成しております。法改正の最新情報や詳細な手続きについては、厚生労働省のホームページをご確認いただくか、当事務所までお問い合わせください。この記事の情報を用いて行う一切の行為について、当事務所は何ら責任を負うものではありません。