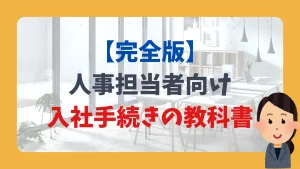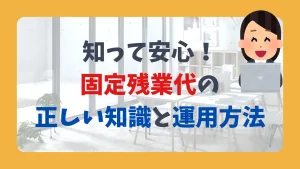【令和7年8月1日改定】育児休業・高年齢雇用継続給付の支給限度額が引き上げ!実務への影響を社労士が解説
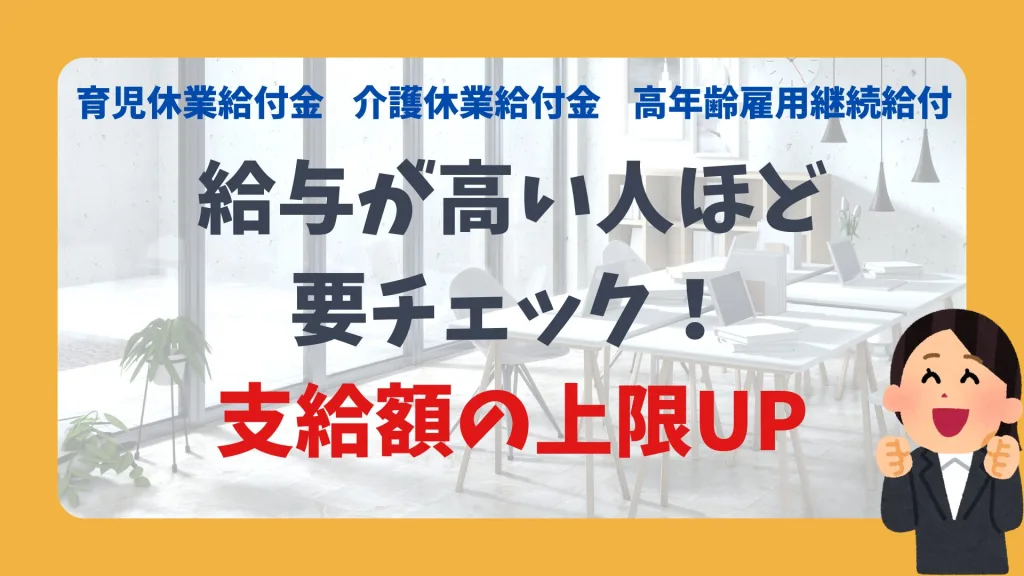
こんにちは!社労士事務所ぽけっとです。
日々めまぐるしく変わる法律や制度。
「また新しい改正?」「うちの会社には関係あるの?」と、情報のキャッチアップに追われている経営者様や人事担当者様も多いのではないでしょうか。
今回は、令和7年8月1日から変更となる雇用保険の「高年齢雇用継続給付」「育児休業給付」「介護休業給付」に関する重要な改正について、特に「支給限度額」と「賃金日額の上限」に焦点を当てて解説します。
「うちの従業員にどう説明したらいい?」「給与計算で注意すべきことは?」そんな疑問にお答えしますので、ぜひ最後までご覧ください。
そもそも「支給限度額」や「賃金日額の上限」って何?
今回の改正内容をご説明する前に、まずは基本となる2つのキーワードについて簡単におさらいしましょう。
これらは、特に休業前のお給料が高かった従業員の方に関係してくる重要なポイントです。
支給限度額とは?
「支給限度額」とは、その名の通り、雇用保険から給付される1ヶ月あたりの金額の上限キャップのことです。
これらの給付金は、休業前の賃金を基に計算されますが、いくら賃金が高い方でも、この限度額を超えて受け取ることはできません。
なぜ上限があるかというと、雇用保険制度の財源を安定させ、多くの人が制度を利用できるようにするためです。
この金額は、毎年8月に、前年度の日本の労働者全体の平均給与額の変動などを基に見直されています。
今回のように平均給与額が上がれば、限度額も引き上げられる仕組みです。
賃金日額の上限とは?
「賃金日額の上限」とは、給付額を計算する際の基礎となる賃金(日額)の上限です。
給付額は、原則として「休業開始前の6ヶ月間の賃金総額 ÷ 180日」で算出した「賃金日額」を基に計算されます。
しかし、この「賃金日額」にも上限が設けられており、計算結果が上限額を上回る場合は、上限額を使って給付金の計算が行われます。
こちらも「支給限度額」と同様の理由で設けられており、毎年見直しが行われます。
【本題】令和7年8月1日からの具体的な変更点
それでは、今回の改正で各給付金の限度額が具体的にいくらに変わるのかを見ていきましょう。
主に、賃金水準の高い従業員の方に影響がある改正です。
<令和7年8月1日からの主な支給限度額>
- 高年齢雇用継続給付金
支給限度額:376,750円 → 386,922円(+10,172円)- 育児休業給付金
支給上限額(支給率67%):315,369円 → 323,811円(+8,442円)
※育休開始から181日目以降(支給率50%)の上限額も同様に引き上げられます。- 介護休業給付金
支給上限額:347,127円 → 356,574円(+9,447円)
どんな時にこの「限度額」が関係するの?具体例で解説!
「数字だけ見てもピンとこない…」という方のために、実務でよくあるケースを基に具体的にご説明します。
ケース1:育児休業給付金の場合(月給50万円の社員)
休業前の月給が平均50万円だったAさんが、令和7年8月1日から育児休業を取得したとします。
育児休業給付金の額は、休業開始前の賃金を基に計算されます。
仮にAさんの賃金から計算した月額が335,000円(50万円×67%)になったとします。
この計算額(335,000円)は、改正前の支給上限額「315,369円」も、改正後の新しい上限額「323,811円」も超えています。
そのため、給付額は上限額に抑えられます。
もし改正がなければ、Aさんが受け取る額は月々315,369円でした。
しかし、今回の改正により、支給額は新しい上限額である323,811円となります。
つまり、月々8,442円(323,811円 - 315,369円)、半年で約5万円も手取りが増えることになるのです。
これは従業員にとって非常に大きなメリットです。
ケース2:高年齢雇用継続給付金の場合(60歳以降も働く社員)
60歳定年後、再雇用で働き続けるBさん(61歳)のケースで、給付額の計算まで見ていきましょう。
今回は「支給限度額」がどのように影響するかを分かりやすくするため、少し複雑な例で解説します。
- Bさんの60歳時点の月給:52万5千円
- 再雇用後の月給:38万円
高年齢雇用継続給付には、主に2つの支給要件があります。
- 60歳時点の賃金に比べて、現在の賃金が75%未満に低下していること
- 現在の賃金が「支給限度額」未満であること
これをBさんのケースに当てはめてみましょう。
ステップ1:賃金の低下率をチェック
380,000円 ÷ 525,000円 = 約72.38%
→ 75%未満なので、第一の条件をクリアです。
ステップ2:支給限度額をチェック
現在の賃金38万円は、改正前の限度額(376,750円)は超えていますが、改正後の新しい限度額(386,922円)は下回っています。
→ これにより、第二の条件もクリアし、給付金が支給されることになります。
ステップ3:本来の給付額を計算
ハローワークの早見表から仮に2.01%として計算します。
380,000円(現在の賃金) × 2.01% = 7,638円
ステップ4:最終的な支給額の調整
ここで、現在の賃金とステップ3で算出した給付額を合計します。
380,000円(賃金) + 7,638円(本来の給付額) = 387,638円
この合計額(387,638円)が、新しい支給限度額(386,922円)を超えてしまいました。
このような場合は、「支給限度額から現在の賃金を差し引いた額」が最終的な支給額となります。
【最終的な支給額】
386,922円(支給限度額) - 380,000円(賃金) = 6,922円
この月額6,922円が、Bさんの給付額となります。
もし改正がなければ1円も支給されなかったため、改正の恩恵を直接受けられるケースと言えます。
会社として何をすればいい?実務上のポイント
今回の改正を受けて、企業の人事担当者様が対応すべきことはシンプルです。
- 対象となる従業員への周知
特に、給与水準が高く、今後育児休業や介護休業を取得する可能性のある従業員や、現在高年齢雇用継続給付を受けている(またはこれから受ける)従業員へ、今回の改正がプラスになる情報であることを伝えてあげると親切です。 - 給与計算システム等の確認
もし給与計算システムなどで給付金の概算額を計算している場合は、令和7年8月以降の計算に新しい上限額が適用されるよう、設定の確認や更新が必要になるかもしれません。 - 申請手続き自体に変更はなし
なお、今回の改正による申請手続きの変更点は特にありません。ハローワーク(公共職業安定所)が、支給対象期間に応じて自動的に新しい上限額を適用して計算してくれます。
まとめ
今回の雇用保険の支給限度額引き上げは、物価上昇などを背景とした、従業員の生活を支えるための重要な改正です。
特に、専門的なスキルを持つ高賃金の従業員が、育児や介護、または60歳以降も安心して働き続けるための後押しとなります。
「うちの会社のこの従業員の場合はどうなるんだろう?」
「他にも最近の法改正で気になることがある」
そんな具体的なご相談やご不安がございましたら、いつでもお気軽に私たち社労士事務所ぽけっとにご連絡ください。
専門家の視点から、貴社に最適なアドバイスをさせていただきます。
【免責事項】
本記事は、令和7年8月1日時点の法令等に基づき一般的な情報を提供することを目的として作成しております。特定の個別の事案については、必ず専門家にご相談ください。本記事の情報を用いて行う一切の行為について、当事務所は何ら責任を負うものではありません。