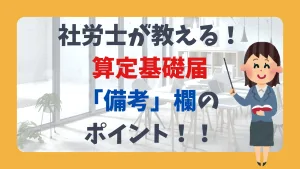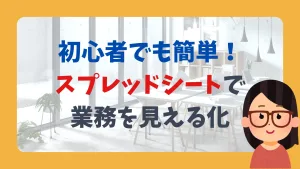【2025年10月施行】養育両立支援休暇とは?子の看護等休暇との違いを解説!
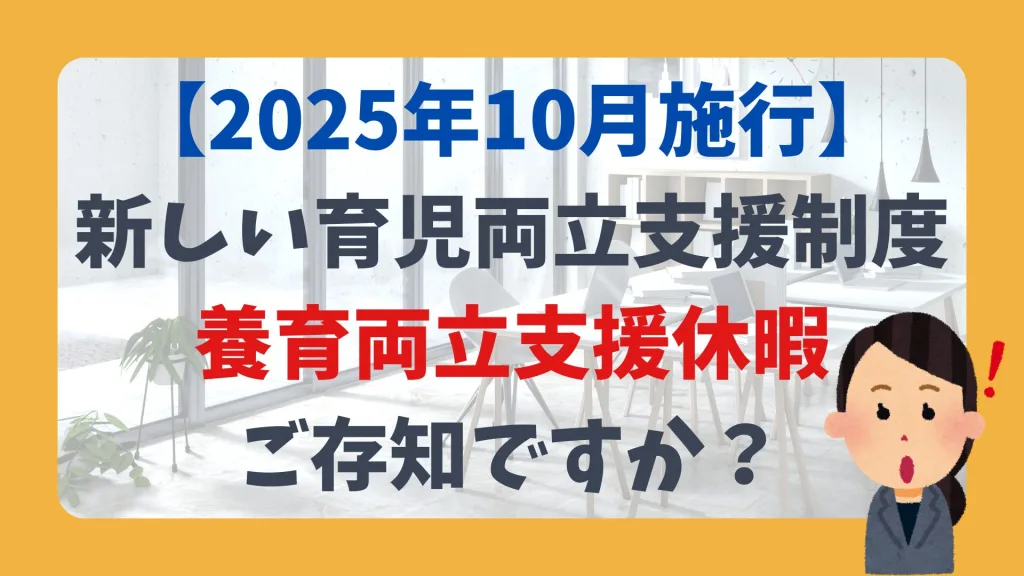
こんにちは!社労士事務所ぽけっとです。
2025年度は、育児・介護休業法に関する改正が多く、人事労務のご担当者様は情報収集に追われていることと存じます。
4月には「子の看護休暇」が「子の看護等休暇」へと見直され、対象となる子の範囲や取得事由が拡大されました。
そしてこの秋、2025年10月1日からは、仕事と育児の両立支援をさらに推進するため、3歳から小学校就学前の子を養育する従業員を対象とした「柔軟な働き方を実現するための措置」が事業主に義務付けられます。
その選択肢の一つとして新設されるのが「養育両立支援休暇」です。
これは、4月から拡充された「子の看護等休暇」とはまた目的や位置づけが異なる、新しい両立支援の形となります。
今回は、この「柔軟な働き方を実現するための措置」の概要と、選択肢の一つである「養育両立支援休暇」について、企業が準備すべきことを客観的に解説していきます。
【10月1日スタート】「柔軟な働き方を実現するための措置」の概要
まず、2025年10月1日からすべての企業に義務付けられる「柔軟な働き方を実現するための措置」の全体像をご説明します。
これは、3歳から小学校就学前の子どもを育てる従業員を対象とした制度です。
事業主は、以下の5つの選択肢の中から、2つ以上の措置を選択して講じる必要があります。
【事業主が講ずべき5つの措置(この中から2つ以上を選択)】
- 始業時刻等の変更(フレックスタイム、時差出勤など)
- テレワーク等(月に10日以上利用できるもの)
- 保育施設の設置運営等(ベビーシッター費用の補助など)
- 養育両立支援休暇の付与(年に10日以上の新たな休暇)
- 短時間勤務制度(1日の所定労働時間を原則6時間とする措置)
そして、会社が講じた措置の中から、従業員自身が利用したいものを1つ選んで活用できる仕組みです。
「養育両立支援休暇」と「子の看護等休暇」の違い
今回の改正で注目される選択肢の一つが「養育両立支援休暇」です。
この休暇の最大の特徴は、その目的と位置づけにあります。
● 目的の範囲
「子の看護等休暇」は、子の病気やケガ、予防接種、さらには入園・卒園式への参加など、利用できる目的(取得事由)が法律で具体的に定められています。
一方、「養育両立支援休暇」の目的は「就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇」とされており、利用目的が具体的に限定されていません。
そのため、子の看護等休暇の対象とならないような、より幅広い育児関連の用事での利用が想定されます。
例えば、習い事の行事や個人面談、家庭訪問への対応などが考えられます。
● 制度の位置づけ
この2つの休暇は、下表の通り対象となる子の年齢や導入義務の有無も異なります。
| 子の看護等休暇(施行済み) | 養育両立支援休暇(10月施行の選択肢) | |
|---|---|---|
| 対象 | 小学校3年生修了までの子 | 3歳~小学校就学前の子 |
| 目的 | 法律で具体的に定められている(病気、予防接種、学級閉鎖、入園式など) | 目的が限定されていない(「子の養育を容易にするため」と広範) |
| 導入義務 | 全企業で義務 | 事業主が選択した場合に導入する措置の一つ |
このように、「子の看護等休暇」は全ての企業に必須の基本的な休暇制度であり、「養育両立支援休暇」は、事業主が両立支援をさらに充実させるために選択する、追加的な措置の一つと理解すると分かりやすいでしょう。
10月の施行に向けた企業の対応
施行日は2025年10月1日です。
以下のステップに沿って、計画的に準備を進める必要があります。
● Step1:措置の選択と従業員への意見聴取
まず、5つの選択肢の中から自社で導入する2つ以上の措置を検討します。
その際、過半数組合または労働者の過半数代表者から意見を聴く必要があります。
● Step2:就業規則の改定と届出
導入する措置が決定したら、その内容を就業規則に明記し、所轄の労働基準監督署へ届け出る必要があります。
「養育両立支援休暇」を導入する場合には、休暇の目的、日数、取得手続きなどを具体的に定めることになります。
● Step3:従業員への周知
制度を設けた後は、その内容を従業員に周知することが重要です。また、子が3歳になる前の従業員に対しては、会社が講じた措置の内容等を個別に知らせ、利用の意向を確認することも別途義務付けられています。
【まとめ】計画的な準備で法改正に対応しましょう
今回は、2025年10月1日から施行される「柔軟な働き方を実現するための措置」と、その選択肢の一つである「養育両立支援休暇」について解説しました。
【この記事のポイント】
- 2025年10月1日から、3歳~就学前の子を持つ従業員のため、企業は5つの選択肢から2つ以上の両立支援措置を講じる義務があります。
- 選択肢の一つ「養育両立支援休暇」は、既存の「子の看護等休暇」とは異なり、より幅広い目的で利用できるのが特徴です。
- 施行に向けて、措置の選択、就業規則の改定、従業員への周知といった準備が必要です。
法改正への対応は、企業の労務管理において重要な課題です。どの措置を選択すべきか、就業規則の具体的な記載方法など、ご不明な点がございましたら、専門家である社労士にご相談ください。
社労士事務所ぽけっとでは、法改正に対応した制度設計のご相談から、就業規則の作成・変更まで、的確にサポートいたします。
免責事項
本記事は、2025年6月時点の公開情報に基づき作成しています。法改正の動向や具体的な解釈については、変更される可能性があります。記事の内容の正確性については万全を期しておりますが、その内容の完全性・正確性を保証するものではありません。本記事の情報を用いて行う一切の行為について、当事務所は何ら責任を負うものではありません。実際の運用に際しては、必ず専門家にご相談ください。