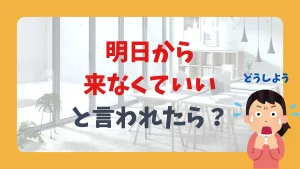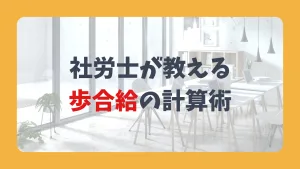月末1日だけの育休で社会保険料が免除に?知らないと損する特例と給付金の話
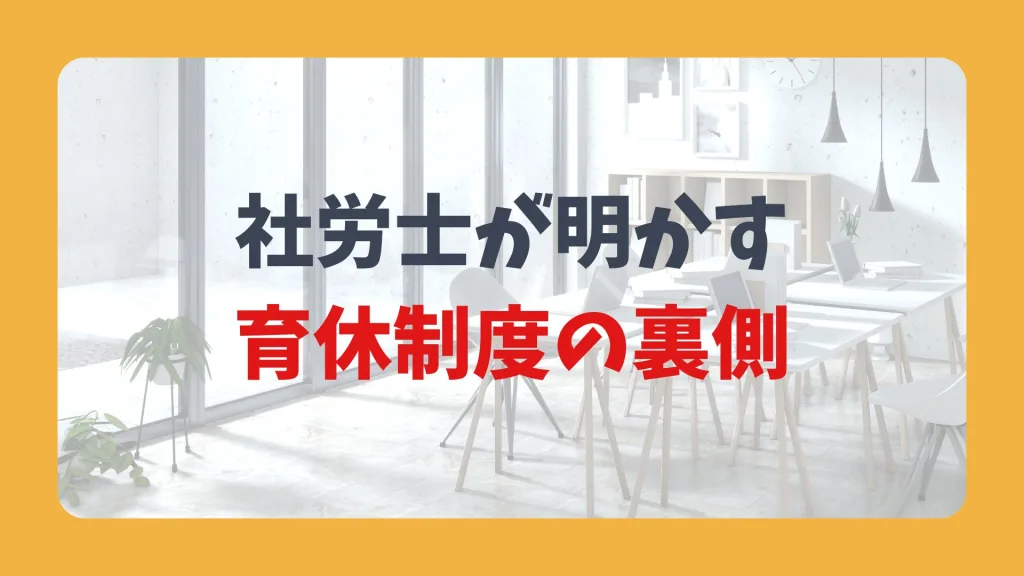
中小企業の経営者様、人事労務担当者の皆様、こんにちは。社労士事務所ぽけっとです。
従業員の方のライフイベントである「育児休業」。
その期間中、従業員と会社の双方で社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が免除されることは、多くの方がご存知かと思います。
これは、休業中で給与の支払いがない(または少ない)従業員の負担を軽減し、企業の法定福利費を抑える、非常にありがたい制度です。
しかし、この免除制度、実は「いつ」育休を取得するかによって、適用されるかどうかが変わるケースがあることをご存知でしょうか?
特に、「月末に1日だけ育休を取得した場合」と「月中の1日だけ育休を取得した場合」では、結論が大きく異なります。
今回は、そんな少しイレギュラーなケースに焦点を当て、社会保険料免除の仕組みと、合わせて知っておきたい雇用保険からの給付金について、分かりやすく解説していきます。

本記事で解説する「月末1日のみの育休取得」による社会保険料免除は、現行法上、認められている手法です。
しかし、私たち社会保険労務士としては、制度の趣旨を逸脱した利用を推奨するものではありません。
育児休業は、本来、子の養育に専念するために設けられた大切な制度です。
この記事は、あくまで制度に関する正確な「知識」として皆様にご提供するものであり、適切な労務管理の一助となれば幸いです。
【結論】月末1日の育休なら免除、月中1日なら免除されない!
早速ですが、結論からお伝えします。
- ケースA:月の末日(例:5月31日)に1日だけ育児休業を取得した場合 → その月(5月分)の社会保険料は免除されます。
- ケースB:月の途中(例:5月15日)に1日だけ育児休業を取得した場合 → その月(5月分)の社会保険料は免除されません。
「たった1日の違いで、なぜこんなに結果が変わるの?」と疑問に思われたかもしれません。
この違いを生むのが、社会保険料免除の基本的な考え方です。
なぜ?社会保険料免除の鍵は「月末」にあり
社会保険料の免除は、「育児休業等を開始した日の属する月から、その育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月まで」の期間について適用されます。
少し分かりにくい表現ですが、ポイントは「月末時点で育児休業を取得しているかどうか」です。
社会保険料は月単位で計算されるため、月の末日に被保険者資格があるかどうかで、その月の保険料がかかるかどうかが決まります。
ケースA(月末1日育休)の場合、月末日である5月31日に育児休業を取得しているため、「5月分の保険料は免除」という扱いになります。
従業員本人負担分だけでなく、会社負担分も同様に免除されます。
一方、ケースB(月中1日育休)では、月末の5月31日時点では育児休業を取得していません。
そのため、免除の対象とはならないのです。
【法改正ポイント】同月内でも14日以上の育休なら免除対象に!
これまでのルールでは、同じ月内に育休を開始し、終了する場合(月をまたがない場合)、月末に育休を取得していない限り免除の対象外でした。
しかし、2022年10月の法改正により、新たなルールが追加されました。
それは、「同じ月内に14日以上の育児休業を取得した場合」でも、その月の社会保険料が免除されるというものです。
これにより、例えば5月10日から5月25日まで(16日間)育休を取得した場合でも、5月分の社会保険料が免除されるようになりました。
男性の育児休業取得促進にも繋がる、柔軟な改正と言えます。
※賞与に関する注意点※
法改正により、賞与にかかる社会保険料の免除要件は厳しくなりました。
賞与については、「その賞与が支払われた月の末日を含み、連続して1ヶ月を超える育児休業」を取得した場合にのみ、免除の対象となります。
月末1日だけの育休では、月給分の社会保険料は免除されますが、同月に支給された賞与分の社会保険料は免除されないので注意が必要です。
合わせて知りたい!雇用保険からの給付金
育児休業中は、社会保険料の免除だけでなく、雇用保険から経済的な支援を受けることができます。
代表的な給付金について確認しておきましょう。
1. 育児休業給付金
原則として子どもが1歳になるまでの間、育児休業を取得した被保険者が受け取れる給付金です。
- 支給要件(主なもの)
- 育児休業を開始した日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(または就業した時間数が80時間以上の月)が12か月以上あること。
- 育児休業期間中の1か月ごとに、休業開始前の1か月の賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。
- 就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間)で10日以下(10日を超える場合は就業時間が80時間以下)であること。
- 支給額の目安
- 育休開始から180日間: 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
- 181日目以降: 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%
2. 出生時育児休業給付金(産後パパ育休)
子の出生後8週間以内に4週間(28日)まで取得できる「産後パパ育休(出生時育児休業)」を取得した場合に受け取れる給付金です。
- 支給要件(主なもの)
- 育児休業給付金と同様の被保険者要件を満たしていること。
- 子の出生日(または出産予定日)から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間を定めて、その子を養育するための産後パパ育休を取得したこと。
- 休業期間中の就業日数が最大10日(10日を超える場合は80時間)以下であること。
- 支給額の目安
- 休業開始時賃金日額 × 産後パパ育休の日数 × 67%
3. 出生後休業支援給付金
2025年度から創設された給付金です。
子の出生後、両親がともに14日以上の育児休業を取得した場合に、休業期間中の所得を補償するものです。
共働き世帯の育児休業取得をさらに後押しすることを目的としています。
- 支給要件(主なもの)
- 対象の子の出生後8週間以内に、被保険者とその配偶者がともに14日以上の育児休業を取得すること。
- (育児休業給付金と同様の被保険者要件を満たすこと)
- 支給額の目安
- 休業開始時賃金日額の13%相当額を、最大28日間分支給。
- これにより、既存の育児休業給付金(67%)と合わせて、休業前賃金の8割相当が支援されることになります。
これらの給付金は、従業員の生活を支える重要な制度です。
手続きは原則として会社経由で行いますので、対象となる従業員の方へは、漏れなくご案内できるよう準備しておきましょう。
まとめ
今回は、育児休業中の社会保険料免除に関する少し特殊なケースについて解説しました。
- 月末に1日でも育休を取得すれば、その月の社会保険料は免除される。
- 月をまたがない場合でも、14日以上の育休であれば免除対象となる。
- 賞与保険料の免除は「1ヶ月超」の育休が必要。
- 雇用保険からは「育児休業給付金」「出生時育児休業給付金」、そして2025年度からは「出生後休業支援給付金」が支給される。
制度を正しく理解し、活用することは、従業員の安心に繋がり、ひいては会社の信頼にも繋がります。
手続きや判断に迷われた際は、ぜひ私たち社労士事務所ぽけっとのような専門家にご相談ください。
【免責事項】
本記事は、2025年8月時点の法令に基づき作成しております。法改正等により内容が変更となる場合がございますので、最新の情報をご確認ください。また、個別の事案については、必ず専門家にご相談いただきますようお願い申し上げます。本記事の情報を利用したことによるいかなる損害についても、当事務所は一切の責任を負いかねます。