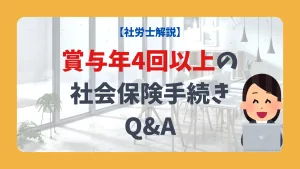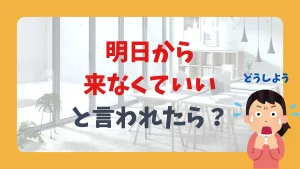育休取得者の「有給5日取得義務」は免除される?人事担当者が知るべきルール
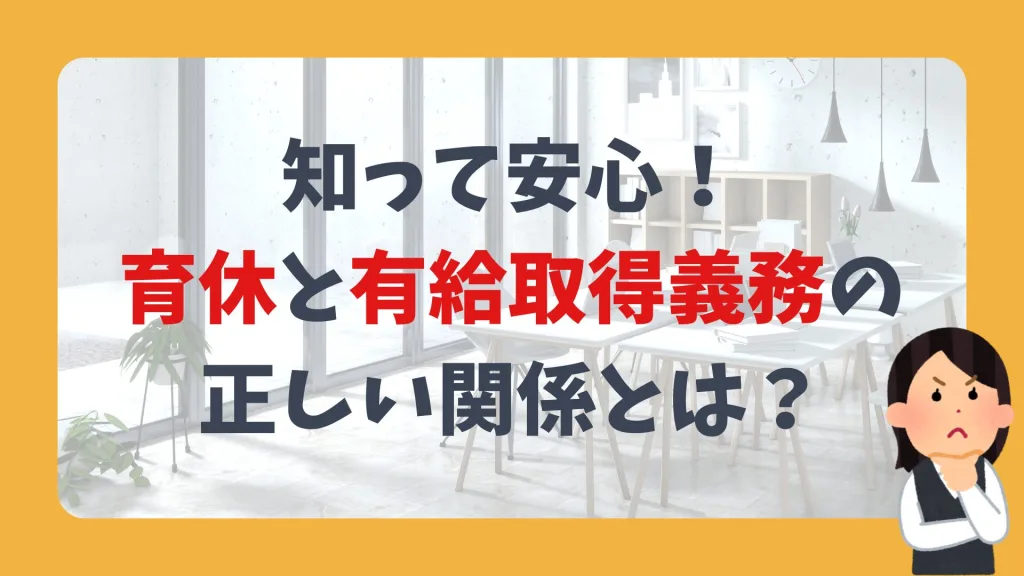
こんにちは!社労士事務所ぽけっとです。
企業の経営者様や人事担当者様から、こんなご相談をいただくことが増えました。
「育児休業で長期間お休みする社員がいるのですが、その社員にも年5日の有給休暇を取得させないといけないのでしょうか?現実的に難しいのですが…」
2019年4月からスタートした「年5日の年次有給休暇の取得義務化」。
すっかり定着してきましたが、育児休業のような長期休暇を取得する社員への対応は、判断に迷うポイントですよね。
お気持ち、とてもよく分かります。
結論から申し上げますと、育児休業の期間が長く、物理的に有給休暇を5日取得させることが不可能な場合は、5日に満たなくても法律違反にはなりません。
この記事では、「育休取得者の有給5日取得義務」について、なぜ免除されるケースがあるのか、企業としてどのように対応すればよいのかを、具体例を交えながら分かりやすく解説していきます。
そもそも「年5日の有給休暇取得義務」とは?
まず、基本のルールをおさらいしましょう。
「年5日の有給休暇取得義務」とは、「年10日以上の有給休暇が付与される労働者」に対して、会社が「有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内」に、「最低でも5日間」は有給休暇を取得させなければならない、というルールです。
社員自ら5日以上取得してくれれば問題ありませんが、取得日数が5日に満たない場合は、会社側が「〇月〇日に休んでください」と日付を指定してでも、必ず取得させなくてはなりません。
このルールの根底にあるのは、「有給休暇は“労働義務のある日”の労働を免除し、心身をリフレッシュしてもらうための制度」という考え方です。
この「労働義務のある日」という点が、育休取得者のケースを考える上で非常に重要なキーワードになります。
本題:育休取得者の場合、どう考えればいいの?
では、本題の育休取得者のケースについて見ていきましょう。
なぜ育休期間中は有給休暇が取れないのか?
育児・介護休業法に基づき取得する育児休業期間中は、そもそも労働義務が免除されています。
先ほど説明した通り、有給休暇は「労働義務のある日」にしか取得できません。
つまり、お休みすることが決まっている育休期間中に、重ねて有給休暇を取得することはできないのです。
そのため、年5日の取得義務を考える際は、育休期間を除いた「出勤日(労働義務のある日)」をベースに判断する必要があります。
【ケース別】具体例で見てみよう!
言葉だけだと分かりにくいので、具体的なケースで考えてみましょう。(※いずれのケースも、有給休暇は毎年4月1日に付与されるものとします)
ケース1:1年の大半を育児休業で休むAさんの場合
- 状況:4月1日に有給休暇が付与された後、4月16日から翌年3月31日まで育児休業を取得。
- 労働義務のある日:4月1日から育休に入る前までの数日間のみ。
この場合、Aさんの出勤日は数日しかありません。
会社が「5日間の有給を取ってね」と言っても、取得するための「労働日」が足りませんよね。
このように、年間の労働日が5日に満たない場合は、その労働日の日数分の有給休暇を取得させれば義務を果たしたことになり、5日に満たなくても法律違反には問われません。
もし労働日が3日しかないなら、3日取得させればOKです。
ケース2:年の途中で職場復帰するBさんの場合
- 状況:育児休業を取得しており、10月1日に職場復帰。
- 労働義務のある日:復帰した10月1日から、次の基準日(翌年3月31日)までの約6ヶ月間。
Bさんの場合、復帰後の約6ヶ月間は労働義務があります。
この期間の労働日は、祝日などを除いても100日以上はあるでしょう。
これは、取得させなければならない5日間よりも明らかに多いです。
したがって、会社はBさんに対して、復帰後の6ヶ月の間に5日間の有給休暇を取得させる必要があります。
(※育休前に取得した日数があれば、その残りの日数)
根拠は?厚生労働省のQ&Aを確認
こうした考え方は、厚生労働省が示している公式な見解に基づいています。
Q. 年度の途中に育児休業から復帰した労働者等についても、年5日の年次有給休暇を確実に取得させる必要があるのでしょうか。
A. 年度の途中に育児休業から復帰した労働者等についても、年5日の年次有給休暇を確実に取得していただく必要があります。
ただし、残りの期間における労働日が、使用者が時季指定すべき年次有給休暇の残日数より少なく、5日の年次有給休暇を取得させることが不可能な場合には、その限りではありません。(出典:厚生労働省『年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説』より)
ここで出てくる「使用者が時季指定すべき年次有給休暇の残日数」という少し難しい言葉は、要するに「会社として、あと最低何日、社員に有給を取らせる義務が残っているか」という日数のことです。
つまり、復帰後の出勤日数が、会社が休ませなければいけない義務の日数より少ない場合は、「物理的に不可能」と判断され、免除されるというわけです。
人事担当者が注意すべきポイント
育休取得者の有給休暇管理で最も大切なのは、復帰後の社員とのコミュニケーションです。
特に、年の途中で復帰した場合、本人も仕事のペースを取り戻すのに必死で、休暇のことまで頭が回らないかもしれません。
会社側は、
- 復帰のタイミングで、有給休暇の残日数と取得義務について丁寧に説明する。
- いつ頃休暇を取得したいか、本人の希望を聞く。
- 業務の状況を見ながら、計画的に取得できるよう上司も交えて調整する。
といった配慮をすることが、トラブルを防ぎ、社員が安心して働き続けられる環境づくりに繋がります。
まとめ
今回は、育休取得者の年5日の有給休暇取得義務について解説しました。
最後にポイントをまとめます。
- 育休期間中は労働義務がないため、有給休暇は取得できない。
- 年5日の取得義務は、育休期間などを除いた「労働日」をベースに考える。
- 復帰後の労働日が、取得すべき有給の残日数より少ない場合は、その労働日数分を取得させればOK。
- 年の途中で復帰した場合は、残りの期間で計画的に5日取得できるよう、会社が配慮することが重要。
法律のルールは一見複雑に思えますが、一つひとつの意味を理解すれば、実務での対応もスムーズになります。
社労士事務所ぽけっとでは、給与計算や社会保険手続きのアウトソーシングはもちろん、こうした日々の労務管理に関するご相談にも丁寧に対応しております。
何かお困りのことがございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。
【免責事項】
本記事は、掲載時点の法令や情報に基づき作成しておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。また、個別の事案に対する具体的な助言を提供するものでもありません。本記事の情報を用いて行う一切の行為について、当事務所は何ら責任を負うものではありませんので、ご了承ください。具体的な事案については、必ず専門家にご相談ください。