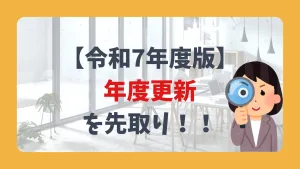【令和7年4月以降】高年齢者雇用確保措置の完全義務化!貴社の対応は万全ですか?確認ポイント解説
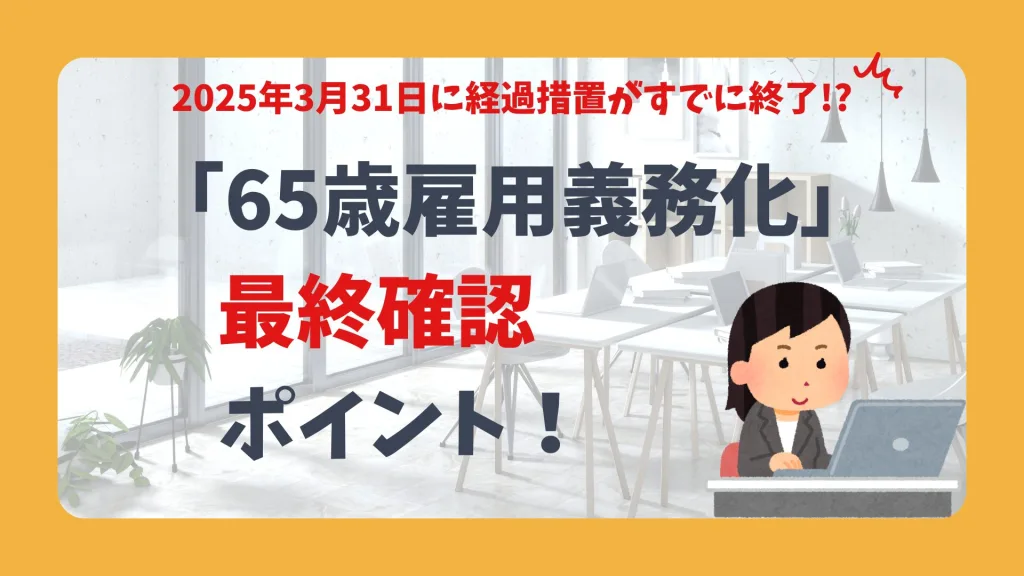
高年齢者の雇用に関する大切なルールの経過措置が終了してから、少し時間が経ちました。確認は万全でしょうか?
令和7年(2025年)3月31日。
この日をもって、高年齢者雇用安定法(高年法)で定められた「65歳までの雇用確保義務」に関する経過措置が終了しました。
「うちはちゃんと対応できているかな?」「何か確認すべきことはある?」と改めて思われた事業主様もいらっしゃるかもしれませんね。
ご安心ください。この記事では、
- 何が変わったのか?(経過措置終了のポイント)
- なぜ対応が必要だったのか?確認はお済みですか?
- 事業主として確認・対応すべきこと
- 活用できる支援制度はあるのか?
といった点について、改めて分かりやすく解説していきます。
少子高齢化が進み、人手不足が深刻化する現代において、経験豊富な高年齢者の方々の力は、企業の持続的な成長にとってますます重要になっています。法改正への適切な対応は、変化に強い組織を作るための基礎となります。
さあ、一緒に確認していきましょう!
そもそも「高年齢者雇用確保措置」と「経過措置」って何だった?
まず、基本をおさらいしましょう。
高年齢者雇用安定法という法律では、働く意欲のある高年齢者の方々が、年齢に関わなく活躍し続けられる社会を目指して、事業主に65歳までの安定した雇用を確保することを義務付けています。
具体的には、以下のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じている必要がありました。
- 65歳までの定年引き上げ
- 定年制の廃止
- 65歳までの継続雇用制度の導入
- 希望者全員を対象とする必要があります。
- 「継続雇用制度」とは、定年を迎えた従業員を、本人の希望に応じて引き続き雇用する制度のことです(例:再雇用制度、勤務延長制度)。
多くの企業では、段階的にこれらの措置を導入してきましたが、そのスムーズな移行のために設けられていたのが「経過措置」でした。
例えば、以前は継続雇用の対象者を労使協定で定めた基準によって限定することが認められていましたが、この基準による限定が認められる経過措置が、令和7年3月31日をもって終了したのです。
ポイント:令和7年4月1日以降は、原則として、希望者全員を65歳まで継続雇用する体制が整っている必要があります。
なぜ対応が必要だったのか?確認はお済みですか?
経過措置が終了した今、改めて対応の必要性を確認しましょう。
- 法的義務の完全履行: 令和7年4月1日から、全ての企業で「希望者全員の65歳までの雇用」が完全に義務化されています。未対応の場合、法律違反となるリスクがあります。 対応が完了しているか、再度ご確認ください。
- 人手不足への対応: 日本は深刻な人手不足に直面しています。豊富な経験、知識、スキルを持つ高年齢者の方々は、企業にとってかけがえのない財産です。彼らが意欲を持って働き続けられる環境を整備することは、人材確保の観点からも非常に重要です。
- 70歳までの就業機会確保(努力義務)への準備: 現在、法律では「70歳までの就業機会の確保」が努力義務とされています。65歳までの雇用確保は、その先の70歳までの活躍支援を見据えた第一歩です。高年齢者が活躍できる体制を整えておくことが、将来的な企業の競争力に繋がります。
事業主が確認・対応すべきことリスト
確認・対応すべきことをリストアップしました。
- 就業規則の確認
- 現在の定年年齢や継続雇用制度の内容が、法改正に対応したものになっているか確認しましょう。
- 特に、以前の経過措置で認められていた『労使協定で定めた基準』など、継続雇用の対象者を限定する条項が就業規則や関連規程に残っていないか、そして『希望者全員』を対象とする旨が明記されているかを重点的に確認してください。
- 具体的な就業規則の改定や助成金の活用など、専門的なアドバイスが必要な場合は、弊社の社会保険労務士がお手伝いできますので、お気軽にご相談ください。
- 雇用確保措置の運用状況の確認
- 導入した雇用確保措置(定年引き上げ、定年廃止、継続雇用制度)が適切に運用されているか確認しましょう。
- 継続雇用制度の場合、対象となる従業員への説明や意向確認が適切に行われているか、労働条件は明確になっているかなどを確認します。
- 従業員への周知・理解
- 制度の内容について、従業員(特に高年齢層)が正しく理解しているか、必要に応じて再度説明の機会を設けましょう。
- 社内体制の整備状況
- 高年齢者が意欲と能力に応じて活躍できるような、柔軟な働き方や、適切な業務分担、安全衛生への配慮などが実践できているか確認しましょう。
高年齢者雇用がもたらすメリットとは?
改めて、高年齢者の雇用には多くのメリットがあります。
- 豊富な経験と熟練スキルの活用: 長年培ってきた知識や技術は、若手社員への指導や、業務改善、新たな発想に繋がります。
- 人手不足の緩和: 採用難の時代において、貴重な労働力となります。
- 職場環境の活性化: 多様な世代が共に働くことで、新たな視点や価値観が生まれ、組織全体の活性化に繋がります。
- 顧客からの信頼向上: 幅広い年齢層の従業員がいることで、多様な顧客ニーズに対応しやすくなります。
活用できる支援制度(助成金など)
国も、高年齢者の雇用促進に取り組む企業を支援するための助成金制度を用意しています。(※制度は変更される可能性があるため、常に最新情報をご確認ください)
- 65歳超雇用推進助成金
- 65歳超継続雇用促進コース: 65歳以上への定年引き上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入などを行った場合に助成。
- 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース: 高年齢者の雇用管理制度(評価・処遇制度など)の整備を行った場合に助成。
- 高年齢者無期雇用転換コース: 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた場合に助成。
- 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース): 60歳以上65歳未満の高年齢者などをハローワーク等の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れた場合に助成。
これらの助成金は、制度内容や申請要件が変更される場合があります。最新の情報は、厚生労働省のウェブサイトや、管轄のハローワーク、労働局で必ず確認するようにしましょう。
【まとめ】変化への対応を確認し、未来へ繋げよう!
令和7年3月31日に、高年齢者雇用確保措置の経過措置は終了しました。
対応が完了しているか、今一度、就業規則等をご確認ください。
法改正への適切な対応は、単なる義務の履行に留まりません。経験豊かな人材が長く活躍できる環境を整えることは、人手不足という大きな課題を乗り越え、企業の持続的な成長を実現するための重要な戦略です。
変化への対応状況を確認し、高年齢者の方々がいきいきと働ける魅力的な会社づくりを、さらに進めていきましょう。もし対応に不安がある場合や、就業規則の見直し、最適な制度設計、活用可能な助成金の申請サポートなど、具体的な進め方について専門家のアドバイスが必要な場合は、弊社まで、ぜひお気軽にお問い合わせください。