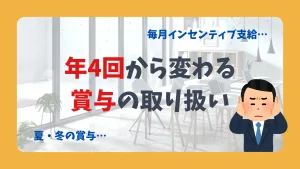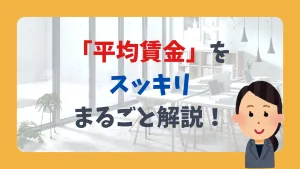従業員の業務災害、「最初の3日間」の補償はどうする?会社が支払うべき休業補償を解説
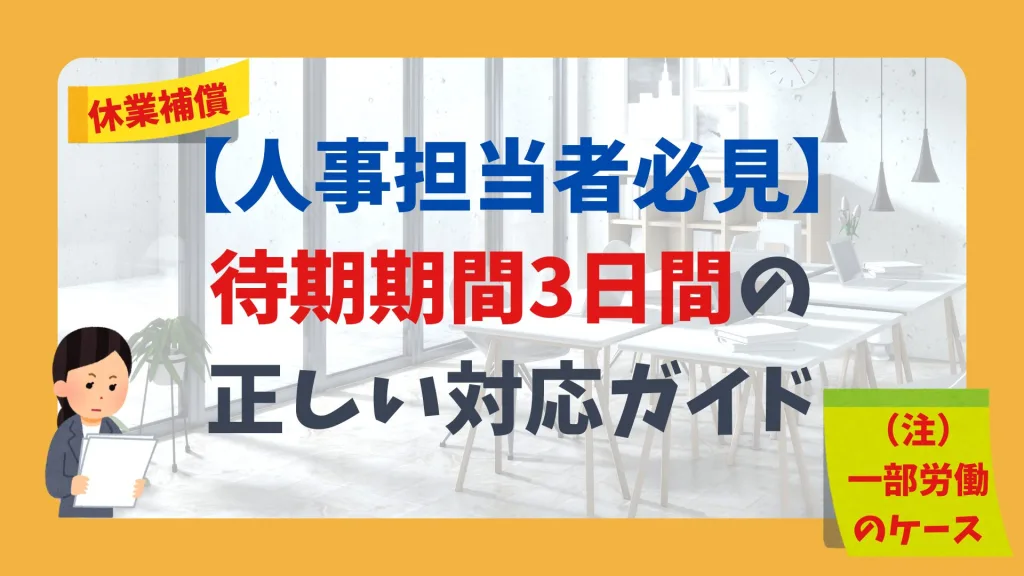
こんにちは!社労士事務所ぽけっとです。
「従業員が業務中にケガをした!明日から休むそうだが、会社として何をすべきだろうか?」
このような事態が発生した際、多くの経営者様や人事担当者様が思い浮かべるのは「労災保険」かもしれません。
しかし、労災保険からの給付が始まる前に、会社自身が補償を行うべき期間があることをご存知でしょうか。
それが、従業員が休み始めてから最初の3日間です。
今回は、意外と知られていないけれど非常に重要な、労働基準法で定められた「会社が支払うべき休業補償」について、その役割と具体的な内容を徹底解説します。
労災保険との違いを正しく理解し、万が一の際に適切な対応ができるよう、ぜひ最後までお付き合いください。
会社が支払う「休業補償」とは?(労働基準法の災害補償)
今回ご説明する「休業補償」とは、労働基準法第76条で定められている、企業の義務(=災害補償責任)です。
労働基準法 第七十六条 労働者が(業務上の)負傷又は疾病にかかり、療養のために労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。
簡単に言うと、「従業員が仕事が原因のケガや病気で療養するとき、会社は従業員の生活を守るために、お給料の代わりに一定額を補償してくださいね」というルールです。
これは、国の制度である労災保険とは別に、会社(使用者)に直接課せられた義務であるという点が最大のポイントです。
なぜ会社が補償?最重要ポイント「待期期間の3日間」
「業務災害なら、全部労災保険がみてくれるんじゃないの?」そう思われる方も多いかもしれません。
しかし、労災保険の「休業(補償)給付」は、休業した最初の3日間は支給されないというルールがあります。
この最初の3日間を「待期期間」と呼びます。
この待期期間中、従業員は労災保険からの給付を受けられず、収入が途絶えてしまいます。
その間の生活を保障するために、労働基準法では会社に対して休業補償を支払うよう義務付けているのです。
- 休業1日目~3日目(待期期間): 会社が労働基準法に基づき「休業補償」を支払う
- 休業4日目以降: 労災保険から「休業(補償)給付」等が支払われる
つまり、会社が支払うべき休業補償が主に発生するのは、この「待期期間の3日間」ということになります。
(※なお、この待期期間は、連続している必要はなく、通算で3日に達するまでとなります。)
休業補償の具体的な計算方法
では、会社が支払うべき休業補償はいくらになるのでしょうか。
労働基準法では、「平均賃金の60%」を支払うよう定められています。
計算式: 平均賃金 × 60% × 休業日数(最大3日)
【平均賃金とは?】 原則として、災害が発生した日の直前3ヶ月間に、その従業員に支払われた賃金総額を、その期間の暦日数で割った1日あたりの賃金額です。
(例:4月1日に災害発生 → 1月、2月、3月の賃金総額 ÷ その3ヶ月間の総日数)
《計算例》 平均賃金が12,000円の従業員が、業務災害により丸1日休業した場合…
- 1日あたりの休業補償額: 12,000円 × 60% = 7,200円
この7,200円を、休業した日に対して会社が支払います。
【重要】災害発生日に早退した場合の扱いは?
「業務災害があったその日に、定時まで働かずに早退して病院に行った」というケースは非常に多く発生します。
この場合、待期期間はどうカウントするのでしょうか。
結論として、所定労働時間内に発生した災害で早退した場合、その日も待期期間の1日目としてカウントします。
ただし、その日は一部労働しているため、休業補償の額は調整が必要です。
具体的には、「その日に支払われるべき賃金(平均賃金)と、実際に働いて得た賃金の差額」に対して補償を行います。
計算式: (平均賃金 - 災害当日に実労働に対して支払われた賃金)× 60%
《計算例》 平均賃金12,000円の従業員が、災害当日に早退し、その日の労働に対して5,000円の賃金が支払われた場合…
- 差額を計算:12,000円 - 5,000円 = 7,000円
- この差額に対して60%を補償:7,000円 × 60% = 4,200円
この場合、会社は4,200円を休業補償として支払います。
そして、この早退した日が「待期期間の1日目」となります。
労災保険の給付との関係を整理
| 会社の休業補償(労働基準法) | 労災保険の休業(補償)給付等 | |
| 支払う人 | 会社(使用者) | 政府(労災保険) |
| 対象期間 | 休業1日目~3日目(待期期間) | 休業4日目以降 |
| 支払額 | 平均賃金 の60% | 給付基礎日額 の60%(休業(補償)給付) + 給付基礎日額 の20%(休業特別支給金) |
| 根拠 | 業務災害 | 業務災害・通勤災害 |
重要な注意点:通勤災害の場合 待期期間中に会社が休業補償を支払う義務があるのは、「業務災害」の場合のみです。通勤途中のケガである「通勤災害」の場合、待期期間の3日間について会社に補償義務はありません。
休業補償と社会保険・税金の取り扱い
- 社会保険料(健康保険・厚生年金保険): 支払いは必要です。 待期期間中も被保険者資格は継続しますので、社会保険料は発生します。
- 所得税: 非課税です。 労働基準法の規定により使用者が支払う「休業補償」は、非課税所得とされています。
Q&Aコーナー
Q1. 待期期間の3日間に、会社の公休日や祝日が含まれている場合はどうなりますか?
A1. 会社の公休日や祝日も、待期期間の3日間に含まれます。待期期間は暦日でカウントします。
Q2. 待期期間中に、本人の希望で有給休暇を使った場合は、休業補償を支払う必要はありますか?
A2. いいえ、支払う必要はありません。有給休暇を取得した場合、その日は「賃金」が支払われるため、休業補償の支払義務は発生しません。ただし、その日も待期期間の1日としてはカウントされます。
Q3. 1日休んで次の日に出勤し、またその次の日から休んだ場合、待期期間はどう数えますか?
A3. 待期期間は、必ずしも連続している必要はなく、通算でカウントします。休業日が断続的であっても、合計3日に達するまでが会社の補償対象となります。
まとめ
今回は、従業員が業務災害に遭った際に、会社が支払うべき「休業補償」について解説しました。
- 会社が支払う休業補償は、労働基準法で定められた義務である。
- 主に、労災保険が給付されない「待期期間(休業開始から3日間)」に対して支払う。
- 金額は「平均賃金の60%」で、所得税はかからない。
- 業務災害で早退した日は、待期期間の1日目としてカウントし、差額に対して補償する。
特に、一部労働した場合の計算は誤解が生じやすいポイントです。
正しい知識を持つことが、法令遵守と従業員との信頼関係構築に繋がります。
少しでもご不明な点があれば、ぜひ私たち社会保険労務士にご相談ください。
【免責事項】
本記事は、公開日時点の法令や情報に基づいて作成しております。今後の法改正等により、内容が変更となる可能性があります。また、個別の事案については、必ず専門家にご相談の上、ご判断いただきますようお願い申し上げます。