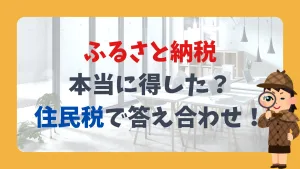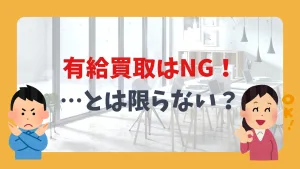労働基準法における「休日」の定義と休日出勤時の注意点とは?
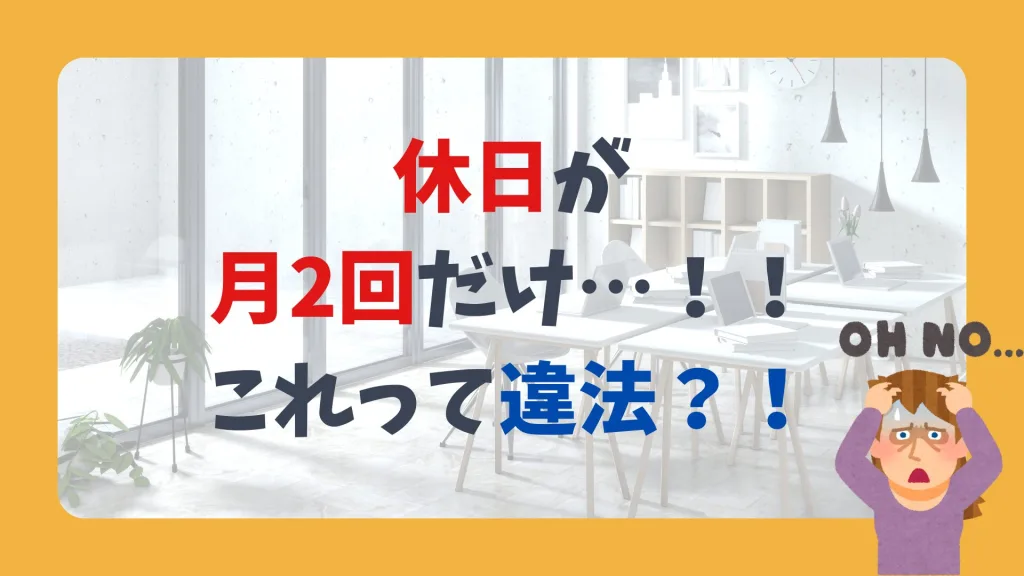
繁忙期の休日出勤で「週1日休み」を守れないと法律違反?
中小企業の経営者様や人事担当者様で、このようなお悩みはありませんか?
「普段は週休2日だけど、繁忙期でどうしても休日出勤してもらいたい…。」
「労働基準法では『週に1回、または4週4休』と聞くけれど、休日出勤させたら法律違反になるの?」
実は、多くの方が誤解されているポイントがここにあります。
労働基準法が定める「休日」のルールを正しく理解し、適切な手続きを踏めば、繁忙期の休日出勤も法律違反にはなりません。
この記事では、労働基準法における休日の定義から、休日出勤時に企業が守るべきルール、そして、いざという時に困らないための注意点まで、分かりやすく解説します。
労働基準法が定める「休日」のルールとは?
労働基準法第35条には、以下の通り定められています。
- 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
- 例外として、4週間を通じて4日以上の休日を与えることができる。
これが、いわゆる「法定休日」と呼ばれるものです。
この法定休日の目的は、労働者の健康と生活を守るために、一定期間の休息を必ず与えることです。
多くの方が「週休2日制」に慣れているため、「週に2日休まなければならない」と思われがちですが、実は労働基準法が直接的に義務付けているのは「週に1回」または「4週4休」です。
「法定休日」と「法定外休日(所定休日)」の違い
ここで理解しておきたいのが、「法定休日」と「法定外休日(所定休日)」の違いです。
- 法定休日:労働基準法によって、週に1回(または4週4休)与えることが義務付けられている休日です。例えば、就業規則や雇用契約書で「毎週日曜日」と定めている場合は、その日が法定休日となります。
- 法定外休日(所定休日):法定休日を除いた、会社が独自に定める休日です。例えば、週休2日制の会社で、日曜日が法定休日、土曜日が法定外休日(所定休日)と定められている場合などです。
この違いは、後述する休日出勤手当の計算にも大きく影響します。
繁忙期に休日出勤!法律違反にならないためのポイント
ご質問のように、「本来の就業カレンダーで毎週日曜日が休日(法定休日)だが、繁忙期で休日出勤することになった」というケースについて見ていきましょう。
結論から申し上げると、適切な手続きを踏めば、繁忙期の休日出勤であっても法律違反にはなりません。
ただし、いくつか重要なポイントがあります。
1. 36協定の締結と届出
法定休日に労働者を労働させる場合(休日出勤をさせる場合)は、労働基準法第36条に基づく労使協定(通称「36協定」)を締結し、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。
36協定は、法定労働時間(原則として1日8時間、週40時間)を超える時間外労働や、法定休日における労働を可能にするための協定です。
これがないまま休日出勤をさせると、法律違反となりますので注意が必要です。
【36協定で定めるべき休日労働に関する事項】
36協定(時間外労働・休日労働に関する協定届)の様式には、法定休日労働について具体的に定めるべき項目があります。
特に以下の2点については、必ず記載が必要です。
- 労働させることができる法定休日の日数: 例えば「1ヶ月に2日」や「1年間で20日」など、具体的な日数を定めます。無制限に休日労働をさせることができないように、上限を設ける必要があります。
- 労働させることができる法定休日における始業および終業の時間: 例えば「午前9時から午後5時まで」のように、休日労働を行う具体的な時間帯を定めます。これにより、労働者がいつ、どのくらいの時間休日労働をするのかが明確になります。
これらの項目は、労働者の健康と生活を守るために、使用者が無制限に休日労働をさせることができないようにするためのものです。
協定で定めた内容を超えて休日労働をさせることはできません。
2. 割増賃金の支払い
法定休日に労働させた場合、会社は労働者に対して通常の賃金の35%以上の割増賃金(休日手当)を支払う義務があります。
例えば、時給1,000円の労働者が法定休日に8時間勤務した場合、通常の賃金は8,000円ですが、これに加えて2,800円(8,000円 × 0.35)以上の休日手当を支払う必要があります。
【休日手当の計算例】
時給1,000円の労働者が、法定休日に8時間勤務した場合 1,000円 × 8時間 × 1.35 = 10,800円
もし、時間外労働も発生した場合は、休日労働の割増率と時間外労働の割増率をそれぞれ適用するのではなく、休日労働として35%以上の割増賃金を支払います。
【ここがポイント!】
法定外休日(所定休日)に労働させた場合は、通常の労働時間としてカウントされ、週40時間を超えた場合に時間外労働として25%以上の割増賃金(時間外手当)が発生します。
法定休日と法定外休日(所定休日)では、割増率が異なるため、どちらの休日なのかを明確にしておくことが重要です。
3. 代替休日の設定
法定休日に労働させた場合、その代わりに他の労働日を休日とする「代替休日」を付与することも可能です。
代替休日を付与することで、週1日の休日確保の義務を果たすことができます。
ただし、代替休日を設定する場合でも、休日出勤した日自体は法定休日の労働として、35%以上の割増賃金を支払う義務があります。
代替休日が与えられたからといって、休日出勤の割増賃金が不要になるわけではない点に注意してください。
4. 労働時間の管理の徹底
繁忙期で休日出勤が増える場合でも、労働時間の管理は厳格に行う必要があります。
長時間労働による健康被害を防ぐためにも、労働時間の上限規制や、連続勤務日数の制限にも配慮することが重要です。
休日の設定でトラブルを防ぐための社労士からのアドバイス
「労働基準法は難しくて、うちの会社は大丈夫かな…」と不安に感じる経営者様もいらっしゃるかもしれません。
しかし、適切な知識と対策があれば、労使トラブルを未然に防ぎ、従業員が安心して働ける環境を整えることができます。
- 就業規則の整備と周知:休日の定義、休日出勤のルール、割増賃金などについて、就業規則に明確に記載し、従業員に周知徹底しましょう。
- 36協定の内容確認:毎年、労働時間の上限や休日労働の回数などを確認し、実態に合った内容になっているか見直しましょう。特に、労働させることができる法定休日の日数や、労働させることができる法定休日における始業および終業の時間が実態に即しているか確認が重要です。
- 労働時間管理の徹底:タイムカードや勤怠管理システムなどを活用し、従業員の労働時間を正確に把握しましょう。
- 専門家への相談:労働基準法の解釈や運用で迷った場合は、社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
社労士事務所ぽけっとは、給与計算や社会保険手続きだけでなく、このような労務管理全般に関するお悩みにも寄り添い、貴社にとって最適な解決策をご提案いたします。
【まとめ】法定休日と休日出勤のルールを正しく理解し、健全な労務管理を
「休日は週に1回もしくは4週4休」という労働基準法のルールは、労働者の健康と生活を守るための重要な定めです。
繁忙期に休日出勤が必要となる場合でも、36協定の締結・届出(定めるべき事項の明記含む)、適切な割増賃金の支払い、そして労働時間の厳格な管理を行うことで、法律に違反することなく対応が可能です。
不明な点や不安なことがあれば、いつでもお気軽にご相談ください。
社労士事務所ぽけっとが、貴社の労務管理をしっかりとサポートさせていただきます。
免責事項
本ブログ記事は、一般的な情報提供を目的としており、特定の法的アドバイスを提供するものではありません。個別の事案については、専門家にご相談ください。本記事の内容に基づいて被ったいかなる損害についても、当事務所は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。