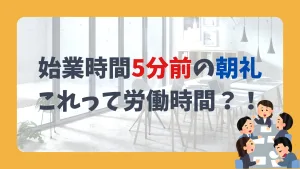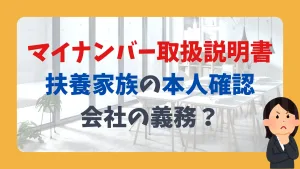遅刻を繰り返す社員への正しい対応|指導から懲戒処分までのステップ
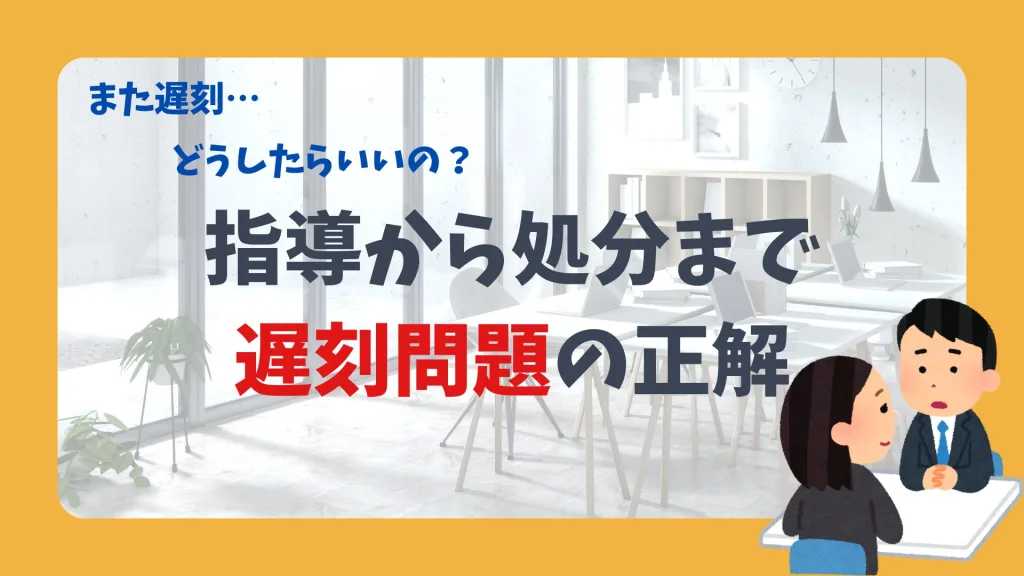
「またあの社員が遅刻している…」
「何度注意しても一向に改善されない」
従業員の遅刻は、多くの経営者や人事担当者が頭を悩ませる問題です。
たかが5分、10分の遅刻と軽く考えていると、職場の規律が乱れ、真面目に働く他の社員のモチベーション低下にも繋がりかねません。
しかし、感情的に叱責したり、いきなり厳しいペナルティを科したりするのは、パワハラと捉えられたり、法的なトラブルに発展したりするリスクも。
大切なのは、就業規則という会社のルールに基づき、段階的かつ毅然と対応することです。
この記事では、社会保険労務士の視点から、遅刻がやまない社員への正しい対応ステップを「指導」から「制裁(懲戒処分)」まで、具体的な注意点を交えて分かりやすく解説します。
なぜ遅刻は放置してはいけないのか?
そもそも、なぜ遅刻を問題として真剣に捉えるべきなのでしょうか。
その影響は、単に「始業時間に間に合わなかった」という事実以上に大きいものです。
- 職場の規律の乱れ:「あの人が許されるなら自分も」という雰囲気が蔓延し、組織全体の規律が緩みます。
- 他の従業員の士気低下:時間通りに出勤している真面目な従業員が、「なぜ自分だけがルールを守っているのか」と不公平感を抱き、モチベーションの低下を招きます。
- 生産性の低下:朝礼やミーティングに遅れる、業務の引継ぎが滞るなど、チーム全体の業務効率が悪化します。
- 顧客からの信頼損失:従業員の遅刻が原因で、顧客との約束の時間に遅れるなど、会社の信用問題に発展する可能性もあります。
遅刻は「個人の問題」ではなく、会社全体に悪影響を及ぼす「組織の問題」として捉えることが重要です。
大前提:すべての対応は「就業規則」に基づいて行う
指導や処分を行う上で、絶対的な拠り所となるのが「就業規則」です。
特に、従業員に不利益を及ぼす可能性のある懲戒処分は、あらかじめ就業規則に懲戒の種類と、どのような場合にどの処分を受けることになるのか(懲戒事由)が明記されていなければ、行うことはできません。
「遅刻を繰り返した場合、懲戒処分の対象となる」といった内容がきちんと定められているか、まずは自社の就業規則を再確認しましょう。
遅刻社員への対応 3つのステップ
では、具体的にどのように対応すればよいのでしょうか。
重要なのは、いきなり厳しい処分を下すのではなく、段階を踏んで対応することです。
これにより、会社は従業員に対して改善の機会を十分に与えたという正当性を主張できます。
ステップ1:まずは「指導」から【証拠を残す】
何よりもまず、客観的な事実確認と記録から始めます。
「最近よく遅れるな」という感覚的なものではなく、「〇月〇日 〇分遅刻」「〇月〇日 〇分遅刻」というように、日付と時間を正確に記録しましょう。
タイムカードのコピーや勤怠管理システムの記録などが客観的な証拠となります。
個別面談でのヒアリングと指導
記録が揃ったら、本人と個別に面談します。
高圧的な態度で問い詰めるのではなく、まずは遅刻の理由を冷静にヒアリングしましょう。
- 体調不良や家庭の事情など、やむを得ない理由があるかもしれません。
- 単なる寝坊や準備の遅れが原因であれば、社会人としての自覚を促し、改善を求めます。
この際、「遅刻は就業規則で定められた服務規律に違反する行為である」という事実を明確に伝え、改善に向けた具体的な約束(例:目覚まし時計を増やす、家を出る時間を15分早めるなど)を取り付けます。
指導記録の作成
面談後は、「いつ、誰が、どのような内容で指導し、本人はどう回答し、何を約束したか」を記録した「指導記録書」を作成します。
本人に内容を確認してもらい、署名をもらっておくと、後のトラブル防止に非常に有効です。
「指導した・していない」という水掛け論を避けるためにも、必ず書面に残しましょう。
ステップ2:改善が見られない場合は「警告」【書面で通告】
口頭での指導を複数回行っても改善が見られない場合、次のステップに進みます。
会社としてこの問題を重く見ているという、より強いメッセージを伝える必要があります。
始末書または顛末書の提出を求める
始末書は、本人が非を認め、反省と謝罪の意を示す文書です。
これを提出させることで、本人に事の重大さを認識させ、再発防止を誓約させます。
【重要ポイント】
ただし、たとえ就業規則に懲戒処分(譴責など)として「始末書を提出させる」と定めていたとしても、その提出を強制することはできません。
反省や謝罪といった内心の意思表示を強制することは、憲法で保障された「思想・良心の自由」に抵触する可能性があるためです。
もし本人が始末書の提出を拒否した場合は、事実関係の報告のみを目的とする「顛末書(てんまつしょ)」の提出を業務命令として求めましょう。
これに正当な理由なく応じない場合は、業務命令違反として新たな懲戒処分の対象となり得ます。
警告書の交付
警告書は、会社から本人に対して「服務規律違反を警告し、改善を命令する」という意思を明確に示す書面です。
ここには、以下の内容を盛り込みます。
- 対象となる遅刻の事実(日時、回数など)
- 就業規則のどの条項に違反しているか
- このまま改善されない場合、就業規則に基づき懲戒処分(減給など)の対象となる可能性があること
- 改善の最終期限
この警告書を本人に直接手渡し、受領のサインをもらうことが重要です。
これにより、会社は「改善の機会を十分に与え、次の処分があり得ることも明確に予告した」という証拠を残せます。
ステップ3:最終手段としての「制裁(懲戒処分)」【ルールに則り厳格に】
書面による警告にもかかわらず、一切の改善が見られない。
ここまできて初めて、就業規則に基づく「懲戒処分」を検討します。
懲戒処分の種類
遅刻に対して行われる可能性のある懲戒処分は、一般的に以下の通りです。
これらも全て就業規則に定めが必要です。
- 譴責(けんせき)・戒告:始末書の提出を求め、将来を戒める処分。最も軽い懲戒処分です。(※ただし、前述の通り始末書の提出は強制できません)
- 減給:一定額を給与から差し引く処分。
- 出勤停止:一定期間の出勤を禁止し、その間の給与は支払わない処分。
- 懲戒解雇:最も重い処分。ただし、遅刻常習のみを理由とする解雇は、よほど悪質でない限り無効と判断される可能性が高く、ハードルは非常に高いです。
減給処分の注意点
遅刻に対する制裁として「減給」を選択する場合、法律上の上限が定められているため注意が必要です。
労働基準法第91条により、1回の減給額は「平均賃金の1日分の半額」まで、減給の総額は「一賃金支払期(月給制ならその月)の賃金総額の10分の1」までと定められています。
これを超える減給は違法となります。
懲戒処分を行う際の鉄則
懲戒処分は従業員にとって非常に不利益な処分であるため、手続きは慎重に進めなければなりません。
- 就業規則上の根拠が明確であること。(最重要)
- 処分の重さが、行為の悪質性に対して妥当であること(懲戒権の濫用に当たらないこと)。
- 本人に弁明の機会を与えること。
これらのプロセスを無視して処分を下すと、後々「不当な処分だ」として訴訟に発展し、会社側が敗訴するリスクがあります。
よくある質問 Q&A
Q1. 遅刻した時間分の給与をカットするのは問題ない?
A1. はい、問題ありません。
これは懲戒処分としての「減給」とは異なり、「ノーワーク・ノーペイの原則」に基づきます。
労働の提供がなかった時間分の賃金を支払わないのは当然の権利です。
ただし、5分の遅刻に対して15分や30分単位で切り上げてカットするなど、実際に遅刻した時間を超えて給与をカットすることは違法です。
Q2. 遅刻の理由が「うつ病などの精神疾患」や「家族の介護」の場合は?
A2. 本人の責に帰すべき事由ではない可能性があるため、一方的な指導や処分は禁物です。
まずは産業医との面談を設定したり、時差出勤や時短勤務制度の利用を勧めたりするなど、安全配慮義務の観点から柔軟な対応が求められます。
状況によっては、休職を検討する必要もあるでしょう。
Q3. 注意・指導を受けている時間や、始末書を書く時間は労働時間になりますか?
A3. 重要なポイントです。これは分けて考える必要があります。
- 注意・指導を受けている時間:原則として「労働時間」です。
上司からの指導は業務の一環であり、従業員は会社の指揮命令下にあると解釈されるためです。 - 始末書を書いている時間:原則として「労働時間」ではありません。
始末書の作成は、業務そのものではなく、従業員自身の問題行動に対する反省の意を示す行為であり、本人の責任において勤務時間外に行うべきものと解釈されます。
ただし、会社が就業時間内に作成するよう具体的に命じた場合は、その時間は指揮命令下にあると見なされ、労働時間となる可能性があります。
【まとめ】毅然としつつも、ルールと手順を踏んだ丁寧な対応を
遅刻を繰り返す社員への対応は、感情的にならず、法と会社のルール(就業規則)に則って進めることが鉄則です。
- 就業規則を根拠に、証拠を残しながら指導する。
- 改善がなければ、書面で警告し、改善の機会と最終通告を行う。(始末書の強制はNG)
- それでも改善されなければ、就業規則に基づき、適切な重さの懲戒処分を検討する。
この段階的なプロセスを踏むことで、会社は従業員を守り、組織の規律を維持することができます。
「自社の就業規則は懲戒処分に対応できる内容になっているだろうか?」
「このケースで処分を下しても問題ないだろうか?」
など、具体的な対応に不安を感じた際は、ぜひ一度、私たち社労士事務所ぽけっとにご相談ください。
貴社の状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。
【免責事項】
本記事は、掲載日時点の法令や情報に基づき、一般的な情報提供を目的として作成しております。特定の個人や組織の具体的な状況に対応するものではなく、法的アドバイスとして解釈されるべきではありません。個別具体的な事案については、必ず専門家にご相談ください。