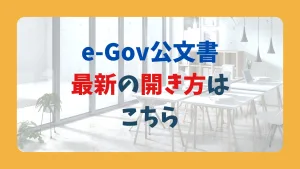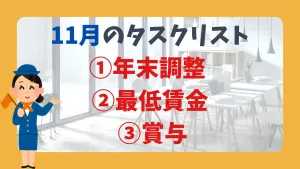「まかないが無料じゃなかった…」その理由、ご存じですか?
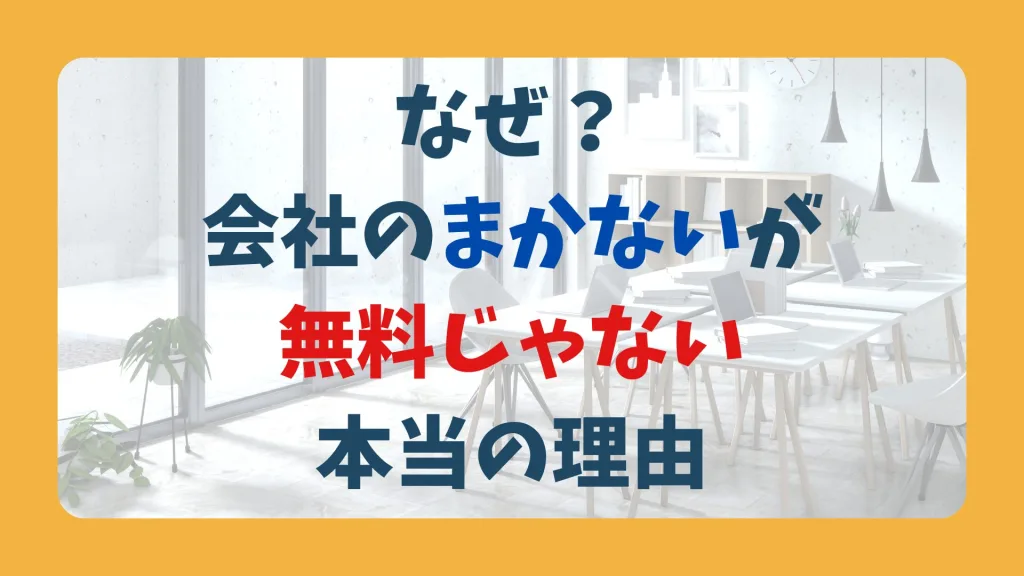
こんにちは!社労士事務所ぽけっとです。
飲食店などで働いていると、美味しい「まかない」が提供されることがありますよね。
従業員にとっては、食費が浮いてとても助かる嬉しい福利厚生の一つです。
しかし、ある日の給与明細を見て、「あれ?食事代が引かれてる…!無料じゃなかったの?」と驚いた経験はありませんか?
もしくは、これから食事補助を導入しようと考えている経営者の方で、「従業員のために無料で提供したいけど、何か問題はあるのだろうか?」と疑問に思っている方もいらっしゃるかもしれません。
実は、会社が食事代を給料から天引きしたり、一部負担をお願いしたりするのには、ちゃんとした理由があります。
それは、社会保険料の計算に深く関わる「現物給与(げんぶつきゅうよ)」という大切なルールが関係しているのです。
今回はこの「まかない」をテーマに、一見すると少し複雑な現物給与と社会保険の仕組みについて、身近な例を交えながら分かりやすく解説していきます。
そもそも「現物給与」って一体なに?
普段、私たちがお給料としてもらうのは「お金(通貨)」ですよね。
しかし、給与は必ずしもお金だけで支払われるとは限りません。
「現物給与」とは、その名の通り、お金以外の「現物」で支給される給与のことを指します。
今回のテーマである食事の提供のほかにも、以下のようなものが現物給与にあたります。
- 社宅や寮を無償、または非常に安い家賃で提供する
- 通勤定期券そのものを支給する(現金で交通費を支給する場合は通貨給与)
- 自社製品を無償、または割引価格で提供する
「福利厚生として提供しているだけなのに、これも給与なの?」と思われるかもしれませんが、従業員にとって経済的な利益となるものは、原則として給与(報酬)の一部と見なされるのです。
最重要ポイント!現物給与は社会保険料の計算に含まれる
では、なぜ「まかない」が現物給与として扱われることが重要なのでしょうか。
それは、毎月の給与から天引きされる健康保険料や厚生年金保険料といった社会保険料は、「標準報酬月額」という基準を基に計算されており、この標準報酬月額には現物給与も含まれるからです。
(※もちろん、このルールは社会保険に加入している従業員が対象です。)
標準報酬月額とは、給与の金額を一定の範囲(等級)で区切ったもので、この等級が高くなるほど、支払う社会保険料も高くなります。
つまり、食事を無料で提供すると、その食事の価値に相当する金額が給与に上乗せされ、標準報酬月額が上がり、結果として従業員が支払う社会保険料が増えてしまう可能性があるのです。
【標準報酬月額に含まれるもの】
基本給、役職手当、残業手当、通勤手当など、名称を問わず労働の対償として支払われるものすべてが含まれます。
そして、通貨で支払われるものだけでなく、食事や住宅などの「現物」で支払われるものも対象となります。
「まかない」の価値はどうやって決まる?
「現物である食事の価値を、どうやってお金に換算するの?」という疑問が湧きますよね。
これには明確なルールがあり、厚生労働大臣が都道府県ごとに「現物給与の価額」を定めています。
この価額は食事の提供状況(朝・昼・夕すべてか、昼食のみか等)によって異なります。
令和7年4月1日からは価額が改正され、例えば香川県では「昼食のみ」の場合は1人1日あたり280円、「3食すべて」の場合は1日あたり790円と定められています。
(※令和7年3月31日までは昼食のみ270円、3食すべて760円です)
(出典:日本年金機構「全国現物給与価額一覧表」)
【要注意:随時改定の対象になります】
令和7年4月の現物給与の価額変更は、社会保険上、固定給の変動とみなされます。
そのため、この価額変更によって標準報酬月額に2等級以上の差が生じた場合は、社会保険料を改定する「随時改定」の手続きが必要になる場合がありますので、注意が必要です。
仮に、会社が1食500円相当のまかないを月20日、無償で提供したとします。
この場合、単純計算では500円×20日=10,000円が給与に上乗せされるように感じますが、社会保険の計算上は、国が定めた基準額で評価されることになります。
給料から天引きされる理由がここに!食事代の特例ルール
さて、ここからが本題です。
「じゃあ、従業員の社会保険料負担を増やさないためにはどうすればいいの?」という疑問に対する答えが、ここにあります。
社会保険における食事の提供については、所得税のルールとは別に、以下のような特例が設けられています。
【社会保険における食事提供のルール】
ポイントは、従業員が食事の価額(国が定めた基準額)の「3分の2以上」を負担しているかどうかです。
- 従業員の負担額が、食事の価額の3分の2未満の場合
→ 食事の価額から、従業員が負担した額を差し引いた差額分が「現物給与」として給与に上乗せされます。 - 従業員の負担額が、食事の価額の3分の2以上の場合
→ 食事の提供はなかったものとみなされ、給与に上乗せされる金額は0円になります。
このルールがあるため、多くの会社では食事を「完全無料」にするのではなく、従業員の社会保険料負担を増やさないように、「食事の価額の3分の2以上」を目安に従業員に負担してもらう、という形をとっているのです。
具体例で見てみよう!
少し分かりにくいかもしれませんので、具体的な例で考えてみましょう。(※令和7年4月からの香川県の価額「3食すべて」の場合、月額23,700円を例に考えてみましょう)
この場合、社会保険料に影響しないためのボーダーラインは、23,700円の3分の2、つまり15,800円となります。
ケースA:会社が食事をすべて無料で提供した場合
- 従業員負担:0円(3分の2未満)
→ 食事の価額23,700円が、まるごと給与に上乗せされて社会保険料が計算されます。
ケースB:食事代として10,000円を給料から天引きした場合
- 従業員負担:10,000円(3分の2未満)
→ 従業員の負担が3分の2(15,800円)に満たないため、差額が給与に上乗せされます。
23,700円 - 10,000円 = 13,700円が給与にプラスされます。
ケースC:食事代として16,000円を給料から天引きした場合
- 従業員負担:16,000円(3分の2以上)
→ 従業員が3分の2以上を負担しているため、食事の提供はなかったものとみなされます。
給与に上乗せされる金額は0円となり、社会保険料の計算に影響しません。
このように、従業員と会社の双方にとって最適なバランスをとるために、食事代の一部を給料から天引きするという方法がとられているのです。
所得税のルールは?
ここまで社会保険のルールについて解説してきましたが、実は所得税には非常によく似た、しかし少し異なるルールがあります。
所得税のルールは、社会保険に加入していないパート・アルバイトさんを含め、給与の支払いを受ける全ての従業員に関わります。
所得税の場合、「従業員が食事代の半分以上を負担」しており、かつ「会社の負担額が月額3,500円(税抜)以下」であれば、その食事代は非課税となり、所得税がかかりません。
このように、社会保険と所得税では基準となる金額や割合が異なりますので、給与計算を行う際には両方のルールを正しく理解しておく必要があります。
※税金に関する最終的な判断や詳細なご相談については、顧問税理士などの専門家にご確認いただくことをお勧めします。
【まとめ】適切な労務管理が従業員の安心に繋がります
今回は、「まかないがなぜ有料なのか?」という身近な疑問から、「現物給与」と社会保険の仕組みについて解説しました。
ポイントのまとめ
- 食事や社宅など、お金以外で支給されるものも「現物給与」として扱われる。
- 社会保険では、従業員の負担額が現物給与価額の3分の2以上であれば、給与に含めなくて良い。
- 所得税では、従業員の負担額が食事の価額の半分以上で、かつ会社の負担額が月額3,500円以下であれば、非課税となる。
- 給料から食事代が引かれるのは、これらのルールを活用し、従業員の社会保険料や税金の負担を増やさないようにするための配慮である場合が多い。
現物給与の計算や取り扱いは、少し複雑で分かりにくい部分も多いかと思います。
しかし、これを正しく行わないと、社会保険料の計算ミスに繋がり、後々の調査で追徴されるといったトラブルに発展する可能性もあります。
また、従業員にとっては、将来受け取る年金額にも影響する重要な問題です。
「うちの会社の食事補助のやり方は、これで合っているのかな?」
「これから福利厚生を充実させたいけど、何に注意すればいい?」
など、給与計算や労務管理に関するお悩みや疑問がございましたら、どんな些細なことでもお気軽に社労士事務所ぽけっとにご相談ください。
専門家の視点から、貴社に最適な方法を一緒に考えさせていただきます。
【免責事項】
この記事は、掲載日時点の法令や情報に基づき、一般的な情報提供を目的として作成しております。法改正や個別具体的な事情により、取り扱いが異なる場合がございます。この記事の情報を用いて行う一切の行為について、当事務所は何ら責任を負うものではありませんので、あらかじめご了承ください。最終的な意思決定や具体的な手続きについては、必ず専門家にご相談ください。