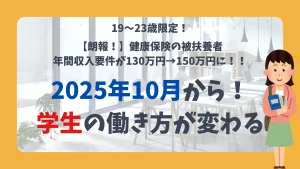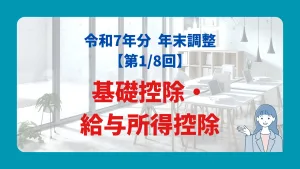男性育休取得率40.5%!知らないと損する制度の仕組みを徹底解説
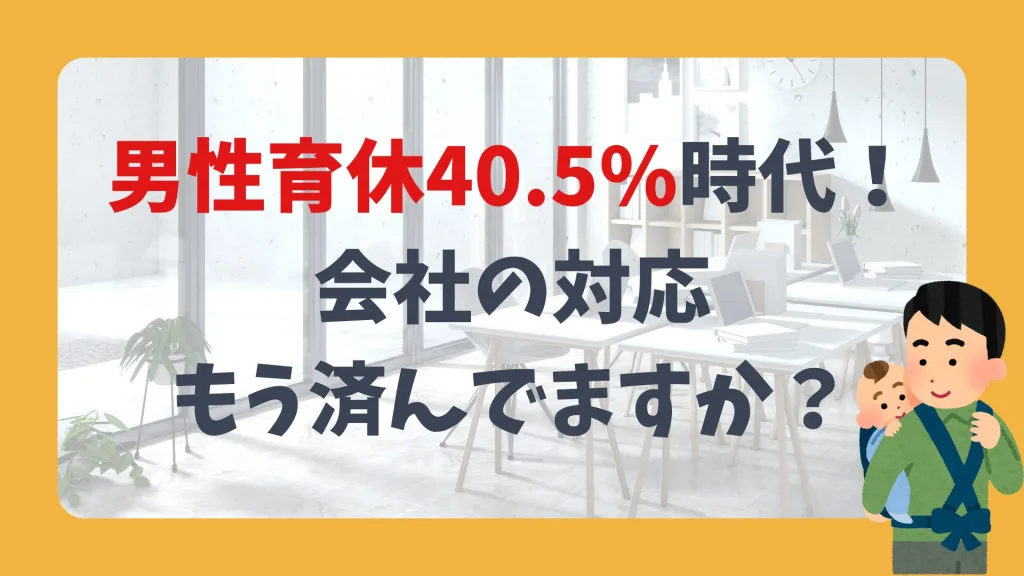
男性育休取得率40.5%!過去最高を記録した今、知っておくべき制度のすべて
先日、厚生労働省から「令和6年度雇用均等基本調査」の結果が公表され、男性の育児休業取得率が過去最高の40.5%に達したことが大きな話題となりました。
これは、前年度の23.7%から大幅に上昇しており、男性の育児参加が社会的に急速に浸透していることを示す象徴的な数字です。
「部下から育休取得の相談をされた」
「制度が複雑で、何をどう説明すれば良いかわからない」
中小企業の経営者や人事担当者の皆様の中には、このような戸惑いを感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
男性の育児休業は、もはや特別なことではありません。
企業の成長戦略として、制度を正しく理解し、積極的に活用していくことが求められています。
この記事では、社会保険労務士の視点から、複雑な男性の育休制度を分かりやすく整理し、企業が取るべき対応や活用できる支援制度まで、網羅的に解説します。
【基本を解説】男性が利用できる育児休業は主に2種類!
男性が取得できる育児休業制度は、大きく分けて2種類あります。
それぞれの特徴をしっかり押さえておきましょう。
① 産後パパ育休(出生時育児休業):生まれてすぐの時期を支える制度
「産後パパ育休」は、子の出生後8週間以内に4週間(28日)まで取得できる、比較的新しい制度です。
母親の産後の心身の負担が大きい時期に、男性が柔軟に休みを取得し、家庭を支えることを目的としています。
分割して2回まで取得できるため、「退院時に1週間、その後落ち着いてから3週間」といった柔軟な使い方が可能です。
② 育児休業:原則1歳まで取得できる従来の制度
こちらは従来からある育児休業制度で、原則として子どもが1歳になるまでの期間で取得できます。
産後パパ育休とは別に取得することができ、こちらも分割して2回まで取得が可能です。
保育園に入所できないなどの特定の理由がある場合は、最長で2歳まで延長することができます。
「産後パパ育休」と「育児休業」は何が違う?分かりやすい比較表
2つの制度の主な違いをまとめました。
| 項目 | 産後パパ育休(出生時育児休業) | 育児休業 |
|---|---|---|
| 対象期間 | 子の出生後8週間以内 | 原則、子が1歳になるまで |
| 取得可能日数 | 通算4週間(28日)まで | 対象期間内で従業員が申し出た期間 |
| 分割取得 | 2回まで可能 | 2回まで可能 |
| 申出期限 | 原則、休業の2週間前まで | 原則、休業の1か月前まで |
| 休業中の就業 | 労使協定があれば可能(上限あり) | 原則不可 |
ポイントは、この2つの制度は併用できるという点です。
例えば、産後パパ育休を出産直後に2週間取得し、その後、数か月経ってから育児休業を1か月取得する、といった組み合わせが可能です。
パパの育休を強力サポート!知って得する給付金と優遇制度
「育休中の収入が心配…」という従業員の不安を解消するため、国は様々な経済的支援策を用意しています。
これらを活用することで、従業員は安心して育児に専念でき、企業も育休を勧めやすくなります。
① 育児休業給付金:育休中の生活を支える収入の柱
雇用保険の被保険者が育児休業を取得した場合、「育児休業給付金」が支給されます。
これは、休業中の生活を支えるための非常に重要な制度です。
支給額は、「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%(育休開始から6か月経過後は50%)」で計算されます。
この給付金は非課税のため、社会保険料の免除と合わせると、実質的な手取り額は休業前の8割程度になるケースが多いです。
② 出生後休業支援給付金(新設):手取り収入を増やすための新しい給付金
2025年4月から「出生後休業支援給付金」という新しい制度が始まります。
これは、産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した男性従業員を対象とした給付金です。
産後パパ育休中に労使協定に基づいて就業した場合、その就業日数に応じて給付金が支給されます。
具体的には、「休業開始時賃金日額 × 休業日数 × 13%」が育児休業給付金に上乗せされるイメージです。
これにより、育休中の手取り収入の減少をさらに緩和し、より育休を取得しやすくすることが期待されています。
③ 社会保険料の免除:申請すれば本人・会社負担分ともに免除に!
育児休業期間中(産後パパ育休含む)は、健康保険・厚生年金保険の保険料が、従業員負担分・会社負担分ともに免除されます。
これは非常に大きなメリットです。
免除を受けるためには、事業主が年金事務所(または健康保険組合)へ「育児休業等取得者申出書」を提出する必要があります。
申請を忘れると免除が受けられないため、従業員から育休の申し出があった際は、必ず手続きを行いましょう。
④ パパ・ママ育休プラス:夫婦で協力すれば、育休期間が1歳2か月まで延長できる
両親がともに育児休業を取得する場合、「パパ・ママ育休プラス」という特例を利用できます。
これにより、育児休業の対象となる子の年齢が原則1歳から1歳2か月に延長されます。
例えば、母親が産後休業に続けて10か月育児休業を取得し、その後父親が2か月取得するといった形で、夫婦で協力して育児期間をカバーできます。
男性の育休取得を促進し、柔軟な育児体制を築くための制度です。
経営者・人事担当者必見!男性育休が会社にもたらす3つのメリット
男性育休は、従業員のためだけではありません。
会社にとっても大きなメリットがあります。
- メリット1:優秀な人材の確保と定着につながる
ワークライフバランスを重視する若い世代にとって、育休の取りやすさは就職先・転職先を選ぶ上で重要な指標です。
男性育休に積極的な企業は「従業員を大切にする会社」として認知され、採用競争において有利になります。 - メリット2:企業のイメージアップと社会的信用の向上
女性活躍推進やSDGsへの関心が高まる中、男性の育休取得推進は企業の社会的責任(CSR)活動の一環として高く評価されます。
企業のブランドイメージ向上や、取引先からの信頼獲得にも繋がります。 - メリット3:多様な働き方を認め、組織全体の活性化へ
従業員が育休を取得することで、業務の属人化が見直され、多能工化や情報共有の仕組みが整備されるきっかけになります。
結果として、組織全体の業務効率化やリスク対応力の強化に繋がります。
導入前に押さえておきたい!企業側の準備と注意点
男性育休をスムーズに導入するためには、事前の準備が不可欠です。
- 育休取得者が出た際の業務の引き継ぎと代替要員の確保
誰が休んでも業務が滞らないよう、日頃から業務マニュアルの整備や情報共有を徹底しておくことが重要です。
短期の育休であれば、部署内のメンバーでカバーし合う体制づくりが求められます。 - 「休みづらい」雰囲気を作らないための職場環境づくり
経営層や管理職が率先して育休取得の重要性を発信し、歓迎する姿勢を示すことが何よりも大切です。
取得事例を社内で共有し、「お互い様」の文化を醸成していきましょう。 - 育休に関する社内規程の整備と周知
育児・介護休業法に沿った社内規程を整備し、従業員に周知徹底することが基本です。
特に、産後パパ育休中の就業など、労使協定が必要な項目については早めに準備を進めましょう。
国も後押し!育休導入で活用できる助成金制度
国は、中小企業が育休制度を導入・運用しやすくなるよう、助成金制度を設けています。
代表的なものが「両立支援等助成金」です。
- 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
男性従業員が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土づくりに取り組み、実際に育休を取得させた場合に支給されます。 - 育児休業等支援コース
育休取得者の業務を代替する従業員への手当支給や、育休からの円滑な職場復帰を支援した場合に支給されます。
これらの助成金を活用することで、企業の金銭的負担を軽減しながら、制度導入を進めることができます。
支給要件が細かく定められているため、活用を検討する際は、ぜひ一度ご相談ください。
これってどうなるの?男性育休に関するQ&A
Q1. 育休の申し出があった場合、会社は拒否できますか?
A1. 原則として、法律で定められた要件を満たす従業員からの育休の申し出を、事業主が拒否することはできません。
申し出を拒否したり、育休取得を理由に解雇や降格などの不利益な取り扱いをしたりすることは、法律で固く禁じられています。
Q2. 有期契約社員やパートタイマーでも育休は取得できますか?
A2. はい、一定の要件を満たせば、有期契約社員やパートタイマーなどの非正規雇用の従業員も育児休業を取得できます。
主な要件は「子が1歳6か月になるまでの間に契約が満了することが明らかでないこと」などです。
雇用形態に関わらず、対象となる従業員には制度をきちんと周知する必要があります。
Q3. 育休中に少しだけ働くことはできますか?
A3. 「産後パパ育休」の期間中であれば、労使協定を締結している場合に限り、従業員の合意のもとで休業中に就業することが可能です。
ただし、就業できる日数や時間には上限があります。
一方、従来の「育児休業」中は、原則として就業することは想定されていません。
臨時・一時的な就労であれば認められる場合もありますが、その際は給付金が減額・停止される可能性があるため注意が必要です。
【まとめ】男性の育児休業を、企業の成長の力に
男性育休取得率40.5%という数字は、一過性のブームではなく、社会の大きな変化の表れです。
これからの企業経営において、男性の育児休業への対応は、避けては通れない重要な課題となります。
制度を正しく理解し、給付金や助成金を賢く活用しながら、従業員が安心して子育てできる環境を整えること。
それが、従業員のエンゲージメントを高め、優秀な人材を惹きつけ、ひいては企業の持続的な成長に繋がっていくはずです。
「自社の場合はどうすれば?」
「規程の作り方がわからない」
など、具体的なお悩みやご不明点がございましたら、いつでもお気軽に社労士事務所ぽけっとにご相談ください。
貴社の状況に合わせた最適なサポートをご提供いたします。
【免責事項】
本記事の内容は、公開日時点の情報に基づき、一般的な情報提供を目的として作成しております。法改正や制度の変更、個別の事情により、取り扱いが異なる場合がございます。具体的なご判断をされる際には、必ず専門家にご相談いただくか、最新の公的情報をご確認いただきますようお願い申し上げます。