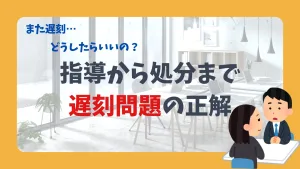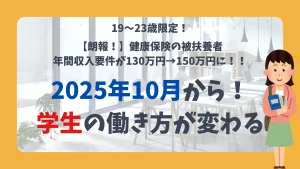【完全ガイド】マイナンバー収集、従業員と扶養親族で確認方法が違うって本当?
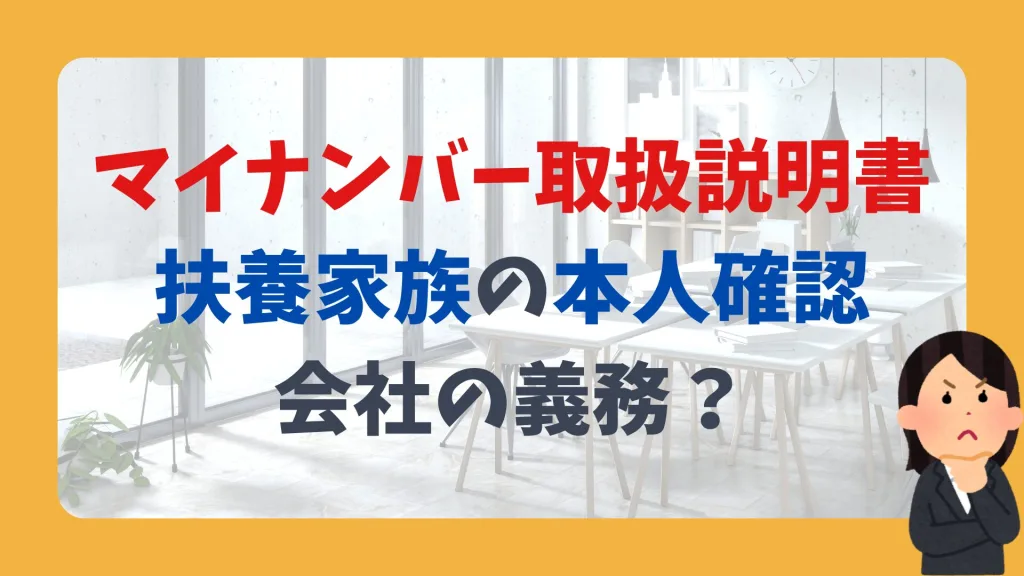
「新しく従業員を雇ったけど、マイナンバーってどうやって集めたらいいんだろう?」
「従業員の扶養家族のマイナンバーも必要って聞いたけど、本人と同じように確認すればいいの?」
こんにちは!社労士事務所ぽけっとです。
企業の労務管理を担当されている方にとって、マイナンバーの取り扱いは、非常に重要でありながら、少し複雑で分かりにくい業務の一つではないでしょうか。
特に、従業員本人だけでなく、そのご家族(扶養親族)のマイナンバーが必要になる場面では、「誰の」「何を」「どうやって」確認すれば良いのか、迷ってしまうことも多いかと思います。
実は、従業員本人のマイナンバーを確認する場合と、その扶養親族のマイナンバーを確認する場合とでは、法律上のルールが異なります。
この違いを知らないまま業務を進めてしまうと、思わぬトラブルに繋がる可能性もゼロではありません。
そこで今回は、給与計算や社会保険手続きの専門家である社労士が、従業員と扶養親族のマイナンバー収集における「確認方法の違い」を、分かりやすく徹底的に解説していきます。
この記事を読めば、自信を持ってマイナンバーの収集業務を行えるようになりますので、ぜひ最後までお付き合いください!
そもそも、なぜ会社はマイナンバーを集める必要があるの?
本題に入る前に、なぜ会社が従業員やその家族のマイナンバーを集めなければならないのか、基本をおさらいしておきましょう。
会社がマイナンバーを必要とするのは、主に以下の2つの手続きのためです。
- 社会保険に関する手続き(健康保険、厚生年金保険、雇用保険など)
- 税に関する手続き(給与の源泉徴収、年末調整、給与支払報告書の作成など)
これらの行政手続きを行う際、提出する書類に従業員や扶養親族のマイナンバーを記載することが、法律(番号法)で義務付けられています。
これは、正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイトといった雇用形態に関わらず、すべての従業員が対象となります。
つまり、会社は法律で定められた義務を果たすために、従業員からマイナンバーを提供してもらう必要がある、というわけです。
マイナンバー確認の基本!「番号確認」と「身元確認」
マイナンバーを収集する際には、ただ番号を聞くだけでなく、厳格な「本人確認」が求められます。
この本人確認は、以下の2つの確認をセットで行うのが原則です。
① 番号確認:提供されたマイナンバーが正しい番号であることを確認すること。
② 身元確認:マイナンバーを提供した人が、その番号の「本当の持ち主」であることを確認すること。
この2つの確認を、どういった書類で行うのかが重要なポイントになります。
最もスムーズなのは、顔写真付きの「マイナンバーカード」です。
これ1枚で、裏面で「番号確認」、表面で「身元確認」が同時に完了するため、非常に便利です。
もし従業員がマイナンバーカードを持っていない場合は、以下の組み合わせで確認します。
- 番号確認書類:通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しなど
- 身元確認書類:運転免許証、パスポートなど顔写真付きの身分証明書
この「番号確認」と「身元確認」が、マイナンバー収集の基本ルールとなります。
これを踏まえた上で、いよいよ本題である「従業員本人」と「扶養親族」の確認方法の違いを見ていきましょう。
【最重要】従業員本人と扶養親族、確認方法の決定的な違い
ここが今回の記事で最もお伝えしたいポイントです。
従業員本人と、その扶養親族とでは、会社(事業者)が行うべき確認の範囲が明確に異なります。
従業員本人のマイナンバー確認方法
従業員本人からマイナンバーの提供を受ける場合、会社(事業者)は、先ほど説明した「①番号確認」と「②身元確認」の両方を行う法的義務があります。
具体的には、以下のいずれかの方法で確認を行います。
- パターンA:マイナンバーカード(これ1枚でOK)
- パターンB:通知カード + 運転免許証などの顔写真付き身分証明書
- パターンC:マイナンバー記載の住民票 + 運転免許証などの顔写真付き身分証明書
これは、会社が「本人から直接」マイナンバーの提供を受けるため、その番号と本人に間違いがないかを、会社自身の責任で確認する必要があるからです。
扶養親族のマイナンバー確認方法
一方、年末調整などで必要となる「扶養親族」のマイナンバーについては、取り扱いが大きく異なります。
結論から言うと、扶養親族のマイナンバーについて、会社(事業者)に「本人確認(番号確認+身元確認)」を行う法律上の義務はありません。
「え、確認しなくていいの?」と驚かれるかもしれませんが、これには明確な理由があります。
法律上、本人確認は「マイナンバーの提供を受ける者」が行うことになっています。
扶養親族の場合、会社は扶養親族から直接マイナンバーを受け取るわけではありません。
従業員本人が、自分の扶養親族からマイナンバーの提供を受け、それを「扶養控除等(異動)申告書」に記入して会社に提出する、という流れになります。
この場合、扶養親族の「本人確認」を行う責任者は、会社ではなく、従業員本人となるのです。
従業員が、いわば「個人番号関係事務実施者」として、自分の家族の番号に間違いがないかを確認する、という立て付けになっています。
そのため、会社は従業員から提出された申告書に記載されている扶養親族のマイナンバーを信頼し、そのまま各種手続きに使用することが認められています。
ただし、会社として、記載された番号が正しいかどうかを確認するために、任意で扶養親族のマイナンバーカードのコピーなどを提出してもらうことは可能です。
しかし、これはあくまで任意の協力であり、法律上の義務ではない、という点をしっかりと区別しておきましょう。
実務担当者が知っておきたいQ&A
最後に、マイナンバー収集の実務でよくある質問にお答えします。
Q1. 従業員がマイナンバーの提出を拒否したら、どうすればいいですか?
A1. まず、税や社会保険の手続きのために必要不可欠であることを丁寧に説明し、利用目的や会社での厳重な管理体制を伝えて、理解と協力を求めましょう。
それでも提出を拒否された場合は、強制することはできません。
その代わり、「提出を依頼したにもかかわらず、本人の意思で提供されなかった」という経緯を記録として残しておくことが非常に重要です。
この記録があれば、会社が安全管理義務を怠ったとは見なされません。
Q2. 収集したマイナンバーが記載された書類は、いつまで保管すればいいですか?
A2. マイナンバーは、法律で定められた行政手続きに必要な期間のみ保管が許されています。
例えば、税務関係の書類は法律で7年間の保存が義務付けられていますので、その期間は保管が必要です。
保管期間を過ぎたマイナンバーは、復元できないようにシュレッダーにかけるなど、速やかに廃棄しなければなりません。
「とりあえず保管しておく」ということは認められないので注意が必要です。
Q3. 収集したマイナンバーはどうやって管理すれば安全ですか?
A3. マイナンバーは重要な特定個人情報ですので、漏えいや紛失がないよう厳重に管理しなければなりません。
紙で管理する場合は、鍵のかかるキャビネットなどで保管し、誰がアクセスできるのかを明確に定めておく必要があります。
しかし、手作業での管理は手間がかかり、人的なミスのリスクも伴います。
そこで、安全かつ効率的に管理するために、マイナンバーに対応した労務管理システムや専用の管理ツールを導入することも非常に有効な手段です。
これらのツールは、誰がいつマイナンバーを閲覧したかというアクセスログ(閲覧履歴)が自動的に記録されたり、データが暗号化されたりと、法律が求める安全管理措置に対応しているものが多く、手作業での記録も不要になり管理の手間を大幅に削減できます。
【まとめ】正しい知識で、信頼される労務管理を
今回は、マイナンバー収集における従業員本人と扶養親族の確認方法の違いについて解説しました。
最後に、重要なポイントをもう一度おさらいしましょう。
- 従業員本人:会社が「番号確認」と「身元確認」の両方を行う義務がある。
- 扶養親族:本人確認の義務は従業員本人にあり、会社にはない。会社は従業員が提出した申告書の番号を信頼して手続きを進める。
この違いを正しく理解し、適切に業務を行うことが、従業員との信頼関係を築き、会社のコンプライアンスを守る上で非常に大切です。
マイナンバーは極めて重要な個人情報だからこそ、丁寧で正確な取り扱いが求められます。
社労士事務所ぽけっとでは、給与計算や社会保険手続きはもちろん、こうした日々の労務管理に関するご相談にも、親身に対応しております。
「これで合っているか不安…」
「もっと効率的な方法はないかな?」
など、どんな些細なことでも、ぜひお気軽に私たち専門家にご相談ください。
【免責事項】
本記事は、掲載日時点の法令や情報に基づき作成しております。法改正等により、今後の取り扱いが変更される可能性があります。また、個別の事案については、必ず専門家にご相談いただくか、管轄の行政機関にご確認くださいますようお願い申し上げます。記事の内容の利用によって生じた一切の損害について、当事務所は責任を負いかねますのでご了承ください。