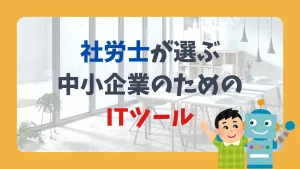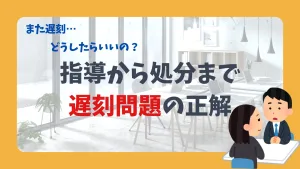給与計算の「勤怠の丸め」その方法、大丈夫ですか?正しい労働時間管理の基本
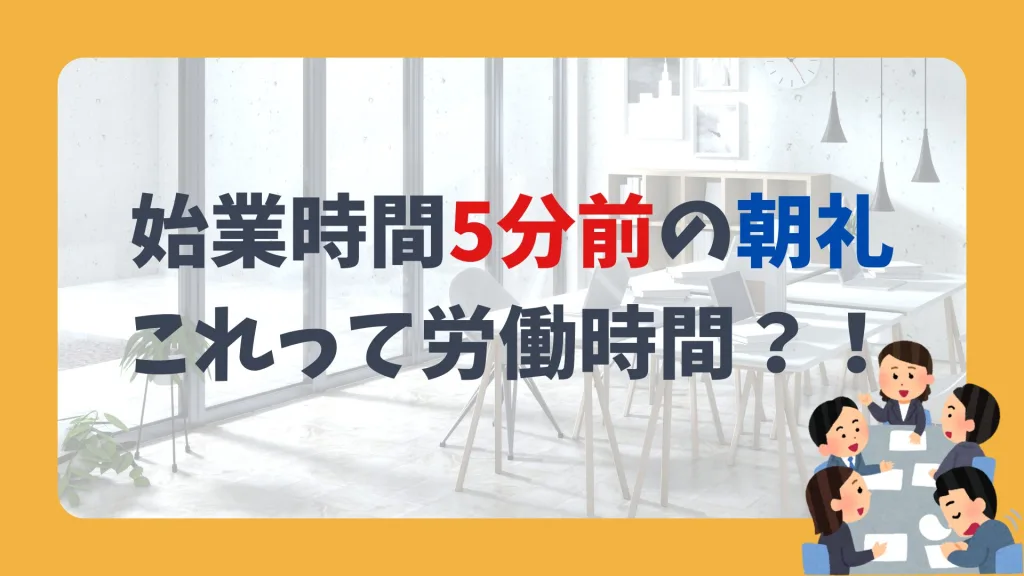
「従業員から『給与明細の残業時間が少し違う気がする』と指摘された…」
「毎日の勤怠を15分単位で丸めているけど、これって法律的に問題ないのだろうか?」
「給与計算をするたびに、勤怠の集計方法がこれで合っているのか、なんとなくモヤモヤする…」
中小企業の経営者様や人事労務ご担当者様の中には、このようなお悩みをお持ちの方が少なくありません。
日々の業務効率化のために行っている「勤怠の丸め(端数処理)」が、知らず知らずのうちに法律違反となり、従業員とのトラブルや未払い賃金の発生といった大きなリスクに繋がる可能性があるからです。
この記事では、給与計算の基礎となる「勤怠の丸め」について、どこまでが許容され、どこからが違法となるのか、具体的な例を交えながら分かりやすく解説します。
自社の勤怠管理は大丈夫か、少しでも不安を感じた方は、ぜひ最後までお読みいただき、正確で公正な給与計算にお役立てください。
大原則:労働時間は「1分単位」での管理が基本
まず、最も重要な大原則からお伝えします。
労働基準法では、労働時間は1分単位で計算し、その分の賃金を支払わなければならないと定められています。
これは「賃金全額払いの原則」に基づくものです。
ここで重要なのが、タイムカードの打刻時間である「出勤時間」と、実際に業務を開始する「始業時間」は必ずしもイコールではないという点です。
労働時間にあたるかどうかは、「会社の指揮命令下に置かれている時間」であるかどうかが判断のポイントになります。
例えば、始業時刻が9時の会社で、8時50分から全従業員参加必須の朝礼やラジオ体操を行っている場合、その10分間は会社の指示によって拘束されているため、明確に労働時間に含まれます。
同様に、会社から義務付けられている制服への着替えや、始業前の清掃なども労働時間と判断される可能性が非常に高いです。
たとえ従業員がタイムカードを始業時刻の9時に打刻していたとしても、8時50分から労働は開始していると見なされ、賃金の支払いが必要になります。
この原則を理解することが、勤怠の丸め問題を考える上での出発点となります。
こんな「丸め」はNG!法律違反となる可能性のある行為
原則として1分単位での管理が必要なため、会社が一方的に労働時間を切り捨てたり、従業員に不利になるような処理を行ったりすることは認められません。
以下に、よく見られる不適切な例を挙げます。
1. 毎日の労働時間の端数を切り捨てる
これは最も多い違反ケースです。
例えば、「15分未満の労働時間は切り捨て」といったルールを設け、9時始業・18時終業の従業員が18時14分まで働いたとしても、18時ちょうどまでの勤務として扱うことはできません。
この場合、14分間の労働に対する賃金が未払いとなってしまいます。
2. 遅刻や早退の時間を実態より多く切り上げる
これも違反となります。
例えば、9時始業の従業員が9時5分に遅刻した場合、その遅刻時間を「15分の遅刻」として処理し、15分分の賃金を控除することはできません。
実際に労働しなかった5分を超えて賃金をカットすることは、労働基準法違反にあたります。
3. 常に労働者に不利になるように丸める
出勤時間は切り上げ(例:8時55分の打刻を9時00分とする)、退勤時間は切り捨て(例:18時14分の打刻を18時00分とする)といった、常に会社側に有利(従業員側に不利)な運用は、従業員の労働時間を正しく反映していないため、認められません。
例外的に認められる「勤怠の丸め」とは?
原則1分単位での管理が基本ですが、事務処理を簡便化する目的で、例外的に以下の方法であれば端数処理が認められています。
重要なのは、これが「1ヶ月単位の集計」に対してのみ適用されるという点です。
労働基準法では、1ヶ月における時間外労働、休日労働、深夜労働の合計時間数に1時間未満の端数が生じた場合に、以下の処理を行うことが通達(昭和63年3月14日基発第150号)で認められています。
- 30分未満の端数を切り捨て
- 30分以上1時間未満の端数を1時間に切り上げる
【具体例】
ある月の時間外労働の合計が「20時間25分」だったとします。
この場合、端数の25分は30分未満なので、切り捨てて「20時間」として残業代を計算することができます。
もし、時間外労働の合計が「20時間40分」だった場合はどうでしょうか。
この場合、端数の40分は30分以上なので、1時間に切り上げて「21時間」として残業代を計算することができます。
この方法は、常に労働者の不利になるわけではなく、有利になる場合もあるため、例外として認められています。
毎日の労働時間に対してこの処理を行うことはできませんので、くれぐれもご注意ください。
よくあるご質問(Q&A)
Q1. 就業規則に規定すれば、毎日の労働時間を15分単位で切り捨てても良いですか?
A1. いいえ、認められません。
たとえ就業規則に「15分未満の労働時間は切り捨てる」と規定し、従業員の同意があったとしても、労働基準法に違反する労働契約は無効となります。
法律が就業規則よりも優先されるため、毎日の労働時間の切り捨ては違法です。
Q2. 遅刻した場合のペナルティとして、減給の制裁を設けることはできますか?
A2. はい、可能です。
ただし、そのためには就業規則に「減給の制裁」に関する規定を設ける必要があります。
また、減給できる金額にも上限が定められており、1回の減給額が平均賃金の1日分の半額を超え、かつ総額が一賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えてはならない、という厳しい制限があります。
単なる「遅刻時間の切り上げ」とは全く異なる手続きが必要となります。
勤怠管理や給与計算でお困りなら、専門家にご相談ください
「自社の勤怠管理、本当にこれで合っているのか不安…」
「法律を守りながら、効率的に給与計算を行う方法が知りたい」
もしあなたがそう感じているのであれば、私たち社労士事務所ぽけっとが全力でサポートいたします。
私たちは、労働に関する法律と人事労務管理の専門家として、貴社の状況を丁寧にヒアリングし、最適な解決策をご提案します。
- 法律に則った適切な勤怠管理体制の構築サポート
- 正確かつ効率的な給与計算のアドバイスおよび代行
- 就業規則の見直しと作成支援
- 労働トラブルを未然に防ぐための労務相談
など、貴社の成長を支えるパートナーとして、あらゆるお悩みを解決に導きます。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
【免責事項】
本記事は、掲載時点の法令や情報に基づき作成しておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。本記事の情報を利用した結果生じた損害について、当事務所は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。具体的な事案については、必ず専門家にご相談ください。