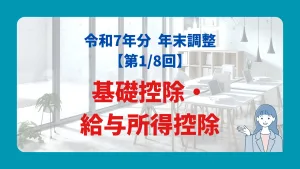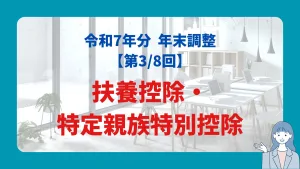【第2/8回】配偶者控除・配偶者特別控除-「103万円の壁」はもう古い!令和7年からの新しい働き方
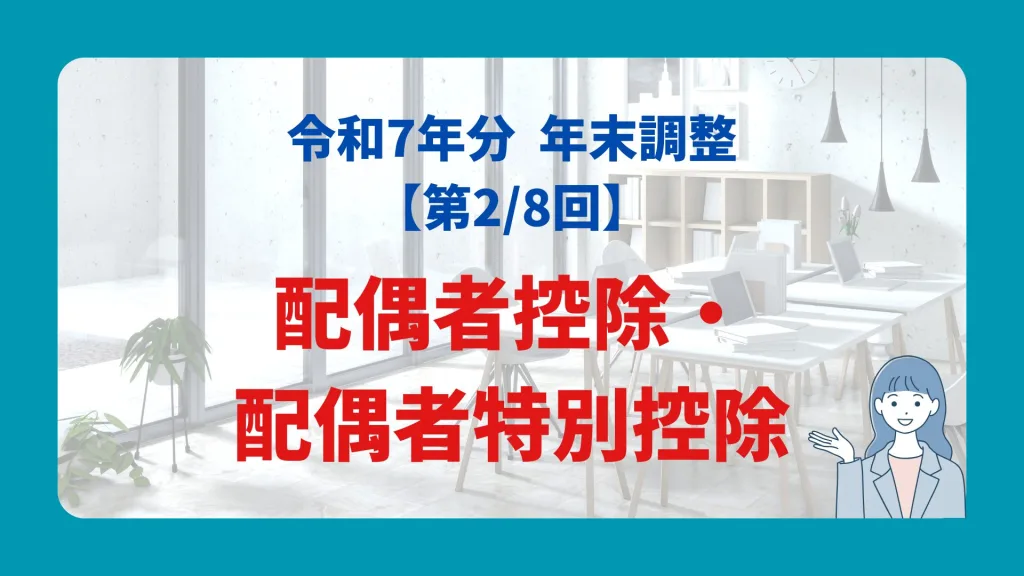
こんにちは!社労士事務所ぽけっとです。
令和7年分年末調整の解説、第2回は多くの方が関心を寄せる「配偶者控除」と「配偶者特別控除」についてです。
第1回で解説した通り、基礎控除等の見直しにより、パートタイマーの方などが意識する「年収の壁」は大きく変わります。
特に、配偶者の扶養内で働いている方にとっては、働き方を左右する重要な改正です。
「103万円の壁」という言葉は、令和7年からは過去のものになります!
【令和7年改正】配偶者控除の所得要件が引き上げ!
今回の改正で最も重要なポイントは、配偶者控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が、48万円以下から58万円以下に10万円引き上げられることです。
【改正内容:配偶者控除の所得要件】
- 改正前:合計所得金額 48万円以下
- 改正後:合計所得金額 58万円以下 (+10万円)
「所得」と「収入」はどう違う?配偶者の所得の計算方法
ここで大切なのが、「年収の壁」を考える上で混同しやすい「収入」と「所得」の違いです。
法律上の要件は、税込みの年収である「給与収入」ではなく、そこから必要経費を差し引いた「合計所得金額」で判断されます。
パート収入のみの方の場合、計算はとてもシンプルです。
合計所得金額 = 給与収入 - 給与所得控除
第1回で解説した通り、令和7年からの給与所得控除は最低でも65万円です。
これを使って、なぜ年収123万円が壁になるのか計算してみましょう。
例:配偶者の給与収入が123万円の場合
123万円(給与収入) - 65万円(給与所得控除) = 58万円(合計所得金額)
このように、合計所得金額が要件である「58万円」にぴったり収まります。
これが、新しい「123万円の壁」の正体なのです。
新しい「123万円の壁」の誕生
上記の計算から、所得税法上の扶養に入れる年収の上限が「123万円」になることがお分かりいただけたかと思います。
これにより、これまで「103万円の壁」と言われていたものが、令和7年からは「123万円の壁」へと変わるのです。
つまり、配偶者の給与収入が123万円までであれば、納税者本人は満額の配偶者控除(38万円)を受けられるようになります。
「160万円の壁」と「123万円の壁」、どうして2つあるの?
ここで、多くの方が混乱するポイントを整理しましょう。
「第1回の記事では『160万円の壁』と説明があったのに、今回は『123万円の壁』なのはなぜ?」と感じるかもしれません。
この2つの壁は、誰の税金を計算するかの視点が違うのです。
① 160万円の壁(本人の所得税の話)
これは、パートで働く方自身に所得税がかかるかどうかのラインです。
第1回で解説した通り、令和7年・8年は特別な基礎控除(95万円)があるため、年収160万円までなら本人に所得税はかかりません。
② 123万円の壁(配偶者控除の話)
これは、納税者(例えば夫)が、パートで働く配偶者を扶養に入れて「配偶者控除」を受けられるかを判断するためのラインです。
法律で、配偶者控除の対象となる配偶者の所得は58万円以下と決まっているため、これを年収に換算すると123万円になります。
つまり、パートで働くA子さんの年収が140万円だった場合、A子さん自身に所得税はかかりませんが(160万円の壁の内側)、夫のBさんはA子さんを対象とした配偶者控除は受けられない(123万円の壁の外側)、ということになります。
この視点の違いが非常に重要です。
【コラム】数字が苦手な方へ!控除額の覚え方(語呂合わせ)
年末調整にはたくさんの数字が出てきて混乱しますよね。
そこで、主要な控除額を覚えるための語呂合わせをご用意しました!
- 給与所得控除(65万円):「給料もらって、老後(ろうご → 65)も安心!」
- 配偶者控除の所得要件(58万円):「配偶者、ごはん(5・8)作って待ってる」
- 基礎控除(通常:58万円):「生活の基礎は、ゴーヤ(5・8)で元気に!」
(配偶者控除の「ごはん」と同じ「58」ですね!セットで覚えましょう) - 基礎控除(特例:95万円):「生活の基礎を、救護(きゅうご → 9-5)します!」
毎月の給与計算と年末調整、それぞれの「配偶者」の役割
年末調整の話をしていると、「源泉控除対象配偶者」や「配偶者控除」など、似たような言葉が出てきて混乱しますよね。
この2つは、使う場面と役割が明確に違います。
① 毎月の給与計算で使う「源泉控除対象配偶者」(仮の姿)
これは、主に毎月の給与から天引きする源泉所得税の額を決めるために使われます。
年の初めに従業員が提出する「扶養控除等申告書」で、配偶者がこの「源泉控除対象配偶者」に該当する場合、毎月の税額計算上の「扶養親族等の数」が1人としてカウントされます。
扶養人数が多いほど毎月の所得税は安くなるため、この申告は非常に重要です。
会社は、この申告(年間の見積り)を基に、毎月の給与から天引きする税額をざっくりと計算します。
② 年末調整で使う「配偶者控除」「配偶者特別控除」(最終的な答え合わせ)
こちらは、年末に行う「最終的な答え合わせ」で使います。
1年間の給与額が確定した時点で、「結局、配偶者の所得は最終的にいくらだったか」を基に、1年間の正しい税額を計算し直します。
この答え合わせの段階で初めて、「配偶者控除」や「配偶者特別控除」のどちらが使えるかが正式に決まり、毎月天引きしてきた税額との差額を精算(還付または追徴)します。
このように、「源泉控除対象配偶者」は毎月の仮計算のための区分、「配偶者控除/特別控除」は年末の本計算のための区分、と覚えておくとスッキリしますね。
【最重要】「税金の壁」と「社会保険の壁」は別です!
第1回でもお伝えしましたが、今回も非常に重要な注意点なので繰り返します。
今回の「123万円の壁」への変更は、あくまで「所得税」の話です。
手取り額に大きく影響する「社会保険の壁(106万円・130万円の壁)」は、今回の税制改正では何も変わっていません。
例えば、従業員51人以上の企業で働く方が、年収120万円で働いたとします。
この場合、新しい制度では「123万円の壁」の内側なので、配偶者は所得税の扶養に入れます。
しかし、「106万円の壁」は超えているため、自分で社会保険に加入し、保険料を支払う必要があります。
その結果、税金上の扶養には入れても、社会保険料の負担で手取りが大きく減ってしまう可能性があります。
働き方を検討する際は、必ずこの2つの壁をセットで考えるようにしましょう。
企業の人事・労務担当者が準備すべきこと
配偶者がいる従業員の方から、今回の改正に関する質問が多く寄せられることが予想されます。
- 正しい情報の提供
「123万円まで大丈夫」という情報だけでなく、「ただし社会保険の壁は別です」という注意喚起をセットで行いましょう。 - 扶養控除等申告書の確認
年末調整時に従業員から提出される「扶養控控除等申告書」の「源泉控除対象配偶者」欄の記載に間違いがないか、より注意深く確認する必要があります。
従業員の家庭状況に深く関わる部分だからこそ、丁寧な情報提供が求められます。
まとめ
今回は、令和7年分年末調整における「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の改正点について解説しました。
- 配偶者控除の所得要件が48万円→58万円にアップ!
- これにより、所得税の扶養に入れる壁は「103万円」から「123万円」に変わる!
- 123万円を超えても「配偶者特別控除」で、控除額は段階的に続く。
- 【最重要】ただし、社会保険の「106万円の壁」は変わらないため、働き方には注意が必要!
「103万円」という数字に捉われず、新しい基準で働き方を考えることが重要です。
次回は、お子様やご両親を扶養している方に関係が深い「扶養控除」について、新設される制度や注意点を詳しく解説します。
どうぞお楽しみに。
次は
【令和7年分 年末調整ブログ 全8回シリーズ】
▶ 第1回:【基礎控除・給与所得控除】すべての給与所得者必見!令和7年税制改正の基本
▶ 第2回:【配偶者控除・配偶者特別控除】「103万円の壁」はもう古い!令和7年からの新しい働き方 ★現在この記事を読んでいます
▶ 第3回:【扶養控除】大学生に新制度!令和7年改正の重要ポイント
▶ 第4回:【生命保険料控除・地震保険料控除】改正はなくても節税効果大!申告書の書き方ガイド
▶ 第5回:【社会保険料控除と小規模企業共済等掛金控除】iDeCoや国民年金も全額控除!
▶ 第6回:【住宅ローン控除】2年目以降の手続きと令和7年改正後の注意点
【免責事項】
本記事は、2025年8月時点の法令等に基づき作成されております。今後の法改正等により、内容が変更となる可能性があります。また、個別の税務相談等には応じかねますので、ご了承ください。正確な情報提供を心がけておりますが、本記事の内容に基づくいかなる行為についても、当事務所は一切の責任を負いかねます。