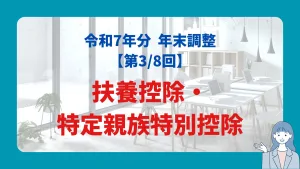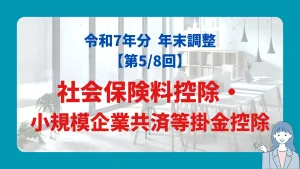【第4/8回】生命保険料控除・地震保険料控除-改正はなくても節税効果大!申告書の書き方ガイド
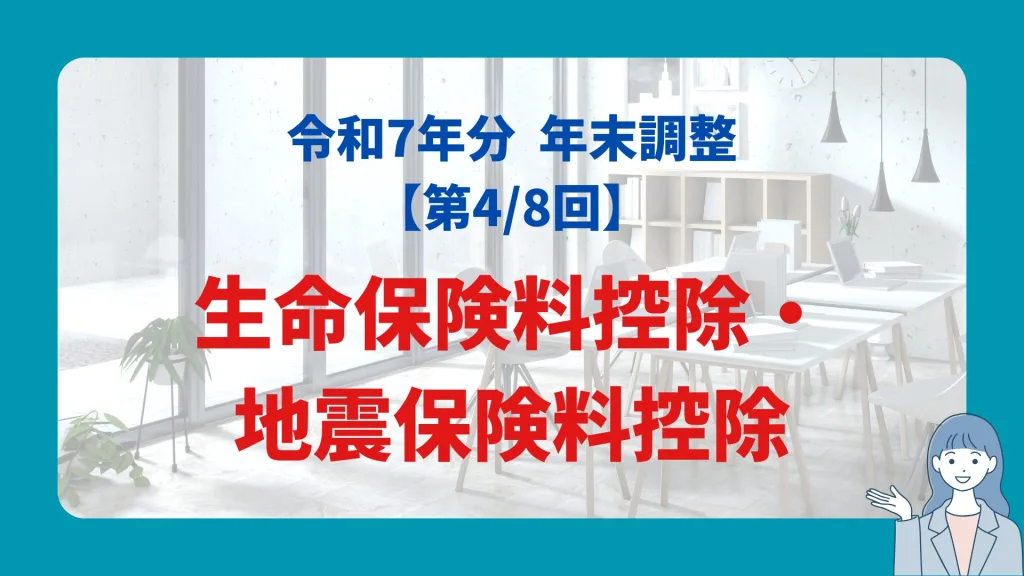
こんにちは!社労士事務所ぽけっとです。
令和7年分年末調整の解説、第4回は、多くの方が対象となる「生命保険料控除」と「地震保険料控除」です。
これまでの回で解説してきたような大きな税制改正は、この2つの控除にはありません。
しかし、節税効果が非常に高く、申告しないと大きな損をしてしまう重要な控除です。
今回は、基本に立ち返り、「控除証明書」の見方や申告書の正しい書き方について、しっかりおさらいしていきましょう。
生命保険料控除とは?3つの区分を理解しよう
生命保険料控除とは、1年間に支払った生命保険料や医療保険料、個人年金保険料のうち、一定の金額を所得から差し引くことができる制度です。
これにより、所得税や住民税の負担を軽くすることができます。
この控除は、保険の種類によって以下の3つの区分に分かれています。
- 一般生命保険料控除:死亡保険や学資保険など、生存または死亡によって保険金が支払われる保険が対象です。
- 介護医療保険料控除:医療保険やがん保険、介護保険など、入院や通院、介護状態によって給付金が支払われる保険が対象です。
- 個人年金保険料控除:税制適格特約が付いた個人年金保険が対象です。
それぞれ最大4万円、3つ合わせて最大で12万円の所得控除が受けられます。(※平成24年1月1日以降に契約した新制度の場合)
地震保険料控除とは?
地震保険料控除は、その年に支払った地震保険の保険料が対象となる控除です。
こちらはシンプルで、支払った保険料に応じて、最大で5万円の所得控除が受けられます。
ここで注意したいのが、火災保険料だけでは控除の対象にならないという点です。
控除の対象となるのは、あくまで火災保険契約に付帯して契約した「地震保険」の部分の保険料となります。
【豆知識】古い火災保険も対象になる?「旧長期損害保険料」とは
「火災保険は対象外」と聞くと、がっかりする方もいるかもしれません。
しかし、平成18年(2006年)12月31日までに契約した、一定の条件を満たす長期の積立型火災保険などは、「旧長期損害保険料」として、今でも控除の対象になる場合があります。
これは、現在の地震保険料控除ができる前の制度の名残で、経過措置として残されているものです。
以下の条件を満たす契約がないか、古い保険証券を確認してみましょう。
- 平成18年12月31日までに契約
- 保険期間が10年以上
- 満期返戻金などがある積立型の保険
もし該当すれば、最大で15,000円の所得控除が受けられます。
控除証明書に「旧長期」といった記載がないか、ぜひチェックしてみてください。
控除証明書の見方と申告書の書き方
10月頃になると、保険会社から「生命保険料控除証明書」や「地震保険料控除証明書」といったハガキや封書が届きます。
これが、年末調整で控除を受けるために必要な、非常に大切な書類です。
ステップ1:控除証明書の内容を確認する
証明書には、保険の種類(一般用、介護医療用など)や、その年に支払った保険料(申告額)が記載されています。
申告書を書く前に、どの保険がどの区分に該当するのか、申告額はいくらかをしっかり確認しましょう。
ステップ2:保険料控除申告書に転記する
会社から配布される「給与所得者の保険料控除申告書」に、証明書の内容を書き写していきます。
- 保険会社名、保険の種類、保険期間、契約者名などを記入します。
- 証明書に記載されている「申告額」を転記します。
- それぞれの区分ごとに合計額を計算し、所定の計算式に当てはめて控除額を算出します。
書き方に迷ったら、保険会社が同封している申告書の記入例などを参考にするのがおすすめです。
ステップ3:証明書を添付して提出
申告書への記入が終わったら、証明書を添付して会社に提出します。
提出方法は、会社の年末調整のやり方によって異なります。
- 紙で提出する場合
申告書に、保険会社から送られてきた「控除証明書」の原本を添付します。 - 電子(データ)で提出する場合
多くの場合は、控除証明書のデータをアップロードしたり、証明書に記載された情報を入力したりします。
この場合、証明書の原本は、後日会社が内容の確認のために回収するのが一般的です。
そのため、申告が終わった後も大切に保管し、会社の指示に従って提出してください。
最近は、保険会社からハガキではなく電子データ(XMLファイルなど)で証明書が送られてくるケースも増えています。
このデータは、年末調整システムに直接読み込ませることができるため非常に便利です。
どちらの形式で受け取った場合でも、証明書は大切に保管してください。
企業の人事・労務担当者の方へ
保険料控除は、ほとんどの従業員が対象となる手続きです。
年末調整の書類を配布する際に、以下の点をアナウンスすると、回収やチェックがスムーズになります。
- 「10月頃に保険会社から届く『控除証明書』をなくさずに保管してください」と早めに周知する。
- 紙と電子、どちらで年末調整を行うか、また証明書の提出方法(電子申告の場合は原本を後日回収するなど)を明確にアナウンスする。
- 記入漏れや計算ミスがないか、チェックリストなどを用意してあげる。
まとめ
今回は、年末調整の基本である「生命保険料控除」と「地震保険料控除」について解説しました。
- 令和7年の年末調整で、この2つの控除に大きな制度改正はない。
- 生命保険料控除は「一般」「介護医療」「個人年金」の3区分で最大12万円の控除。
- 地震保険料控除は最大5万円の控除。火災保険料は対象外。
- 申告には、保険会社から送られてくる「控除証明書」が必須!提出方法は会社のルールを確認!
自動的に適用される控除ではないため、自分で申告しなければ節税の恩恵は受けられません。
忘れずに手続きを行いましょう。
次回は、iDeCo(イデコ)やご自身で支払った国民年金保険料などが対象となる「社会保険料控除と小規模企業共済等掛金控除」について解説します。
これも節税効果が非常に高い控除ですので、ぜひご覧ください。
【令和7年分 年末調整ブログ 全8回シリーズ】
▶ 第1回:【基礎控除・給与所得控除】すべての給与所得者必見!令和7年税制改正の基本
▶ 第2回:【配偶者控除・配偶者特別控除】「103万円の壁」はもう古い!令和7年からの新しい働き方
▶ 第3回:【扶養控除】大学生に新制度!令和7年改正の重要ポイント
▶ 第4回:【生命保険料控除・地震保険料控除】改正はなくても節税効果大!申告書の書き方ガイド ★現在この記事を読んでいます
▶ 第5回:【社会保険料控除と小規模企業共済等掛金控除】iDeCoや国民年金も全額控除!
▶ 第6回:【住宅ローン控除】2年目以降の手続きと令和7年改正後の注意点
【免責事項】
本記事は、2025年8月時点の法令等に基づき作成されております。今後の法改正等により、内容が変更となる可能性があります。また、個別の税務相談等には応じかねますので、ご了承ください。正確な情報提供を心がけておりますが、本記事の内容に基づくいかなる行為についても、当事務所は一切の責任を負いかねます。