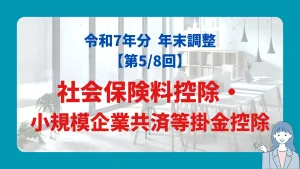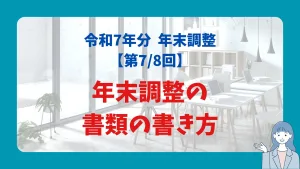【第6/8回】住宅ローン控除-2年目以降の手続きと令和7年改正後の注意点
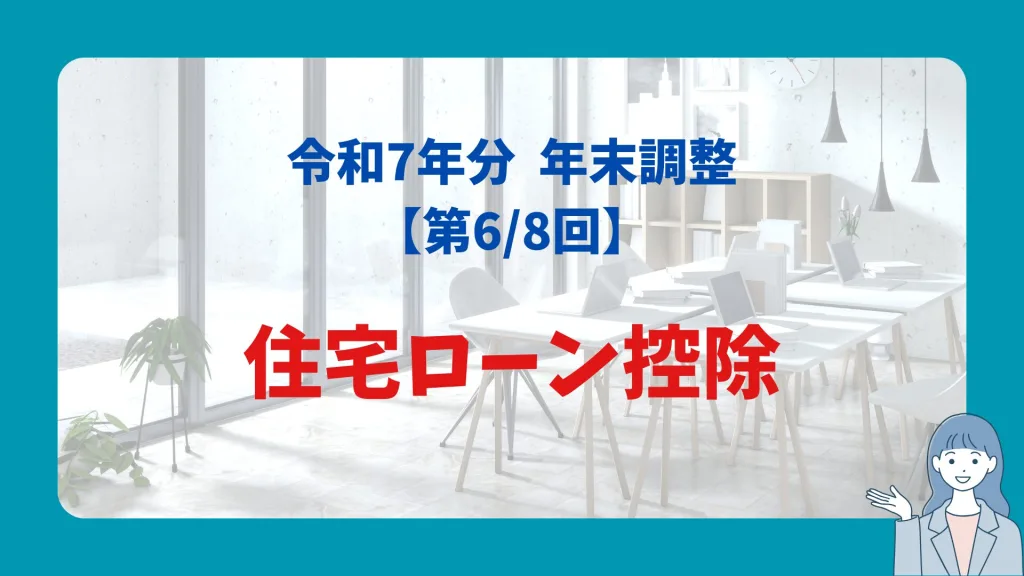
こんにちは!社労士事務所ぽけっとです。
令和7年分年末調整の解説、第6回は、マイホームをお持ちの方にとって最大の節税策である「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」です。
控除額が大きく、十数年にわたって続くこの制度。
特に、住宅を購入して2年目以降の方は、年末調整で手続きが完結するため、正しい知識が不可欠です。
今回は、2年目以降の手続き方法と、令和7年の税制改正が間接的に与える影響について解説します。
住宅ローン控除とは?
住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用してマイホームを購入・新築・増改築した場合に、年末時点のローン残高の一定割合(通常0.7%)が、所得税から直接差し引かれる(税額控除)という非常に強力な制度です。
原則として10年または13年間にわたって控除が受けられます。
所得から一定額を引く「所得控除」と違い、計算された税額から直接引く「税額控除」なので、節税効果が非常に高いのが特徴です。
家の性能で控除額が変わる!住宅の種類と借入限度額
「住宅ローン控除」と一言で言っても、実は購入した住宅の環境性能や入居した年によって、控除の対象となるローン残高の上限額(借入限度額)が変わります。
省エネ性能が高い住宅ほど、より多くの控除が受けられる仕組みになっています。
申告書の正式名称が「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」となっているように、省エネ性能が高い「特定の住宅」や、特別な改修工事などが優遇されるのです。
ご自身の住宅がどれに当てはまるか、以下の表で確認してみましょう。(※新築住宅の場合)
| 住宅の種類 | 令和6・7年(2024・2025年) 入居の場合の借入限度額 |
|---|---|
| 認定住宅 (長期優良住宅・低炭素住宅) | 4,500万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 |
| その他の住宅 | 0円 (※原則として控除対象外) |
※「その他の住宅」でも、令和5年末までに建築確認を受けている場合は2,000万円が限度額となる特例があります。
ご自身の住宅がどの種類に該当するかは、通常、住宅の売買契約書や建築の請負契約書などに記載されています。不明な場合は、住宅の販売会社や工務店に確認してみましょう。
2年目以降は年末調整で手続きを!
住宅ローン控除を受けるためには、1年目だけは必ずご自身で確定申告を行う必要があります。
しかし、2年目以降は、会社員の方であれば年末調整で手続きを済ませることができます。
毎年税務署に行く必要がないので、とても便利ですね。
その手続きに必要な書類は、主に以下の2つです。
- 「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」
1年目の確定申告をすると、税務署から残りの控除期間分の申告書がまとめて送られてきます。(通常9年分または12年分が1つの冊子になっています)
毎年1枚ずつ使いますので、絶対に紛失しないようにしましょう。 - 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
住宅ローンを組んでいる金融機関から、毎年10月頃に送られてくる書類です。
その年の年末時点でのローン残高がいくらになるかの見込み額が記載されています。
申告書の書き方のポイント
手続きは、この2つの書類の内容を転記していくのが基本です。
- 税務署から送られてきた「住宅借入金等特別控除申告書」の中から、該当する年分の用紙を1枚切り離します。
- 金融機関から届いた「年末残高等証明書」に記載されている年末残高を、申告書に書き写します。
- 年末残高に、申告書にあらかじめ印字されている控除率を掛けて、その年の控除額を計算します。
(控除率は通常0.7%ですが、入居した年などによって異なる場合があります) - 必要事項をすべて記入したら、「年末残高等証明書」を添付して会社に提出します。
【注意】令和7年改正が住宅ローン控除に与える間接的な影響
今回の税制改正で、住宅ローン控除の制度自体に直接の変更はありません。
しかし、これまでの回で解説してきた「基礎控除」などの所得控除額が増えることで、間接的に影響が出る可能性があります。
どういうことかと言うと、住宅ローン控除は、自分が納めるべき所得税の額が上限となるからです。
【例】
- 住宅ローン控除で戻ってくる計算上の金額:15万円
- 自分が納めるべき年間の所得税額:12万円
この場合、戻ってくるのは、自分が納める税額である12万円が上限となります。15万円全額が戻ってくるわけではありません。
令和7年からは、多くの人で基礎控除などの額が増え、その結果として納めるべき所得税額そのものが減る可能性があります。
そのため、これまで控除額を全額使い切れていた人でも、改正後は所得税額が控除額を下回り、結果的に還付される金額が減るというケースが考えられるのです。
(※所得税から引ききれなかった分は、一部住民税から控除される仕組みもあります)
まとめ
今回は、住宅ローン控除の2年目以降の手続きについて解説しました。
- 1年目は確定申告が必須!2年目以降は年末調整でOK。
- 必要な書類は税務署から届く「申告書」と金融機関から届く「残高証明書」の2つ。
- 控除額の上限は、家の性能や入居年によって異なる!
- 令和7年改正で他の控除が増え、結果的に住宅ローン控除で戻る額に影響が出る可能性も。
非常に節税効果の高い制度だからこそ、仕組みを正しく理解し、毎年忘れずに手続きを行いましょう。
次回は、いよいよ佳境です。
これまでの改正点を踏まえ、令和7年版の新しい年末調整の書類の書き方について、具体的に解説していきます。
また、近年普及が進む年末調整ツールを使った申告方法についても触れていきますので、どうぞお楽しみに。
次は
【令和7年分 年末調整ブログ 全8回シリーズ】
▶ 第1回:【基礎控除・給与所得控除】すべての給与所得者必見!令和7年税制改正の基本
▶ 第2回:【配偶者控除・配偶者特別控除】「103万円の壁」はもう古い!令和7年からの新しい働き方
▶ 第3回:【扶養控除】大学生に新制度!令和7年改正の重要ポイント
▶ 第4回:【生命保険料控除・地震保険料控除】改正はなくても節税効果大!申告書の書き方ガイド
▶ 第5回:【社会保険料控除と小規模企業共済等掛金控除】iDeCoや国民年金も全額控除!
▶ 第6回:【住宅ローン控除】2年目以降の手続きと令和7年改正後の注意点 ★現在この記事を読んでいます
【免責事項】
本記事は、2025年8月時点の法令等に基づき作成されております。今後の法改正等により、内容が変更となる可能性があります。また、個別の税務相談等には応じかねますので、ご了承ください。正確な情報提供を心がけておりますが、本記事の内容に基づくいかなる行為についても、当事務所は一切の責任を負いかねます。