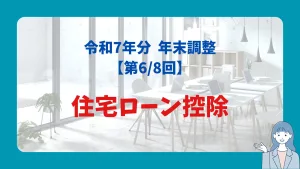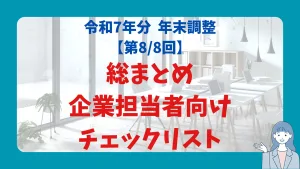【第7/8回】書類の書き方編-令和7年改正対応!新しい年末調整申告書の記入例
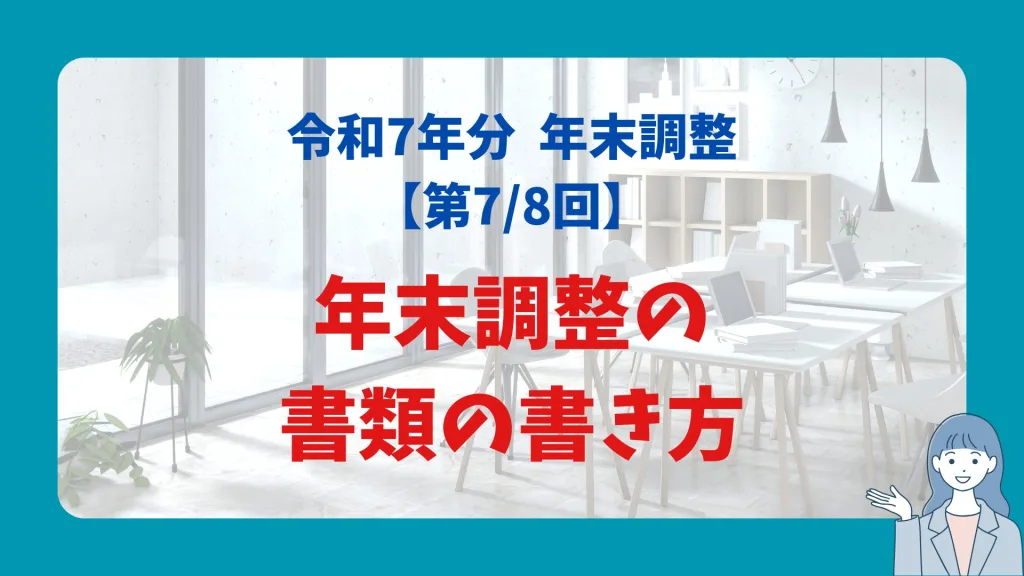
こんにちは!社労士事務所ぽけっとです。
令和7年分年末調整の解説、いよいよ佳境の第7回です。
今回は、これまでの改正点をすべて踏まえ、実際に私たちが記入・提出する年末調整の書類に焦点を当てます。
特に、令和7年から新しくなる申告書や、近年普及が進む年末調整ツールについて、具体的に見ていきましょう。
令和7年の年末調整、主に変わる申告書はコレ!
これまでの連載で解説してきた税制改正に伴い、私たちが年末調整で使う申告書にも変更があります。
特に大きな変更点は、おなじみの、あの長い名前の申告書です。
正式名称「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」が、さらに長くなります。
新しい名称は「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」となる予定です。
つまり、新設される「特定親族特別控除」の申告欄が、独立した書類ではなく、この既存の申告書に統合される形になります。
① 基礎控除申告書の書き方:「所得の見積額」がカギ!
正式には「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という長い名前の書類です。
令和7年からの大きな変更点は、第1回で解説した通り、基礎控除額が所得に応じて段階的に変わることです。
そのため、申告書ではまずご自身の「給与所得」の金額を計算し、どの控除額区分に当てはまるかを正しく判断する必要があります。
- 「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」の計算
申告書に記載の表などを使って、ご自身の年収(見積額)から給与所得控除を差し引き、所得金額を計算します。 - 「控除額の計算」の判定
算出した所得金額がどの区分に当てはまるかを確認し、対応する基礎控除の額(95万円、88万円、58万円など)を記入します。
特に令和7年・8年は特例措置で区分が細かくなっているため、落ち着いてご自身の所得を見積もり、正しい控除額を転記することが重要です。
② 新しく追加される「特定親族特別控除」欄の書き方
第3回で解説した、19歳~22歳のお子様がいる方向けの新制度です。
お子様のアルバイト収入が年収123万円を超える場合に、この申告書を提出します。
記入する主な項目は以下の通りです。
- 対象となる特定親族の情報
お子様の氏名、マイナンバー、生年月日、あなたとの続柄など。 - 特定親族の本年中の合計所得金額の見積額
お子様のアルバイト収入などから、所得金額を計算して記入します。
この欄に正しく記入することで、お子様の所得額に応じた控除が受けられます。対象となるお子様がいる方は、申告書を受け取ったらこの新しい欄を忘れずにチェックしましょう。
もう迷わない!年末調整ツールの活用
「毎年、紙の申告書とにらめっこするのは大変…」と感じる方も多いのではないでしょうか。
近年、そうした悩みを解決するために、多くの企業で年末調整ツール(システム)の導入が進んでいます。
年末調整ツールとは、スマートフォンやパソコン上で年末調整の申告が完結するサービスです。
従業員のメリット
- 質問に答えるだけ
「配偶者はいますか?」「生命保険に加入していますか?」といった質問に答えていくだけで、自動的に申告内容が作成されます。
どの書類に何を書くか、自分で判断する必要がありません。 - 計算が不要
控除額の計算などはすべてシステムが自動で行ってくれるため、計算ミスがありません。 - 証明書の提出が楽
生命保険料控除証明書などをスマホのカメラで撮影してアップロードしたり、保険会社から送られてくる電子データ(XMLファイル)をそのまま提出したりできます。
もし、あなたの会社が年末調整ツールを導入しているなら、ぜひ活用しましょう。
紙の申告書よりもずっと簡単かつ正確に、手続きを終えることができます。
まとめ
今回は、令和7年版の新しい年末調整の書類と、便利な年末調整ツールについて解説しました。
- 「基礎控除申告書」は、所得の見積額を正しく計算して、自分の控除額を判定するのがポイント。
- 大学生の子がいる方向けに「特定親族特別控除申告書」が新設される!
- 年末調整ツールを使えば、質問に答えるだけで申告が完了し、非常に便利。
紙での申告でも、ツールを使った電子申告でも、これまでの連載で解説してきた知識が必ず役に立ちます。
落ち着いて、ご自身の状況に合った申告を行いましょう。
次回はいよいよ最終回。これまでの内容を総括し、企業の人事・労務担当者様向けの最終チェックリストをお届けします。どうぞお楽しみに。
次は
【令和7年分 年末調整ブログ 全8回シリーズ】
▶ 第1回:【基礎控除・給与所得控除】すべての給与所得者必見!令和7年税制改正の基本
▶ 第2回:【配偶者控除・配偶者特別控除】「103万円の壁」はもう古い!令和7年からの新しい働き方
▶ 第3回:【扶養控除】大学生に新制度!令和7年改正の重要ポイント
▶ 第4回:【生命保険料控除・地震保険料控除】改正はなくても節税効果大!申告書の書き方ガイド
▶ 第5回:【社会保険料控除と小規模企業共済等掛金控除】iDeCoや国民年金も全額控除!
▶ 第6回:【住宅ローン控除】2年目以降の手続きと令和7年改正後の注意点
▶ 第7回:【書類の書き方編】令和7年改正対応!新しい年末調整申告書の記入例 ★現在この記事を読んでいます
【免責事項】
本記事は、2025年8月時点の法令等に基づき作成されております。今後の法改正等により、内容が変更となる可能性があります。また、個別の税務相談等には応じかねますので、ご了承ください。正確な情報提供を心がけておりますが、本記事の内容に基づくいかなる行為についても、当事務所は一切の責任を負いかねます。