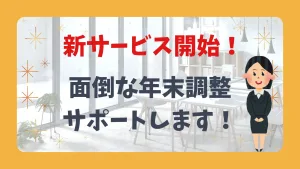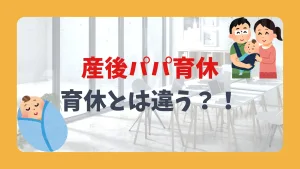給与の日割り計算、どうしてる?迷わないための基礎知識と計算方法
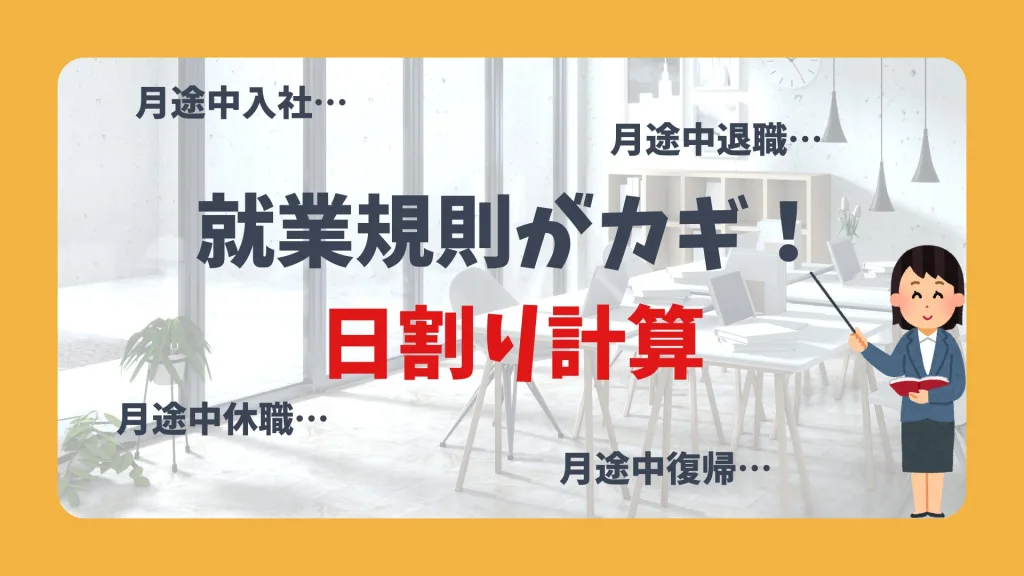
「月の途中で入社した社員の給料って、どう計算すればいいの?」 「急に社員が辞めることになったけど、最後の給料は日割り?」 「欠勤が多い社員がいるんだけど、給与計算はどうなる?」
会社を経営していると、従業員の給与計算で「日割り計算」が必要になる場面が必ず出てきますよね。特に、毎月のルーティンから外れる計算は、ちょっと面倒に感じたり、どう計算するのが正しいのか迷ったりすることもあるのではないでしょうか。
この記事では、そんな事業主の皆さまの疑問やお悩みを解決すべく、給与の日割り計算について、基本から分かりやすく解説していきます。複雑そうに見える日割り計算も、ポイントを押さえれば大丈夫。自信を持って給与計算に取り組めるようになりますよ!
なぜ日割り計算が必要なの?どんな時に発生する?
そもそも、なぜ給与の日割り計算が必要になるのでしょうか?
多くの会社では、給与は「月給制」を採用しています。これは、基本的に1ヶ月間働いた対価として、毎月決まった額の給与を支払う制度です。
しかし、従業員が月の途中で入社したり、退職したりすると、その月の勤務日数は1ヶ月まるまるにはなりません。また、病気や私用で欠勤したり、育児休業や介護休業などで長期間休んだりする場合も、実際に働いていない期間が発生します。
このような場合、まるまる1ヶ月分の給与を支払うのではなく、実際に勤務した日数や在籍した日数に応じて給与額を調整する必要があります。これが「給与の日割り計算」です。
具体的には、以下のようなケースで日割り計算が発生します。
- 中途入社: 月の途中から新しく従業員を雇用した場合
- 中途退職: 月の途中で従業員が退職した場合
- 欠勤: 従業員が自己都合や病気などで会社を休んだ場合(欠勤控除)
- 休職: 従業員が育児休業、介護休業、私傷病などで長期間休む場合(休職期間中の給与支払いは会社の規定による)
これらのケースで適切に日割り計算を行わないと、給与の過払いや未払いが発生し、後々トラブルの原因になることも。従業員との信頼関係を保つためにも、正しい知識を身につけておくことが大切です。
ややこしい?日割り計算の主な方法をチェック!
日割り計算と一口に言っても、実はいくつかの計算方法があります。法律で「この方法で計算しなさい」と厳密に定められているわけではないため、どの方法を採用するかは基本的に会社の判断に委ねられています。
ただし、どの方法を採用するにしても、就業規則などで計算方法を明確に定めておくことが非常に重要です。(これについては後ほど詳しく説明しますね!)
ここでは、代表的な3つの計算方法を見ていきましょう。
計算方法1:その月の「暦日数」で割る方法
これは、比較的シンプルな計算方法です。
計算式: 月給額 ÷ その月の日数 × 在籍日数(または勤務日数)
- その月の日数: 30日や31日(2月なら28日か29日)といった、カレンダー上の日数です。
- 在籍日数: 中途入社・退職の場合に使います。
- 勤務日数: 欠勤控除の場合に使うこともあります。(この場合は
月給額 - (月給額 ÷ その月の日数 × 欠勤日数)のように控除額を計算します)
メリット
- 計算が比較的簡単。
- 月の大小(30日か31日か)が反映される。
デメリット
- 土日祝日など、会社の休日も含めて計算するため、実際の労働日ベースで見ると不公平感が出る可能性がある。(例:休日が多い月に途中入社すると、労働日が少なくても給与が高めになる)
計算方法2:その月の「所定労働日数」で割る方法
こちらは、より実態に近い計算方法と言えます。
計算式: 月給額 ÷ その月の所定労働日数 × 実際の勤務日数
- その月の所定労働日数: 会社が定めた、その月に働くべき日数(年間カレンダーなどで決まっていることが多い)。
- 実際の勤務日数: 実際に出勤した日数。
メリット
- 実際に働いた日数に基づいて計算されるため、公平感がある。
- 欠勤控除の計算にも分かりやすい。
デメリット
- 月ごとに所定労働日数が変動するため、毎月計算が必要。
- 年間の労働日カレンダーなどを整備しておく必要がある。
計算方法3:「月平均の所定労働日数」で割る方法
毎月の所定労働日数を計算するのが大変…という場合に用いられることがある方法です。
計算式: 月給額 ÷ 月平均所定労働日数 × 実際の勤務日数
- 月平均所定労働日数: 年間の所定労働日数を12ヶ月で割った、平均の日数。就業規則などで固定の数値を定めておくのが一般的です。(例:21.5日など)
メリット
- 割る数が毎月固定されるため、計算の手間が少し省ける。
デメリット
- 実際のその月の所定労働日数とはズレが生じるため、場合によっては不公平感が出る可能性もある。
- 月平均所定労働日数をどう設定するか、根拠を明確にしておく必要がある。
どの計算方法を選ぶ? 就業規則の重要性
さて、3つの主な計算方法を見てきましたが、「結局どれを選べばいいの?」と思いますよね。
先述の通り、法律で特定の計算方法が義務付けられているわけではありません。どの方法を採用するかは、会社の状況や考え方によって決めることができます。
ただし、最も重要なのは「どの計算方法を採用するかを就業規則に明確に記載しておくこと」です。
なぜなら、就業規則に記載することで、
- 計算根拠が明確になり、従業員への説明責任を果たせる
- 従業員ごとに計算方法がバラバラになるのを防ぎ、公平性を保てる
- 労務トラブルを未然に防ぐことができる
からです。
就業規則には、「中途入社・退職者の給与は、〇〇の方法により日割り計算する」「欠勤した場合は、〇〇の方法により算出した額を控除する」といった形で、具体的な計算方法を記載しましょう。
もし、まだ就業規則に日割り計算の規定がない場合や、規定が曖昧な場合は、この機会に見直しを検討することをおすすめします。社会保険労務士などの専門家に相談するのも良いでしょう。
ここも注意!日割り計算のポイント
最後に、日割り計算を行う上で注意しておきたい点をいくつかご紹介します。
1. 端数処理はどうする?
日割り計算をすると、1円未満の端数が出ることがよくあります。この端数を切り捨てるのか、切り上げるのか、四捨五入するのかも、あらかじめルールを決めておく必要があります。これも就業規則に明記しておくと、より丁寧です。一般的には、従業員に不利にならないよう「円未満切り上げ」とするケースが多いですが、「四捨五入」なども可能です。一貫したルールで運用しましょう。
2. 社会保険料は日割りされる?
これは非常によくある誤解なのですが、健康保険料や厚生年金保険料といった社会保険料は、原則として日割り計算されません。
- 入社: 月の途中で入社した場合でも、その月の1ヶ月分の保険料が発生します(会社負担分・本人負担分ともに)。
- 退職: 月の途中で退職した場合、その月の保険料は原則かかりません。ただし、「月末」に退職した場合は、その月分の保険料が発生します。また、同月内に転職し、新しい会社で社会保険に加入した場合など、例外的なケースもあります。
雇用保険料については、その月に支払われる給与総額に応じて計算されるため、結果的に日割り計算された給与額に基づいて計算されることになります。
社会保険料の扱いは複雑な場合もあるため、不明な点があれば年金事務所や専門家にご確認ください。
3. 通勤手当や諸手当の扱いは?
通勤手当や役職手当、資格手当などの諸手当を日割り計算に含めるかどうかも、会社の規定によります。
- 通勤手当: 定期代で支給している場合は、日割りになじまないことが多いですが、出勤日数に応じて実費支給している場合は、日割り計算(実費計算)となります。
- 役職手当など: その性質(労働日数に関係なく固定で支払うものか、日々の業務に関連するものか)によって判断が分かれます。
これらの手当の扱いについても、就業規則で明確にしておくことが望ましいです。
まとめ:ルールを決めて、迷わない給与計算を!
今回は、給与の日割り計算について解説しました。ポイントをまとめると…
- 日割り計算は、中途入社・退職、欠勤などの際に必要
- 計算方法には主に「暦日数基準」「所定労働日数基準」「月平均所定労働日数基準」がある
- どの方法を採用するかは会社の判断だが、就業規則で明確に定めることが超重要!
- 端数処理のルールも決めておく
- 社会保険料は原則日割りされない点に注意
- 諸手当の扱いもルール化しておく
給与計算は、従業員の生活に直結する大切な業務です。日割り計算のようなイレギュラーな対応も、あらかじめルールを明確にしておくことで、迷わずスムーズに進めることができます。
この記事が、事業主の皆さまの日々の給与計算業務の負担を少しでも軽くする一助となれば幸いです。もし、自社での判断に迷われたり、より専門的なアドバイスが必要だと感じられたりした際には、どうぞお気軽に弊社社労士事務所へお問い合わせください。皆さまの会社運営をサポートさせていただきます。