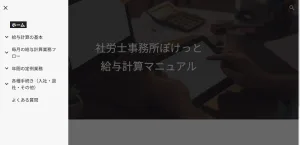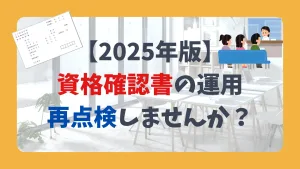算定基礎届で標準報酬月額が変わらない?「従前のまま」になるケースとは
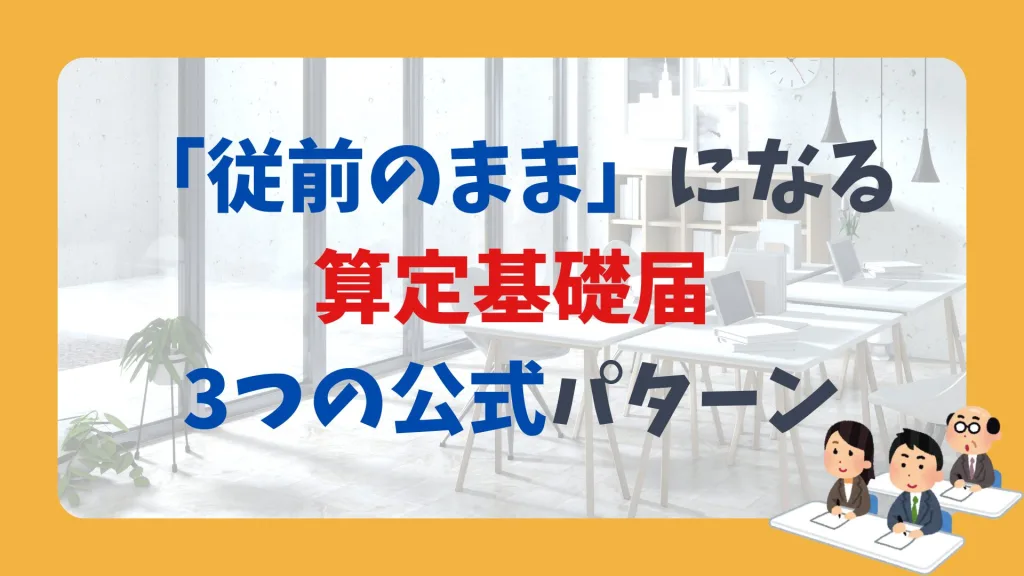
毎年7月は、社会保険の手続き、特に「算定基礎届」のシーズンですね。
人事労務ご担当者の皆様は、まさに今、準備の真っ最中かもしれません。
算定基礎届は、4月・5月・6月に支払った給与にもとづき、9月からの社会保険料の基準となる「標準報酬月額」を決定(定時決定)するための、年に一度の重要な手続きです。
「今年は4〜6月の給与に変動があったから、標準報酬月額も変わるだろう」
そう思って手続きを進めていたのに、決定通知書を見たら「あれ?標準報酬月額が去年と同じだ…」という経験はありませんか?
実は、算定基礎届を提出しても、必ずしも標準報酬月額が改定されるわけではなく、「従前の標準報酬月額」のままになることがあるのです。
こんにちは!社労士事務所ぽけっとです。
私たちは、中小企業の皆様の「給与計算」や「社会保険手続き」といった、複雑で時間のかかる労務管理をサポートしています。
今回は、日本年金機構の『算定基礎届の記入・提出ガイドブック』を基に、「算定基礎届を提出しても標準報酬月額が従前のまま決定されるパターン」について、その理由と具体的なケースを分かりやすく解説します。
なぜ「従前の標準報酬月額」のままになるの?
結論から言うと、それは「新しい標準報酬月額を計算するための基礎となる月が、4月・5月・6月の3ヶ月の中に1つもなかった」からです。
算定基礎届は、原則として4月・5月・6月に支払われた給与額の平均で新しい標準報酬月額を算出します。
しかし、何らかの理由で、この3ヶ月のいずれも「算定の基礎」として採用できない場合があります。
その場合、新しい月額を計算しようがないため、やむを得ず、これまで適用されていた「従前の標準報酬月額」で引き続き決定される、というわけです。
では、具体的にどのような場合がこれに該当するのでしょうか。主なパターンを見ていきましょう。
パターン1:3ヶ月とも「支払基礎日数」が基準未満だった
これが、従前の標準報酬月額で決定される最も代表的なケースです。
標準報酬月額を計算する対象にできるのは、報酬の「支払基礎日数」が一定の日数以上ある月に限られます。
この基準に、4月・5月・6月の3ヶ月とも満たなかった場合、算定の基礎となる月が「0」となるため、従前の標準報酬月額で決定されます。
支払基礎日数の基準は、従業員の区分によって異なります。
- 一般的な被保険者:支払基礎日数が17日未満の月は算定対象外 。3ヶ月とも17日未満の場合は、従前の標準報酬月額で決定されます。
- 短時間就労者(パートタイマー):支払基礎日数が17日以上の月がない場合、15日以上ある月を対象とします。しかし、3ヶ月とも15日未満の場合は、従前の標準報酬月額で決定されます。
- 短時間労働者:支払基礎日数が11日以上ある月を対象とします。3ヶ月とも11日未満の場合は、従前の標準報酬月額で決定されます。
ぽけっとメモ
「支払基礎日数」とは?その報酬の支払い対象となった日数のことです。
・月給制・週給制:暦日数が基礎日数となります。 ただし、欠勤日数分を給与から差し引く場合は、所定の日数から欠勤日数を引いた日数になります。
・時給制・日給制:実際の出勤日数が基礎日数となります。
パターン2:病気や休業で、3ヶ月とも給与の支払いが全くなかった
病気による長期欠勤や、育児休業・介護休業などにより、4月・5月・6月の3ヶ月間、全く給与の支払いを受けなかった場合も、従前の標準報酬月額で決定されます。
この場合も、算定の基礎となる報酬そのものがないため、新しい標準報酬月額を計算することができません。
パターン3【特殊ケース】:一時帰休から復帰したが、算定対象月が休業手当のみだった
少し特殊な例ですが、一時帰休に関するケースです。
7月1日時点で一時帰休は解消していても、4月・5月・6月のいずれの月にも休業手当が支払われている場合は、その低額な休業手当にもとづいて決定するのは不当であるため、改定される前の「従前の標準報酬月額」で決定されます。
【重要】従前の月額で決定される場合でも、算定基礎届の提出は必要!
ここで最も注意していただきたいのは、今回ご紹介したどのパターンに該当する場合でも、算定基礎届の提出は必ず必要だという点です。
「どうせ変わらないから提出しなくてもいいだろう」と判断してしまうと、後から年金事務所から督促が来たり、手続き漏れとなったりする可能性があります。
例えば、病気療養中で3ヶ月とも給与支払いがなかった従業員についても、算定基礎届は提出しなければなりません。
その際は、報酬月額などの欄は空欄のまま、備考欄の「5.病休・育休・休職等」を○で囲み、「9.その他」の欄に「〇年〇月〇日から休職」のように状況を記入して提出します。
こうすることで、日本年金機構側で「従前の標準報酬月額で決定する」という正しい処理が行われます。
【まとめ】毎年だからこそ、正しい知識で確実な手続きを
今回は、算定基礎届で標準報酬月額が「従前のまま」になるパターンについて解説しました。
- パターン1:4〜6月の3ヶ月とも、支払基礎日数が基準未満だった
- パターン2:病気や育休などで、4〜6月の3ヶ月とも給与の支払いがなかった
- パターン3(特殊):一時帰休からの復帰後で、4〜6月の給与が休業手当のみだった
これらのケースに共通するのは、「新しい標準報酬月額を計算するための基礎がない」という点です。
そして、いずれの場合も「算定基礎届の提出は必要」ということを、ぜひ覚えておいてください。
社会保険の手続きは、毎年の法改正や従業員一人ひとりの状況に応じた判断が求められる、非常に専門的で責任の重い業務です。
「このケースはどのパターンに当てはまるんだろう?」
「毎年この時期は、算定基礎届のことで頭がいっぱい…」
もし、このようにお感じでしたら、専門家である社会保険労務士に手続きをまるごと任せてしまうのも、有効な選択肢の一つです。
私たち社労士事務所ぽけっとは、給与計算から社会保険手続きまで、貴社の労務管理をトータルでサポートいたします。
専門家が正確かつ迅速に処理することで、ご担当者様の負担を劇的に軽減し、法令を遵守した安心の企業経営をお手伝いします。
まずはお気軽にご相談ください。貴社の状況を丁寧にお伺いし、最適なサポートをご提案いたします。
【免責事項】
当ブログ記事は、作成日時点での情報(日本年金機構『算定基礎届の記入・提出ガイドブック 令和7年度』等)に基づき、一般的な情報提供を目的として作成しております。特定の個人や企業における状況への適用を保証するものではありません。記事の内容の適用にあたっては、必ず専門家にご相談いただくか、最新の法令等をご確認いただきますようお願い申し上げます。