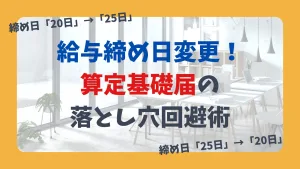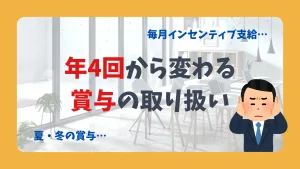4月~6月の働き方が変わったらどうなる?パート・短時間労働者の社会保険料、算定月は要注意!
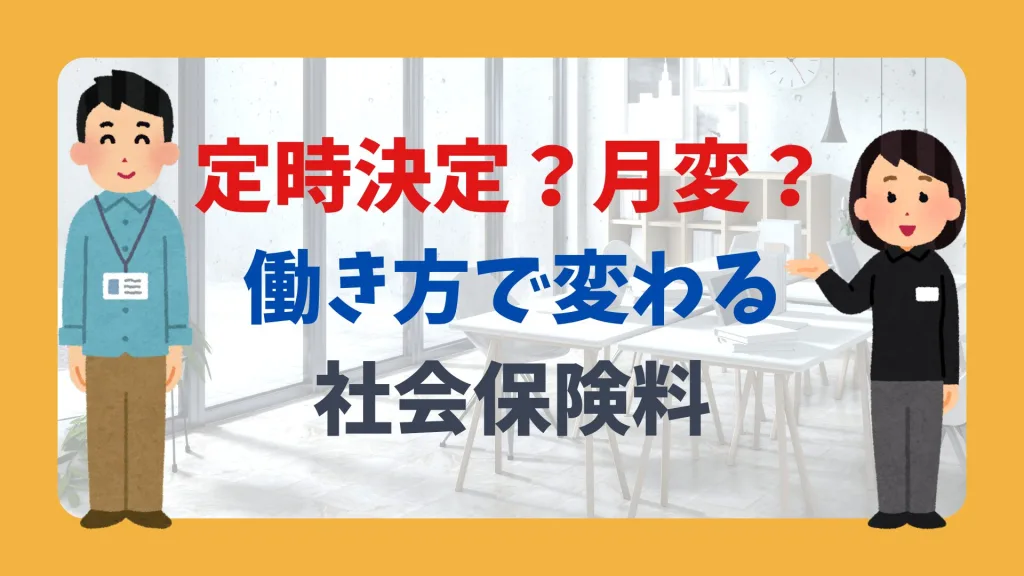
「社会保険料って、毎月給料から引かれるけど、どうやって決まっているんだろう?」
そんな疑問をお持ちの経営者の方や人事担当者の方、いらっしゃいませんか?
実は、社会保険料の計算のもとになる「標準報酬月額」は、年に一度、原則として4月・5月・6月の給与を基に決定されます。
これを「定時決定」と呼び、決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月までの社会保険料に適用されます。
今回は、特にご質問が多い「パートタイム労働者」や「短時間労働者」の方で、4月から6月の間に働き方が変わった場合の標準報酬月額の算定について、具体的な例を交えながら分かりやすく解説していきます。
働き方が変わるとどうなる?定時決定の基本的な考え方
通常、社会保険の被保険者の方の標準報酬月額は、4月・5月・6月の3ヶ月間の給与の平均額を基に決定されます。
この3ヶ月間に支払われた給与は「報酬」と呼ばれ、基本給だけでなく、残業代や通勤手当、家族手当なども含まれます。
しかし、パートタイム労働者や短時間労働者の方の場合、働き方が頻繁に変わったり、月の途中で被保険者の区分が変わったりすることがありますよね。
そのような場合、算定の対象となる月の考え方が少し複雑になります。
ポイントは、「算定の対象月は、各月の被保険者区分に基づき判断される」という点です。
つまり、4月はパートタイム労働者だったけれど、5月からはフルタイムになった、といったケースでは、それぞれの月の被保険者区分に応じて、算定対象とするかどうかの判断基準が変わるのです。
ここが肝心!「支払い基礎日数」ってなに?
標準報酬月額を算定する上で、とても重要なのが「支払い基礎日数」です。
これは、その月に賃金支払いの対象となった日数のことを指します。
- 一般の被保険者(パートタイム労働者を含む): 支払い基礎日数が17日以上の月が算定の対象となります。
- 短時間労働者: 支払い基礎日数が11日以上の月が算定の対象となります。
つまり、どんなにたくさん給与を支払っても、支払い基礎日数がこの日数に満たない月は、原則として算定の対象にはなりません。
具体例で見てみよう!働き方が変わった場合の算定方法
では、実際に具体的なケースを見てみましょう。
<例:4月・5月は一般(パート)、6月は短時間労働者に変更になった場合>
| 被保険者区分 | 月 | 支払い基礎日数 | 報酬月額 |
| 一般 | 4月 | 16日 | 135,000円 |
| 一般 | 5月 | 18日 | 150,000円 |
| 短時間労働者 | 6月 | 12日 | 108,000円 |
このケースでは、以下のように判断されます。
- 4月(一般の被保険者): 支払い基礎日数が16日のため、算定の対象外となります。(一般の被保険者の基準は17日以上)
- 5月(一般の被保険者): 支払い基礎日数が18日のため、算定の対象となります。(一般の被保険者の基準は17日以上)
- 6月(短時間労働者): 支払い基礎日数が12日のため、算定の対象となります。(短時間労働者の基準は11日以上)
結果として、この方の標準報酬月額は、5月と6月の報酬月額に基づいて決定されます。
それぞれの月の被保険者区分に応じた支払い基礎日数の基準を満たしている月が算定対象となるのですね。
パートタイム労働者の特例「支払い基礎日数15日以上」とは?
ここで、パートタイム労働者の方に適用される特例についても触れておきましょう。
パートタイム労働者の場合で、もし4月・5月・6月のいずれの月も、上記の「支払い基礎日数17日以上」の基準を満たす月がない場合はどうなるのでしょうか?
この場合は、例外的に「支払い基礎日数が15日以上」の月を算定の対象として、標準報酬月額を決定します。
これは、パートタイム労働者の働き方の実態に配慮した措置と言えます。
働き方の変更は「随時改定(月変)」の可能性も
今回の例では、定時決定における被保険者区分の変更に着目しましたが、もし6月以降の働き方の変更が、単なる一時的なものではなく、今後も継続するもので、その結果として給与額が大きく変動し、かつ社会保険料の等級が2等級以上変わるような場合は、「随時改定(月変)」の対象となる可能性もあります。
随時改定は、定時決定とは異なり、主に固定的賃金の変動(基本給の昇給・降給、手当の新設・廃止など)があった場合に適用されます。
ただし、固定的賃金の変動がなくとも、被保険者区分の変更に伴う業務内容や勤務時間の変更により、結果的に継続的な報酬の変動が生じ、2等級以上の差が出た場合にも適用されることがあります。
例えば、6月から働き方が変わり、残業が増えて恒常的に給与が大幅に変わったようなケースでは、6月・7月・8月の給与を基に、9月から社会保険料が変更になる、といったことも考えられます。
定時決定と随時改定は、社会保険料を適正に算定するための重要な制度です。
ご自身の状況や従業員の方の働き方の変化に応じて、どちらの制度が適用されるかを適切に判断することが大切です。
【まとめ】適切な社会保険料の算定のために
今回は、4月~6月の間にパートタイム労働者から短時間労働者へ、またはその逆といった被保険者区分の変更があった場合の標準報酬月額の算定と、随時改定(月変)の可能性について解説しました。
- 算定対象月は、各月の被保険者区分に基づき判断される。
- 「支払い基礎日数」が重要な判断基準となる。
- 一般の被保険者(パート含む):17日以上
- 短時間労働者:11日以上
- パートタイム労働者で17日以上の月がない場合は、15日以上の月を対象とする特例がある。
- 固定的賃金の変動を伴う働き方の変更は、随時改定(月変)の対象となる可能性もある。
社会保険料の計算は複雑で、法改正も頻繁に行われます。
特に働き方が多様化する中で、適切に社会保険料を算定し、従業員の方々が安心して働ける環境を整えることは、企業の重要な責務です。
もし、貴社の従業員の方の社会保険料の算定についてご不明な点や不安な点がございましたら、いつでも当事務所にご相談ください。
専門知識を持った社労士が、貴社の状況に合わせて丁寧にご説明し、最適なアドバイスをさせていただきます。
【免責事項】
本ブログ記事は、一般的な情報提供を目的としており、特定の状況における法的アドバイスを構成するものではありません。個別の事案については、必ず専門家にご相談ください。本記事の内容に基づいて被ったいかなる損害についても、当事務所は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。