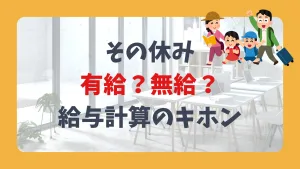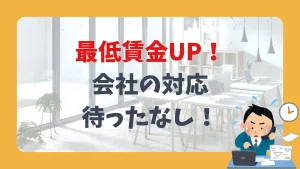退職後も傷病手当金をもらうための4つの条件とは?継続給付のポイント
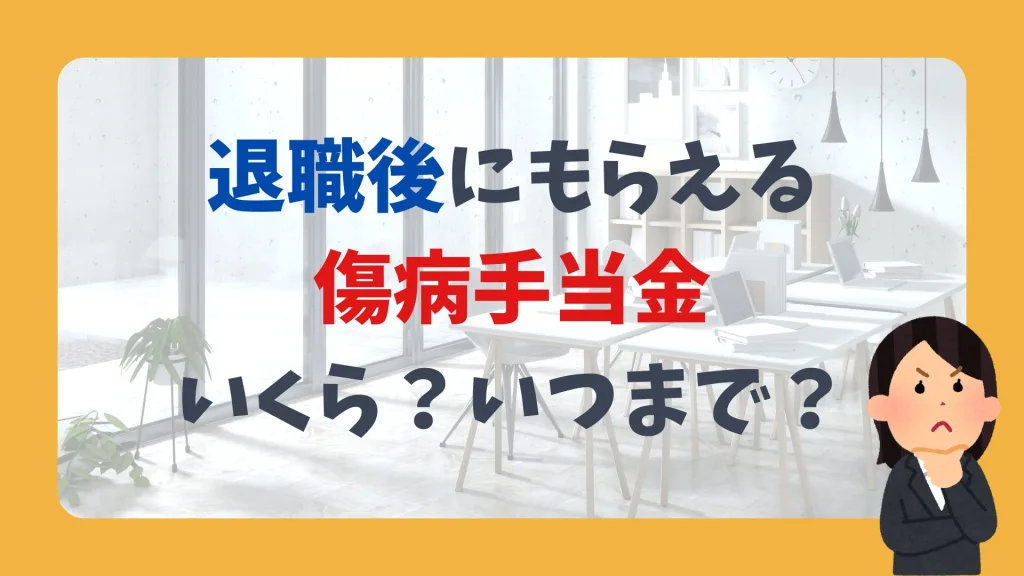
こんにちは!社労士事務所ぽけっとです。
病気やケガで長期間お仕事を休まなければならなくなった時、従業員の生活を支える心強い制度が「傷病手当金」です。
しかし、「もうすぐ退職するから…」「退職してしまったら、もう手当はもらえない」と諦めてしまっている方はいらっしゃいませんか?
実は、一定の条件を満たせば、退職後も傷病手当金を受け取り続けることができるのです。
これは「資格喪失後の継続給付」という制度で、知っていると知らないとでは、退職後の生活設計が大きく変わる可能性があります。
今回は、この「退職後の傷病手当金」を受け取るための重要なポイントについて、人事労務のプロである社労士が分かりやすく解説していきます。
そもそも「傷病手当金」とは?
まずは基本のおさらいです。
傷病手当金とは、健康保険の被保険者が業務外の病気やケガが原因で会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給される所得保障制度です。
ポイントは「業務外」という点です。
通勤中や業務上の災害によるものは「労災保険」の対象となります。
この制度のおかげで、療養に専念している間の生活費の心配を和らげることができる、非常に大切なセーフティーネットなのです。
いくらもらえるの?支給額と支給期間
では、実際に傷病手当金は一日あたりいくらくらい支給されるのでしょうか。
また、いつまで受け取れるのでしょうか。
支給額の計算方法
傷病手当金の1日あたりの支給額は、おおよそ「月給の約3分の2」を日割りした金額とイメージすると分かりやすいです。
正式な計算式は以下のようになります。
【支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額】÷ 30日 × (2/3)
少し難しく感じるかもしれませんね。「標準報酬月額」とは、社会保険料を計算するために、お給料を一定の範囲で区切ったものです。
給与明細に記載されていることが多いです。
<計算例>
過去12ヶ月間の標準報酬月額の平均が30万円だった場合
300,000円 ÷ 30日 × (2/3) = 6,667円(1日あたり)
この金額が、休んだ日数分(待期期間を除く)支給されることになります。
支給される期間
傷病手当金が支給される期間は、支給を開始した日から通算して最長1年6ヶ月です。
以前は支給開始から1年6ヶ月が経過すると、途中で出勤した期間があっても支給が終了していましたが、法改正により、実際に休んだ日数をカウントする「通算」方式に変わりました。
これにより、復職と休職を繰り返すような場合でも、手厚く保障を受けられるようになっています。
【最重要】退職後に傷病手当金を受け取るための4つの条件
退職後も傷病手当金の支給を受け続けるためには、以下の4つの条件をすべて満たしている必要があります。
一つずつ丁寧に見ていきましょう。
条件1:退職日までに「継続して1年以上」の被保険者期間があること
これが最初の関門です。退職日(資格喪失日の前日)までに、継続して1年以上、健康保険の被保険者であった期間が必要です。
「継続して」というのがポイントで、例えば転職した場合でも、被保険者資格の喪失日から次の資格取得日までの間に1日も空きがなければ、期間は通算されます。国民健康保険に加入していた期間は含まれないので注意が必要です。
ご自身の被保険者期間が分からない場合は、年金事務所で確認するか、ねんきんネットを利用すると便利です。
条件2:資格喪失時(退職日の翌日)に、傷病手当金を受給しているか、受給できる状態であること
これは、「退職する時点で、すでに傷病手当金をもらっているか、もらえる条件を満たした状態であった」ことを意味します。
具体的には、以下の3つの条件を満たしている状態です。
- 療養のためであること
- 労務不能(仕事に就けない状態)であること
- 連続する3日間(待期期間)を含み、4日以上仕事に就けなかったこと
簡単に言えば、「在職中に病気やケガで休み始め、3日間の待期期間を終えて、4日目以降も休んでいる状態で退職日を迎える」というイメージです。退職してから初めて病院にかかった、というケースは対象外となります。
条件3:在職中から続く「同じ病気やケガ」により、退職後も労務不能であること
退職後に受け取れる傷病手当金は、あくまで在職中に発症し、その原因となった病気やケガの治療が続いている場合に限られます。
例えば、在職中にうつ病で傷病手当金を受給していた方が、退職後もそのうつ病の治療のために働けない、というケースが該当します。
退職後に発症した全く別の病気やケガについては、この制度の対象にはなりません。
条件4:退職日に出勤していないこと
これは意外と見落としがちですが、非常に重要なポイントです。
退職日に、たとえ短時間でも挨拶や引き継ぎのために出勤してしまうと、「その日は労務不能ではなかった」と判断され、退職後の継続給付を受ける権利が消滅してしまいます。
有給休暇を取得して退職日を迎える場合は「出勤」には当たらないため問題ありません。
最終出勤日と退職日が異なる場合は、退職日当日の過ごし方にくれぐれもご注意ください。
よくあるご質問(Q&A)
ここでは、お客様からよくいただく質問にお答えします。
Q1. 失業保険(雇用保険の基本手当)と同時に受け取れますか?
A1. いいえ、原則として同時に受け取ることはできません。
傷病手当金は「働けない状態」で支給され、失業保険は「働ける状態だが仕事がない」場合に支給されるため、目的が異なります。
一般的には、まず傷病手当金の受給を優先し、働ける状態に回復してから失業保険の手続きを行うことになります。
Q2. 退職後にアルバイトをしたら、傷病手当金は止まりますか?
A2. はい、支給が停止される可能性が非常に高いです。
傷病手当金は「労務不能」な状態に対して支給されるため、アルバイトであっても収入を得る活動をすると、労務不能ではないと判断されます。
自己判断で行動せず、必ず保険者(健康保険組合や協会けんぽ)に確認しましょう。
Q3. 申請手続きはどうすればいいですか?
A3. 退職後も、在職中に加入していた健康保険組合または協会けんぽに申請します。
申請書には、ご自身で記入する部分のほかに、療養を担当した医師に意見を記入してもらう部分があります。
退職後は事業主の証明は不要です。申請期間には時効(2年)があるため、早めに手続きを進めましょう。
【まとめ】諦める前に、まずは専門家へご相談を
今回は、退職後も傷病手当金を受け取るための4つの条件について解説しました。
- 1年以上の被保険者期間
- 退職時に受給中、または受給できる状態
- 在職中と同じ傷病で労務不能が続いている
- 退職日に出勤しない
これらの条件は複雑に感じるかもしれませんが、ご自身の状況が当てはまるかどうかを正しく判断することが大切です。
「自分は対象外かもしれない」とすぐに諦めず、まずはご加入の健康保険組合や協会けんぽ、あるいはお近くの社会保険労務士に相談することをお勧めします。
社労士事務所ぽけっとでは、こうした社会保険の手続きに関するご相談も承っております。
従業員の方の生活を守るための大切な制度です。お困りの際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
【免責事項】
本記事は2025年8月時点の情報に基づき作成しております。法改正や制度変更により、掲載内容が最新の情報と異なる場合がございます。正確な情報については、必ず公式サイト等でご確認いただくか、専門家にご相談くださいますようお願い申し上げます。個別の事案については、本記事を根拠に判断されず、必ず専門家にご相談ください。