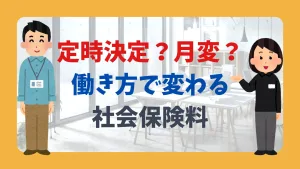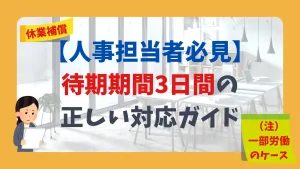賞与が年4回は要注意!社会保険料の罠と正しい計算方法を社労士が完全解説
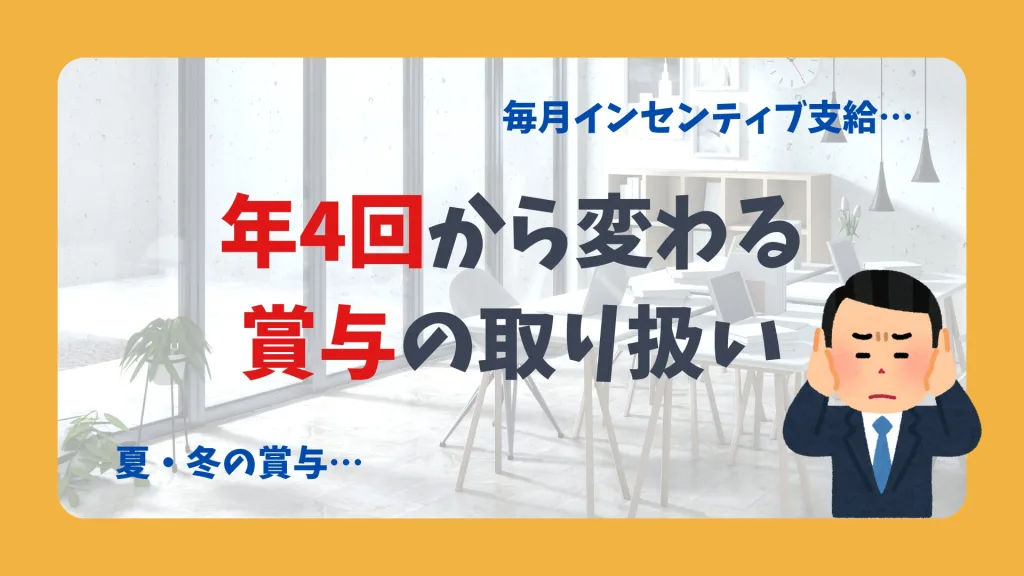
こんにちは!社労士事務所ぽけっとです。
「従業員の頑張りに応えるため、夏・冬のボーナス以外に、業績に応じたインセンティブも支給している」
「支払い回数が年によって変動し、社会保険の計算が合っているか不安…」
こうしたお悩みをお持ちの経営者様、人事・経理担当者様は、実は非常に多くいらっしゃいます。
従業員にとって喜ばしい賞与。
しかし、その支払い回数によって社会保険料の計算方法が全く異なり、気づかないうちに間違った処理をしてしまうリスクが潜んでいることをご存知ですか?
この記事では、これまでのやり取りでいただいた数々の疑問にお答えする形で、「年4回以上の賞与」に関する社会保険のルールを、詳しく、分かりやすく解説します。
この記事を最後まで読めば、複雑な賞与の取り扱いがスッキリ整理できるはずです。
【大原則】年3回までか、4回以上か。全ては回数で決まる
まず、絶対に押さえておくべき大原則です。
社会保険の世界では、賞与的な性質を持つ支払いが年間に何回行われたかで、その法的な扱いが決定的に変わります。
| 年3回以下の賞与 | 年4回以上の賞与 | |
| 社会保険上の扱い | 賞与 | 報酬(賞与に係る報酬) |
| 保険料の計算 | 賞与支給額から直接天引き | 毎月の給与に上乗せして計算 |
| 必要な手続き | 賞与支払届の提出 | 賞与支払届は不要 |
「年4回以上」支払われた時点で、その金銭はもはや「賞与」ではなく、毎月の給与と同じ「報酬」として扱われるのです 。
なぜルールが違うの?「保険料負担の公平性」という考え方
この複雑なルールの背景には、**「保険料負担の公平性」**という社会保険制度の根幹をなす考え方があります。
例えば、年収が全く同じ600万円のAさんとBさんがいるとします。
- Aさん: 月給50万円、賞与なし
- Bさん: 月給30万円 + 四半期ごとの賞与60万円(年4回)
もし、Bさんの年4回の賞与を「報酬」と見なさなければ、Bさんの毎月の社会保険料は「月給30万円」を基に計算され、Aさんより著しく安くなります。
同じ収入なのに保険料が違うのは不公平ですよね。
この不公平をなくすため、「年4回以上もらうお金は、もはや臨時収入ではなく、生活を支える経常的な報酬の一部だ」と考え、毎月の給与に合算して保険料を計算するルールになっているのです。
【重要】実務上の正しい計算手続き
「報酬として扱う」と言っても、具体的にどう計算するのでしょうか。
実は、支払い方によって計算方法が異なります。
- パターンA:インセンティブ等が「毎月の給与に上乗せ」で支払われる場合
- 扱い: 通常の報酬(給与の一部)
- 計算方法: 毎年7月の定時決定(算定基礎届)では、**4月・5月・6月に支払われた「インセンティブ込みの給与総額」**をそのまま用いて平均額を算出します。特別な計算は不要です。
- パターンB:賞与やインセンティブが「給与とは別に」年4回以上支払われる場合
- 扱い: 賞与に係る報酬
- 計算方法: 毎年7月の定時決定(算定基礎届)で、以下の合算を行います。
- 4月・5月・6月の給与の平均額を算出
- 前年7月1日から当年6月30日までに支払われた賞与の合計額を12で割った額を算出
- 上記1と2を足した金額で、新しい標準報酬月額を決定
【Q&A】これで解決!担当者が本当に知りたい疑問のすべて
ここからは、皆様からいただいた具体的な疑問に、一問一答形式でお答えします。
Q1. 「賞与」と「インセンティブ」、名称が違うものはどう数える?
A1. 名称が異なっても、同じ「賞与的な性質」を持つものであれば、年間の支払い回数を合算して判断します 。例えば、「夏・冬の賞与(計2回)」と「半期ごとのインセンティブ(計2回)」があれば、合計「年4回」となり、全てが「賞与に係る報酬」として扱われます。
Q2. 業績次第で、年によって支給回数が4回以上になるか分からない場合は?
A2. 毎年7月の定時決定の際に、過去1年間の実績に基づいて判定します。 具体的には、「前年7月1日~当年6月30日」の支給実績を数え、4回以上であればその年は「報酬」として、3回以下であれば「賞与」として、翌年8月までの取り扱いを決定します 。予測ではなく、過去の実績で判断するのがルールです。
Q3. 年の途中で規程が変わり、賞与が年4回以上に増えたら、すぐに扱いも変わる?
A3. いいえ、すぐには変わりません。年の途中(7月2日以降)で支給回数が年4回以上に増えても、次回の定時決定で新しい標準報酬月額が適用されるまでは、引き続き「賞与」として扱います 。つまり、それまでは都度「賞与支払届」の提出と保険料の天引きが必要です。
Q4. 月給が下がって随時改定(月額変更)をする時、賞与分の計算も見直す?
A4. いいえ、見直しません。通常の給与に大きな変動があって随時改定を行う場合でも、一度定時決定で決まった「賞与に係る報酬」の額は変更せず、そのまま変動後の給与額に加算します 。
Q5. 「実態として、年4回でも賞与支払届を出している会社は多い」と聞きますが?
A5. それは法律上、誤った手続きです。ルールの認知度が低いことや、制度の複雑さから慣例的に行われているケースが見受けられますが、決して正しい方法ではありません。年金事務所の調査では必ず確認される項目であり、発覚すれば過去に遡っての訂正と保険料の追徴が求められます。
【戦略的視点】いっそ、賞与を年3回以内に統一するのはどう?
この煩雑さを根本的に解消するために、「賞与の支給を年3回以内に統一する」というのは、管理面から見れば非常に的確で有効な解決策です。
判定業務や計算ミスがなくなり、将来のリスクを完全に回避できます。
**一方で、**人事戦略の視点も重要です。
短期的なインセンティブが従業員のモチベーション維持に繋がっている場合、回数を減らすことが意欲や採用競争力に影響を与える可能性も考慮しなくてはなりません。
最終的には、「管理コストやリスク」と「人事戦略上のメリット」を天秤にかけ、貴社にとって最適な着地点を見つけることが重要です。
まとめ
賞与の社会保険手続きは、支払い回数という一つの要因で大きく変わる、非常にデリケートな業務です。
- 年4回以上の賞与は「報酬」として、毎月の給与と合算して保険料を計算する。
- 判断基準は「名称」ではなく「性質」と「実績回数」。
- 毎年の定時決定が、過去1年の実績を基に翌年の扱いを決めるリセットポイント。
- 手続きを簡素化するために支給回数を見直す際は、人事戦略も併せて検討する。
「うちの会社の計算方法は本当に正しいだろうか…」「従業員ごとに扱いが違って、管理が限界…」 そのお悩み、ぜひ私たち専門家にお聞かせください。
社労士事務所ぽけっとは、複雑な給与計算・社会保険手続きを正確に代行し、企業様を将来のリスクからお守りします。どうぞお気軽にご相談ください。
【免責事項】
本記事は、掲載日時点の法令および情報に基づき作成しております。法改正等により、今後の取り扱いが変更される可能性があります。また、個別の事案については、必ず専門家にご相談いただくか、管轄の行政機関にご確認くださいますようお願い申し上げます。