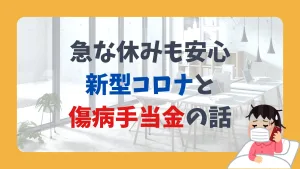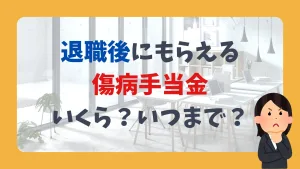お盆休み、会社のルールは大丈夫?社労士が教える夏季休暇の定め方と給与計算の注意点

こんにちは!社労士事務所ぽけっとです。
毎年夏になるとやってくるお盆の季節。
多くの企業が夏季休暇を設け、従業員の方々も心身をリフレッシュさせる大切な時期ですね。
しかし、経営者様や人事担当者様にとっては、「うちの会社の夏季休暇のルール、これで本当に大丈夫だっけ?」と、ふと不安になる瞬間はないでしょうか。
「昔からの慣例で、毎年カレンダー通りに休みにしている」「従業員には有給を使ってもらっている」など、運用方法は会社によって様々だと思います。
しかし、そのルールが曖昧なままだと、思わぬ労務トラブルに発展したり、従業員の不公平感に繋がったりする可能性も否定できません。
そこで今回は、お盆休みを機に見直したい「夏季休暇」のルールについて解説します。
正しいルールを定め、会社も従業員も気持ちよく夏を過ごせる体制を整えましょう!
そもそも「夏季休暇」は法律上の義務ではない
まず大前提として、労働基準法では「夏季休暇」を与える義務は会社に課されていません。
法律で定められた休日は「法定休日(週に1回または4週に4回)」、休暇は「年次有給休暇」などです。
つまり、夏季休暇は会社が任意で設ける「法定外休暇(特別休暇)」という位置づけになります。
だからこそ、会社ごとにルールが異なり、そのルールを従業員にきちんと周知しておくことが非常に重要になるのです。
あなたの会社はどのタイプ?夏季休暇の主な3つのパターン
夏季休暇の運用方法は、主に以下の3つのパターンに分けられます。
それぞれの特徴を理解し、自社に合った方法を選択することが大切です。
パターン1:年次有給休暇の取得を奨励する
会社として一斉の休みは設けず、従業員が各自で「年次有給休暇(年休)」を取得する方法です。
- メリット
会社としては新たな休暇制度を設ける必要がなく、導入が最も手軽です。
従業員は好きなタイミングで休みを取得できます。 - デメリット
年休の取得はあくまで従業員の権利なので、会社が取得を強制することはできません。
また、従業員ごとに休みがバラバラになるため、業務の連携が取りにくくなる可能性があります。 - 注意点
2019年4月から、全ての企業で「年5日の年休取得義務」が課されています。
お盆の時期などに年休を取得してもらうことは、この義務を果たす上でも有効な手段と言えます。
パターン2:会社独自の「特別休暇」として付与する
会社の福利厚生の一環として、年休とは別に「夏季休暇」という名称の特別休暇を付与する方法です。
多くの企業で採用されている一般的な方法と言えるでしょう。
- メリット
全従業員が一斉に休むため、業務の調整がしやすく、気兼ねなく休暇を取得できる雰囲気を作れます。
「従業員を大切にする会社」というアピールにも繋がります。 - デメリット
年休とは別の休暇を付与するため、会社にとっては人件費の負担が増えることになります。 - 注意点
この特別休暇を「有給」にするか「無給」にするかは、会社の自由です。
しかし、どちらにするかを就業規則に明確に定めておく必要があります。
この点が曖昧だと、給与計算の際にトラブルになる可能性があります。
パターン3:年次有給休暇の「計画的付与(計画年休)」を活用する
「計画年休」とは、従業員が持っている年休のうち、5日を超える部分について、会社が計画的に取得日を指定できる制度です。
- メリット
会社主導で計画的に休暇を設定できるため、業務への影響を最小限に抑えられます。
また、従業員の年休取得率を確実に向上させることができます。 - デメリット
導入には「労使協定」の締結が必要です。
また、付与日数が5日以下の従業員(入社して間もない従業員など)には適用できないため、その従業員への対応(特別休暇の付与など)を別途検討する必要があります。 - 注意点
全従業員に一斉に同じ日数を与える「一斉付与方式」のほか、グループや班ごとに交代で取得させる「交替制付与方式」など、柔軟な設定が可能です。
トラブル防止の要!就業規則への記載が不可欠
どのパターンを選択するにせよ、夏季休暇のルールは必ず就業規則に明記しておきましょう。
「言った・言わない」のトラブルを防ぎ、公平なルール運用の根拠となります。
特にパターン2の「特別休暇」を設ける場合は、以下の点を明確に記載することが重要です。
【就業規則の記載例(特別休暇の場合)】
(夏季休暇)
第〇条 会社は、毎年8月13日から8月15日までの3日間を夏季休暇とする。
2 前項の休暇は、有給とする。
3 業務の都合により前項の期間に休暇を取得できなかった従業員については、別途所属長と協議の上、9月末までに代替の休暇を取得するものとする。
4 第1項の夏季休暇の日が、会社の所定休日にあたるときは、当該休日を除き、別に休日を与えるものとする。
ポイントは、第2項の「有給とする」という一文です。
ここを「無給とする」と定めることも可能ですが、有給か無給かは賃金に関わる非常に重要な事項ですので、必ず明記してください。
また、第4項のように、休暇日と会社の休日が重なった場合のルールを定めておくと、年によって休日日数が変わることへの不公平感がなくなり、より親切な規定となります。
【重要】休暇中の給与と社会保険料の扱いはどうなる?
最後に、夏季休暇中の給与と社会保険料の扱いについて確認しておきましょう。
ここを誤ると、給与計算のミスに直結します。
給与の計算方法
- 年次有給休暇・有給の特別休暇の場合
休暇を取得しても給与は減額されません。通常通り出勤したものとして給与を計算します。 - 無給の特別休暇の場合
休暇を取得した日の給与の扱いは、給与形態によって注意が必要です。- 月給制の従業員の場合
月給制の場合、特別休暇が「有給」か「無給」かは特に注意が必要です。
一般的に月給は月の労働に対する固定給のため、数日間の休暇では給与が減額されない(=実質的に有給扱いとなる)ケースが多く見られます。
しかし、これは会社のルール次第です。就業規則や給与規程で、その特別休暇が「無給」であり、給与から控除(欠勤控除)すると明確に定められている場合は、その規定に従います。
そのため、「無給休暇」と聞いてすぐに給与が減ると判断せず、まずは自社の就業規則をしっかりと確認することが何よりも重要です。 - 時給制・日給制の従業員の場合
「ノーワーク・ノーペイの原則」に基づき、休暇を取得して労働しなかった時間・日数分の給与は支払われません。
- 月給制の従業員の場合
社会保険料(健康保険・厚生年金保険料)の扱い
「無給の休暇で給与が減ったら、社会保険料も安くなるの?」と疑問に思われるかもしれませんが、答えは「原則、変わらない」です。
社会保険料は、毎月の給与額ではなく、4月~6月の給与の平均から算出される「標準報酬月額」を基に決定されます。
そのため、夏季休暇(無給)によって一時的に給与が減ったとしても、その月の社会保険料が変動することはありません。
給与計算の際には、給与総額から通常通りの社会保険料を控除することを忘れないようにしましょう。
【まとめ】ルールを明確にして、安心して休める夏に
今回は、夏季休暇の基本的な考え方から、具体的な運用方法、就業規則への記載、給与計算の注意点までを解説しました。
ルールを明確に定め、全従業員に周知しておくことは、無用なトラブルを避けるだけでなく、従業員の会社に対する信頼感や満足度の向上にも繋がります。
「うちは大丈夫」と思っている会社様も、ぜひこの機会に一度、自社のルールが明文化されているかを確認してみてはいかがでしょうか。
「自社に合った休暇制度がわからない」「就業規則の変更や労使協定の作り方が難しい」など、具体的なお悩みやご相談がございましたら、いつでもお気軽に社労士事務所ぽけっとまでお問い合わせください。
貴社に最適なご提案をさせていただきます。
【免責事項】
当ブログ記事は、掲載時点での情報に基づき、一般的な情報提供を目的として作成しております。法改正や個別の事情により、記事の内容が適合しない場合もございます。実際の労務管理にあたっては、必ず専門家にご相談いただくか、最新の法令等をご確認いただきますようお願い申し上げます。記事の内容の利用によって生じた一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。