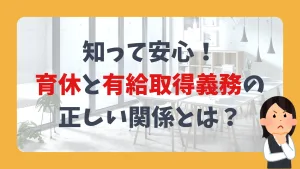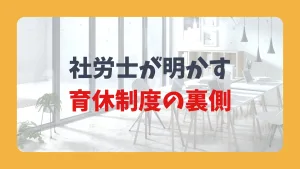パートの勤務時間を会社が一方的に変更!これって違法?対処法も紹介
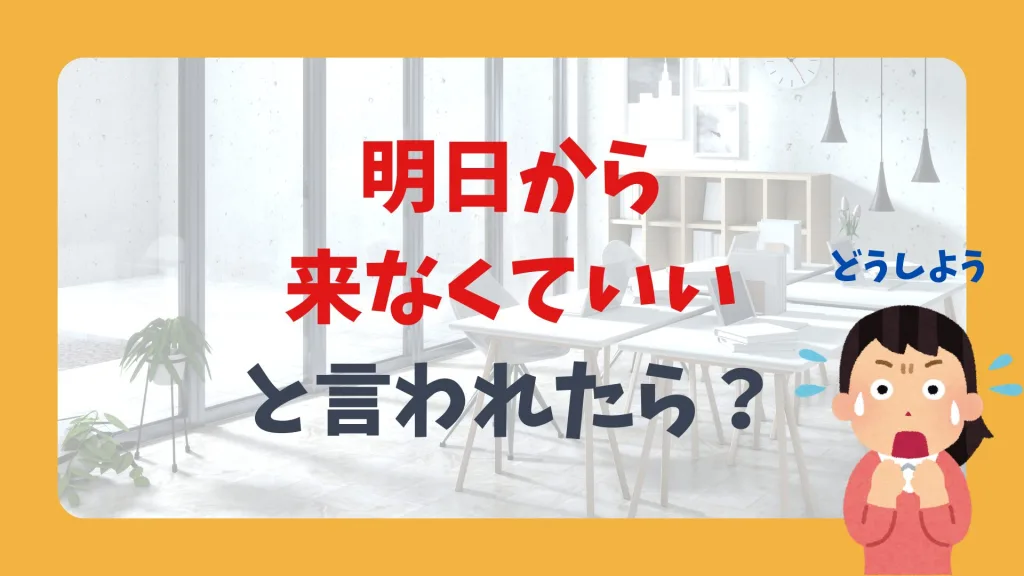
「明日から勤務時間を半分にします」
もしあなたがパートタイマーとして働いていて、会社からこのように一方的に勤務時間の短縮を告げられたら、どう感じますか?
「収入が減って困る」「予定が狂ってしまう」と、不安や怒りを感じるのは当然のことです。
先日、私たちの身近でも「1日6時間勤務だったのに、急に明日から午前中の3時間勤務になると言われた」というご相談がありました。
このような会社の対応は、法的に許されるのでしょうか?
結論から言うと、原則として、労働者の同意なく会社が一方的に勤務時間を変更することは違法です。
この記事では、なぜそれが違法なのか、例外はあるのか、そして実際にそのような状況に直面したときにどうすればよいのかを、社会保険労務士が分かりやすく解説します。
なぜ、会社は一方的に勤務時間を変更できないのか?
会社と労働者は、「労働契約」という約束で結ばれています。
「週に〇日、1日〇時間働く」という勤務時間は、この労働契約の非常に重要な要素です。
労働契約法第8条では、労働条件の変更は「労働者及び使用者は、その合意によって、労働契約の内容である労働条件を変更することができる」と定められています。
つまり、契約内容を変更するには、必ず働く人(労働者)と会社(使用者)の双方の合意が必要なのです。
これは、正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイトにも等しく適用される大原則です。
会社が「業績が悪いから」「仕事が減ったから」といった理由で、あなたの同意なく勤務時間を短くすることは、この原則に反するため、基本的には認められません。
同意がなくても変更が認められる「例外的なケース」とは?
原則は「同意が必要」ですが、法律には例外も存在します。
それは、「就業規則」を変更することによって労働条件を変更する場合です。
ただし、これにも厳しい条件があります。
会社が就業規則を変更して、労働者にとって不利益な内容(今回のケースでは勤務時間の短縮)を有効にするためには、以下の2つの条件を両方満たす必要があります(労働契約法第10条)。
- 変更後の就業規則を労働者に周知させていること。
- 変更が「合理的」であること。
特に重要なのが、2番目の「合理性」です。この合理性は、以下の要素を総合的に見て判断されます。
- 労働者が受ける不利益の程度:勤務時間が半分になれば収入も大きく減るため、不利益は非常に大きいと判断されるでしょう。
- 労働条件の変更の必要性:会社が倒産寸前であるなど、よほど高度な経営上の必要性がなければ認められにくいです。
- 変更後の就業規則の内容の相当性:他の従業員とのバランスや、社会的な常識に照らして妥当な内容かどうかが問われます。
- 労働組合等との交渉の状況:労働組合や従業員の代表と十分に話し合い、合意形成に努めたかどうかも重要なポイントです。
ご相談のケースのように、「明日から」という急な通告は、労働者への不利益が極めて大きく、代替案を検討する時間も与えられていないため、合理性が認められる可能性は非常に低いと言えます。
勤務時間が減ったら「休業手当」がもらえる?
会社の都合で一方的に勤務時間を短縮された場合、それは「休業」の一種と見なされることがあります。
労働基準法第26条では、会社の都合で労働者を休業させた場合、会社は休業させた日について、平均賃金の60%以上の「休業手当」を支払わなければならないと定められています。
どんなケースが「会社の都合」にあたるの?
では、この「会社の都合」とは、具体的にどのような場合を指すのでしょうか。
法律上は「使用者の責に帰すべき事由」と呼ばれ、会社側の経営・管理上の問題が原因で休業する場合が広く含まれます。
例えば、以下のようなケースです。
- 経営難や資金難になった
- 仕事の量が減った、客足が遠のいた
- 機械が故障した、メンテナンスが必要になった
- 原材料や商品が不足している
- 親会社の経営不振の影響を受けた
一方で、「会社の都合」と見なされないのは、地震や台風といった天災地変など、どうしようもない「不可抗力」の場合です。
ただし、「不可抗力」と認められるには、「原因が外部から発生したこと」と「事業主が最大限の注意をしても避けられなかったこと」という厳しい条件があり、会社が「仕方なかった」と主張しても、それが簡単に認められるわけではありません。
より詳しい実例で平均賃金を計算してみましょう
では、具体的なモデルケースで平均賃金と休業手当を計算してみましょう。
【モデルケース】
- 時給:1,200円
- 勤務:週4日、1日6時間
- 1ヶ月の勤務日数を16日とする(週4日×4週)
ステップ1:平均賃金の計算
平均賃金は、原則として「直近3ヶ月間の賃金総額 ÷ その期間の総日数(暦日数)」で計算します。
ただし、パートタイマーのように労働日数が少ない場合は、計算結果が非常に低くなることがあるため、最低保障額が定められています。
① 原則の計算
- 1ヶ月の賃金:1,200円 × 6時間 × 16日 = 115,200円
- 3ヶ月の賃金総額:115,200円 × 3ヶ月 = 345,600円
- 直近3ヶ月の暦日数を92日と仮定すると…
345,600円 ÷ 92日 = 3,757円(小数点以下切り上げ)
② 最低保障額の計算
「直近3ヶ月間の賃金総額 ÷ その期間の労働日数 × 60%」で計算します。
- 3ヶ月の労働日数:16日 × 3ヶ月 = 48日
- 345,600円 ÷ 48日 × 60% = 7,200円 × 60% = 4,320円
この場合、①よりも②の方が高いため、この方の平均賃金は4,320円となります。
ステップ2:休業手当の計算
休業手当は、「平均賃金の60%以上」を支払う必要があります。
- 休業手当の最低額:4,320円 × 60% = 2,592円
もし1日まるごと休業させられた場合は、会社は最低でも2,592円を支払う義務があります。
今回のケース(勤務時間が半分になった場合)
今回のケースは、6時間勤務が3時間に短縮された「一部休業」です。この場合、実際に支払われた賃金が、上記の休業手当の最低額(2,592円)を上回っているかどうかがポイントになります。
- 実際に支払われた賃金:1,200円 × 3時間 = 3,600円
支払われた3,600円は、休業手当の最低額である2,592円を上回っています。そのため、このケースでは、会社は法的に追加の「休業手当」を支払う義務まではありません。
しかし、これは非常に重要なポイントですが、休業手当の支払い義務がないからといって、「会社の行為が許される」わけでは決してありません。
あくまで問題の核心は、労働者の同意なく一方的に労働契約の内容(勤務時間)を変更したことにあります。
この行為自体が、労働契約法に違反する可能性が高いのです。
会社から一方的な勤務時間変更を告げられた時の対処法
では、実際にこのような状況に陥ってしまったら、どうすればよいのでしょうか。
冷静に、以下のステップで対応しましょう。
ステップ1:まずは「同意しません」と明確に伝える
最も重要なのは、その場で安易に同意しないことです。
「分かりました」と言ってしまうと、合意したと見なされ、後から覆すのが難しくなります。
「生活に影響が出るので同意できません」「一度持ち帰って検討させてください」など、まずはっきりと意思表示をしましょう。
ステップ2:労働条件通知書(雇用契約書)を確認する
入社時に交わした契約内容を確認しましょう。
「勤務時間:〇時~〇時(休憩〇分)」といった記載があるはずです。
この書面が、あなたが会社と交わした「約束」の証拠になります。
ステップ3:会社に変更の理由を詳しく聞く
なぜ勤務時間を変更する必要があるのか、書面で説明を求めましょう。
理由の正当性を判断する材料になりますし、会社側にも慎重な対応を促す効果が期待できます。
ステップ4:専門家や相談窓口に相談する
当事者同士での話し合いが難しい場合は、第三者に相談しましょう。
お近くの労働基準監督署や、私たちのような社会保険労務士が専門的なアドバイスを提供できます。
一人で悩まず、ぜひ専門家の力を頼ってください。
まとめ
企業の経営においては、業績の変動や業務量の増減により、従業員の勤務時間を見直さざるを得ない場面もあるかと存じます。
しかし、法律で定められた手続きを無視して、一方的にパートタイマーの勤務時間を短縮することは、労働契約法に違反する行為であり、深刻な労務トラブルに発展するリスクを伴います。
従業員の信頼を失い、企業の評判を損なう前に、適切な対応をとることが不可欠です。
まずは、勤務時間変更の必要性について従業員へ丁寧に説明し、真摯に話し合い、合意を得るというプロセスが原則となります。
やむを得ず就業規則の変更を検討する場合でも、その合理性については厳しく判断されます。
将来のトラブルを未然に防ぎ、健全な労使関係を築くためにも、労務管理の専門家にご相談いただくことをお勧めします。
社労士事務所ぽけっとでは、企業の皆さまが抱える労務問題に対し、法的な観点から最適な解決策をご提案いたします。
従業員との円滑な合意形成のサポートや、就業規則の見直しなど、お困りの際はぜひお気軽にお問い合わせください。
【免責事項】
本記事は、掲載時点の法令や情報に基づき、一般的な情報提供を目的として作成しております。個別の事案については、必ず専門家にご相談ください。本記事の情報を用いて行う一切の行為について、当事務所は何ら責任を負うものではありません。